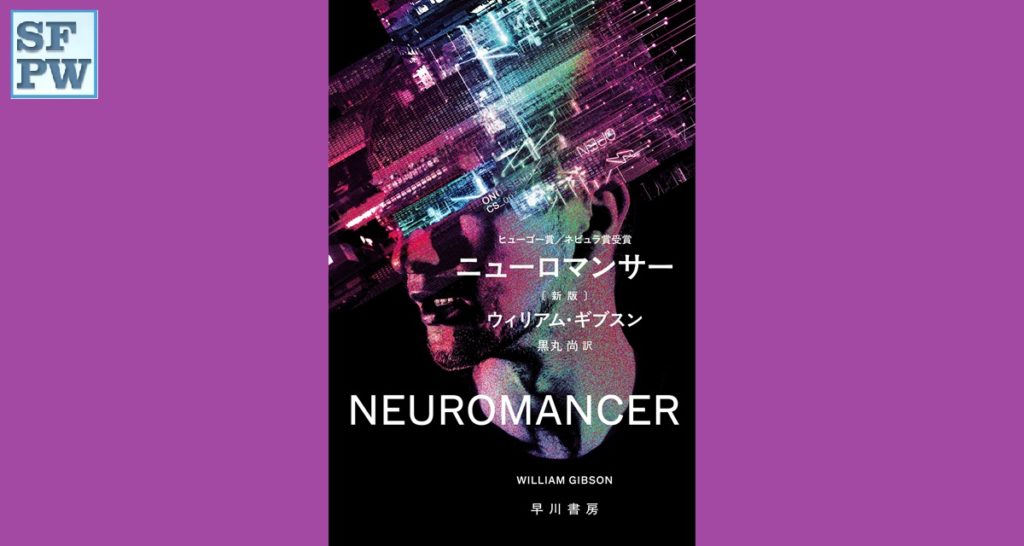

1982年の映画『ブレードランナー Blade Runner』では、ビルの壁に大きく映し出される芸者が「強力わかもと」の錠剤を、これ見よがしに呑みこんでいた。リドリー・スコット監督を含むスタッフは、ゲイシャ・ガールの娼婦的な面を強調するため、あれをピル(経口避妊薬)のつもりで映したという。だが日本人である我々は、それが胃腸薬であることを知っている(あるいは容易に知りうる)ため、そんな意図になかなか思い当たらない。ロスト・イン・トランスレーションの一種だが、正しく読めるがゆえに誤読(?)してしまうという捻じれ現象である。
当時、『ニューロマンサー』の第一部である「千葉市憂愁/チバ・シティ・ブルース Chiba City Blues」を書き上げていたウィリアム・ギブスンは、映画館に入って30分で席を立たずにいられなかった。どちらがどちらを真似したわけでもないのに、『ブレードランナー』のロス・アンゼルスは、ギブスンの創作した近未来都市チバ・シティそっくりなのだ。まあ前者が東洋化されたアメリカであるのに対し、後者がオキュパイド・ジャパンのイメージを引きずる西洋化された日本と方向は逆だが、体感としては、その混淆具合が極めて似通っている。
ということは『ニューロマンサー』内にも、捻じれ/誤読/読みすぎなどがありはしないだろうか? ワイドスクリーンバロックを意識した、あの圧倒的な情報量のテキストから、全てのサブテキストを読みきるのは難しい。きっと無数にあるだろうが、気づいたことを少し書いてみたい。
なお、本稿は4gamerに掲載された書評に対する補講である。「書評」https://www.4gamer.net/games/897/G089779/20250911001/のほうは、これから読む潜在的な読者のことを考えてネタバレは必要最低限に抑えたが、本稿では内容を示さないと解説が無理であるという性質上、その辺は気にしていない。したがって『ニューロマンサー』を未読のかたは、回れ右して読後に戻って来ていただきたい。なお本論だけで筋が通って読めるように、上記書評と内容が一部かぶっている点については、復習と思ってご容赦いただければ幸いである。

2025年7月2日、Apple?TV+が『ニューロマンサー』の実写ドラマ化を公表し、原作者ギブスンも祝福の「コメントhttps://x.com/GreatDismal/status/1940130126202839445を発表した。Youtubeで発信された「テイザー動画」https://www.youtube.com/watch?v=HJBnlZKgeUgは、チバ・シティにあるガイジン専用(日本人お断りの)バー《チャツボ》のネオン輝く店内であった。作中では“喋り場”という意味を重ねてか、チャット(Chat)とも略されている。
そこから2ブロックに西に、喫茶店《ジャール・ド・テ Jarre de Th?》がある。カタカナで音訳しかされていないので見逃しがちだが、これはフランス語で、Th?=Tee=茶、de=of=の、ジャール=ジャー=壺、すなわち《茶の壺》であり、上記の《チャツボ》と全く同じ意味になる。作品世界内で考えると系列店と解釈できるが、英語と日本語とフランス語に通じていなければ気づけないよう、意図的に潜まされている。「分かるものなら、この暗号を解いてみよ」と挑戦状を突きつけられている気がする。
この3言語に通じているのは、誰あろうギブスンの妻デボラ・ジーン・トンプスン(Deborah Jean Thompson)である。『ニューロマンサー』の主人公ケイスは、電脳空間に侵入する能力を失い、活路を見出すためにハイテク犯罪都市チバ・シティに逃げこんだが、当のギブスンはベトナム戦争への徴兵に異を唱え、アメリカ南部からカナダ(公用語が英語&仏語)のトロントへと移住、そこでデボラと出逢った。
言語学に優れるデボラは、やがてESL(English as a Second Language 第二言語としての英語)の教師を務めるようになり、そこで日本人の学生から(ギブスン共々)大きな影響を受ける。ギブスンが作品冒頭の舞台をチバ・シティに選んだのは「その千葉出身の“さらりまん”が、東京に生まれなかったことで不幸せに見えた」からだという。
作中には他にも、さまざまな日本語由来の概念や単語が散りばめられている。敢えて誤解を導くような用法もされるが、基本的には原義を十分に知った上での意図的な改変であり「強力わかもと」の事象とは異なる。であるからこそ我々日本人も、あの作品を熱狂的に受け容れることができた。
とするなら、茶壷などという茶道でもかじっていなければ出てこない非日常単語がわざわざ配されているのだから、あの二店舗の名から自然に誘導されるこの歌を、我々日本人は思い浮かべるべきであろう:
ずいずいずっころばし
ごまみそずい
茶壺に追われて
とっぴんしゃん
抜けたら、どんどこしょ
俵のねずみが
米食ってちゅう、
ちゅうちゅうちゅう
おっとさんがよんでも、
おっかさんがよんでも、
行きっこなしよ
井戸のまわりで、
お茶碗欠いたのだぁれ
ご存じ「ずいずいずっころばし」である。わらべ歌の例にもれず全体的な意味は解明されていないが、「茶壷」で始まり「茶碗」で終わるというところから、その背景に茶道の伝統が強く想起される。
この歌での茶壷は、大名行列にも似た「茶壷道中」を謳ったもので、無礼打ちに合わぬよう、庶民は戸をぴしゃっと閉めて家に閉じこもって耐えた、という説が優勢のようである。
茶碗には、曜変天目など再現不能で極めて高価な“名物”もあり、大名に好まれた。もしそれが割れたというなら、番町皿屋敷ではないが、手打ちで済むレベルではない大ごとである。
すなわち、いずれも「失敗によって切り殺される」という不穏なイメージがつきまとう。
ネズミ(rat)は、日本語でも英語でもスパイや裏切り者や盗人を意味する。「俵のねずみが米食ってちゅう」というのは、依頼人から盗みを働いたことが発覚して脳神経を焼かれたケイスに相応しい表現だ。そんなヘマをやらかしたケイスは、アメリカ東海岸の混合都市群《スプロール》から《茶壷》に追われてくる。ケイスには、おっ父さんもおっ母さんもいないが、AIに連れ込まれた仮想空間で、故買屋のフィンに呼ばれても、元カノのリンダに呼ばれても、頑なな拒否の態度をとっている。
井戸は『ニューロマンサー』では、重力井戸(Gravity Well)の文脈で頻出する(入り込むと抜け出すことが非常に困難な、量子力学の井戸型ポテンシャルの意味もかけられているのだろうか?)。とりあえず重力井戸の線で解釈すると、軌道上から地球を見下ろす視点で「お茶碗(=大事なもの)を壊したのは誰?」になる。『ニューロマンサー』は、壊れたものたちのオンパレードである。ヒロインのモリイは、主人公たるケイスに似た恋人・記憶屋ジョニイを失っている。隊のリーダーたるアーミティジは、戦争のPTSDで人格を失った。ケイスの師匠ディクシー・フラットラインは肉体を失ってROMに幽閉されている。依頼者であるウィンターミュートは、分断されたベターハーフを探している。そもそもケイス(Case)とは「容器」の意味であり、茶の入れ物である茶壷に一致している。
冒頭の「ずいずいずっころばし ごまみそずい」が最も難解だが「胡麻味噌をすり鉢で擦っていると」という一般的な解釈にしたがうと、軌道上でぐるぐるぐると回って人口重力を作り出している紡錘(スピンドル)形の《自由界/フリーサイド》のアナロジーにも見えてくる。
深読みのしすぎかもしれない。こじつけかもしれない。ただ全体を俯瞰すると、『ニューロマンサー』は「ずいずいずっころばし ごまみそずい」の創造的ノベライズとして読むことができる。
けれど諸外国の人々はそもそもこの歌を知らないし、日本人は「まさか関係ないだろう」と勝手な判断で無視してきた。今のぼくなら、『ニューロマンサー』のドラマの中で「ずいずいずっころばし」の旋律が、哀調をこめた「千葉市憂愁/チバ・シティ・ブルース」として流れてきたとしても、驚きはしない。
アメリカ南部の黒人霊歌にルーツがあるブルースは、1920年代には都市部へと浸透し、やがてシティ・ブルースと呼ばれるサブジャンルを生み出していた。ブルース形式という12小節のコード進行が決まっており、ブルー・ノート・スケールという音階に、シャッフルという中抜き三連符の刻みなど幾つかの決まりがある。語源となったブルー(Blue)すなわち青は悲しみを示す色ではあるものの、本来のブルースはその憂さを晴らすためのものであり、明るい楽曲が多い。
ところが日本では、ブルース形式になっていなくても、悲しい/暗い曲調(マイナーキーを基調とした憂鬱なメロディとコード進行)のものをブルースと呼ぶ風潮がある。服部良一が、本場のブルースに傾倒しながらも「日本なりのものを」と生み出し、淡谷のり子の歌で大ヒットした(神戸の港が舞台の)「別れのブルース」(1937)や「雨のブルース」(1938)が、そもそもブルース形式ではなかったせいであろう。
同じ頃アメリカでは、レイモンド・チャンドラーが短編「ベイ・シティ・ブルース Bay City Blues」(1938/邦訳1964)を発表している。作中ではブルース自体への言及はない。ただ作品の底流には、高潔さと卑劣さが同居する皮肉に対する侘(わび)しさがあり、比喩としてタイトルにブルースの語が採用された。
この「ベイ・シティ・ブルース」が、チャンドラーを特集した日本版〈エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン〉1964年10月号に稲葉明雄訳で掲載されて以降、日本ではSFやハードボイルドものに“ブルース”を含むタイトルをつけることが流行った。

そのハシリがハリイ・ハリスンの『宇宙兵ブルース』である(1965/邦訳1967)。原題は『Bill the Galactic Hero 銀河英雄ビル』と味も素っ気もないが、エンディングで主人公のビルが、酒場の楽隊に「《宇宙兵ブルース》をやれ」(浅倉久志訳)とリクエストし、そこから涙なくしては読めない非情な展開となる。それを邦題にしたわけだが、その部分の原文《A Spaceman’s Lament》の直訳は《ある宇宙船乗りの哀歌》であって、ブルースではない。チャンドラーの影響の大きさと、日本におけるブルースという用語の自由さを物語る実例である。

平井和正の短編「サイボーグ・ブルース」の発表はその翌年で、〈SFマガジン〉1968年10月号に掲載された。これを含む連作短篇は、1971年に長編『サイボーグ・ブルース』としてまとめられる。生身の脳と機械仕掛けの肉体の齟齬に悩むサイボーグ捜査官という設定は、映画『ロボコップ』に先んじること19年。後のサイバーパンクの先駆けであった。展開やキャラクターの端々には、明確なオマージュとして、チャンドラーの最大傑作と名高い『長いお別れ』のエッセンスが散りばめられていた。主人公のアーネストは黒人であり、かつては歌えたブルースが、機械の体になってからはうまく歌えず、それは自分の魂が損なわれたせいではないかと感じている。

ハードボイルドではチャンドラーの師匠筋にあたるダシール・ハメットや、ふたりの後継者たるロス・マクドナルドなどを訳してきた小鷹信光が、その名もズバリ『探偵物語』という小説を1979年に発表。同年、松田優作が探偵・工藤俊作を務めてドラマ化されたが、その第2話は、伊豆という港町を舞台にした
「サーフ・シティ・ブルース」https://www.youtube.com/watch?v=O2jGkrwRco0であり、俊作はヒロインに「長いお別れになりそうだ」と告げる。監督は村川透、脚本は那須真知子。

第12話「誘拐」では、工藤俊作=松田優作は、第4の壁を超えて「日本のハードボイルドの夜明けはいつ来るんでしょうかね、小鷹信光さん」と画面越しに作者に話しかけてくる。
そして1980年4月1日、第27話「ダウンタウン・ブルース」で、放送は華々しく終了する。
ところが松田優作のハードボイルド愛は止まらない。1981年、『長いお別れ』(の映画版である1973年のロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』)に対するオマージュとして、映画『ヨコハマBJブルース』を制作した。監督は工藤栄一。松田演じるBJはブルースシンガー兼探偵だ。松田はオリジナル楽曲「Bay City Blues」や「灰色の街」の作詞を担当し、自ら歌い、アルバムにもなっている。

同年、当時イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)だった高橋幸宏が、『ニューロマンサー』のタイトルに影響を与えたソロ・アルバム『NEUROMANTIC ロマン神経症』を発表する。不安とロマンがないまぜになった潜在意識まで刺激する音楽群は、確かなBGMとして『ニューロマンサー』に合っている。
前述のとおり、ギブスンが『ニューロマンサー』の第一部「千葉市憂愁/チバ・シティ・ブルース」を書き上げたのは、『ブレードランナー』が全米公開された1982年6月25日前後である。作中にブルースは登場しないのに、どうして章題に入っているのか?
ギブスンは「チャンドラーは好みに合わないからほとんど読まない」と言っている。したがって短編「ベイ・シティ・ブルース」から採用したとは考えにくい。ただし間接的な影響は否定していない。だとするなら、ここまで見てきた日本の小説や映画での一連のブルースの用法に、気づかぬうちに浸潤された可能性がある。悲しみや憂いに満ちた、灰色で雨が篠突く港町のイメージである。
この憂いをぶっ飛ばすのが、軌道上のザイオン集合体で常に流れているダブであろう。
なお日本では、このようなブルースとハードボイルドの関係は、さらに続いている。サラ・パレツキーの女流ハードボイルド探偵V・I・ウォーショースキーものの1作目は、邦題を『サマータイム・ブルース』(1982/邦訳1985)というが、例によって原題は『Indemnity Only 補償のみ』と関係ない。ただし第5章の章題が、英語/日本語共に「ゴールド・コースト・ブルース Gold Coast Blues」で、そこから持ってきたこともあろう。このゴールド・コーストは、舞台であるシカゴの富裕街のことである。
シリーズの人気が高かったため、後に日本で独自に短編集『ヴィク・ストーリーズ』が編まれたが、逆にこのフォーマットが英語で踏襲され、『Windy City Blues』と名付けられたのは、皮肉というべきか宿命というべきか(邦訳1994/英語版1995)。ちなみにウインディ・シティとは、風が強いシカゴの愛称。

以上で本稿を終了とする。これだけを読むと『ニューロマンサー』との関連が弱いと感じるかもしれないが、前述の「書評」https://www.4gamer.net/games/897/G089779/20250911001/と合わせれば説得力が増すはず。併読をお勧めする。
