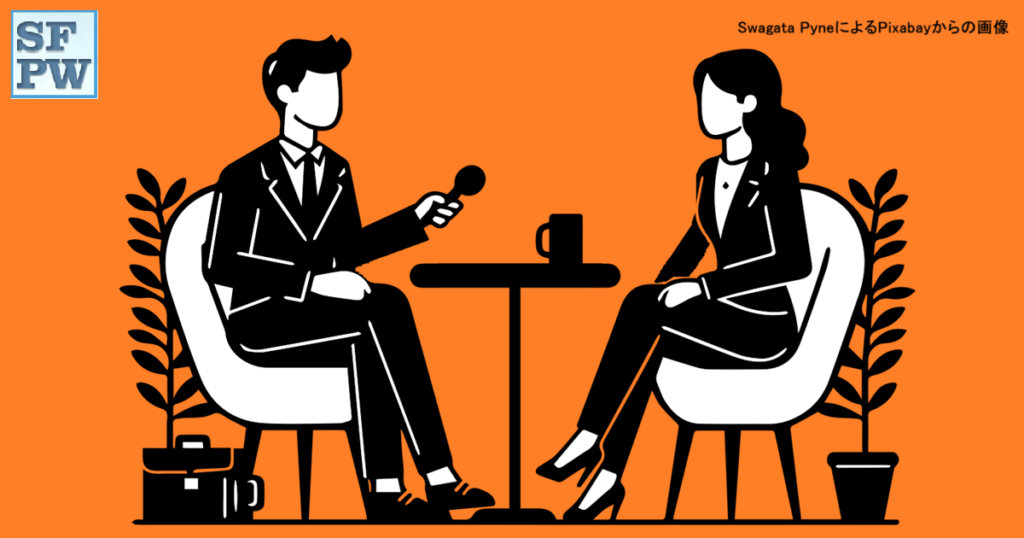
とある国のとある街角にあるオープンカフェのテラスから、一組のカップルが道路をはさんだ向かいにある小さな公園を眺めていた。
「ほら、見て。あの人がマイクを向けてる女の人って、マネキンじゃない? ちっとも動かないわ」
「ほんとだ。あの若い男の子、さっきぼくらにインタビューした人だろ。『この街はお好きですか』って。でもみんな通り過ぎてしまって、誰も答えてくれてなかったよね」
「なんだか自身なさげで頼りなかったもん。だから動かないマネキンに的を絞ったのね。でもどうしてあんなところに、マネキン人形があるのかしら」
*
彼は下請けの制作会社のスタッフで、ラジオ番組の街頭インタビューに駆り出されていた。慣れない仕事でうまくいかず、くさっていたときに彼女を見かけた。
動かない彼女がマネキンなんかじゃないことを、彼は知っていた。彼女は大道芸人。そして彼女の芸は「スタチュー」だった。
彫像のように、ピクリとも動かないのが「スタチュー」。もともとスタチューとは彫像を意味する英単語で、それが大道芸の呼称にもなっている。だからなかには服も身体も同じ色に染めて、本物の銅像に扮する者もいるが、彼女はメイクをしてマネキンのように普通の格好で立っていた。
最初、彼はインタビューの練習のつもりで彼女にマイクを向けたのだが、じっと相手の目を見ているうちに、だんだん好きになっていった。だから街頭インタビューの仕事から異動になっても、毎日毎日仕事の帰りに彼女にマイクを向けた。
もちろん会社の備品ではなく、じいちゃんの家にあった壊れた家庭用カラオケのマイクを使った。
「どうしてスタチューになったのですか?」「将来の望みは何ですか?」「今の政治をどう思いますか?」「生活は充実していますか?」「好きな食べ物は何ですか?」「好きなタレントは誰ですか?」「好きなタイプの男性は?」「恋人はいますか?」「ぼくのことをどう思いますか?」
「ぼくの彼女になってもらえませんか?」
彼女は彼のどんな質問にも、ピクリとも動かず、一言も答えてはくれなかった。
雨の日も風の日も、もちろん晴れた日にも彼女はその公園でマネキンを演じていた。来る日も来る日も彼は彼女にマイクを向け、いつもむなしくそこを立ち去るのだった。
彼は決してストーカーではなかった。だから彼女が少しでも嫌がるそぶりを見せたときには、潔くあきらめようと決心していた。せめて好きか嫌いか示してくれればと思った。
けれど彼女が見せるのは、微動だにしない身体全体で示す無関心の態度だった。それは真摯に芸に打ち込む彼女の姿でもあったのだけれど。
仕事帰りのインタビューが甲斐なく終わると、彼は足取りも重く自分の住むアパートに帰った。しばらくすると、同じアパートの三つ隣の部屋の住人が帰ってくる。
ときどき買い物に出た彼とすれ違うこともあるその住人とは、「スタチュー」の大道芸をする彼女だった。
最初にアパートの前で鉢合わせしたとき、彼女も驚いた顔をした。でも二人はとっさに平静な表情に戻り、お互いに会釈してすれ違った。
インタビュアーとしてマネキンの彼女に答えさせてみせる。それが愛の証のように彼は感じていた。
彼女が嫌がっていないことは、普段はご近所さまとして、無言の挨拶に笑みを湛えることもあるので間違いなさそうだった。けれどいつになっても、インタビューする彼に対して、ゆるぎなく立ち続けるばかりだった。
彼は、彼女を動かす方法を知っていた。むしろ多くの通りすがりの人々が、そうすることで彼女を動かしていた。
それは投げ銭をすることだった。
彼女の足元に置かれたグラスに、コインを投げ入れると、彼女は微笑んでひとしきりパントマイムのような動きをし、それからまたマネキンになるのだった。
それで生活の糧を得ているのだから、彼女がそうやって動くのはあたりまえだった。
けれど彼は決してその方法はとらなかった。それは彼女の本当の姿ではない。自分の気持ちを真摯に伝えることで、彼女の心を動かしたい。
でもとうとう彼は我慢ができなくなった。チャリンという音で彼女がほんの数秒、音をさせた相手に見せる微笑みが欲しくてたまらなくなったのだ。
ある日、彼はマイクを向けることなく、うつむいたままポケットから小銭を出し、彼女のグラスに投げた。
手元が狂って、お金は彼女の足に当たって転がった。
いつもよりゆっくりと身体を折り曲げると、彼女はそれを拾い、彼に向かって微笑みかけ、それから空を見上げる格好で静止した。
うつむいていた彼は、彼女の微笑みを見なかった。彼が頭を上げたとき、上を向いたまま固まった彼女の両目から、二筋の涙が流れていた。
その日から、この街で彼の姿を見なくなった。アパートを引き払い、会社も辞めてしまっていた。
彼女もすぐに気がついた。
毎日来ていたインタビュアーが来なくなり、アパートの隣人も姿を消したことを。
それでも彼女は、いつもの場所でいつものようにマネキンを演じ続けた。いつしかアパートに戻ることも、投げ銭で一瞬微笑んで動くこともしなくなった。
ずっとずっと、昼も夜も彼女は立ち続けた。まるで誰かを待っているかのように。
*
時が過ぎて、街角の古びたカフェテラスで一組の老夫婦がくつろいでいた。
二人は若いころこの街を訪れて、この店でデートを楽しんだことがあった。
「ねえあなた、あの女の人の彫像、昔来たときにもあったわね」
「そうだったね。もうひとつの彫像をきみが生きている若い男性と間違えて、彫像にインタビューなんておかしいねと笑った。そういえば、女性も彫像ではなく、マネキンだったんじゃないかな」
「そんなことあったかしら。忘れてしまったわ」
「ずいぶん昔のことだからね。でもインタビューしている男の像も、受けている女の像も老人なんて――もっと若かったような気がする」
「でもほら、二人ともとても幸せそうに見つめあって微笑んでいるじゃない。なんだか素敵だわ」
老夫婦はまるで自分たちに重ね合わすような気持ちになって、公園にある二つの彫像を眺めた。
そうなのだ。二つの彫像は、話をしている老夫婦と同じぐらいの年齢に見えた。
そして、この街に昔から住んでいる人たちは、像がいつから立っていたのか覚えていないのに、あることを知っていた。
見つめあったまま動かず立っている男と女の彫像が、毎年少しずつ歳を重ねているようなのを。
