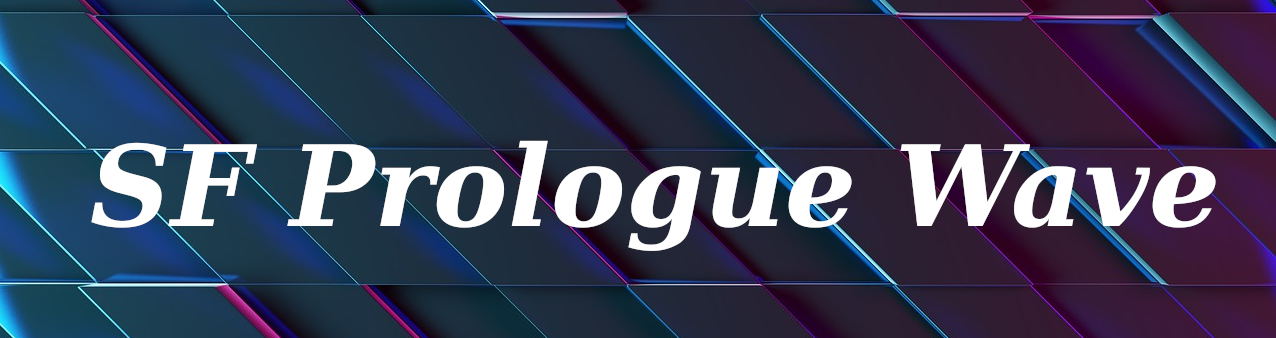アイヌと沖縄とまなざしと――村上靖彦・石原真衣編『アイヌがまなざす』小論
冨山晴
一、沖縄に生まれ育った者として
アイヌに対する差別について、アイヌをルーツに持つ方々の見てきた景色、環境をインタビュー形式で記録し、アイヌの立場から見た差別の歴史と現状について読み取ることのできる『アイヌがまなざす─―痛みの声を聴くとき』。私は本作を、自分の故郷である沖縄での生活と、当地で感じてきたこととを、どこか重ね合わせながら読んでいた。第三部第六章『羽をパタパタさせればいい』での新井かおりさんの語り、第7章『家出少年は傍らに神話を持つ』での結城幸司さんの語りには惹かれるものがあった。差別は既に無くなり、多様性が認められたのだと世間に広がりつつある風潮の傍ら、マイノリティはこれまで、そして今どう扱われているのか。本当に今でも差別は無くなったのか。
二、二風谷ダム裁判と辺野古基地の裁判
農地改革、そして二風谷ダムの一件など植民地的支配とその流れを引き継ぐ問題がアイヌにはある。第二次世界大戦後の農地改革は、日本史において寄生地主と高額な小作料のシステムを解体し小作人に売り渡すことで自作農を活性化させたとしてプラスと捉えられる出来事であり施策とされているが、そのデメリットについて説明される事は少ない。元々アイヌから長期の貸借地として小作人の手に渡っていた土地にも施策が適用され、結果としてアイヌ側は土地を剥奪される形になってしまった。これは戦前戦後そして今にもつながるアイヌや少数民族を下に見る社会構造の下地となってしまっている。その流れの中に、二風ダムとその裁判がある。アイヌにとっての重要な土地、そして文化性に配慮する事無く、政府によって建築が進行されたダム。憲法十三条幸福追求権、環境権の議論として扱われたこの件は最終的に国側が違法と法的な判断が出たが、判決時既にダムは完成し取り消される事も無かった。裁判においてこの裁判で司法はアイヌが先住民族だという事を認めたが先住権は認められなかった。時代の流れにより認識は変化したものの、在り方そのものは未だ否定されているに等しい。
沖縄の二〇二三年の辺野古基地に関する裁判についても、沖縄の基地過重負担や辺野古の土地の気弱性、何より県民意見が一切考慮される事なく棄却され敗訴した。沖縄は法的な手段での抗議を奪われるに至った。「アイヌ問題はこれまで十分に可視化されてこなかった。沖縄の基地問題のような暴力の現場がないし、物理的に中央から離れた北海道という場所での非言語的な差別の温度は、北海道外の市民には伝わらないという背景もあるだろう。」と本書で書かれているように、沖縄の基地問題に対してアイヌへの差別は比較的曖昧で、現場を挙げづらい面がある。しかし二風谷ダムのようにはっきりと可視化された場所も確かにあるのである。
三、言語の剥奪
アイヌや沖縄の歴史や内情について知る機会は限られる。より発信すれば理解者も増えるのだと希望を説くのは簡単だが、政治の現場で後手に後手にと流されていくこの問題に対して、どうしようもないという悲しい諦観を持たざるを得ない当事者達も増えつつある。
土地の浸食と共に、マイノリティとその文化は同化の波に流される。言語文化については顕著である。アイヌは戦後の同化政策と教育の流れでアイヌ語を剥奪されていった。
沖縄は同化政策に加え、第二次世界大戦での地上戦時に「自分たちの言語を使用した」廉でスパイ容疑を掛けられた過去があり、言語を喪失を余儀なくされた。「でも、そのアイヌのおばあちゃんが来ると、アイヌ語で話してるようなところもあるんだけど、僕らが近づくと、やっぱり自分の部屋に入ってくんだよね。後の情報の勝手な思い込みかもしれないです。『みんなそうやって子どもに伝えないようにしたんだ』っていう情報が俺の中に入ってて、『あれはそうだったんではないかな』っていう自分なりの憶測なんですけど。」そう結城さんが語るように、独自の文化、この場合は言語を使うこと自体が悪だというような意識が何処か刷り込まれている。
結城さんの考察が正しいのなら、生き辛さを生んでしまう文化を後世に残さないように口を閉ざすのは当然の帰結といえる。私の祖父祖母も、私の前で沖縄弁を話す事は数少ないし、喋らなくなった背景を話す事もない。そうなると親の世代も話さなくなる。こうして後世を文化から遠ざけ、ルーツ及びアイデンティティーを希釈していく事が、ある意味処世術となってしまうのである。言語文化が希釈化されることは、非文字文化の時期が長かったアイヌにとっては致命的と言ってもいい。日本語が標準語であるという事が根付いた言語意識の中で、独自の文化を貫く事は難しい。
四、イメージの押し付け
しかし一方で、コンテンツとして文化を残す、広めようとする動きもある。コミック、アニメ、映画で人気を博している「ゴールデンカムイ」もその流れの一端に位置している。コンテンツの良さは今までその世界に興味を示さなかった、知識の無かった層にきっかけや取っ掛かりを作り出すことが出来る点である。しかしその反面、「こうでなければならない」「こうでなければらしくない」という固定観念にも似た偏見の生産に拍車をかけてしまう事である。
イメージの押し付けは何も和人側だけの問題ではなく、アイヌのコミュニティ内でも起こるものである。「アイヌに生まれたのだからこう在らなくてはならない」「アイヌなのだからこう思わなくてはならない」。それ以外の在り方を否定する、新井さん曰く「スピってるイメージ」が生まれるのだ。それはかえって文化の寿命を縮め、狭め、破壊する行動である。植民地的思考で接する和人側も、自己を主張しようとするアイヌ側も、誰しもが内面にある偏見や「スピってる」部分と向き合わなくては、和解や深い理解は果たして実現できないのではないか。固定化されたまなざしでは先へは永遠に進めない。
五、能動的に知り、理解しようとすること
SNSにて匿名で無責任な発言場所が生まれ、差別や偏見の動きもそこに流れ込んだ。沖縄基地やアイヌ、移民問題などキーワード検索を掛けてみれば、糾弾や弾圧とも取れる様な意見が数多く飛び交っている。その発言をしている者たちの中で、きちんとした現状や歴史を知っている者が一体何人いるだろうか。「基地が守ってくれているのだから文句を言うな」と言う人達の中で、「アイヌはもう存在しない」と言う人達の中に一体何人いるだろうか。
マイノリティの歴史文化について、日本の教育は深く切り込んでくれない。しかしこれらを語る際、考える際には正しい知識が要る。そして差別や不平等に対して、人は上から目線での理解や受け入れではなく、自分事として向き合う必要がある。その為にはやはり、こういった物事に興味を持ち能動的に知ろうとする姿勢を持つ事が第一ではないか。
世代が変わるにつれて、もともとどうだったかを語ることができる人は減っていく。アイヌの遺骨問題にしても、沖縄の地上戦の記録に関しても、今段々とその原型が消えていこうとしている。そうなると、どう足掻いても主体的に物事を語れなくなる人々――批評家ガヤトリ・C・スピヴァクの言うサバルタン(従属的社会集団)又はそれに準ずる声――が生まれてしまう。理解しようと向き合うと同時に、その埋もれていこうとする声がある事を忘れてはいけない。それらを客観的に見つめて答えを模索する事が、世代交代の狭間に位置する人の役割なのだ。
参考文献
『アイヌがまなざす─―痛みの声を聴くとき』石原真衣・村上靖彦、岩波書店、2024年
『アイヌ文化史辞典』関根達人・菊池勇夫・手塚薫・北原モコットゥナㇱ編、吉川弘文館、2022年
「アイヌ差別の歴史─権利回復と人権尊重への前進を』北原モコットゥナㇱ・紙智子、「前衛」2024・6
※本稿は、岡和田晃が2024年度秋学期に東海大学文芸創作学科で開講した現代アイヌ文学論(「文学精読」内)の期末レポート優秀作です。