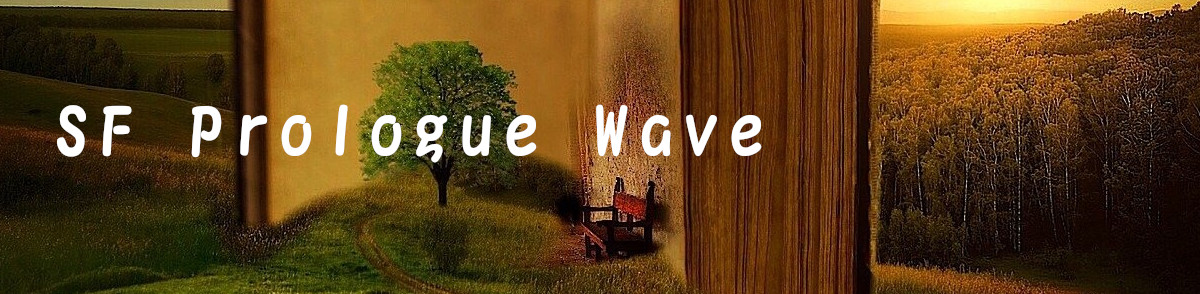「アイヌが世界をまなざす時――村上靖彦・石原真衣編『アイヌがまなざす』小論」
呉中華
北海道の深雪の中、アイヌの歌謡はかつて植民者の足音に踏み砕かれ、「エキゾチックな見世物」の標本と化した。痛みの声を聴くとき、『アイヌがまなざす』(村上靖彦・石原真衣編『アイヌがまなざす』、岩波書店)で最も私の胸を“突き刺した”のは、繰り返し登場する「まなざしの転換」だった——博物館のガラスケースの中の「観察対象」ではなく、灼熱の眼差しで「誰が私たちの歴史を定義するのか?」と問いかけるアイヌの人々。その瞬間、私は気付いた。日本という「統一ナラティブ」の本質は、ポストコロニアルな暴力そのものだと。大学の標本室に眠るアイヌの遺骨、地方文化として扱われ続ける「北海道文学」。このような偏見に満ちた認識を、私たちはどう打ち破ればよいのか?
科学の美名に隠された暴力
北海道大学前で祖父の頭骨返還を求めて座り込む木村二三夫の姿は、現代日本の良心に突き刺さる棘のようだ。明治期の学者が「学術研究」を盾に墓地を盗掘し、アイヌの身体を「絶滅寸前の人種」の記号に変えた行為は、「科学的まなざし」が殖民支配と共謀する構造を露呈する。生きるアイヌには同化政策が強要され、死せる者は「文化保存」の名で標本化されるという矛盾。札幌医科大学に未返還の千体を超える遺骨は、「死体へのコロニアリズム」が今なお継続している事実を告発する。学生たちが木村の座り込みを素通りする時、彼らは歴史の裂け目を踏み越えていることに気付いているのだろうか?
この死者への暴力は、同時に生者の精神世界を蝕んでいる。Bさんが「文化を伝えられなかったことが誇り」(『アイヌがまなざす』p.90)と語る逆説は、沖縄で琉球語を奪われた老人たちの姿と重なる。「アイヌなんて隠して生きる」という彼女の言葉は、単なる生存戦略を超え、殖民化の暴力の軋轢で鍛え上げられた、哲学的な存在論だ。文化伝承の鎖を断ち切った同化政策は、生き残った者に「伝統を守れなかった」という罪悪感まで押し付ける。しかしBさんは「悲劇の先住民」というステレオタイプを拒否し、「隠す」行為そのものに抵抗の可能性を見出す。
これらの「不完全な生存」は、殖民者が築いた忘却の壁から零れ落ちた骨片のように、新たなアイデンティティの地図を紡ぎ出す。空白を武器にし、同化されざる残余を礎とするこの抵抗の手法こそ、「ポストコロニアル」な状況に対する最も辛辣な批判なのである。
性別と民族が交差する時
昨年、中国のSNS上で「男性のまなざし」という用語が頻繁に議論を呼んだ。この概念は英国の美術評論家ジョン・バーガーが提唱したもので、視覚芸術や文学創作において女性が男性視点で描かれ客体化される現象を暴き出すものだ。男性のまなざしは芸術作品を通じて性別化された「見方」を伝達するだけでなく、女性像を男性視聴者の欲望に奉仕させることにより、女性性を消費可能な対象へと還元する。この問題は特にアイヌ女性の表象において顕著に現れている。先住民族としての彼女たちは、客体化という苦境に直面している。
SNKの対戦型格闘ゲーム『サムライスピリッツ』に登場するアイヌの少女ナコルルは、このような客体化現象の典型例である。伝統的なアイヌの衣装を身にまとい、短刀を携え鷹を伴うこのキャラクターは、一見「自然の守護者」という理想化されたイメージを体現しているように見える。
しかしこの表象は単純な賛美ではなく、複雑な二重のまなざしを内包している。まず、エキゾチックな衣装デザインや少女らしい仕草は、男性プレイヤーが抱く「純真な先住民族の少女」への幻想に迎合している。「自然の守護者」というアイデンティティは「未開の神秘性」へと単純化され、男性視聴者による「未開の地」へのロマン的対象となる。
この男性のまなざしは単なる架空キャラクターの現象ではなく、現実のアイヌ女性が直面する課題を反映している。『アイヌがまなざす』第4章で多原良子が闘うのは路上での暴言だけでなく、社会全体がアイヌ女性に注ぐまなざしそのものだ。観光土産のパッケージに繰り返し登場する「伝統衣装姿の微笑む女性」像は、彼女たちを「優しく善良で自然と共生する存在」というステレオタイプに閉じ込める。その存在は観光客の旅行記憶を彩る「異国情緒的な装飾」でしかなく、そこには他者を物象化する俗流ロマン主義が充満している。
ナコルルのゲーム内表象と現実の土産品が示すのは、アイヌ女性が「美しい他者」へと還元され、消費主義の記号に変容させられる過程である。この「文化の商品化」プロセスは個人の複雑性を剥奪するだけでなく、歴史的経験と現実的苦闘を大衆の視野から排除する。男性のまなざしと文化資本化が共謀するこの現象の背後には、長期的な文化抑圧と性別不平等が潜んでいる。それは単に認知の歪みを生むだけでなく、近代社会における周縁化を深化させる。アイヌ女性が直面するのは外部の偏見だけではない。近代性と衝突する歴史的遺産、文化的記憶との不断の格闘こそが、現代に続く苦悩の根源なのである。
まなざしの転換:「観られる」から「見つめる」へ
第8章『思想的消費とまなざしの暴力』が鋭く指摘するように、現代社会におけるアイヌ文化への「善意的な関心」は、新型コロニアリズムの形態へと転化しつつある。この「善意」の裏側では、アイヌ民族の主体性が剥奪され、文化が商品化される暴力が潜んでいる。
環境保護主義者はアイヌを「自然の守護者」として祭り上げる。こうしたラベル貼りの行為は、表面上はアイヌ文化を肯定しているように見えるが、実際にはその文化的な主体性を奪い取る行為にほかならない。
社会学者スチュアート・ホールが指摘したように、「他者化」は侮蔑だけでなく、賞賛という名の定型化によっても進行する。アイヌ文化が「エコ」といったラベルに分解される時、その多層的で複雑な実態は消去され、全体性が断片化されてしまう。アイヌ民族は単なる「環境保護主義者」ではなく、独自の歴史、伝統、そしてアイデンティティを持つ存在である。しかし、こうした複雑性は外部からのラベルでは捉えきれない。
現代社会がアイヌ文化に貼るこれらのラベルは、結局のところ、文化の消費物化と単純化にすぎない。それらはアイヌ民族を自由に装飾できる記号に変え、彼らを語る権利を持つ主体としてではなく、消費される対象として扱う。こうした過度の単純化と定型化は、アイヌ民族の自律性を奪うだけでなく、彼らが現代社会で直面する現実や歴史的な要求をも覆い隠してしまう。
最も重要なのは、こうしたラベル化された「関心」が根本的に見落としている点である――アイヌ民族が本当に必要としているのは、消費されるラベルではなく、自らの文化と歴史を語るための空間であり、外部からの他者化された視線から自由になることなのである。
結:鏡の中
『アイヌがまなざす』の頁を閉じた時、ふと思考が深まりを見せたように思った――もし私がアイヌ民族だったら、自らのルーツを隠して生きる道を選ぶだろうか、それとも誇り高く生き抜こうとするだろうか、と。
しかし重要なのは、その問いそのものではない。むしろ、こう問うべきではなかったか。「アイヌ文化を守る」と声高に叫ぶ私たちは、彼ら自身に「守られる必要があるのか」と尋ねたことがあるのか、と。
真の「まなざしの転換」とは、この単純な事実を認めることから始まる:
アイヌ民族は代弁者を必要としない――自らを定義する権利の奪還こそが求められている
新しいラベルなど不要だ――文化を封じ込めた博物館のガラスケースを打ち砕く時が来ている
偽善的な多文化主義など要らない――「北海道開拓」という未だ乾かぬ血痕の歴史と対峙すべきだ
アイヌが「観察される客体」から「日本をまなざす主体」へと転じた時、私たちは鏡に映し出された自らの植民地性を直視できる覚悟があるだろうか。
手にしたビール缶の中で、泡がゆっくりと浮上する。弾ける泡の儚い軌跡は、私たちが紡いできた虚構のようだ――美しく、刹那的で、やがて消えゆく定めの。しかし耳を澄ませば、そのはかなく消える音の隙間から、新井かおりの言う「羽をパタパタ」と羽ばたく微かな響きが聞こえてくるような気がする。
※本稿は、岡和田晃が2024年度秋学期に東海大学文芸創作学科で開講した現代アイヌ文学論(「文学精読」内)の期末レポート優秀作です。