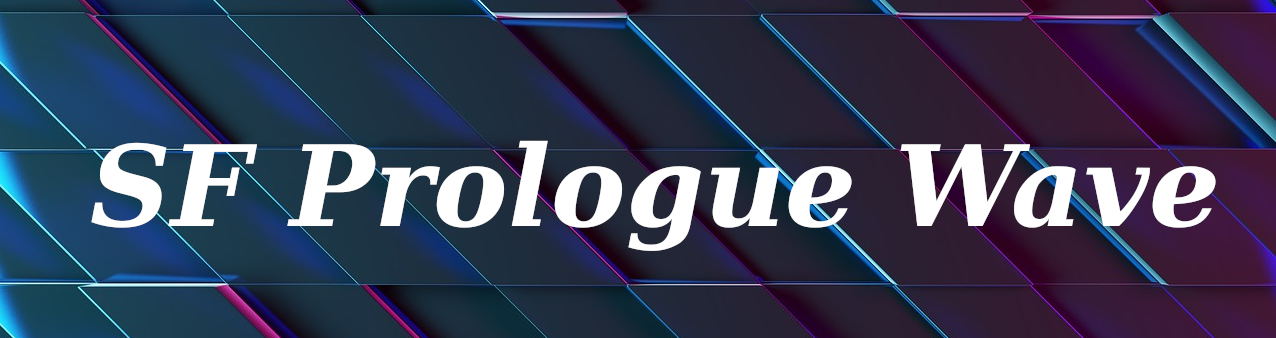「絶望に入り込む水と光――岡和田晃著『世界の起源の泉』書評」
川嶋侑希
詩集を開くと、言葉が水のように自由な形で踊っている。読み進めて行くと言葉が温度、感触、量、色……作品ごとに性質を変えて、私たちの視覚と想像を支配し、魅了していくような感覚がしてくる。これはまさしく生きた言葉だ。
本書『世界の起源の泉』(SFユースティティア、二〇二四)の著者は北海道出身の作家、岡和田晃氏だ。岡和田氏は文芸評論家や大学講師として活躍する傍ら、詩誌「壘」や「潮流詩派」、「白亜紀」、「フラジャイル」などに多くの詩を寄せる現代詩人である。本作は二〇一九年に制作された第一詩集『掠れた曙光』(幻視社/書苑新社、二〇一九)に続く発行で、全二六〇頁、五十三編の詩を収録しておりかなり重厚感のある一冊となっている。本から漏れ出てきそうなほどの物語や言葉たち。私たちはその中に潜り込んで僅かな斜光を見つけ出す旅に出る。ある時は争いや差別の憂いと叫びの中から。またある時は悲しみに寄り添う眼差しの中から。この詩集の根底には、水面を押し上げるほど熱く沸き立つエネルギーが、静かに煮えたぎっている。
前半に収められているのは、神話やいにしえの歴史を想起させる、夢の中にいるように幻想的な形而上詩だ。ひとつめの作品『崩れた微光』では自由を奪われた者の静かな絶望が描かれる。二度と戻れない外の景色に思いを馳せては、今置かれている閉ざされた環境に絶望する。やり場のない苦しみを語る断片的な言葉は、滴り落ちる雫のように成す術がない。淡々と紡がれる言葉が痛々しいのだが、そこに差し込むわずかな光の存在が際立って見えるのだ。このぼんやりとした明かりが、この詩集の入り口を示す始まりの明かりだ。
『まぼろしの先端』は春の夜の散歩道を思わせる七五調の軽やかなリズムが印象的である。歩きながら絶え間なく巡る思考を、歩調に合わせて語っているかのようだ。リズムとどこか寂しそうな雰囲気が相まって、一定の速度で流れる小川を連想させる。ここは何処なのか、この先にあるものは何なのか、何のために進んでいるのか、そんな疑問を私たちにも投げかけてくる作品だ。
言葉の響きやリズムが印象的な作品はいくつもあるが、中でも『斧と逢引』は韻律を意識した興味深い作りとなっている。ここで言葉巧みに表現されているのは、朧気になっていく自我と、幻影のせめぎ合いだ。罪の意識に絡み付いた幻影は美しく、しかし現実は残酷で、混ざり合うことのない二つの世界の狭間に立ち尽くす人間の姿が見える。強烈な赤い血飛沫と人間との間に一体何があったのか。斧を振り下ろした者だけが見える景色を、私たちも覗き込むことができる。韻を踏みながら紡がれる言葉に歪さはなく、とても自然な流れで読み進められた。音読してみるとその技術の高さも窺えるだろう。
本書の題名になっている『世界の起源の泉』は、水面を震わせるような甘美な音が聞こえてくる作品だ。文中の空白や平仮名、英語の選択、行の配置。全ての要素が調和して、世界の長い歴史とその始まりを物語っている。水が遥かな歳月をかけて少しずつ湧き出して、土を湿らせ岩を濡らし、広がり始める。深さが増し、やがて小さな泉となる。静かに揺らめく泉は、何物をも虜にする。「ぽと り」と始まったのは果たして地球の歴史なのか、誰かの人生なのか。音と目線を通して視点が広がってゆく様子は厳かで芸術的である。
やがて遠くから自由を、権利を、叫ぶ声が聞こえ始める。最後の章には、プロレタリア詩や現代社会の諸問題に関する詩が多く収録されている。筆者の実体験に基づいたものであり、読めば筆者自身の生い立ちを知ることができるだろう。『プロレタリア詩の誕生』には十六年前の筆者の様子が描かれている。現在の日本の政治や経済の状態は非常に悪いが、それは十六年前も大きくは変わっていない。そして労働者はいつの世も理不尽な扱いを受けて虐げられてきた。私自身もいくつかの職場を経験したが、信じがたい労働環境やぞんざいな人の扱い方は確かに存在する。だが、私はそれを何かで訴えたことはない。そんな私に活を入れてくれるような作品だ。武器を持って攻撃するだけが闘いではなく、言葉ひとつでも社会に抗うことができる。どんな形でも気持ちを言葉で記録しておくことで、時が経っても苦しみを忘れずにいられる。ここに収められた激情はこの先何年経っても残り続け、お高くとまったこの国の政治家の喉元に氷柱を突き付け続けるはずだ。
『匂いとともに棘で刺す――風刺詩人・小熊秀雄に』には権力者に対する批判と共に、我々読者を鼓舞する強いメッセージがあった。中でも同じ詩人として見過ごすことのできない一文があった。「ところで若き詩人は何をもって語るべきか?」という言葉だ。きっと詩以外にあるまい。言葉という武器を詩に仕立て上げ、喜びも悲しみも痛みも増幅させて人の心に刻み込む。
消えてしまいそうな叫びをすくい上げ、詩という居場所を作ることもできる。『わたしが響いている』は二〇二一年に北海道旭川市で起きた女子中学生イジメ凍死事件を基にしている。当時ニュースを見ていた人は、この凄惨な事件を覚えているだろう。被害者の苦しみは計り知れないものだったに違いないが、この詩はその苦しみに寄り添い、共に涙を流す。たとえ長い時が経って事件が風化してしまっても、私たちが詩集を開く限り、言葉は何度でも蘇り続ける。
岡和田氏の詩は氷柱のように鋭く、川のように美しく、波のように激しく、涙のように温かい。そして地表の奥底から一時も絶えることなく湧き出している。そのあらゆる性質を使い分けながら誰かの絶望に寄り添い、光を届け、未来を切り開こうとする。
(初出:「潮流詩派」281号、2025年4月、潮流出版社)