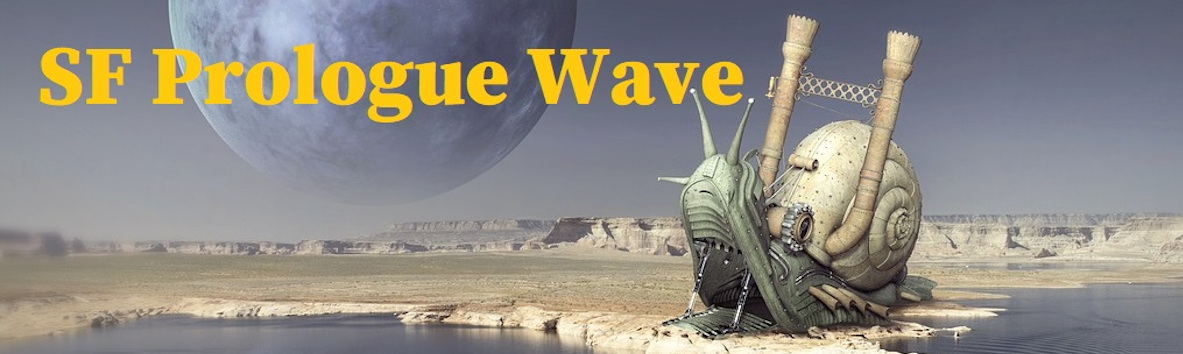SF、冒険小説、歴史小説、妖怪・妖術ファンタジー、サイコミステリ、はてにはパストリー(お菓子)小説など、ジャンルを超えて幅広く活躍する上田早夕里の力作シリーズ「戦時上海・三部作」が三作目となる『上海灯蛾』をもって完結した。今回、三作目となる『上海灯蛾』が文庫化されるのに合わせて、三作すべてを評してみたい。
■「戦時上海・三部作」とは何だったのか?
第二次世界大戦直前の上海とは何を意味するのか?
さまざまな国の意図が交錯し、人種や文化が混ざり合う混沌とした都市である。各国の諜報機関や暴力組織が暗躍する魔都である。当然、血なまぐさい出来事は日常茶飯事であった。
かくいう日本も上海には貿易商や軍人などが多数居住して、それぞれの生活を送っていた。有名なところでは、養神館合気道の創設者である塩田剛三は、自伝の中で諜報員として上海に派遣され、危険な目に遭ったとも書いている。(事実なのかどうかはわからない)
そのような背景を考えれば、ノワール(暗黒小説)の最高の舞台になる。実際、森川久美氏による漫画『南京路に花吹雪』は戦後の日本で書かれた最高の上海作品ではないかと思われる。
では、上田早夕里の「戦時上海・三部作」は、そんなノワールなのかというと、確かに十分によく書かれているものの、決してそれだけではない。ノワールの部分だけを取り上げると作者の意図を確実に見誤るので注意しなければならない。
戦時上海・三部作の背景には、「科学と人間性の対立」という、これまでの上田作品で繰り返し語られてきたテーマがより深く練り込まれている。
つまり、娯楽性とテーマを見事に同居させた、現時点における上田作品の頂点だとも言える。
以下、各作品を取り上げるが、それぞれ完全に独立しているので、順番に意味はない。
『上海灯蛾』
双葉社刊
■利益と交換される命。それが歴史の一面である
芳香異体という特殊な体質を持った女性が存在するとされている。具体的には、何もしていなくても良い匂いを発するとされている。その匂いは桃のようでもあり、金木犀のようでもあるという。二〇一七年、日本のロート製薬により、若い女性が発する良い匂いの正体として、ラクトンという物質が特定された。それは桃とココナツミルクを合わせたような匂いなのだという。
ということは、芳香異体とは、ラクトンが特に多く、ある程度の年齢を重ねても低下しにくい体質なのではないかとも推測される。歴史的には、楊貴妃や西太后がそうだったとも言われている。
さて、他の二作では細菌兵器「キング」、謀略の計画「榛工作」が話の中心に添えられているのだが、本作で中心となるのは、最上級のアヘンを作り出す芥子「最(ズイ)」である。アヘンを扱うとなると、当然のごとく登場するのは裏社会ということになる。戦前の上海で裏社会を描くとなると、裏社会の組織として青幇(チンパン)と呼ばれた、かつて実在した集団が登場するのは必然であるし、本書においても青幇を結束させている義侠という精神と、家と呼ばれるの結びつきが詳しく書かれている。
そして、青幇に「最」を渡すのは、驚くことに芳香異体の日本人女性なのである。渡すと言っても大量の「最」からとれたアヘンと販売ルートなどというお決まりすぎるものではない。なんと、「最」の種なのである。これさえあれば、栽培方法さえわかれば、どこまででも増やすことができてしまう。それが成功すれば青幇が「最」を独占することすら可能になる。もし、独占できるのであれば、ぜひともそうしたいに決まっている。
その当時、日本と中国は戦争状態にあり、関係はかなり険悪だった。日本人が中国人に協力するのは何か裏があるに違いない。だが、その理由が伏せられたまま進み、他の登場人物たちと丁々発止の心理戦が繰り広げられる。
そもそも、なぜ中国人に「最」の種を渡すのか? その理由と狙いは何なのか? どこから「最」を持ってきたのか? このような謎に満ちた人物なので、当然、色恋沙汰は起こらない。たしかに、物語の中心にいるわけなのだが、決してヒロイン的な立場ではなく、したたかで食えない人物として、体質的に異性を魅惑しながらも決して色香で惑わせるようなことはしない独特な立場にある。この女性が人物が男ばかりの中で特異な位置に立ち、読者にとても強い印象を残す存在になっている。
しかも、悪いことに女性が「最」を中国側に渡した理由が謎のまま青幇と日本軍(現代の日本に「軍」は無いので旧軍のことなのは自明である)が自分たちだけで「最」を独占しようと大規模な殺し合いが始まる。上海という土地で麻薬による利益を独占しようと、毒蛇と毒蛇による壮絶な殺し合いが始まるのだ。
こんな血なまぐさい抗争が起こってしまうような「魔都」としての顔も持つ上海は、作者によってこう説明されている。
「男たちがそうであるように、女たちもまた、金と出世の欲望を胸に、上海租界の灯りに群がってくる蛾なのだ」
本書に登場するのは、全員がそういった蛾である。ある者は富のために、ある者は理想のために、殺人ですら厭わない。
ここで描かれているのは、正義をなしとげるために行われる麻薬流通という巨大な悪事、さらに正義のための戦争という大量虐殺と破壊である。大量虐殺の後には麻薬中毒患者が残されるという二重の犯罪である。そんな矛盾をなんとも思わないどころか、その矛盾を大きくしようとしている愚者による壮絶な騙し合いと殺し合いである。人間の業はどこまでも深いのだ。しかも「最」が作り出された背景も興味深い。とてつもなく大きな陰謀と計画が隠されていることがわかる。そんなことが知られてしまったら国際的なスキャンダルになりかねないので、「最」の出所となった組織も必死で女性と「最」の回収へと動く。
このように、各勢力の思惑が入り混じり、陳腐な表現だが、血で血を洗う抗争になる。その描写は容赦なく、かなり凄まじい。その背後にある命すら犠牲にする価値観を作者は登場人物にこう話させている。
「人はみな憐れなものだ。だからこそ、それだけでは終わるまいとして、あの手この手で図太く生き延びようとする」
昨今、民族と国籍と思想がすべて同じでないと異端にされるような風潮がある。本書では、どれかが違いながらも事情によって、どこかの集団に入り民族と国籍と思想を合わせているような奇妙な現象が描かれている。これはどこかに属していないと不安になるし、社会での生活が立ち行かなくなるためなのだが、どこか滑稽であり、悲劇的でもある。
そんな奇妙さを説明しているのは、次のようなセリフだろう。
「日本は小さな国だ。国土が狭いという意味だけでなく、その国民性も多民族国家と比べると限定された範囲に留まっている」
かつて存在した華やかさと混沌、犯罪にまみれた上海租界の中で行われる重層的な話の中で最終的に利益を得るのは誰なのか? 誰の得になるように仕向けられた殺戮合戦なのか? 女性が起こした行動の根源には何があるのか? それは本書の中で確かめていただきたい。
最後に、この事には触れておかなければならない。本書のもう一つの主役とも言えるスィングジャス(ビッグバンドジャスとも言う)が扱われている。ちょうどこの頃に誕生し、世界中で愛好されたのだ。ネットなどで聞けるので、雰囲気を味わうことができるだろう。ぜひとも、ベニー・グッドマンやグレン・ミラーの作品を聞いてみてほしい。きっと、どこかで耳にしたことのある曲だと思う。
多文化が同居しつつ栄えている華やかさの一部が味わえるに違いない。
『破滅の王』
双葉社刊
■道具が作られるのは「使われるため」である
ここ最近は変わってきているが、もともとなぜ道具が作られるのか? これについて考えてみたい。
「だいたい、道具って使うために作られるんちゃうの?」
さて、これ以外に合理的な説明はあるのだろうか?
「使われない事を前提にして作る」というのは、技術や資源、知識の無駄遣いでしかないのだが、この数十年、明らかに価値が変わっていることにお気づきだろうか?
その最たるものが兵器である。核兵器などは過剰生産がすぎていて無駄以外の何物でも無いし、進んで使いたい人はそうそういないだろう。これは生物兵器や化学兵器にも同じことが言える。「使う気はないけど、持っているだけで価値がある」。それって何なの? としか言えないけど、現実には暴力団がタマ数を揃えて脅かし合っている状況と何も変わらない。
と、ここまでは本書を語るうえでの前提だったりする。
本書で話の中心となるのは「治療薬が無い生物兵器」である。第一次世界大戦でドイツが塩素ガスを化学兵器として使い、第二次世界大戦ではついに核兵器まで使われてしまった。化学兵器は限定的に使える可能性もあるのだが、核兵器や生物兵器となるとそう上手くはいかない。なぜかというと、使った側が後のことまで責任を取れないからである。生物兵器がパンデミックを起こす、核兵器が使えない土地を増やしてしまうなど、危険が大きすぎるのである。
特に生物兵器は、兵器そのものの威力と治療法があるという点が矛盾しているために特に危険だ。
そんな危険極まりない兵器を開発すること、実際に使ってしまうこと、こんなことはありうるのか? 著者はその「イフ」を投げかけてくる。
舞台は第二次世界大戦中の上海租界、そして華北から始まる。主役は悪名高き「石井部隊」。後に森村誠一氏の「悪魔の飽食」によって日本人に大いなるショックを与えた問題のドキュメンタリーがある。それが、
『悪魔の飽食 日本細菌戦部隊の恐怖の実像!』、森村誠一著、KADOKAWA
である。
満州に置かれていた「731部隊」が細菌兵器の開発と実用を促進するために「マルタ」と呼ばれた捕虜や現地人などを人体実験の道具として用いていたというとても衝撃的な内容である。すでに証拠も揃っているので全否定できる人も少なくなってきている。
本書では「キング」と呼ばれる極めて致死性の高い細菌兵器をめぐる諜報戦を描いている。特徴的なのは、細菌の開発者が、その情報を分割して多数の国に分配してしまうという異常事態によって連鎖的に数々の事件が起きてしまう点である。
「この細菌を独占し、人類滅亡の危険を顧みずに使うのか?」、それとも「各国が協力して情報を統合し、治療法を発見するのか?」。そんな困難なパズルを開発者が世界に問いかけ、自らが命を絶ってしまうのである。ここで「戦争に勝利するという短期的な利益を狙うのか」と「人類滅亡を避けるために長期的な利益に立つことができるのか」という究極の選択肢に直面し、関係者の思惑が交差して事件が複雑になっていく。
著者の視点はあくまでも冷徹で容赦がない。局地的に使われてしまった細菌を封じ込める地獄と、積極的に使用を拡大しようとする悪魔的な思惑が作り出す一大戦争の地獄が出現する。もちろん、こんな情報が公になれば世界中がパニックになるので、細菌をめぐる戦いは局地的な諜報戦と封じ込め作戦、使用を妨害する工作などが中心となる。
見えない大量殺戮兵器との戦いになるので、とても地味に見えるかもしれない。実際、本書ではとても根気がいる地味な細菌研究、撲殺や惨殺、銃殺は当たり前といった危険な諜報戦が繰り広げられる。細菌や個人の思惑といった見えない敵と戦うシリアスさと緊張感は凄まじい。
兵器開発が暴走して人類が滅んでいくのは簡単だ。しかし、そこで生き延びるため、防疫を最重要視するために感染したという理由だけで焼かれる人々が必要になってしまう非道徳的な部分からも著者は逃げていない。それを必要悪などと言い切ることなどはできない。あまりにも残酷すぎるのだ。本書に出てくる「キング」は苦痛を与えない死を許さないほどに残忍な存在なのだ。
では、どうするのか?
本書において、大局的に判断できる人はいない。単に戦争で勝ちたいから使う者、自殺欲の延長として「人類に対する審判」だと言い切る者、研究者として医師として命を守るために治療薬を研究する者が、それぞれの論理で動くわけである。意見が一致するはずもない。
では、著者が下した結論は何か? ネタバレを避けるために書かないが、「世界はキングの脅威から、偶然によって助かったにすぎない」としか解釈できない結末が待っている。
この結論は決して安直ではない。これまでにキューバ危機や大規模テロをきっかけとした報復戦合戦など、世界戦争に発展しかねない事件は数多く存在した。現在、なぜ我々が生きていられるのか、「そんなものは偶然にすぎないんちゃう?」と問われたら、反論できないのは事実だ。
とても地味で汗臭い小説なのだが、世界とは? 戦争とは? 兵器とは? を熟考するための機会になってほしいと願う。
『ヘーゼルの密書』
光文社刊
■普通という名の狂気、個人という名の自由
間違いなく、本書は「今の日本だからこそ読まれるべき一冊」である。
人は誰もが安心を求めたがるものである。安全であることを優先するためにはたとえ誰かの犠牲が必要なのだとしても、実行される際にはまるで関係はなくなる。
後になって間違っていたと知っても、「あの時にはそれが正しい道だと思った」、「その時は逆らえなかった」 などと弁解しがちだ。自分で自分の失敗を認めるのは困難なことなのだ。それであるがゆえに、「後悔先に立たず」とまで言われるのだ。
世の中から犯罪は無くならない。計画的なものであろうが、衝動的なものであろうが、起こしてしまった以上、「それが悪い(間違った)事だとは知らなかった」では済まされない。では、犯罪から人を遠ざけているのは何だろうか? 答えはわからない。倫理でも道徳でも法律でも、中止する、または思いとどまる理由はたくさんある。だが犯罪は無くならない。
個々人の犯罪ですらこのような状態なので、紛争や戦争でも同じロジックが使われるし、国民・民族・思想など集団的な行動となるので事態はいっそう厄介なことになる。そこには「自分が正しい」という信念を周りの人たちが認めてくれるから、という安易すぎる思考の怠慢が存在する。安直に右に習えの態度で自分の半径十メートルの範囲で「普通」だと解釈されれば本人は安心できるかもしれない。そういった同調圧力の中で平穏に過ごせるから、集団に属するというのは楽なのである。
したがって、戦争や紛争、テロなどでさえ、半径十メートルの世界で普通になれるのであれば簡単に従ってしまい、どんな酷いことでも可能となる。それが半径十メートルではなく、半径千キロメートル、総人数数千万となると、従わない選択肢を取るのが極めて困難になる。なぜなら、自分が普通ではないという理由で排除されてしまうからである。
さて、感想はこれくらいにしておいて本書の内容に入る。
満州国が誕生した後、日華事変が起こった頃、すでに世界大戦の予感を感じる人々は少なくなかった。人によってはそれを是とし、中には否とする人々もいたが、多勢に無勢であり、転び始めた雰囲気に対抗するのは至難の業だったと考える。
それは本書のなかでも様々な形で現れる。八紘一宇を本気で信じている一派と、反人道的な大量殺戮でしかない戦争は絶対に避けなければならないと考える一派が、当時の上海租界で繰り広げる諜報戦が描かれている。諜報戦は非常に地味で表に出てこないものなのだが、古来から情報収集と交渉に通じた人たちの手によって戦争が回避されたり、半ば強制的に戦争に突入したりと、その後の結果に関わるとても重要な活動である。
本書は、日中間の和平派が中心となっているが、もちろん反対派の横槍や、相手国とのすり合わせなどの苦難を味わうことになる。結果は史実のとおりなので触れる必要は無いだろう。
本書で繰り広げられるのは、大量殺人行為を中止させるために命をかける人物、それを潰すためならどんな非情な手段でも使ってくる人物、間で考えが変わってしまう人物、矛盾したまま流れに関わってくる人物など、様々な登場人物が関係し合う群像劇であり、心理劇である。
主人公は上海租界にある語学学校で教師を務めている女性である。交渉にはどうしても通訳が必要になるので、彼女に白羽の矢が立ったのだ。当時の日本本土であれば「祖国に逆らうなんて!」ともなりそうな話だ。しかし、国際感覚を身に着け多様な文化に接しながら生きている主人公の心境は、次の一言でまとめられる。
「普通じゃないことが、これほど楽しく、幸せだとは想像もしていなかった」
この一言は、息苦しい社会の中で生きる我々にとって、どこまでも魅惑的だ。これ以上に重要な動機は存在しないのではないか? と考えてしまうほどに自由なのだ。自由であればこそ、非人道的な戦争を回避させるという危険な諜報戦に関わる強い動機となりえるのである。
自由であるがゆえに合理的かつ常識的に行動ができる。これこそが本書の肝であるのではないか。
ではなぜ日本にとって到底勝ち目の無い戦争に突入してしまったのか、本書のセリフが強烈に指摘してくれる。
「絶対に無理だと言われない限り、人間は、とんでもない選択をしてしまうものですよ」
こんな事態を二度と繰り返さないよう、とにかくまともでいる努力、冷静かつ理性的である努力を欠かしてはならない。
「とにかく、考えるんだ。自分の頭で。ただし、人の意見は聞き入れて、お互いに十分に納得する・同意する努力も忘れるな」とだけは書いておこう。
※※ 参考文献 ※※
上田早夕里・岡和田晃・大野典宏・長澤唯史、「歴史記述とフィクション」、図書新聞、3596号
なお、「破滅の王」および「ヘーゼルの密書」の評は、かつて存在した書評Webサイト「シミルボン」に投稿した文章に一部手を入れたものである。