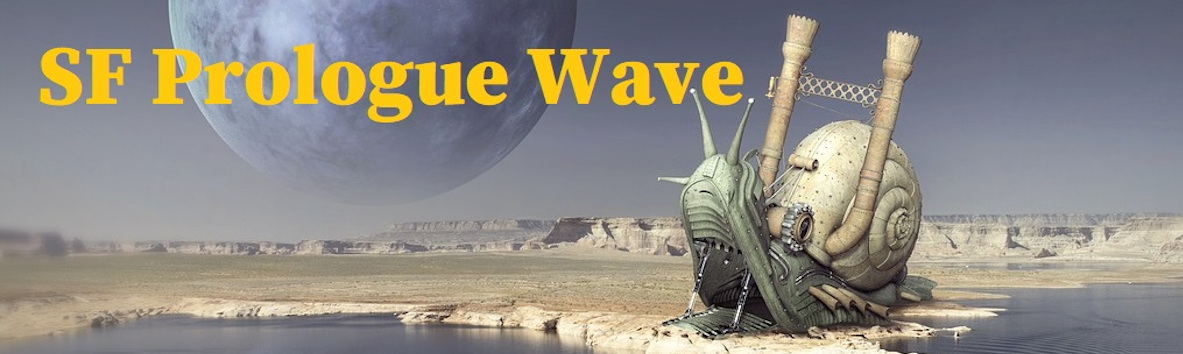クトゥルフものだからこそのゲームブック――大瀧啓祐『暗黒教団の陰謀』書評 思緒雄二
まず最初に本作における幾つかのウケ要素について端的に説明させてください。
初心者でもOKか・・・クトゥルフ神話の予備知識がある人、特にそのTRPGなりをプレイしたことがある人じゃないとキツイです。主人公が理不尽に、あっけなく死ぬことをもって醍醐味として愉しめなければ難しいかも。
一般人に受けいれられやすい内容か・・・上記前提を満たして諦観なり達観なりマゾなりできる方には、受けいれられるでしょう。
再読したくなるスルメ作品か・・・すぐ死ぬんで。とりあえず1、2回は、まず再プレイする人が多いはず。
このゲームブックで何度か出くわす「事前の手がかりも無く、あっけなく死ぬ」ということ、無力感は、クトゥルフ神話を代表とするコズミックホラーというジャンルだからこそ許されるものなのかもしれません。
〝まだ隣の惑星にすら進出せず、ほとんどが狭い地球にのみ暮らしている人間たち。
ごく僅かの例外である宇宙飛行士すら、地球周回軌道のステーションでへばりつくよう棲息するのみ。
そして地球の歴史を一年間にみたてれば、大晦日の午後11時37分に出現した超新参者ホモサピエンス。
万物の長と錯覚してるヒトというヤツらの、なんと小さく無力なことか・・・・・・〟
の前提のもと、それを思い知らせるのが外宇宙の神々(アウターゴッズ)や、人間に比べれば圧倒的に長く地球を支配していたクトゥルフ等の旧支配者たち――というのが、クトゥルフ神話の設定。
「彼らにとって、人間の生死など、そもそも普段の意識にすらのぼらない。そう(敬虔なジャイナ教徒とか特殊例を除き)アリをふんづけて大さわぎする人間がいないよう。
クトゥルフにとって人間の銃器など、蚊に刺されたほどのものでもない。核攻撃を受けてすら、クトゥルフは1日もたたず復活するのだから」
というのが、私が初めてケイオシアム社のクトゥルフRPGオリジナル英語版をする時に、キーパーから教えてもらった説明です。(キーパーとは、ケイオシアム社のクトゥルフRPGにおけるゲームマスターの呼称。TRPGでシナリオを管理、プレイヤーを導いて物語をつむぐ役割の人を指します)
ちなみに彼は、ケイオシアム社のクトゥルフRPGを最初に日本語に翻訳する仕事をし、その後、ケイオシアム社公認のオリジナル日本版クトゥルフRPGを出した人間でもあります。
今はどうだか知りませんが、少なくともそのころのクトゥルフRPGは絶望と対峙する人間のあがき、そのものを愉しむようなゲームでした。ぶちあけて言えば、どんな死に様でキメるか、であって、生き残れば奇跡というカンジです。
クトゥルフを夢の中で見てしまっただけで発狂したり、カルト教団へ潜伏調査してたらニャルラトテップの股くぐりさせられて潰されたり、シャーロックホームズがもつ変人要素はクトゥルフ神話の知識と引き替えだったり・・・と、様々に愉快な体験をさせてもらいました。
ゲームブックが乱造されてた時代「事前の手がかりもなく、アッサリ死ぬ。サイコロすら振らせてもらえない」という作品が、普通に多かった印象があります。自分も(一応)作者側なので、なぜそんなものが多かったのか、わかります。
編集者は「じゃあボリュームは200~300パラグラフぐらいで」と発注し、書き手側は、かんたんにパラグラフ数をかせぐため、またメインストーリー以外のサイドストーリーを引っぱるのは面倒なので、安易にデッドエンドをつくって終わりにしたいのです。
しかし、これは読者の目線にたってない創作方法であり、単なるノルマをこなして早く原稿料が欲しいだけとみなされて仕方のない方法。読者を、そしてなにより物語を大事にしていない。
こんな粗製濫造が続いたのも、ゲームブックのもつ表現的可能性を狭め、衰退をまねいた一因かもしれません。
けれど本作は、こうしたデッドエンドがあるにも関わらず(〝要予備知識〟という条件付きではあるものの)一定のクオリティを保っています。
冒頭述べたよう、それは、しっかりした世界観の下支えがあるからに他なりません。
世界観があり、そこを逍遙し、あそぶ人々がおり、その目線にたっている部分があるので、たとえ唐突な横死があろうと作品の雰囲気をたのしめる。
また、モノクロで描かれたイラストがいい。原作者ラヴクラフトの生きた時代の雰囲気が、とてもよく出ています。
結論として、クトゥルフ神話が好きな人、とりわけ『インスマ(ウ)スの影』を読んで気にいった方にとっては、あそんでみて損のない作品と言えましょう。
もっとも、シュルズベリィ博士も登場するし、メインストーリーのエンディングには(クトゥルフ神話比で)それなりの達成感も用意されています。
そういった意味で、別のレビューで紹介したギリシャ神話モノのエンディングである悲劇ゆえのドラマ性とは、また別のものであり、ノーマルな〝ゲームのクエスト達成エンド〟。
なので、ダーレスの『永劫の探求』をも愉しめる人が、より適してるかもしれません(同じクトゥルフ神話として一緒くたにされがちですが、ラヴクラフトとダーレスには、世界観の雰囲気に大きな差があると個人的に感じています。ダーレスの方が、より〝ゲーム的〟といったカンジでしょうか)。
自分は、ラヴクラフトという作家に関しては書きたいことがもうすこしあります。
ですが、それは書評という枠組みをこえ作家や時代論にまで関わっていくことになるでしょう。
よって今回は、ここで、ひとまず筆をおかせていただきます。
(初出:シミルボン「思緒雄二」ページ2016年3月23日号)
採録:川嶋侑希・岡和田晃