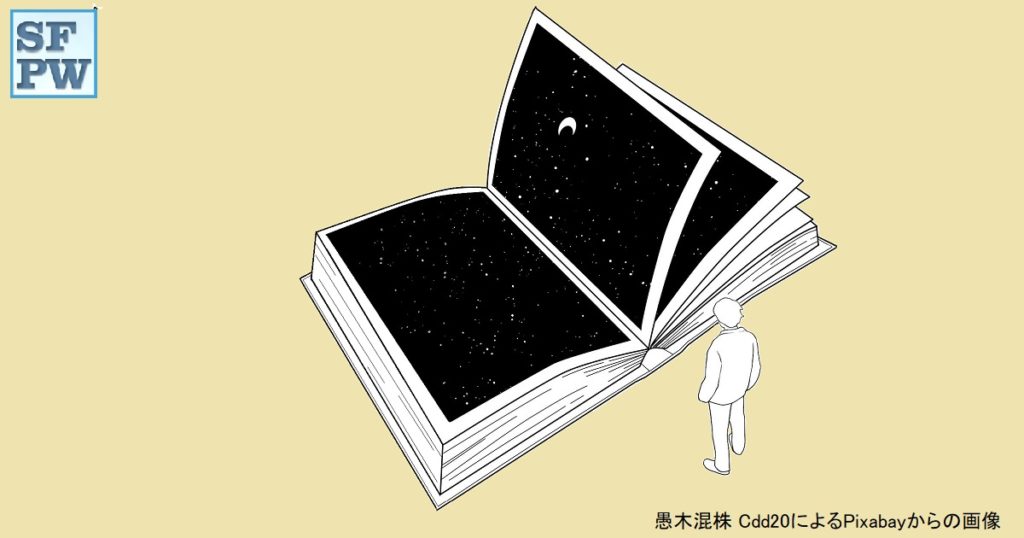
書けないのが哀しいのか、もう書かなくていいことにほっとしているのか、それさえ、よく分からない。そうした混乱した気持ちを整理するためにこそ、以前はよく書いていたのだが、そのクールダウンの方法は今はもう使えない。ただただ、心のなかで反芻(はんすう)することができるだけだ。
書いているかのように考えることができたら、落ち着くことができるだろうか。
ことの初めから順番に、誰かに話しかけるようなつもりで考えてみたら?
あのとき、いや、あれがまだ、たった二日前だってことが信じられないんだが、ともかく、あの日は賞の締め切りが近い原稿を前に、なんとか次の展開を思いつけないものかと頭を悩ませていた。文芸サークルの仲間のなかには、小説を書き始める時にはストーリーがラストまではっきり見えているって奴もいたが、自分は、ぼんやり浮かんでいる話の筋を、書きながら補強していくタイプだ。何気なく書いた一行のために、その後の展開がまるで変わってしまうことも珍しくない。だから、いちど流れが詰まってしまうと、それまで書いた文章を何度も読み返しては、良い打開策がないか悩み続けることになる。たとえは悪いが便秘中みたいなもので、出そうで出ないのが気持ち悪いから、昼飯も食わず、空きっ腹をかかえて、脳にかかった霞のような障害物めがけて突撃をかけているところだった。
その最中での突然の暗転。
すべての文字が読めなくなった。
まずは文字変換キーを打ち間違えたと思い、いつまでも直らないので、パソコンが壊れたと思い、そのわりには黒い線形が鮮明かつ精緻に並んでいるのが不思議で、脳の障害かもしれないと思ったら怖くなって、救急車を呼ぶべきかと悩んだけれど、すぐに電話がかかってきた。
「おい、おまえ、文章、読めるか?」
タカシだった。保険会社に入社して二年目、まだまだ新人扱いだろうに、昼間から私用電話をかけてていいのか、と普段なら突っ込んだところだが、このときはそんな余裕がなかった。
「何で、そんなことを訊く?」
「読めるのか、どうなんだ」
「読めない。おまえは?」
そこから一人でしゃべりまくり始めたタカシの話は、全然、要領を得なかったが、自分だけがおかしくなったわけじゃないらしいと知ることができた。
その後、テレビニュースで全世界が失読症にかかったと知らされた。何が何だか分からないまま、とにかく、まずは食料を確保しようと近所のスーパーマーケットに出かけたが、動きが遅かったせいか、どこも臨時休業中。数日前に、親が山ほど備蓄食料を送りつけてきていたから、しばらくは食いつなげるだろうと思って、部屋に戻って寝てしまった。
次の日は朝から断水、電車も止まって、電話は生きてはいるようだったが、話し中で大混乱だった。アルバイト先のレストランにもつながらず、直接、出向いてみると、入り口に臨時休業の札がかかっていた。ほかに行くあてもなく、卒業以来はじめて大学へ足を運んでみたものの、教授もサークルの後輩たちも、みんな不安がっているばかりで話にならない。そもそも、なぜこんなことになったのか、宇宙からの放射線が脳の一部を破壊したっていう説が有力らしいが、与太話の域を出ない。開いているスーパーがみつかったというんで、後輩たちと出向いてみた。
そこはスーパーというより個人営業の八百屋だった。値札の表示が数字じゃなくて、紙幣やコインの写真になっていたのが面白く、売れ残っていた酢昆布を買うため行列に並んだ。親しい後輩に「今、この状態で、それを買います? 買っちゃう? 買わなきゃならないものですか?」と呆れられたが、この酸っぱさ、嫌いじゃない。それに、昆布って放射線障害に効くんじゃなかったっけ? 今から食っても意味ないか。
「ここみたいな小さなお店が頑張ってるんだから、全国チェーンのスーパーだって、お店を開けてほしいですよね。ああいうところって、今どき、オートレジじゃないですか。スキャンで値札を読み取ればいいんだから、文字が読めないって関係なくないですか」
「大企業はかえって泡くってるさ。全国津々浦々のオートレジからデータは本部に自動で集計されるんだろうが、その後、販売数量やら金額がいっくら画面に表示されたって、それを担当者が読めないんだから。実績まとめたって偉いさんが読めないし。それじゃ、何のために売ってるんだ、損してたって分からないだろって話で、方針決まるまで、めっちゃ時間かかるね。今ごろ、二十四時間耐久レースみたいな会議してるさ、きっと」
「先輩、この事態を楽しんでませんか。いつまでもお店が開かなかったら、みんな、困るのに」
急に声のトーンが高くなった。さっきまでは一緒にふざけていたはずなのに、どうしたわけか、後輩の目は赤かった。他の奴らも口に出しこそしないが、俺の態度がこの場にふさわしくないと感じているようだ。
「おまえ、冷静だな」
そういえば、電話の切り際、タカシも言っていた。
そうかもしれない。
就職活動もせずに小説家になりたいなんて言い出して、あてもない生活に入ったくせに、もう二度と、文字を読めない書けないかもしれないという事態に対して、あまり感情を動かされていない。なぜだろう。まだ食いもんの心配をしないですんでるからかもしれないが、それだけじゃなくて、今回の事態は、こと自分にとっては想定外ではなかったからかもしれない。
後出しで予知能力者を気取ろうってわけじゃない。人類が文字を読めなくなる日がくるなんてこと、予知できるはずがない。そうではなくて、昔からずっと不思議に思っていたことがあるのだ。
物心ついてからの活字中毒で、朝起きてから夜までずっと本を読み続けてきた。朝食時には親父の手から新聞を奪い、授業中は教師の解説を聞いているのがまどろっこしくて教科書の先を読み、休み時間には図書室で本を読み、家に帰って寝るまでには借りてきた一冊を読み終えた。人から趣味を訊かれて答えられず「読書だろ」と言われた時、読書を趣味に入れるのは変な気がしたものだ。まるで食事が趣味と言われたみたいだった。そんな人間はきっと、俺だけじゃないはずだ。
我が輩と同類である、本の虫諸君。
君たちは、よる寝ている間に、本を読んでいる夢を見たことがあるだろうか。
いや、本でなくてもいい。夢の中で何かしらの文字を読んだことがあるか?
自分には経験がない。
テストを受けている夢を見て、どっと疲れたことはある。だが、そのときもテストの紙面を眺めてはいたが、問題文を読んではいなかったと思う。小説の主人公になりかわって活躍する夢は見たが、その小説の文字の一つずつを目で追っていたわけではない。
日常生活のほとんどの時間を「文字を読む」ことにあてている人間が、夜の夢では一度も、その行為を経験しない。それこそがつまり、どんなに慣れ親しんでいても、文字の読み書きが、動物としての人間にとって、ものすごく不自然な行為である証しではないか。ある日とつぜん、できなくなったって、おかしくはない。
子どもの頃、友達はたくさんいたが、自分みたいに小説を読む奴はいなくて寂しかった。漫画やアニメの好きな奴とは話せたけど、相手の好きな漫画の話はできるのに、こちらの好きな小説の話にはならなかった。小説なんか読むのは変わり者だけだから仕方ない。子ども心に諦めていた。その環境が一変したのが大学だ。周りに本好きがたくさんみつかって嬉しかった。文芸サークルにも入ってタカシとつるむようになった。
なのに、ちくしょう、あのコロナ禍だ。大学の講義はあっという間にオンライン、半年ぐらいで元に戻るかと思えば、結局、卒業するまで影響が残った。不完全燃焼な大学生活。
本だけはたくさん読めたが、いくら本好きでも、人は本のみにて生きるにあらず、だ。旅行だって飲み会だって、もっとたくさんしたかった。就活しなかったのは、そのせいだと思う。ろくに楽しむこともないまま卒業というのが納得いかず、大学時代がクソだった分を取り戻したくなった。
学生時代はお遊びで短篇を書いていたが、長篇に挑戦したのは卒業してからだ。初めて応募した賞で一次選考に残り、小説誌に名前が載って有頂天になった。だが、次の作品は単なる落選。それでも何とか心を奮い立たせて三作目に挑戦している最中に、この失読症騒ぎだ。祟られてるのか、呪われてるのか、いい加減にしてほしい。
漫画はいいよな。ストーリーを絵だけで見せることができる。映画も台本がなくたって、即興で撮るという手法があるだろう。けど、小説は駄目だ。文字なしで小説をどうやってつくる? 水のない海ってぐらいの絶対不可能事だ。
デスク脇の本棚には、ついこの間、本屋でみかけて衝動買いしただけ、まだ読んでもいない小説の書き方のハウツー本もあれば、わざわざ実家から持ち出してきた愛読書もある。タイトルは読めなくなったけど、「シートン動物記」は背表紙の色から他の本と区別がついた。
このまま文字が読めないなら、もう二度と、これらの本を手にとることはないだろう。「狼王ロボ」だって読めない。ブランカを亡くしたロボの咆哮(ほうこう)を、心の耳に聞くことは二度とない。今となっては、ここにあるのは単なる紙屑だ。場所ふさぎの、分厚くて重い、処分に困る紙の束だ。でも、捨てられない。肉親が死んでしまって、もう話すことができないからと言って、その体を粗末に扱うことができないのと同じだ。
それでも、いつかは捨てるかもしれない。日に焼けて変色し、虫に食われるだけなら、捨ててしまったほうがいい。親の遺体だって、いつかは焼くんだ。ここにある本だけでなく、世界中の本屋、図書館、学校、何億冊という本が焼かれることになるんだろう。
こんなことで焚書が起きるなんて、始皇帝もびっくりだ。
世界中にあがる、たくさんの大きな炎。
いやいや、まだ永遠に文字が読めなくなると決まったわけじゃないのに考えすぎだ。コロナ禍が始まった頃も、未知のウィルスによる人類破滅物の映画や小説を連想したせいで、さんざん悲観論をぶちまくってタカシに笑われたじゃないか。
俺の理性はそうツッコミを入れてきたが、いやあな気分からは逃れられなかった。こういう時こそ本でも読めば、頭の中身を強制的に入れ替えられるんだが、小説どころかスマホでネットも読めやしない。
このまま散らかした部屋のなかに閉じこもっていたら、頭がおかしくなると思って外に出た。最初はどこへ行こうという気持ちもなかったが、歩いているうちに目的地が定まった。閉鎖されている遊園地の動かない観覧車を見上げながら、大通りを進む。
脳にたまった熱を発散させるのに、ウォーキングは絶大な効果があるものだ。少し気分が浮上してきて、東京ドームの前を通り過ぎる頃には、今日の夕方、野球はおこなわれるかな、と疑問に思う余裕があった。スコアをつけられなくても野球自体のプレーは可能だ。なんとしてでも野球を観たい層がいる以上、今日は無理でも、いずれ野球の試合は復活するだろう。スポーツが趣味の奴らがうらやましい。
お目当ての場所に到着したのは三時前だった。こんなところに来るような酔狂者は自分くらいだろうと思っていたのに、通りには意外なくらいの人がそぞろ歩きしていた。多くは中高年男性で、いずれ自分もこんなふうになるかもしれないと想像し、いや、そんな未来は絶対にないと打ち消した。失読症がこのまま続けば、自分はもう絶対に小説家にはなれないし、小説家志望で居続けることさえできない。であれば、平日の昼間からこの街をうろうろできる身分になれる見込みはゼロだ。
この街に初めて足を踏み入れたのは、大学に入学した年のゴールデンウィークだった。帰省するのは交通費がもったいないし、といって、アルバイトはまだみつけておらず、サークルにも入ったばかりで、休みのうち一日はタカシと遊ぶ約束を取りつけたものの、ほかに予定がない。さて、どうしようかと迷ったあげく、行きたいところとして思いついたのが神保町だった。
夏のように暑い日、今のようにせっせと歩いた後、喉が渇いたと自販機を探して目を泳がせて、自分が書店街のどまんなかにいることに気づいた時の、あの驚きと喜びは忘れない。通りの端から端までが本屋なのだった。ビルの一階が書店というんじゃない。ビル一棟丸ごとが書店なのだ。自分の出身地なら、親に車を出してもらって電車も乗り換えて丸一日がかりで出かけていかなければお目にかかれないような大型書店、小さな町の文化レベルを一店舗で支えているような巨大書店がずらりと並んで、歩道にまで安売り文庫を並べたワゴンがはみ出ていた。
あのころは大学に受かったばかりで、自分の将来にも無限の希望を抱いていた。やってやるぜ。何しろ、もう二度と数学を勉強しなくていいというだけでテンションは上がりまくりだった。これから自分の気の向くまま、何を読んでもいい時間が四年間も続くのだ。
天井にまで届く書棚には「歴史」「文学」とジャンル名が割り振られていた。びっしり並んだ茶色い箱には「平安文学解明」「仏教史」「関東地方の交易」と厳めしい題名が筆書きされている。そうかと思えば、「映画・サブカルチャー」の棚には、芸能人へのインタビュー、業界裏話、アイドルのグラビア写真集、、人気ドラマの脚本などがビニールのかかった状態で並んでいた。「ビジネス」には「できる上司になるには」とか「組織のまとめ方」とか、時間の有意義な使い方のマニュアル本がまとまっていた。
何を読もうか。専攻の社会学については生協で教授の本も買ったことだし、とりあえず置いておくとして、他に何を読めばいい? 会社で出世する方法が必要になるのは、まだ先だ。今はカタカナタイトルの哲学でもかじってみようか。それとも、ビギナー向けの宇宙論に手を出すか?
全部、読みたい。
腹の底が焼けただれるような、鼻の奥がつんとするような、じっとしていられない欲望を感じた。目の前に、世界の広さ、奥深さが広がっていて、手を伸ばせば、その一つに入り込むことができるのだ。
五年も前のことなのに、鼻息荒く書棚の前に立っていた時のことは鮮明に思い出せた。
あの時から、何と遠いところまで来てしまったんだろう。
同じように神保町に来て、書棚の前に立っている。大量の背表紙が目に見えている状況は変わらないのに、タイトルを読んで理解することができない。
トマトとキュウリの絵が貼られた棚は家庭菜園のコーナーだったらしいが、ほとんど売り物が残っていなかった。きっと、写真やイラストの多い本から売れていったのだろう。目端のきく奴ってのはどこにでもいるもんだなと感心しながら、出口に向かうと、レジにはGジャンを着た、初老のおっさんが呆然と座っていた。
店長か、それとも長く勤めた従業員なのか。この人にとっては生活がかかってるんだから、そりゃあ、魂が抜けたみたいになっているのも無理はない。この状態がいつまで続くのか、明日には元通りになっているんじゃないか、と思い続けて三日目だ。これが一週間続くことも、一ヶ月続くことだってありえる。コロナは新種のウィルスによる病気だってことは分かっていた。今回のこれの場合は、感染症なのか放射線障害なのかさえ分からない。
結局、何も買わずに書店から出てみると、きちんとスーツを着込んだエリートサラリーマン風の男が店に向かって敬礼していた。
そのまま店には入らず、さっさと立ち去っていく。
その後を追いかけて「おい」と呼びかけ、それでは喧嘩になると思って「すみません」と切り替えた。
「何ですか」
穏やかに訊き返されて、慌てるしかなかった。自分がなぜ追いかけて声までかけたのか、分からなくなったからだ。
「頭下げてたのは、あれは、えっと、どうして」
しどろもどろな問いかけに、その男は「墓参りです」と言い切った。
細面の白い顔に銀の眼鏡、細い目に小さな口、白い狐が人間の顔をもったら、こんな顔なのかもしれない。
「鉄筋コンクリートのビルって墓石に似てますよね」
「ね」と同意を求められても、何と答えるべきなのか返答に迷う。
男は去っていった。
若い頃、この書店街に通い詰めていた男が感傷的になって、馴染みの本屋の最後の姿を見にやってきたというあたりが正解なのだろうけれど、醸し出す空気が人間っぽくなかった。もしかしたら、近くの稲荷神社から神さんの使わしめがやってきたんじゃないかと想像してしまった。
このまま、人類は滅亡しちまうのかもしれないな。
ふっと、思った。
ミサイルとか核兵器とか原発とか、文字なしで何ごともなく維持できるとは思えない。それだけじゃない、文字がなくなれば、法律が消える。教育もできない。水道が止まったのは法定の水質検査ができないからだとニュースで言っていた。鉄道だって、誰も駅名すら読めない状態で、どうやって運転再開するんだ?
それとも、一時期を乗り切ったら、何とかなるもんだろうか。いろんな産業で自動化が進んでるんだし、人間が書類なんか読まなくても機械が勝手に判断していくかもしれない。そもそも、百年前は、字が読めない人が多かったわけだ。究極のところ、食いもんさえ確保できれば、あとは何がどうなってもいいわけで。
そうしたら、その後はどうなる?
不意に、強い衝動が突き上げてきた。
生きてやるぞ、という決意だった。その昔、本屋丸ごと、全部の本を読みたいと願った時の荒々しい気分がよみがえったかのようだった。
何百年、何千年も積み重なった知識の恩恵はなくなるが、同時に、その知識を引き継いで伝えていかなくてはいけないというプレッシャーも消えるんだ。
何があっても生き抜いて、できたら子どももつくってやろう。
その子たちは、文字なしで生きる第一世代だ。
そいつらがどんなふうに育つのか、見てみたい。
文字を覚えなくていい子どもは何を覚えるんだ? 教科書なしの学校では何を教える? 法律のない社会で、人間はどうやって秩序を保つんだろう。
くそ、書きたいな。
この一年で、最も激しい執筆意欲に襲われた。
文字ってのは、まだ形をもたない頭のなかのもやもやした霞みたいなものに、形を与える、いちばん簡単な方法だ。書いておかなきゃ、忘れるじゃないか。
くそ、くそ、くそ。
一作目のときのような、自分は今、やりたいことを思いっきりやっているぞ、という喜びは消え、二作目のときのような、今度こそ受賞してやるという執念さえ消えていた。どうせ、今回も駄目だろう、そろそろ年貢の納め時、親のいうとおり人並みに就職したほうがいいんじゃないか、そんな諦めまじりで三作目に取り組んでいた。こんな気持ちで書いてるんじゃ、ろくなものにはならないよな、と意欲は下がる一方だった。
だから、あれが起きたとき、自分は心の裏の裏で「しめた」と思ったらしいのだ。これで大手を振って書くことを辞められる。一生に一度、勇気をもって自分のやりたいことに正面から挑戦したが、やむをえない事情で挫折した。才能がなかったからじゃない、根性が足りなかったのでもない、全人類の読み書き能力がなくなったんだから、仕方ないじゃないか。
他の誰にでもない、自分自身に、そう言い訳できることにほっとしていた。
だけど、そんなメンツなんて、本当はどうでもいい。
もっと書いていたかった。もっとたくさん読みたかった。小説を一冊読むってことは、たとえば、タカシと徹夜して一つのテーマについて語り明かす、そんな行為に近い。感情を揺さぶられ、知識を注ぎ込まれ、作者と意見を戦わせ、読む前とはどこかしら違う人間になって読み終わる。それが読書だった。文字を読む、本を読むってことだった。
今にみてろ。
俺は、青空を睨みつけて、俺たちから読み書き能力を奪った奴(そいつが神なのかウィルスか、宇宙線なのか宇宙人なのかは知らないが)に宣戦布告した。
これで終わりと思うなよ。百年かかろうが二百年かかろうが、俺たちの脳みその中身をこの外界に撒き散らす、もっと凄い方法を編み出してやる。
注)この話と同じ現象が起きた世界の話を、ほかに二作アップしています。「夜の浜辺で語られた事」「すぐ元に戻ると思った事」です。よろしければ、ご一緒にどうぞ。
