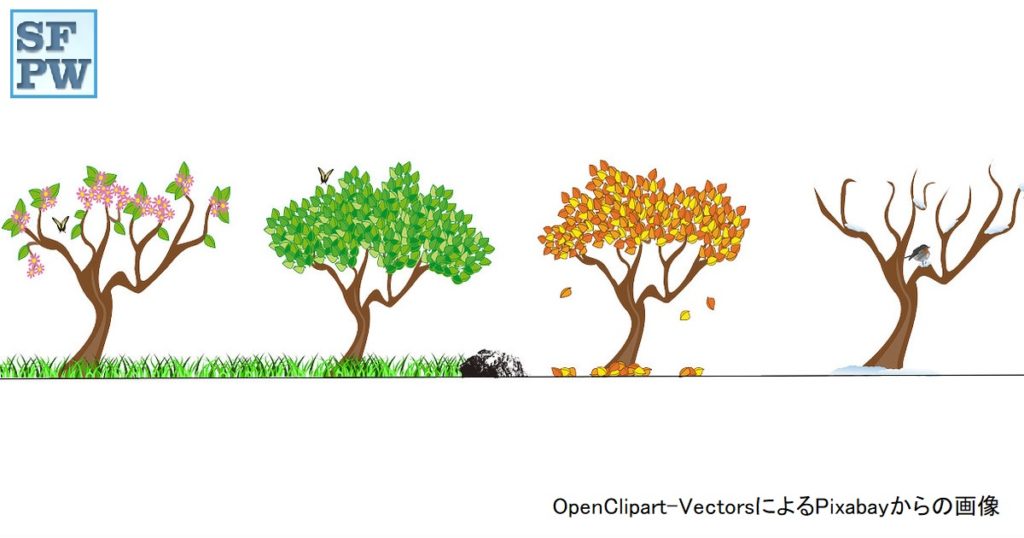
「深田亨の3оr4(スリー・オア・フォー)・『四季その2』」深田亨
《3行(句点三つ)また4行(句点四つ)に圧縮したショートショート作品/会話(鍵括弧の中)の句点の数は数えません!》
<春の季語>
【花疲れ(はなづかれ)】
どこかで休みたいわとあの人は言った。
それは満開の桜並木をぬけ、人通りもまばらになった夕暮れのことだった。
ひっそりと隠すようなHOTELの入口が目の前にあった偶然が、春の女神の配剤のように思えた。
人妻のはかりごとなど疑ってもみなかった、初心な頃の思い出。
【雁風呂(がんぶろ)】
原子力戦闘機は逆V字の雁行型編隊で北に向かって飛んでいく。
撃墜された仲間を累々と荒野に残して。
わずかに生き残った人々は、その機体から壊れていない原子炉を取り出して、生活の糧となるエネルギーを得る。
もちろんそれで風呂も焚く。
【長閑(のどか)】
ポーという汽笛が遠くで聞こえる。
菜の花が一面に咲き、緩やかな時間が過ぎる。
陽炎(かげろう)の向こうに葬列が見える。
そんな夢を閉じ込められた瓦礫の中で見た。
【八十八夜(はちじゅうはちや)】
夏も近づく八十八夜の前の晩。
野にも山にもカップルが潜む。
あれに見えるはあの娘じゃないか。
あかね色のスカーフあげたのはぼくなのに。
<夏の季語>
【雲の峰(くものみね)】
山腹のこのホテルから望遠鏡をのぞくと、ほらあそこにもうすぐ頂上を極めるばかりのパーティがいるでしょう。
山ではなく、そのむこうにむくむくと湧きあがる入道雲のてっぺんあたりをご覧なさい。
雲への登山者は、ここから見るのが特等席。
飛行機で近づいても、なにも見えないのが不思議なんですけれどね。
【星祭(ほしまつり)】
去年の七夕の笹竹をそのままにしておいたら、根をはってずんずん伸びて、先端が見えないほど高く育った。
笹の葉もレジャーシートぐらい広く、折り畳んで笹舟を作ると、ぼく一人なら乗れる大きさなんだ。
小川に浮かべて、満天の星が映る水面をゆらゆらと流れていった。
いつの間にか天の川につながっていて、織姫に会いに行く彦星を乗せて渡ったことも、夏休みの日記に書いておこう。
【蚊遣火(かやりび)】
キャンプするのに虫よけスプレーや蚊取り線香を入れた袋を忘れてきたのは致命的でした。
代わりに昔おばあちゃんがやっていた「蚊遣火」を焚こうと、その辺の枯れ草を集めただけなんです。
星空がずいぶん綺麗に見えて、そのうち星がどんどんこぼれてきて、あたりは夢のような世界になりました。
枯れ草が大麻とは知らなかったし、人目につかない裏庭でキャンプしても違法じゃないですよね、刑事さん。
【金魚売り(きんぎょうり)】
金魚売りから金魚を百匹買って水槽に入れておくと、いつの間にか半分に減っていた。
猫に捕られたか、はたまた共食いしたのか。
残った金魚を見張っていたら、夜半つぎつぎと鳥になって飛んでいった。
案の定、しるしをつけておいた金魚を、金魚売りが翌日また売りに来た。
<秋の季語>
【今朝の秋(けさのあき)】
朝起きると窓の外に秋がいた。
どうも、秋です。
それはわかっているが、夏はどうした。
雪解けの早春と、ゆうべ酒を酌み交わしたばかりなのに。
【野分過ぎて(のわけすぎて)】
秋の嵐が地上のあらゆるものを吹き飛ばして過ぎていった。
ゴミ屋敷のゴミもことごとくなくなり、あとには直径一メートルほどの深そうな穴がぽかりとひとつ。
これはもしかして……。
おーい、でてこ――と穴にむかって叫ぼうとして、やめた。
【生身魂(いきみたま)】
おじいはもう十分歳をとったから。
盆になると生身魂さまとして祀りあげられるんじゃ。
おばあはそれを見て。
今年こそ送り火を焚いてやらねばと手を合わすんじゃ。
【星月夜(ほしづきよ)】
ずっと月と星が輝く夜だと思っていた。
月のない夜のことだと知ったのは、そんな満天の星空の下を歩いていて、彼女が教えてくれたから。
ごめんね、ぼくのせいで帰るところを見失ったのだよね。
謝るぼくに、あなたのせいじゃないわとかぐや姫は、寂しそうに答えたのだった。
<冬の季語>
【底冷え(そこびえ)】
俺が殺したわけではないよ。
彼女が勝手に死んだのさ。
冷え切った心を見てしまったから。
絶望したって俺のせいじゃない。
【日向ぼっこ(ひなたぼっこ)】
冬のさなか。
風もなく暖かな陽だまりの中で子どもが一人楽しそうに遊んでいる。
ああいいなあと足を運ぼうとしても、どうしても行き着けないまま、子どもはいなくなってしまう。
ことさら寒さが厳しい日に現れる、そんな妖怪を『ひなたぼっこ』というのです。
【どんど焼(どんどやき)】
正月の終わりのお焚き上げ。
門松や注連縄(しめなわ)や書初めの半紙もどんどんくべろ。
庭木も納屋も家すらも村ごと燃やしてしまうのだ。
それが歳神さまのお望みとあらば。
【湯豆腐(ゆどうふ)】
ぼくは何人の違う女の人と湯豆腐を食べたのだろう。
もうこれで最後にしたいと土鍋を囲んだのは、ついせんに知りあったばかりの彼女。
逢引き宿の外は雪になり、次の間に敷かれた蒲団の枕もとに、薬瓶と妻に宛てたぼくの遺書。
なんて古風なとあきれた彼女は、SNSでお別れの挨拶を残していなくなる。
