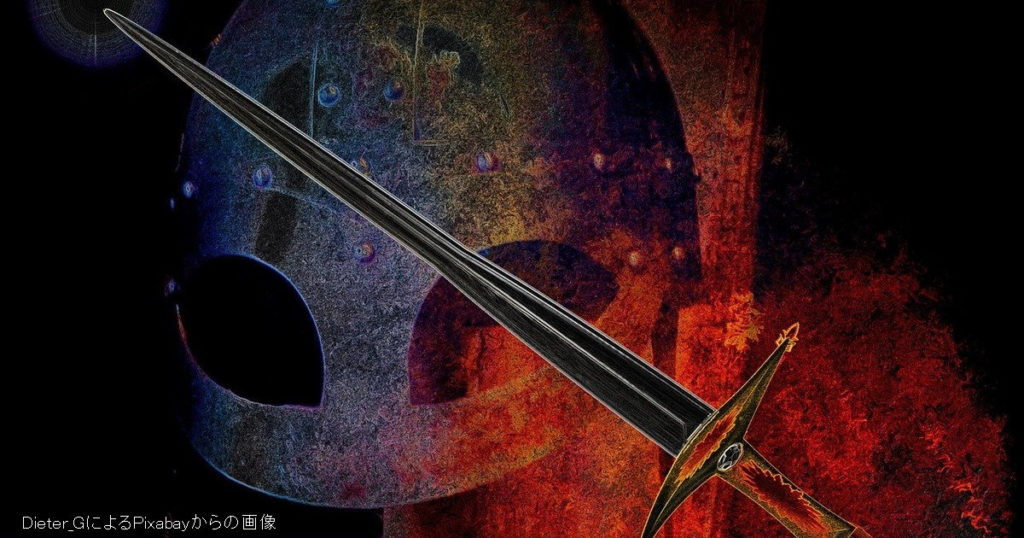
「そなたがヴァレンハレルか?」
玉座からヴァレンハレルを見下ろすウールルースの王は、見るからに疲れていた。壮健で屈強、知略に長け、人望も厚い文明世界の守護者は、東方の蛮族との間で続く戦いに傷つき、疲れ果てていたのだ。
「然り。我こそは魔道剣士、ヴァレンハレルなり」
王の臣下であれば、片膝を突き、頭を垂れるべきところ、ヴァレンハレルは直立の姿勢を保ったままで頷いた。両足を肩幅に広げて立ち、床にまっすぐに突き立てた長大な黒の魔剣の柄に両手を重ねて乗せている。言ってみれば不遜な態度だった。
「蛮族の軍は二万を超えると言うぞ。本当にそなた一人で打ち破れると申すのか?」
ヴァレンハレルは、望んでこの地に赴いたわけではなかった。南方の海賊船団を沈めてからまだ半年、値切られはしたものの、あと何年かは遊んで暮らせるだけの褒賞金も手に入れていた。気候のいい南方から、これから厳しい冬に向かう東方に来るつもりは毛頭無く、報酬に宝物庫の鍵を要求したのも、長旅を厭うたからに他ならなかった。
「今更、何を問うやら。ウールルースの王が、我が名声を聞いた故に、助力を求めたのであろう?」
王国が追いつめられているのは疑いようがなかった。東方貿易の要として栄えていた都にかつての活気はなく、行き交う者も老人と女子供ばかりで、たまに見かける男たちは兵として使えぬほどの傷を負っていた。謁見の間に列席する臣下の者たちにも、一人として無傷の者はいない。東方の蛮族との間で続く戦いで、最強とも言われたウールルースの軍団は、既に崩壊の一歩手前まで追いつめられているように見えた。
「蛮族の軍の本隊は、都の東の守りの要である、シェウエトン峠の砦まで、あと三日の距離にまで迫っている。その大口のとおり、本当に蛮族の群を追い散らすことができるのだな?」
ヴァレンハレルは、王国の地図を思い描いていた。王の言葉通りなら、蛮族の軍はすでに国境を越えている。蛮族の侵攻を阻むのは、今や峠の砦だけであり、峠の砦が落ちれば、都との間に障害物はない。蛮族が一気にウールルースの都を蹂躙することになるのは目に見えていた。
「このヴァレンハレルを疑うなどと、愚かなことを。蛮族の群など、たった一晩もあれば平らげて見せましょう」
力強く答えたヴァレンハレルだったが、心配がないわけではなかった。何より、前の戦いから半年しかたっていないのである。
「大した自信だな。その自信を信じることができればよいのだが」
ここまで来てみれば、ヴァレンハレルの法外な要求があっさり受け入れられた理由もよくわかる。蛮族を追い返せなければ国が滅びる。東西貿易で蓄えた金銀が山積みとなっているという宝物庫の鍵という報酬も、国が滅びることに比べたら、安いものなのだろう。
「心安らいで、吉報を待たれるが良い」
ヴァレンハレルは漆黒の剣を肩に担ぐようにして持ち、一礼もせずに、謁見の間をあとにした。
ヴァレンハレルは幸運だったと思っている。農民の家の三男として生まれ、故郷を離れて今は無いテビロニア公国の兵士になった。屈強な身体と畑仕事で鍛えた腕力を見込まれて、すでに高齢だった魔導師ガンケルの荷物持ちになったのが十五歳の時。その時、既に黒の魔剣は重く、高齢のガンケルは持ち運ぶことができなくなっていた。
「慎重に運ぶのだぞ。一歩間違えれば、そなたどころか、儂やこの国の人々の命に関わるからな」
専用にあつらえた革の箱に、リネンで幾重にも覆った黒の剣が納められていた。ずっしりと重いその箱を背中に背負い、戦場に運ぶのがヴァレンハレルの仕事だった。
ガンケルは、滅多に黒の剣を使わなかった。雷の魔法や嵐の魔法、雹の魔法で戦い、国を守った。ただ、黒の剣の様子はよく見ており、折に触れて革の箱を空け、剣の重さを量るようにしていたことを覚えている。
魔導師ガンケルが、初めてヴァレンハレルの前で黒の剣を使ったのは、テビロニア公国が圧倒的に強大なレフリア帝国のネフテル将軍の軍に攻め込まれた時のこと。強大な北国の将軍に居城に追い込まれたテビロニア公は、なぜ魔剣を使わないかとガンケルに迫った。
「まだその時ではありません」
ガンケルの言葉にデビロニア公は激高した。ガンケルの首をはねるような勢いに押され、ガンケルは黒の剣を渋々使ったのだった。
夜陰に紛れ、敵陣の近くまで剣を運んだヴァレンハレルは、デビロニア公への伝言を託される。戦いが終わるまで、決して城を出るなと言うのが魔道師の伝言だった。
ヴァレンハレルが城に戻ってすぐに、ネフテル将軍の陣で炎があがった。黒い影が炎の中を舞い、闇がざわめく。敵の陣が混乱するその様子に、血気にはやったテビロニア公は、魔導師の言葉を無視して城を出た。
何があったのか、城を一歩も出なかったヴァレンハレルは知らない。ただ、翌朝、死屍累々たる戦場に出て、敵も味方も分け隔て無く横たわるその中に、魔導師ガンケルが立ちすくんでいたことを覚えている。
戦場から回収した剣はさらにずっしりと重く、力自慢のヴァレンハレルにも持ち上げるのが大変なほどだった。
「覚えておくがいい。この黒の剣の力は、敵も味方も区別できないのだ」
魔導師が言った。
戦場の死体は、損傷が激しく、断ち切られた四肢が誰のものか区別も付かなかった。ネフテル将軍とテビロニア公が確認できたのは、両者の豪華な鎧をつけた胴体があったからで、二人の首は、結局、見つからなかった。
テビロニア公の死で、国が割れ、公国は滅びた。それでも優れた魔導師であるガンケルを召し抱えようとする国は多く、魔導師の剣の運び手たるヴァレンハレルが飢えることはなかった。
ガンケルは諸国を転々とし、ヴァレンハレルは剣を持ってついて回った。ガンケルは魔法を使い、時々魔剣を使った。ヴァレンハレルの役割は黒の剣を魔導師が指示する場所へと運ぶことであり、無数の死体の中から回収することだった。
「その剣は、竜を封じてあるのだよ。解き放てば、竜はあたり構うことなく死をもたらす。竜が十分に殺したなら、古の魔法が蘇り、竜は剣に戻る。それだけなのだよ」
ヴァレンハレルは竜を見たことがなかった。見ていたら、生き延びることはできなかったろう。ただ、死体に埋もれている黒の剣は、使われる前より明らかに重くなっていた。血か肉か、それとも命そのものか、竜が喰らった分だけ重くなるのだろう。
馬の重さほどとは言わないが、肩に乗せた黒の剣はずっしりと重いのだった。王の前でこそ剣を引きずるような事はしなかったが、謁見の間を出るとすぐにヴァレンハレルは、二人の従者に剣を持たせた。どちらも若い頃のヴァレンハレル同様に屈強な若者だったが、それでも一人に持たせるには重すぎる。
命を喰らい重くなった剣は、時とともに軽くなる。それでもヴァレンハレルほどの偉丈夫でなければ持ち歩くことはできないだろう。
都から峠の砦までは、二頭の馬と馬車を仕立てて向かった。ヴァレンハレル自身と同行するウールルースの騎士が馬に乗り、二人の従者が漆黒の剣を乗せた馬車に乗る。護衛のために一団の兵士をつけようと言う王の申し出を断ったのは、戦いの様子を見られたくないこともあったし、竜を見て怯えられても面倒だからだった。
砦に向かう街道を吹く風が肌を切るように冷たい。冬が近いのだ。
蛮族は砂漠や大平原を越え、深い森林地帯を抜けて来ていた。冬越えの準備をしてきていると言うよりは、ウールルースの都を陥として居座るつもりだというのが王の見立てで、峠を越えられたら厳しい戦いになるのは目に見えている。それに、蛮族はウールルースだけで満足しないだろうとも言うが、ヴァレンハレルにとってはどうでも良かった。さっさと一仕事終え、南に帰ることしか考えていなかった。
「砦はあそこです」
遠目には岩と見まがうようだったが、ウールルースの旗が立っている。堅牢そうな石造りの砦だった。峠の砦に着いたヴァレンハレルは見晴らし台に登り、東の方の地形を見る。
「これは確かに守りやすそうだが……」
細い道の左右は急峻な崖になっており、一度に多くの敵が攻めてくることはない。
「この砦は、初代のウールルース王が築いて以降、一度も破られたことはありません」
少年の面影を残した騎士が誇らしげに言ったのに対し、ヴァレンハレルは馬鹿にするように鼻を鳴らした。
「それで矢は何本ある? 投石機の石礫は? 兵は何人いるのだ?」
物量の不足を指摘され、若い騎士は言葉を返せなかった。
「まあいい、ここでは狭すぎる。東に進んで、広いところで出迎えるのが良さそうだ。ついて来いとは言わないがな」
古の魔法の力は強い。竜は深い眠りの底にあり、剣の中に封じられて身じろぎすることもないのだという。
その竜の眠りを覚ますのは、竜の逆鱗に何かが触れた時だ。
漆黒の剣のどこかに、小指の先ほどの金色の鱗がある。まるで、小さな金箔が張り付いたように見えるそこが、竜の逆鱗なのだった。
「でも、どうやって、解き放った竜を剣に戻すのですか?」
ヴァレンハレルは、戦の傷が元で病の床に伏せている老魔導師に尋ねた。
「戻すことはできぬ。戻るのを待つのだ」
目覚めた竜は空腹を満たすために命をむさぼる。手近な命をむさぼり尽くした竜は、人と同じように眠気を催す。眠気を催した竜は、古の魔法に打ち勝つことができず、再び黒い剣に封じられる。死の床にあったガンケルはそれだけをヴァレンハレルに言い残した。
極北の地にガンケルを埋葬したヴァレンハレルは、既に革の箱には収まらないほど長く、太く、重くなった黒の剣だけを持って南に向かった。戦においてはより多くの褒賞金を積んだ者に味方し、魔道剣士として闇夜に竜を放った。竜は見境無く殺し、剣は大きく、重くなっていた。
たった一人でヴァレンハレルは谷筋の道を下っていた。従者も、ましてや若い騎士も同行させるつもりがない。剣の使い方はヴァレンハレルだけが知っていればよいのであり、誰にも知られるつもりはなかった。慎重に布で包み、幅の広い革の帯で肩に掛けてはいたが、重く長い剣は剣先を引きずる。それに加え、土を掘る鋤と毛布、体を隠す土色の布、若干の水と食料を入れた背嚢を持つと、いかに屈強なヴァレンハレルといえども息が上がりそうになるのだった。
「なぜ剣の重さを気にされるのですか?」
随分前に、そんなことを尋ねたことがある。ヴァレンハレルの問いに、老魔導師は答えた。
「竜が貪った命の消化には時間がかかるのだよ。消化が進まなければ食欲もわかない。竜を目覚めさせたところで、満腹のままだったらまた眠るだけだ」
ヴァレンハレルは剣がまだ重いことが気になっていた。
海賊たちを食い尽くした黒の剣は、持ち上げられないほど重くなっていた。その時から比べれば、何とか一人で運べる今は、幾分か軽くなっているが、それでもまだ剣は重い。竜を呼び起こしたところで、食欲がなければ役に立たないかも知れないのだ。とはいえ、役に立たなかったところで問題はない。蛮族はあっさりとウールルースを滅ぼすだろうから、契約が問題になることもない。剣を回収し、何とか南に戻ればいいだけのことだ。ウールルースの側で無理矢理頼み込んできたのだから、剣が役に立たなくても自業自得と言うものだろう。
道がなだらかになり、少し開けたところでヴァレンハレルは道から離れた。あたりを見渡す小高い場所で土を掘り始める。ちょうど、一人が横たわる事ができるくらいの穴を掘って、底に毛布を敷く。物陰で用を足し、干し肉を口にする。ヴァレンハレルは、少し広くなったこの場所で、蛮族が野営を張ると読んでいた。峠の砦に攻め上がるのは翌朝、日が出てからだろう。だが、その前に、竜がすべてを片づけてくれる。
見渡す限りの死体を想像しながら、ヴァレンハレルは干し肉を噛む。竜が殺した死体を見続けてきたヴァレンハレルにとって、どうということのない光景だったし、その想像は外れることがない。
夕暮れになり、地響きが遠くから聞こえ、ヴァレンハレルは黒い剣を包んだ布をほどいた。ちょうど、柄の中央のあたりに逆鱗があり、金箔が張り付いたような光を放っている。四頭の騎馬からなる先遣隊がすぐ目の前を走り抜けたが、木陰のヴァレンハレルには気づかなかった。
道の先に蛮族の軍の幟が見えた。ヴァレンハレルの爪が金箔をひっかくと、剣がぶるぶると身じろぎする。重たい剣を道に置き、ヴァレンハレルは毛布を敷いたくぼみに駆け戻った。身を横たえ、頭から土色の布をかぶった。
すぐに竜の雄叫びが聞こえた。騎馬の嘶きと人の絶叫が始まる。一枚の薄汚れた布の下で、ヴァレンハレルは身体を堅くする。血の匂い、肉が焼ける匂い、鉄と火薬の匂いが周囲を埋め尽くす。蛮族は軍を引かずに竜と戦っていた。
攻撃が続いている間、竜が眠りに落ちることはない。黒い竜は、攻撃が続く限り蛮族の命を喰らい続けるだろう。唯一の心配は、竜が食べ過ぎることだった。
とはいえ、今からどうにかできるようはことではない。ヴァレンハレルは、狭い穴の中で眠りに落ちた。
翌朝、一面を埋め尽くす人と馬の屍肉の中に、ヴァレンハレルは黒い剣を見つける。どれだけの命を喰らったのか、剣はあまりに重く、大きくなり、まるで巨人の剣のようだった。
勇猛な蛮族の兵たちの死体の中にはまだ暖かいものもあった。明け方近くまで抵抗が続いたのだろうとヴァレンハレルは思う。二万という大群は、先頭が総崩れになっても後方の兵はそのことに気付かない。いつまでも攻撃が続くから、竜はさらに命を喰らったのに違いない。それで、ここまで大きく、重くなったのだろう。ヴァレンハレルは主を失った蛮族の馬を使い、綱を架けて曳かせようとしたが、黒の剣はほんの少しも動かない。もはや、重すぎてどうにもできなかった。
日が昇り、死肉を喰らう鳥が空を舞っていた。そのうち、あたりは腐臭に満たされることになるだろう。ヴァレンハレルは、黒の剣を放置したまま、空手で砦に戻った。
「ご苦労だった」
砦には王と王の軍団がいた。せいぜい千騎足らずで老人とまだ子供のように見える若者が目立つ。蛮族が、夜明けとともに攻め上ってくるのに備えるつもりだったのだろうが、その必要はもはやない。
「蛮族はもう、襲っては来ない。疫病が出ないように、屍を片づけておくといい」
竜がどれだけ殺したかはわからない。それでも蛮族の群には致命的な打撃になったろうし、忘れようのない恐怖を植え付けることになったろう。
「そうだろうな」
王の元にはすでに報告が届いていたのだろう。驚いた様子は一切無かった。ヴァレンハレルは何かを考えているような、王の様子をいぶかしむ。
「褒賞金なら……」
最後まで言い終わることはなかった。王ははっきりと首を左右に振る。
「法外な要求ではあるが、約束は約束だ。好きなだけ持って行くがいい」
王は、ヴァレンハレルの足下に宝物庫の鍵束を投げると口の端をゆがめるように笑った。
「さて、蛮族どもの骸だが、わざわざ埋葬してやることもないだろう。谷ごと埋めてしまえばよい」
王の言葉にヴァレンハレルは慌てた。谷には黒い剣がある。
「どうしたのだ?」
慌てた様子のヴァレンハレルを見て、王が尋ねた。谷を埋められてしまえば、地形が変わり、黒の剣の場所がわからなくなる。掘り出すのは難しくなり、二度と使えなくなるだろう。
ただ、あれだけ重く、大きくなった剣が再び使えるようになるのは、どれほど先になることか。一年や二年ではとても足りない。
それに、ヴァレンハレルは師の嘘に気づいていた。竜は空腹ではなくても攻撃されれば命を喰らい続ける。喰い切れぬほどの命を喰らった竜は、さらに大きく、重たい剣になる。もし、二万もの蛮族の命を喰らった竜なら、その竜はとてつもなく強大な竜になるはずだ。果たして、ヴァレンハレルにその剣が使いこなせるのか。
ヴァレンハレルは意を決する。蓄えも十分あるし、さらなる報酬も手に入る。魔道剣士としてはそろそろ潮時なのだろう。
「いや、何事でもありませぬ」
一礼して、王の前を離れたヴァレンハレルは、二人の従者とともに馬を駆り、ウールルースの都へと急いだ。
王宮に入ったヴァレンハレルは、厳重に施錠された宝物庫の扉を開く。
「なんてこったぁ」
頭を抱え、崩れるように膝を突いたヴァレンハレル。目の前に広がるのは、何もないがらんどうの空間だ。
長引いた戦乱の末に、ウールルースの宝物庫はすっかり空になっていた。
* * *
山合いを抜ける道路の建設工事現場だった。
「何ですかね、これ?」
ショベルカーが掘り起こした土から、一本の長い棒のようなものが飛び出ていた。作業員の一人が、無造作に、その棒のようなものを土から抜き出す。
「こんなところにフェンシングの剣か?」
刀身にまとわりつく土を払い落とすと、漆黒の剣が姿を現す。細身で、それでいてあり得ないほどに長い。人の身長よりもさらに長い剣だった。
「巨人の剣か?」
近づいてきた別の作業員が言った。
「それにしても細すぎるぞ」
両手で長い柄を持ち、持ち上げる。それくらい軽いのだ。
「人骨と関係あるのかな?」
工事は大幅に遅れていた。現場は戦場だったらしく、大量の人骨と馬の骨、剣や槍、盾といった武器が出土している。しかも、見つかる骨はバラバラで、整然と埋葬されたような状態ではなかった。
「面倒だけど、報告が必要だな」
出土品があれば、考古学調査に回すのが規則になっている。同時に大量の人骨がでているのだから、なおさらだ。
「錆てないし、軽いから、新しいものかも知れませんよ」
現場の作業員が集まってきていた。コンクリートの上に置き、水で洗い流す。剣はカーボン素材のような黒いものでできていた。
「それ、なんですかね?」
剣の柄の真ん中あたりに、金色に光っている箇所があった。
「金の象嵌かな?」
最初に剣を見つけた作業員が爪でその場所を引っかいた。
「え、なに!?」
漆黒の刀身が身をよじるように震え、作業員は思わず後ずさった。コンクリートの上で、黒い剣は瞬く間に漆黒の竜に姿を変え、作業員の足にからみつく。
叫びをあげる時間もなかった。引きはがそうと身を屈めたところで、小さな歯がびっしりと並んだ竜の口が作業員の顔面を齧りとる。それが、最初の犠牲者だ。
何世紀もの間、土に埋もれ、飢えきっていた竜は、次々と作業員の命を喰らい、それでも餓えを満たすことができずに、かつてウールルースと呼ばれていた街に向かう。
完
