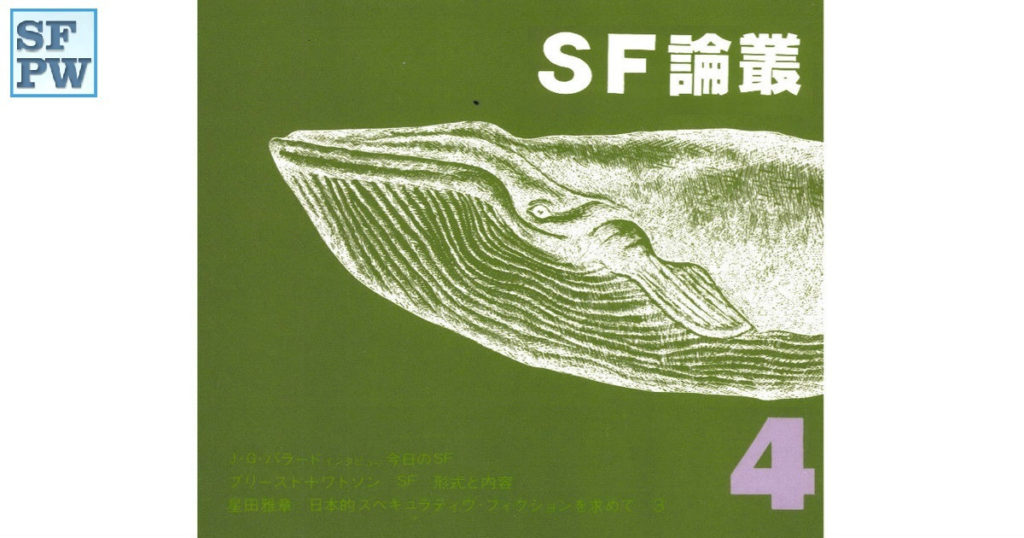
初夢「荒巻義雄は菩薩である」証拠より論(大和田始)初出:「SF論叢」4号(1980)
《おことわり》
本作は、新戸雅明・志賀隆生の両氏が編纂する「SF論叢」誌の4号に発表されたもので、SF評論の歴史に刻まれてしかるべきユニークな批評だとしても、言い過ぎではないでしょう。
このたび「ナイトランド・クォータリー」Vol.25に大和田始インタビューが掲載されることを記念し、「SF Prologue Wave」とのコラボ企画として、ここに同論を採録いたします。
遊び心と思わぬ洞察の深みを愉しんでいただけましたら幸いです。(岡和田晃)
札幌ストーリー 荒巻義雄は1970年から73年にかけて、フルパワーでSFマガジン誌上を駆けぬけた。この時期に彼の作家としての可能性の中心が発光している。初期短編をまとめた『白壁の文字は夕陽に映える』や『柔らかい時計』の中の作品は問題作ぞろいである。その中から、第二作「種子よ」が『神聖代』に発展し、第4作「ある晴れた日のウィーンは森の中にたたずむ」が『白き日旅立てば不死』となり、72年の白亜シリーズは『時の葦舟』にまとめられた。人触れれば人を斬り、馬触れれば馬を斬るこの当時の荒巻義雄の快走ぶりは、手のつけようもない。
恋文・義雄菩薩 荒巻論として知る限りで最もすぐれているのは早川文庫版『白き日――』の鏡明の解説だ。ここに、荒巻義雄という名の電車ならざる問題が集中的に露出している。要約しちゃう。
a 荒巻義雄の描く世界は白い。狂気の、別世界の白さ。
b 視ることと物語を語ることが同居している。
c あいまいさ。何度も、視点をかえて説明がほどこされる。だがどれも決定的な説明とはならない。
この3点は同じ一つの問題のあらわれであるように思える。視ることと語ること、言いかえれば《書くこと》と《読むこと》のせめぎあいのドラマが作品の中に共在しており、作品とはその二つの作用の闘技場であり、本質的に作品は進行中のものとなるのだ。あいまいさと白さは、極めて荒巻的なこの運動の属性であるだろう。荒巻義雄が菩薩でありうるとするならば、それは彼がこの闘いを闘いぬくところに求められる!
のちほど、プレイバック?
視線上のアリア 荒巻義雄は あとがき魔であり、多くのあとがきを残している。しかもそれが普通の「作家のあとがき」とは著しく異なっている。『神聖代』では「あらかじめ意図された作家の計画に従って注意深く、いわゆる文学(既成的意味の)たることを放棄した作品である」という宣言がなされ、『神州白魔伝』では「我々は、今こそ小説を超した小説を書かねばならない。この小説を超えるとは、小説が本来の虚構性に立ちもどった姿である」と誌される。いわゆる〈物語性の復権〉テーゼでもあるだろうが、ここには旧来の小説に対する根本的な違和感も表されている。〈書くこと〉には必然的に〈読むこと〉がともなう。〈読みかえし〉のない〈書くこと〉はありえない。論者の中には〈書くこと〉は〈読むこと〉の一分枝にすぎないと見る人もいるほどである。荒巻作品が従来の小説と決定的にずれてしまうのは、奇妙な言い方だが、〈書くこと〉よりも〈読むこと〉を重視してしまうところにあるだろう。『神州白魔伝』とは、平賀源内の冒険を〈読むこと〉について書かれた作品ではないだろうか。
センチメンタル・ハリケーン 非文学であるか、小説を超えているかどうかはともかく、確かに『時の葦舟』を読むとき、ぼくたちは当惑させられる。これが小説であるためには何かが欠けているのではないか、もっと深みのある世界が描かれていてもよいのではないかというような不満をもってしまう。この不満、それはたとえば「聖杯物語」などを読むときに感じられるものに近いのだろう。おそらく、たぶん『時の葦舟』は物語なのだ。
ブルジョワジーに走って 本号の論文でワトソンが述べているように、小説という文芸形態は市民階級と〈相即〉的な関係にある。そこには神中心の思考はなく、人間生活が中心に語られる。俗なる人間の俗なる日常、感情、過去、記憶。そのような小説を〈虚構〉と呼ぶとすれば、テクノロジーとユートピア志向とが結婚した小説、非日常を、存在しないものを語る小説は〈仮構〉と呼ぶべきだろうか。
牡牛座宮 小説にあっては個人は一人ひとり分断され、それぞれの欲望をもってうごめいているわけだが、資本主義が一段階すすみ、パルコの広告に特徴的なように、イメージによってぼくたちの脳味噌がからめとられ、差異性の戯れとしての商品が張飛している現在、個人の欲望や行為はたちまちのうちに先取され、均質化されてしまっている。荒巻義雄の作品は一見古めかしく、現代性などには乏しいとも思えるが、物語に近づくことによって、小説の属性とされる深層を失い、そのことによって現代的な性格をかちえているようだ。とはいえ、荒巻に即して考えるとすれば、むしろSFという虚構の上に、さらに屋上屋を架したと見るほうが正解かもしれない。この間の事情をウォルハイムは「SFはSFの上につくられる」と喝破したのである。この定理の革命的な意義についてはプレイバックするとして――
曼珠沙華 まづ和歌の本歌どりを考へてみやう。浅沼圭司の『映ろひと戯れ――定家を読む』にはヂュリア・クリステヴァの仮説が紹介されてゐる。彼女はヨオロツパの歴史を二分し、十三世紀から十四世紀にかけて、象徴的思考が記号的思考にかはつたとしてゐるらしい。日本にこれと匹敵するやうな変化を求むるとすれば、おそらく鎌倉時代がその分岐点になるだらう。そして定家の、日本古代を総括し哀惜する歌
春の夜の夢の浮橋とだえして
峯に別かるる横雲の空
がその指標となるだろう。ほいでもって本歌どりとは、理念的な世界・象徴的な思考の世界に所属する本歌から象徴性を奪いとり、記号=仮構に変える行為ということになる。この二つの歌の間の関係は「いわば二枚の鏡の間に現れ出たイマージュの反映の戯れ。(中略)外へでて現実の世界に接することも、その上へ超え出て理念的なものに向うこともない」
たちまちプレイバック なんじゃこりゃ。SF論かいな――本歌どられたSFは、それがもつ象徴性を奪いとられ、たとえばタイム・マシンといったような記号として伝送され、それを超えでることがない。「SFはSFの上につくられる」とは”アイディア” 奪いあいの果てに現出した本歌どりどられの一大白痴、桃源郷、SFの黄金時代の核心をついた名言と申すべきだろうか!
しなやかに歌って 「小説が原泉とする《記憶》を欠いているため、荒巻義雄の作品は《表面的》なるものとならざるをえない。《背後》の深さはここではゲーム的な錯綜としてあらわれ、身体ではなく脳髄を刺激する。《白熱》するのだ。
マホガニー・モーニング ジャスパー・ジョーンズは記号を題材にえらぶことによって、作品を《背後》への無限の溯行から決定的に《表面》へもち来たらす。タブローを星条旗そのものと同一化することによって、作品は《背後》のない純粋な《表面》になるのである。(中略)たえず《記憶》を打ち消してゆく時間論的な《現在》の永遠の自己運動の苦渋に満ちた軌跡は、ここ(プライマリー・アート=引用者註)ではついに、完全に《記憶》を拭い去った《表面》の現前にまで到達するのである。(宮川淳『引用の織物』より)
名前のない時間 『時の葦舟』は神話的な物語。そして第1話「白い環」は最も古く純潔な、おそらくは中生代以前(!)の世界である。ところでこの短編を、現代の科学の用語をつかって解釈してみよう。鏡面反射によって自己励起した粒子が相対性原理の不思議で未来へと旅し、恋という磁場に捕えられ、鏡の回廊をもつ白い環のサイクロトロンの中に封じこめられ、左右逆転の反粒子と対消滅するという物語になるだろうか。「白い環」とはその過程を記録した原始乾板である!
鏡の中のある日 「白い環」で重要なのは鏡のモチーフだろう。面的な街をうつす大鏡面。面と表面の戯れ。たとえ鏡像であったとしても、遠くのものは小さく見えるはずなのに、作品はすべてを近いものとして語っているかのようだ。”自己”を中心とする遠近構造がくずれ、すべてが等距離のものとして立ち現れている。関係の等価値性、経済の悠久性によって “真の自己”は到達しにくい境地となっているのだ。占卜が繁昌しているのはその代替作用でもあろうか。鏡が、夢が、個人の欲望・運命・ありうべき位置をあきらかにする。
湖の決心 ソルティの街のある谷間全体を”自我”とみなしてみよう。閉ざされた自我。揺籃期の幼児の夢の自我。鏡面が谺をかえさないのは当然といえよう。住民たちに過去はなく、時間もない。ゴルドハはそこをぬけだしていく。だが外にはトカゲというあまりに弱い敵しか存在していない。空間と時間を知ったゴルドハは再び内攻する。そして「時の旅人」を知る。鏡に映らない男。高次の自我を象徴する男。導師クリストファネスは内海にうかぶ舟にゴルドハを遣る。鏡の胎道をぬけて、交合の追体験として、ゴルドハは受精時の彼自身に出会う。
イミテーション・ゴールド 無茶苦茶なる “解釈”だが、『神聖代』の解説で筒井康隆が書いているように、荒巻の作品は「内宇宙へ指向する者の『聖書』」であり、作品それ自体、ないしは《背後》に「内容」や「意味」があるのではない。荒巻の作品とは「曼荼羅」や「十牛図」として、一幅の絵として、鏡として、《記憶》や《背後》を欠いた《表面》として我々の前に投げだされているにすぎないのだ。読者はおのおのの似姿をそこに見いだすほかはない。
イミテーション・ホワイト・ホール 問答無用・義雄秘法 荒巻義雄が問題となるのは、SFの仮構世界を築きあげ、『時の葦舟』におけるように、作品のぬしとして振るまうかにみせかけながら、結局はその世界を不分明のものとして放り出し、自らも無知なる一個の読者としてその世界を読もうとする態度であるだろう。作品をこのような文学装置=仕掛としてしまうあり方に、荒巻が我々にもつ意義がある。彼自身は「物語」であると擬装しつつ、ぬし的なふるまいをおこたってはいないが、実際には作品を《内側》に《深さ》に読むのではなく、《外側》に《浅さ》に読んでいるのだ。その間の事情は「〈想像〉は内に向う心の動きであるが、一方〈空想〉はそれとは逆に外に向って拡散する心の働きなのである」と述べられている。荒巻義雄という一個のエゴにおいて作品を終結させようとはしていないのである。
夢先案内人 「 “世界” の意味を教えることが、はたしてよいことかどうか、少なからずためらいますが」と「時の葦舟」の登場人物は語っているけれども、その”意味” とは、おそらく、世界が他者の夢裡のものであるということだろう。とはいえこれは、「黒いものは、不意にかき消えた。(中略)”世界”の意味もかき消える……」と最後の二行が示唆するように、作品が尻をまくると同時に無意味になってしまう。「種子よ」の中にもすでに、この世界は何者かの夢、あるいは異次元から投影された映像ではないかという記述がある。この発想自体は目新しいものではないが、夢また夢という構図を装置として作中にくりこみ、「底なしの深さのなさ」を生んだのは荒巻をもって嚆矢とするのかもしれない。
継承と断念 今やぼくたちは《記憶》と《背後》を読むことによる「文学的感動」というべきものを諦めなければならない。ぼくたちの魂は『神聖代』や『時の葦舟』を読んでうちふるえる。しかしこれは文学装置的振動と呼ぶべきなのだろう。
悲願花 妄想言語系は突然の中断をむかえる。荒巻義雄について考えなければならないことは多い。とりわけルイス・キャロルや宮沢賢治との関連で語らなければならないだろう。ただ、今ようやく長い夢から醒めたばかりの当方にその準備はない。いつの日か初夢が……
【参考文献】
荒巻義雄『白壁の文字は夕陽に映える』早川書房
『柔らかい時計』徳間書店
『神聖代』徳間書店
『ある晴れた日のウィーンは』カイガイ出版
『白き日旅立てば不死』早川書房JA文庫
『時の葦舟』講談社文庫
『神州白魔伝 九来印之壺の巻』奇想天外社
浅沼圭司『映ろひと戯れ――定家を読む』小沢書店・叢書エパーヴ
宮川淳 『引用の織物』
平岡正明『山口百恵は菩薩である』講談社
Web註「ブルジョワジーに走って 本号の論文でワトソンが述べているように」という記述は、掲載号に翻訳されたワトソンとプリーストの対論「SF形式と内容」を指している。
