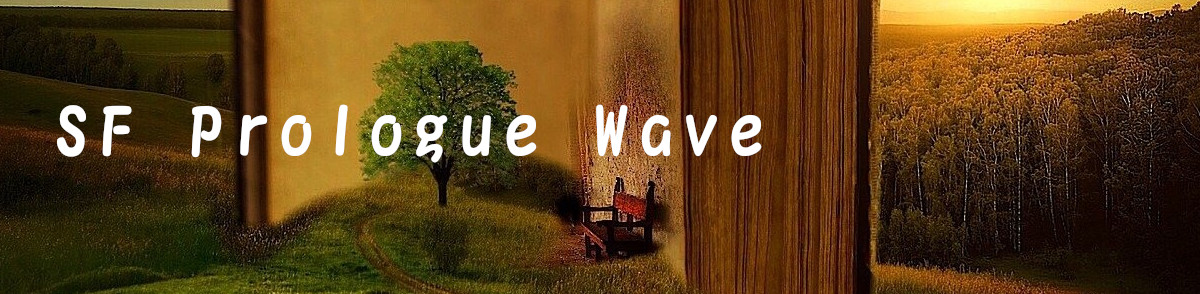『ドン・キホーテ』再入門 その2 樺山三英
ドン・キホーテとは誰か?
ではまず手始めに本作の主人公、ドン・キホーテのプロフィールを確認しておきましょう。作品冒頭の記述によれば「槍掛けに槍、古びた盾、痩せ馬に、足早の猟犬をそなえた、型のごとき一人の郷士」(会田由訳)というのが、彼の初期ステータスです。「郷士」と訳されたのはスペイン語ではイダルゴ(hidalgo)、日本の下級武士に相当します。戦争の必要があれば、王のもとに駆け付けなければなない戦士階級。しかしレコンキスタ(国土回復運動711年~1492年)が一段落して以降、武功の機会は減る一方でした。そこで都会の郷士たちは、役人に転職したり新大陸に進出したりして、それぞれの分野で活躍していきます。しかし田舎住まいの郷士たちにそうしたチャンスが巡ってくることは稀でした。たいていはそのまま、地元で朽ちて埋もれていく運命。いちおうは貴族なので、生活は安定していますが、恵まれない境遇にあることはたしかです。そんな田舎暮らしの典型的な郷士として、本作の主人公は設定されています。
引き続き、冒頭の記述を追いましょう。「われらの郷士の齢はまさに五十歳になんなんとしていた。顔もからだも痩せひからびてはいても、骨組みのがっしりした男で、恐ろしく早起きの、大の狩り好きだった」――50歳手前という年齢は、当時としては高齢と言えるでしょう。しかし老人と言っていいのかどうかは微妙なところです。老いや衰えを感じさせる要素は目立っていません。いっそ多少くたびれたオジサン、というぐらいがイメージとしては適切かもしれない。ドン・キホーテというと、よぼよぼのお爺さんを思い描く人もいますが、原作の記述にはそんな描写は見当たりません。地味で質素だけど堅実な生活を送り、身体は健康。きちんとした服を着て、しばしば狩りに出かける。そんな闊達な人物像が浮かび上がってきます。
そんな彼がとくに入れあげているのが読書で、書庫には蔵書を溜め込んでいる。なかでも愛好していたのが騎士道物語で、このことが彼の運命を決することとなります。読書好きが高じ「本の記述をすべて現実ととらえてしまう」ことで、自らを遍歴の騎士と思い込み、ドン・キホーテを名乗るようになるわけです。ただここでも確認しておきたい事実は、彼の狂気が全面的なものではないということです。元々この地方でいちばんと言われるほどの鋭敏な頭脳の持ち主だった彼は、全面的な狂気に陥ったわけではありません。作中ではしばしば、他の受け答えは実にしっかりしているのに、騎士道物語のことが絡むと、とたんにおかしくなる。そんな様子が記されています。先ほどのよぼよぼのお爺さんのイメージと併せて、痴呆老人のような姿を思い描く人も少なくないですが、これも誤解です。この点ははっきり指摘しておきたいと思います。
物語の構成
さて。いよいよドン・キホーテの冒険が始まります。作中で彼は計3回、遍歴の旅に出ています。18世紀にこの旅の経路を綿密に調べた人がいて、日数と大まかな行程が推定されているそうです。それによると、最初の遍歴はわずか2日で終了。近隣の宿屋(本人は城だと思い込んでいる)で甲冑の不寝番をして、翌日にはラバ追いにコテンパンにやっつけられて村に帰ってくる。2回目の出発からは、従者サンチョ・パンサが道連れになります。主従のちぐはぐなやり取りを軸に、計17日間の遍歴が綴られていきます。と、ここまでが『ドン・キホーテ』前篇の内容。後篇全体にあたる3回目の遍歴は計87日と考えられているので、だんだんとサイクルが長くなってきているのがわかります。銀月の騎士との戦いに敗れ、帰宅したキホーテが正気に戻り死を迎えるところで幕となります。
初めて読む人がたいてい驚くのは、あの名高い風車の場面が、かなり最初の方に来てしまうことみたいです。風車を巨人だと思い込んで突進していくくだりですね。これは第2の遍歴の冒頭のエピソード。文庫本で言うと1巻目100ページを過ぎたあたりです。あれ、もうクライマックスなの? と意外に感じる人は多いでしょう。ちなみに意外ついでに言うと、風車というのは本作のおかげもあって、スペインの代表的な風物だと思われている節があります。が、これは誤解で、風車は当時オランダ発の最新技術として導入されたものでした。作中でもスペインの風土に似つかわしくない、異質な存在として描かれていたようです。つまり最新鋭の施設に突進していく、古びた妄想の騎士という図式。そういうコントラストを意識して読むと、また違った側面が見えてくるかもしれません。この件については、後でスペイン史の問題に絡めてもう一度触れます。
風車の冒険の直後には、囚われの貴婦人を救うために(もちろん勘違い)決闘に挑む場面が描かれます。ここもよく驚かれるポイントです。こともあろうにこの闘いの最中、突如作者のセルバンテスが介入して「種本がここで途切れているので、決闘の続きは書けない」と言い訳をし、物語を中断させてしまうのです。実は『ドン・キホーテ』という小説は、アラビア語の書物を知人に翻訳させたものという体裁を取っています。じっさい、そこで中断した物語は直後に「別の種本が見つかった」という口実で、よどみなく続けられていきます。こういう語りの工夫こそが『ドン・キホーテ』を近代小説の起源たらしめているのだ、という見方もあります。ただ研究者のあいだでは、古文書の発見や翻訳者の介在といった道具立ては、騎士道小説のなかで比較的よく使われるものだという意見もあります。だから必ずしも、セルバンテス独自のものとは言い切れないようです。
しかし後篇に入ると事情は変わってきます。後篇は「前篇の内容が作中世界でも出版されており、皆がドン・キホーテについての情報を共有している世界」が舞台になっているのです。そんな世界の只中を、当の登場人物であるドン・キホーテその人が旅していく。そういう不思議な構成になっているのです。それだけではありません。そこに贋作の問題が絡んでくる。『ドン・キホーテ』前篇の出版後、後篇が出るまでには10年の隔たりがありました。その間にアヴェリャネーダという素性不明の人物(おそらくはセルバンテスの知人による変名)が勝手に『ドン・キホーテ』の続篇を出版してしまったのです。セルバンテスはこれに怒り、そのことで後篇の執筆が促された。そういう経緯がありました。だから後篇の作中世界にはこの贋作のことも出てきて、ドン・キホーテはニセモノに対抗し、旅の行き先を変更したりしています。後篇に書き込まれた、こうした虚実入り乱れた展開は、今日から見てもやはり相当に奇妙かつ斬新で、目新しい手法に思えます。ただ、こうした部分をとらえてよく言われる「『ドン・キホーテ』はメタフィクションの元祖だ」という意見には、若干の違和感も覚えます。「メタフィクション」というのは文字通り「フィクション」を相対化する技法です。しかしセルバンテスの時代にはそもそも、前提である「フィクション」自体が何であるのか、明確な知見などなかったはずです。物語という曖昧な素材に向き合い、いかにしてそれを語っていくのか――この課題に正面から取り組み、暗中模索と試行錯誤を繰り返した末に『ドン・キホーテ』という怪物的作品が生み出されてしまった。我々はこの事実に、もっと端的に驚いた方がいいのではないでしょうか。「メタフィクション」という、今日すでに制度化した枠組みを押し付けるだけでは、セルバンテスがもたらした真の衝撃を受け止めることはできないのではないか。そのように思うのです。
(初出:シミルボン「樺山三英」ページ2016年9月23日号)
採録:川嶋侑希・岡和田晃