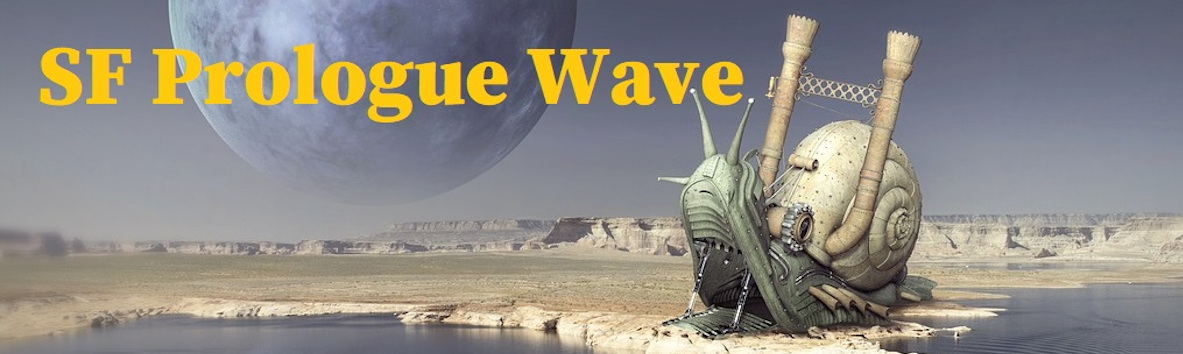『ドン・キホーテ』再入門 その1 樺山三英
本稿は、拙著『ドン・キホーテの消息』の刊行に合わせ、赤坂の双子のライオン堂で行われた講演をまとめたものです。http://liondo.jp/?p=919 近代小説の起源とも言われる傑作『ドン・キホーテ』は、いかにして生まれたのか? 入門的な内容に始まり、受容の変遷を追いながら、その今日的意義まで論じていきます。かなり大部なので、分割し(計6回を予定)順次公開していきます。最後までお付き合いいただけたら幸いです。また催事の場を提供していただいた双子のライオン堂さま、当日ご来場いただいた皆さま、そして進行とテープ起こしを担当してくれた編集N氏には、この場を借りまして改めて深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。
なぜいま『ドン・キホーテ』なのか?
今年2016年はセルバンテスの没後400年に当たる年なのですが、よく知られているようにシェイクスピアも同じ1616年に亡くなっています。この400年という括りは、ちょうど「近代」と呼ばれる時代区分とも重なっているので、一緒にとらえて考えていくとおもしろいものが見えてくるんじゃないか。そういう気もします。あとちょっと意外な人物としては、徳川家康もこの同じ年に亡くなっているのですね。日本の場合「近代」は明治以降なので、江戸時代は「近世」というやや特殊な時代区分になるわけですが、いずれにしても、我々が今日生きている社会の、基本的なシステムが成立する前後。この時期に生き、そして死んでいった彼らが何を考え、何を残していったのかを知ることは、けっして無駄なことではないと思います。
そこで本日のお題『ドン・キホーテ』なのですが、しかしこの作品、日本においてはあまり認知度が高くない。いやもちろん知られてはいる。題名はみんな聞いたことがあるし、例の量販店の名前でもあるし、話の内容だってまあ知ってる、という人は多い。けれどなにぶん長大な作品なので、じっさいに手に取って読んでみようという人は少ない。残念ながらこれは認めざるをえない現実でしょう。ちなみに2002年、ノーベル研究所が各国の作家たちに行ったアンケートで「世界最高の小説」ベストワンに選出されたのが『ドン・キホーテ』でした。『カラマーゾフの兄弟』や『ユリシーズ』を抑えての1位というのだからたいへんなものです。ではこれだけの評価を得た作品が、なぜ我が国ではいまいち浸透していないのでしょうか? 理由は多々考えられますが、ひとつには喜劇より悲劇をありがたがる風潮があるのかもしれません。
じっさい日本では、『ドン・キホーテ』と比べると『ハムレット』の方がはるかに認知度が高く、言及される機会も多いでしょう。たぶん『ハムレット』の方がより深刻で深淵なことが語られている、そういうイメージがあるからだと思います。「生きるべきか、死すべきか?」というあれですね。坂口安吾より太宰治の方が、より「文学的」だと受け止められる、そんな傾向とも相通じるものがありそうです。しかしこのとらえ方には、そもそもの前提からして疑問があります。はたして『ドン・キホーテ』=喜劇/『ハムレット』=悲劇という図式は妥当なのかどうか。安吾と太宰にしてもそうですが、両者の関係はそれほど単純なものではなく、もっと錯綜したものではないのでしょうか。この問題は後で『ドン・キホーテ』の受容史に絡めて改めて触れたいと思っています。
さて。ではそんな『ドン・キホーテ』を、今日改めて読むことには、どんな意味があるのでしょうか? もちろん本作は、単純に物語として読んでも楽しめるものです。自分を騎士だと思い込んだ老人の、勘違いだらけの珍道中――それだけでもう十分に愉快です。しかし先ほど述べたように、この作品は「近代」と呼ばれる時代が始まるちょうどその時期に書かれている。その条件を併せて考えることで、見えてくるものもあるはずです。
このところ世界では、近代的価値観の枠外で起こる出来事が目立ってきています。イスラム過激派のテロや極右政党の台頭、ギリシアの経済危機やイギリスのEU離脱決定等々。近代社会が基本的な前提としてきた約束事が意味を持たない、否むしろ足かせになってしまう事象が多発している。近代発祥の地であるヨーロッパですら、このままではコントロールが保てないのではないかと懸念されている状況です。ひと頃、人文科学の分野ではポストモダニズムが叫ばれ、近代原理はその画一性や秘められた暴力性ゆえに批判の対象になっていました。しかしいまや、そういった批判を受け止める暇すらなく「近代」は自壊し溶解しようとしている。人権や自由、万民の平等といった観念は、遠からず滅びる定めなのかもしません。もしかしたら、もっと先の未来の人類は、素朴に驚くのかもしれない。これだけ問題含みで様々な矛盾を内に抱えつつ、それでも曲りなりに400年は続いたこの「近代」という時代に対して――。
でもそんな現状だからこそ、我々はこの「近代」という時代の理念や成り立ちを、再考してみる必要があるのかもしれません。そしてそのための格好の手掛かりとして、まっさきに挙げたいのが『ドン・キホーテ』なのです。シェイクスピアの作品が、中世世界に投げ込まれた近代人を描いているとすれば、セルバンテスは逆に、近代世界に投げ込まれた中世人を描いています。『ハムレット』を通じて、我々は「近代人」とは何かを考えることができる。同様に『ドン・キホーテ』を通じて、我々は終わりつつあるこの「近代」という時代が何だったか、改めて考え直すことができるのではないでしょうか?
(初出:シミルボン「樺山三英」ページ2016年9月16日号)
採録:川嶋侑希・岡和田晃