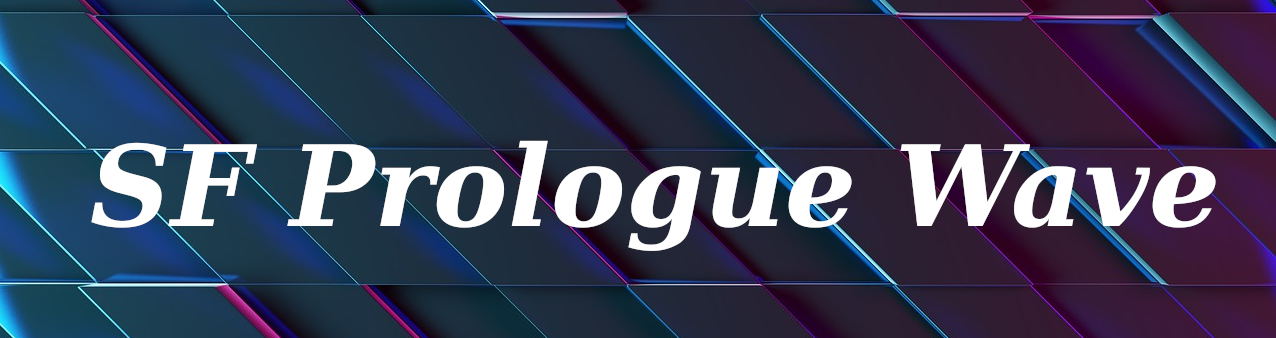【カルタゴ第2回】
Ⅱ 海洋帝国の誕生
1、フェニキア人
●「赤い」人びと
●赤い染料、「帝王紫」
●地形が運命を決める
●海は避難所
2、海洋国家への道
●技術と貿易の開発
●カドモス神話
II 海洋帝国の誕生
1、フェニキア人
「赤い」人びと
幻の名著として名高い『19世紀ラルース辞典』によると、シバの女王の国は「ヒミヤール族の国」とも称していたことが判る。
「ヒミヤール族は、セムの子孫であるシバの女王の子であるヒミヤールの子孫である。ギリシア人は彼らをホメリィト族と呼んでいた。この国は2020年のあいだ生きつづけた。初期のころの王のうちハレト・アライスと名乗る王は、イエーメンの多数の部族を統治し、インダス河まで遠征している。そのころ有名なマレブとサバ (またはシバ) というイエーメンのダムが造られ、王はこの水を公平に配分して豊饒をもたらすことができた。考古学者シーツゼンはザファールに在る古代ヒミヤール族の碑文を発見している。」
[註・「ヒミヤール」は現代の日本では「ヒムヤル」と表記されているようである。参考論文「ヒムヤル王国トゥッバァ朝の実体に関する一仮説」蔀勇造・著 https://cir.nii.ac.jp/crid/1050282813523403136]
シバの女王は旧約聖書によると、ソロモン王の智恵を試そうと豪勢な贈物と多くのお伴をともなってソロモン王のところへ行くが、ソロモンは「そのすべての問[とい]に答えた。王が知らないで彼女に説明できないことは一つもなかった」(列王紀、上、第10章)シバの女王はソロモンの王宮の立派さなどにすっかり心を奪われて、長滞在したらしい。というのは、エチオピアの王統の最初の王であるメネリックはソロモンとシバの女王の子だということになっているからである。
さて、『ラルース19世紀』によると、考古学者が発見した碑文の文字は現代のアラブ文字よりも、ヘブライ文字またはシリヤック文字に近いという。アラブ文字のように文字同志がつながっていなくて、エチオピアのコプト文字のように離れているという。エチオピア人はこの文字を使って左から右へ書くようになったのだということである。
ところでこのヒミヤール (Himyar) という語は、母音をはぶくとHMRという子音になる。セム語の系統の言語では子音だけを書いて母音はない。HMRには現代アラブ語でも「赤い」という色を表わしているという話だ (ジャン・マゼル「フェニキア人と共に」)。そうすると、ヒミヤール人の居住地であった現在の南イエーメンの前面の海を「紅海」(英語で Red Sea フランス語で Mer rouge) と呼ぶのは偶然ではなさそうだ。
ギリシア人はこれを「エリトレの海」と称したが、これも赤と関係があるということであり、ギリシア人がフェニキア人を指して「ポイニックス」と呼んだのもやはり赤い色という意味であるらしい。
ゲルハルト・ヘルムの『フェニキア人――古代海洋民族の謎』(関楠生訳、河出書房新社) によると、
「(赤い人びとを意味する) という説が正しければ、これらの新来者は、のちに世界的に名声を博する名を、すでにたいそう早くからつけられていたことになる。ギリシア語のポイニックスも、ほぼ『紫の国から来た人びと』、あるいはもっと簡単に『赤い人びと』と訳することができる。フェニキア人はいずれにせよ、たいていはカナン人と称していた――アレクサンドロスがテュロスを征服した時代にもなおかつそうだったのである」
とある。カナーンという呼び名も、ヘルムによると、
「低地人を意味するか、もしくはアッカド語のキナフ、すなわち紫から派生したものであるとすれば、赤い人びとを意味する」
ということになる。
いずれにしても、フェニキア人には赤とか紫とかの色が付きまとっているようだ。
通説によると、フェニキア人はアモリ人がシナイ半島を北上する民族移動の途次、カナーンの地にこぼれ落ちたものがその先祖ということになっている。
シバの女王の民がヒミヤール族と呼ばれて赤い色と関係があるとすれば、フェニキアもカナーンも赤い色とかかわりがあり、フェニキア人の出生の謎は「赤」がキーワードとも考えられそうだ。
赤い染料、「帝王紫」
語らぬお前の夢の美しさ
その美しさに私はただぼう然
そうだ これだったのだ
これがフェニキアのむらさきだったのだ。
――深尾須磨子「むらさきの旅情」
私は1970年前後のベイルートに二年間住んだことがある。そのころはまだアラファットのPLOのコンマンドたちが逃げ込んでいなかったので、レバノン共和国の首都は平和な明け暮れのうちに、市民は牧歌的な都市生活を楽しんでいた。
私が知り合いになったレバノン人たちは、いずれも陽気で無邪気な人が多くレバノン人の祖先のフェニキアの自慢をしていたものだ。
「ガラスを発明したのも、高貴な赤い染料を発明したのもオレたちの祖先だ」、と。
ガラスの方は調べてみるとエジプトの方が古いらしいので怪しいのだが、赤色の染料の方は、まさにその通りといってよかった。
フェニキア人の造った海港にティールとシドン (現在はサイーダ) という地中海に面した良港がある。そこではミュレックスという巻貝の内臓から取り出した液汁を使って太古から鮮やかな赤色の染色工芸が盛んであった。ティールに行くと、それらしい巻貝の殻が転がっているのを見ることができたものだ。
ティールの人たちの自慢する特産品が、この赤い色で染めた衣類で、その布はバビロンやエジプトはもとよりギリシアにも輸出されてティール人の富の源泉となったらしい。高貴な人たちの衣類の色だったのである。のちになると、ギリシアでもまたカルタゴでもこの染色工業は盛んになったらしい。
だが、いったい、この赤色というのはどんな色だったのだろう。赤といわれたり紫といわれたりしている色だ。
ところが最近になってこの色を実見することができたのである。そのキッカケは一つの新聞記事であった。宮崎県の綾町に住んで「綾の手紬[つむぎ]」という手織りの草木染の織物を作っている一青年工芸家が、九州南部の沿岸にどこにでも生息する巻貝を使って「帝王紫」の染色に成功したという記事である。その記事によると、「アクキ貝 (悪鬼貝) の貝のエラ下腺 (パープル腺) に蓄積されているブローム・インジゴーと呼ばれる蛍光色素を取り出し、酵素で不純物 (たんぱく質) を分解、これにカシの木を燃やしたあとの灰汁 (アク) を加えて黄色の水溶液を作る。さらに、熱を加えながら絹糸を漬けると、黄色の糸は空気にふれて色が変化し、最後に虹色に輝く帝王紫が誕生する」とある。
この染色法は「紀元前十数世紀、フェニキアで始まり、当時、最も美しい色として世界の帝王たちが熱望、クレオパトラは船に紫の帆を張り、アントニーと恋を語り合ったと伝えられる。東ローマ帝国の滅亡とともに製法も絶えたといわれる」と、その記事は締めくくっていた。
そこで私はその工芸家、秋山さんを訪ねてみた。そしてその鮮やかな色を見たのである。赤というより紫に近い。果して秋山さんは、古代ローマの高官が身につけていたという衣の色を再現し終えたのかどうかは判らない。が、その紫色は確かに眼のさめるような輝きをもっていた。
秋山さんは、いろいろの実験の末、黄色い汁液が空気にふれて変化する途中の色を安定した染料とする科学的なノウ・ハウを編み出したので、今では一定の色として使えるのだと話してくれた。
フェニキア人がその巻貝から取った染料で染めた織物で評判を得ていた時代には、太陽光線を利用して、黄色から赤へ変化する途中の色彩を定着させて大量の工芸生産を可能にしていたのだと、私はレバノン人の書いたお国自慢の本で読んだことがある。フェニキア人はそうやって工芸化に成功し、「赤い色の人」すなわち「フェニキア人」という呼び名をもらったものであろう。そのことは、この染料技術が発明された当初は、それがフェニキア人の独占的な産業であったことを語っている。ギリシア人やカルタゴ人がこの工芸に参入するようになるのは、ずっと後になってからのことであろう。
古くからあった「赤」というフェニキア人につきまとうイメージが、ここで現実とドッキングしたことになる。
ところで、ここにもう一つの異説がある。それは、すべての地中海文明はナイルの上流のヌビアに発達した学術を起源とするという説を立てているシェイク・アンタ=ディオプというセネガル人の人類学者の説である。この人が書いている『黒い民と文化』(Cheik Anta-Diop 《Nations nègres et culture》 présence africaine, 1979) では、人類最初の文明の生みの親は黒人であったとされている。初期のエジプト王朝のファラオは黒い肌をしていたのだという。旧約聖書の「創世記」でハムを父とするクシが居住した国、現在のエチオピアは昔「クシ」と呼ばれていた。この黒い人たちがたてた天文をはじめとする文化がナイル河を下ってエジプト文明を作ったのだとする。この文明の曙[あけぼの]に磨きをかけ伝播したのが北方から来た白い肌の人たちだった。その混血の途中で「濃い赤色の人たち」というものが出来上がっていた。これはフランス語で《Rouge-Sombre》と書かれている。
これは私見であるが、ギリシア人が「赤」または「紫」の名で呼んだフェニキア人とは「濃い赤」と関係があるのではないだろうか。こういう色の命名については常にアイマイさがつきまとうものである。たとえば、日本人は今でも緑色のことを「アオ」と形容することがある。してみると、紅海のほとりから来たというカナーンのフェニキア人を黒い肌のヴァライティの一つである赤銅色と見て、赤または紫と呼んだとする可能性は否定できない。
ディオプによると、古代エジプト人は濃い褐色の肌をしていたというが、エジプト人が残している壁画や浮き彫りをみればその事実は疑うことはできない。ディオプはさらに、フェニキア人もカルタゴ人もネグロ種であったとしている。これはいかにも極論に思えるが、しかし、このことは頭に入れておく必要がある、と私は考えている。
地形が運命を決める
紅海のほとりにあったシバの女王の国のヒミヤール族の一部の者たちが地中海のカナーンの地に移住して、その土地で農耕を営んでいた先住民と混血してフェニキア人が形成されたとするにせよ、またアモリ人の一部がカナーンに定着したとするにせよ、いずれの説に拠っても紀元前3000年のころから地中海の東海岸にフェニキア人という航海に巧みな人びとが住みついていたという事実に変りはない。
シバの女王の民はインド洋までその商業圏をひろげていたとみられている。そこでその子孫は海に慣れ親しんでいたのだとすれば、フェニキア人が航海術に勝れていたということは簡単に説明できるのだが、彼らがアモリ人の支族だとすると、どうして航海術を身につけたかとの説明に窮することになる。そこで考えられたのが、紀元前1200年ごろ北方から南下して、カナーンの海岸を荒した「海の民」との混血説である。謎の民とされる「海の民」は海岸地方を荒したあげくナイル河の河口まで達するが、そこでエジプトのファラオ、ラムゼス三世の反撃に逢って挫折している (紀元前1191年)。出鼻をくじかれた上に、帰りの船をことごとく焼き払われたこの船乗りの民は、その後カナーンの地に定住するようになる。旧約聖書に出てくるペリシテ人、歴史書にいうフリスチン人はその子孫だと考えられている。そうして原フェニキア人がこの人たちと混血し、航海術から造船術に至る技術を身につけたあとで、いわゆるフェニキア人が誕生したという説である。しかし、そういう混血の相手として、紅海のほとりに生れ、インド洋までも通商の海路を開いていたヒミヤール人を加えてみるのはどうだろうか。そうすれば旧約にいう謎の国「オフィール」という黄金の産出国と通商したという民が誰であったかということも説明がつくことになるだろう。

要するに、古代にあって、民族の交叉点であったパレスチナの地で生物的・文化的混血が盛んであったと考えればいいのだろう。
フェニキア人が居住していた地域は、古代のシュクシヤン (現在のシリア領テル・シュカス) からイスラエルのアッコ (アクル)までのほぼ300キロにわたる海岸線に沿った狭くて細長い地域である。東の方はレバノン山脈という険しい山岳がそびえていて、ところどころ、この山脈の支脈は海へ向って突出しているので、東への出口ばかりでなく、南北の交通も意の如くにはならなかっただろう。
たとえばベイルートの市[まち]のすぐ北にある、ナフル・エル・ケブル川 (犬の川) は、乾季には水量も少なく、人も馬も渡渉することができるが、この川に沿って海に突出した崖は古代人にとって極めての難関だったに違いない。現在は崖の下をアスファルトの道路が崖を削って造られているが、この道路が出来るまえは、岩を削った坂道だけが交通路だった。そこを馬も人も一列にならんで登って行ったのだろう。今、その崖の岩肌には、紀元前13世紀のころヒッタイトと戦ったエジプト第19王朝のファラオ、ラムセスニ世にはじまって、古代オリエントの大王の名が、近くは十字軍のボードワン一世、十字軍を征圧したアラブの英雄サラディーンの名も刻まれている。またナポレオン三世の軍隊の名もあれば、第一次大戦のときオスマン・トルコを討つために派遣されたフランス軍の連隊名も三色旗が飾られた銅板に記されて岩に貼りつけられている。
このような交通の自由をはばむ地理的条件がフェニキア人を海の民としたのだ。彼らがバビロンやアッシリアのような古代の大帝国とならなかった条件がそれだったと逆に言うこともできるだろう。フェニキア人は内陸へと発展する代りに海へと出て行った。海上交易のチャンピオンはこうして誕生したのである。
海は避難所
現在のレバノン山脈の西側の傾斜には、レバノン共和国の国旗に描かれている針葉樹、通称「レバノン杉」はほとんど残っていない。杉とは言っても、樅[もみ]とか栢[かや]に近い。もの凄く大木になるので造船用としては最適だったと思われる。
現在、この木がレバノンの数か所にしか残っていないのは大昔、エジプト向けの輸出や、聖書に名高いソロモン王の宮殿の造築のために伐られてしまったからだという。じじつ、世界でいちばん古い都市といわれるビブロスの王アヒラムは盛んにこの木を伐っては筏に組んでナイル河をさかのぼって運んでいた。おかげでビブロスは富んだが、山の樹木は無くなってしまったのだ。
ところで、この木の絶滅の原因を、私がこの国の農林省の役人に尋ねてみたところ、政府は植林のために苗木を植える努力は重ねて来たが、放し飼いの山羊が芽をすっかり食べてしまうので育たないのだという答えが返ってきた。なるほどそういえば、山羊や羊が山肌を歩いていた。しかし、そうかといってすっかり禿山になっている訳ではない。比較的雨の多いこの地には、地中海特有のあの笠松の美しい森林など到るところにある。

とはいえ、レバノン杉 (英語で Cedar フランス語でCèdre) が、フェニキアという海洋民族の飛躍の重要な要素であったことに間違いはなさそうだ。 フェニキア人は初めのうちは刳り舟を造り、のちには板にして継ぎ合わせて大きな船を造るようになった。板と板との隙間をタールで埋めるという技術も覚えた。いわゆる構造船を開発したのである。
船がフェニキア人にとって欠くことの出来ない道具であったことを物語る遺物がある。アッシリアの古都ニネヴェにあるサルゴン王 (前721〜705年) やシェナケリブ王 (前705〜681年) の宮殿跡に発見された浮き彫りがそれである。
サルゴン王の浮き彫りには、曳き船で木材を流して運搬している船の図柄が刻まれている。船は四人ばかりの漕ぎ手で操られているが、まだ帆は使われていない。船の前後は高く突き出ていて舳先[へさき]には馬の頭が付けられている。これは、エジプトやイスラエル向けの材木の運搬の有様をうつしたものであろう。
ニネヴェにあるもう一つの浮き彫りに、シェナケリブ王のころ造られたものがあり、それにはアッシリア軍の攻撃を避けてキプロスヘ渡る、ティールとシドンの王であったリュリ王の一族の姿が刻まれている。これらの船には二つのタイプがあって、一つは長い竜骨のある軍船であり、他の一つは商船である。軍船の船首は先端が鋭くとがっている。敵船に体当りして破壊するためである。舵は二本あって固定されている。
船の中央には帆柱が立っていて索具が結ばれている。商船の方は甲板が二層になっていて、上段には旅客が乗ったのであろう。商船に帆柱が無いのは、軍船にひかれて護衛されて航海したものであることを示している。
もちろん、当時はまだ羅針盤はなかったから、夜の航海は苦手だったに違いないが、それでもフェニキア人は夜間航海の方法を発明した。小熊座を目標にする術である。そのことを証明するのは、ギリシア人が小熊座のことを「ポイニケ」(フェニキア) と呼んでいた事実である。
アッシリアの攻撃をうけて王族が船で避難する図柄は、逃げ道を海に求めたというフェニキア人の安全対策を示している。のちに、カルタゴが北アフリカの岬に港をつくるとき、海こそが彼らの安全の決め手であると考えたのは、このころからの伝統なのであろう。海はもっとも安全な避難所を提供したのである。
2、海洋国家への道
技術と貿易の開発
シリアからパレスチナにかけて、北から南へ伸びる地帯は「肥沃三日月地帯」と呼ばれて来た。 東方には半砂漠の荒野が控え、西方は海がひろがる細長い地域は、たしかに、そう呼ばれるのにふさわしい緑地帯である。が、私たちのように水に恵まれた地味の肥えた国土に住む日本人からみると、羨ましいほどの豊饒さは持っていないように思われる。
じじつ、そこの土壌は小石まじりの石灰質の土質で農業に適しているとはみえない。 かつてローマの穀倉ともいわれたことのあるベッカ高原は、水利に恵まれた平原ではあるが、そこの麦畑の出来は必ずしも良くない。 私は小麦の収穫の季節に行ったことがあるが、作柄は良好とは見えなかった。おそらく、石灰質の多い土質の故ではないかと素人の私にも察しがついたが、そこでは土壌改良がすすめられているとはみえなかった。背の低い小麦畑が続き、いく人かの農民の働く姿がまばらに見られた。そのころ (1970年) から始まった内戦の不安がすでに農民の労働意欲を損ねていたのかもしれない。
おそらく紀元以前の古代にあっても、ここの土質は同じ状態であっただろう。生産性を上げるという社会的なインパクトのなかった古代のことだ。堆肥のような有機肥料を入れる農業生産性向上の動きもなかったに違いない。農業技術の改良などという配慮は払われることはなかっただろう。その証拠に、バールベックの古代神殿の奥深い山の斜面では今でもハッシッシを作るための大麻が作られているという話である。世界中どこへ行っても、大麻やケシの作られている場所は地味の悪いところと相場がきまっているからだ。
石灰質の多い土壌は果樹園芸に向いているといわれるが、レバノンは南のイスラエルと同様にオレンジやブドウの栽培は盛んであるし、良質なものを産出している。ベッカ高原のブドウから造ったワインは食通のあいだでも評価が高いし、ベイルートの街角で売ってくれるオレンジ・ジュースの美味は旅行者の思い出を豊かにしてくれている。
地下資源にはほとんど見るべきものはない。その昔、銅を産したということであるが、今では枯渇してしまっているし、大理石のような石材も出るには出るが、イタリアのような良質なものではない。森林資源の王者であったレバノン杉は、さきにも書いたように伐りつくされてしまっている。木材資源はとうの音に海上に投資されて消えてしまったのである。
そこでレバノンのフェニキア人に残された特産物は、さきに挙げた赤い布の技術と、ヘロドトスが記しているガラス工芸、それに手工芸の皮細工などである。
ガラスを発明したのはエジプト人であるとされているが、カナーンの海岸へ旅行したヘロドトスはティールのメルカルト神殿にあったという「夜も光る柱」のことを記している。ガラス製の円柱の内側に蛍光塗料のような光る物質がぬられていたのではないか、と想像しているのは、レバノン人のジャーナリスト歴史家のジョゼフ・シャミである。
フェニキア人がガラスの発明に関与した根拠として持ち出されるのは、ローマ人カイウス・プリニウスの『自然史』のなかの記述である。それによると硝石を商売にしていたフェニキア人商人が、ある時、海岸に硝石で爐を造って煮物をしていると、硝石が火で溶けて砂と混り合ってガラスに変ったという偶然がガラスの発見へつながったのだそうだ。そしてフェニキアでその製造が盛んになり、シドンの商人などがガラス製の小間物を海外で売りまくったのであろう。後にフェニキアが衰亡すると、その技術はヴェネツィアの沖合の島ムラノヘ移転することになったのである。
ガラス工芸と貝を原料とした染色工芸は、古代にあっては文明の象徴であったに違いない。輝くばかりの赤い布と、色とりどりのガラス製の小間物とがフェニキア人の商品の目玉をなしたという事情は、資源に恵まれないフェニキア人が生き残るために知恵をしぼって、その知能産業の開発に全力を挙げた結果であったことを思い知らしてくれる。
アルファベットを発明してある程度の文明の段階に達した民族が、技術と商才を駆使して地中海の覇者となる基礎はこうして固まった。
カドモス神話
このようにして始まったフェニキア人の海外膨張の業績を伝える神話伝説が残されている。ティール生れのカドモスの冒険の話もその一つだ。
カドモスという神人は、ティールの王アゲノールの三人の息子の一人であるから、当然この神話は「フェニキア神話」でなければならないのだが、「ギリシア神話」のなかに取り入れられてしまっている。というのは、ギリシア神話の主神ゼウスが登場してくるからである。所詮、そのころのことに関してギリシア人とかフェニキア人とかという区別をつけることは困難なのである。「シドンの人」とか「ティールの人」とかという風に、出身の市[まち]の名で、その素姓をのべるのが当時の現実を反映しているのである。
そこでティールの人カドモスは、ゼウスの神が牛に化けて誘拐した妹ユウローペを探しに海を渡ってギリシア本土まで出かける。誘拐された妹の名がエウローペという、いかにも暗示的な名なのだが、神話では、彼女は牡牛に化けたゼウスの背に乗せられてクレタ島へ連れて行かれた、と語られているだけである。

彼女とゼウスとの間に生れるのが、ミノス、サルペドン、それに智恵者をもって鳴るラダマンテュスの三人である。ミノスはクレタ文明の創設者でクノソスの王となったし、サルペドンは小アジァのリュキアに渡って王となる。三番目のラダマンテュスは智恵の神といわれ、法典を作り、死後は地獄の裁判官になったというのがギリシァ神話の伝えるところだが、どうもこのエウローペ誘拐の話は、東方オリエントの、あるいはエジプトの古代文化が、仲介者フェニキア人を通じてギリシアに渡来して行った経路をあとづける話のように思われる。エウローペと名づけられた一つの文化がクレタ島に渡ってミノア文化を作り、一転して小アジアのパンフリアの海岸に移り、エーゲ海文明の開幕となるという順序を物語っているようにみえる。現在のヨーロッパが、その文化の後裔であると考えれば、この話はぴたりと落ちつくのだが、当のヨーロッパ人はどう考えているのだろうか。
ところでカドモス兄弟の三人は、それぞれ手分けしてエウローペの行方を探しに出かけるが、クレタ島に渡ったカドモスの伝説だけが有名である。クレタ島でしばらく滞在したカドモスの一行は、そこに文字などを残したあと北上してギリシア本土へと渡る。デルポイの神殿で占いを立ててもらうと、次のような神託が出た。「お前は人気のない野原で一頭の牡牛に出逢うだろう。その牛について行くと、草の茂った野に行きつく。そこに土台石を置いて、その場所をボォティアと名づけるがよい」というのである。カドモスはその通り実行したが、牡牛が疲労のため倒れたので、そこに自分の名をとってカドメーと名づけた。この町が、のちにテーバイとなったのだ、というのがこの伝説の筋である。

カドモスが建てたテーバイの市はアテネから60キロばかり西に在り、ギリシアの都市のうちで最も古いとされている。およそ紀元前2100年ころのこととされている。
カドモスはまた、その場所に石像を立てて、アテネ神に捧げたという。アテネ女神はのちにアテナイ市の守護神となる神であるが、もとを正せばエジプトの主神、すなわち太陽を意味するエルの娘ということにされている。この神はしばしばオリエントの豊饒の女神、イシュタールと混同されていた。イシュタールとは周知のようにフェニキア人の周辺で崇拝されていた美と豊饒の女神アシュタルテの前身であり、これがギリシアに渡るとアフロディテとなり、ローマヘ行くとヴェヌス (ヴィーナス) と変貌を遂げる。
このような神々のメタモルフォーズの過程で、フェニキア人の神アナトが、ギリシアに渡るとアテネとなったのである。アナト神自体も、イシュタール女神の神格の変化から生れたものであるが、いつの間にか「戦いの女神」に変貌してしまった。現在のシリアの地中海岸に発見されたウガリト (ラス・シャムラ) の遺蹟から出土した「バールとアナト」という叙事詩に歌われているアナトである。この女神がカルタゴに引越すとタニトとなり、パールというカルタゴでもっとも崇敬を集めた男神の妹とされることになる。
アナトはアテナイ市民の守り神となると、アテネと名を変え神格も変るが、もとを正せばアラブ語の「泉 (ain)」と語原をひとしくするものだと言う。してみるとカルタゴ人がこれを豊饒の女神としたことは理にかなっていることになる。
要するに神とは人びとの心の中に生れるものだから、人びとのコンセンサスさえ得られれば、どのようにも変化し得るのである。エジプト人の主神エルがギリシアに渡るとヘリオスという太陽神になったし、ペルシアに渡るとエリム (イランの古名) となったのである。
カドモスの話から思わず脇道へ迷いこんでしまったが、カドモスがエウローペを追ってギリシアへ渡ったという神話は、エジプトやオリエントの文明がギリシアへ伝播して行った歴史の反映であろう。フェニキアの船乗りを通じて文化が移転して行ったことは、とりも直さず多数の民衆の移動があったということだろう。カドモスにしても、一人でブラブラ出掛けたわけではないだろう。一族郎党を引き連れての移動で、そのためには家畜や食糧の予備も用意して行っただろう。フランスの史家フェステル・ド・クーランジュ (1830〜1889) に依ると、アテナイがまだ村落にすぎなかったころ、そこにオリーヴの栽培を教えたのはフェニキア出身の移民だったということである。そうすると、カドモスたちの引越し荷物のなかにはオリーヴの種も入れられていた、ということになる。
さきに上げたセネガルの人類学者ディオプはカドモスのことを「王」と呼んでいるが、彼の考えによると、カドモスはギリシアに君臨した植民王だったことになる。
[カルタゴ 第2回 終]