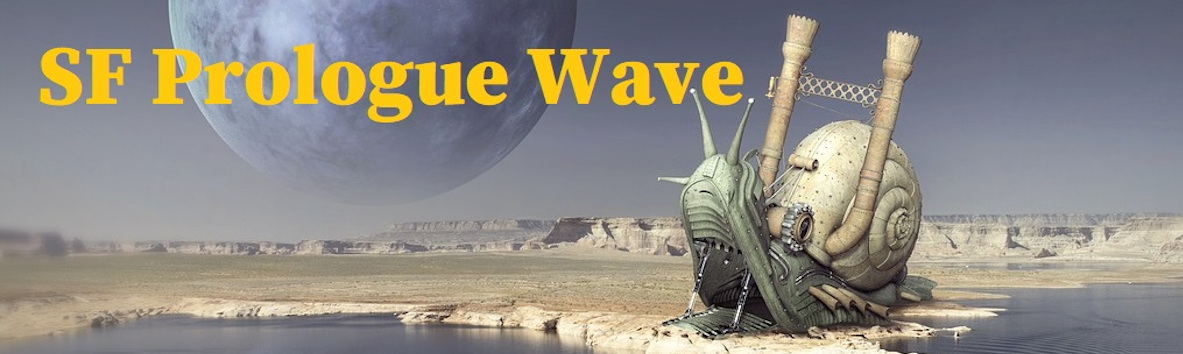●はじめに(岡和田晃)
詩人・フランス文学者である服部伸六を再評価していく企画の第8弾は、第1次「詩と思想」に掲載された「黒アフリカの詩人たち」特集です。「現代詩手帖」と並ぶ商業詩誌の雄が、現在は土曜美術社出版販売の「詩と思想」ですが、その1974年3月号に掲載されたもの。第1次は版元が土曜社→土曜美術社→日本電通社と移り変わりました。国会図書館にも所蔵がないもので、なかでも、マダガスカルの詩人について、たっぷりの紙幅で論じているのですから貴重です。奇しくも、2023年には、現代マダガスカルの詩人トーキョー・ハーレムが来日してイベントを行ったばかり。トーキョー・ハーレムの朗読はYouTubeでも観られます(https://www.youtube.com/watch?v=x0WwvFiJHpc)。そうした現代詩人のルーツを探る記事としても重要です。文字起こしと注釈は大和田始氏が担当しております。校閲は忍澤勉氏の協力を得ました。
黒アフリカの詩人たち
マダガスカルの詩人たち(1)
服部伸六
「大きな島」とフランス人から呼ばれるマダガスカル島はアフリカ大陸の東方海上に浮ぶ。この島は日本列島の島々を合わせた面積よりも1・6倍も大きいが、人類の発生以前にアフリカ大陸から分れたらしく、いままでのところここでは原人の骨は発見されていない。そこで、この島に住む人間は、海をこえて流れついたものたちの子孫である、と結論されることになる。
この国の住民のうち最も多い種族はメリナ族という、アジアのマレーシヤ人に近い人びとだ。インド洋の海流に乗り漂流したアジア人たちである。しかし、モザンビーク海峡をへだてたアフリカ大陸からも黒人種が流れついている。そこでかなりの混血がすすんだ。メリナ族のなかにはわれわれ日本人と見分けのつかないくらいの人相と体つきのものがいるかと思えば、明らかにアフリカ婦人と見まがうものもいる。このメリナ族の約二百万人を含めて、島の人口は約七百万人である。
メリナ族は中央高地の1000メートルも高い、小丘陵の起伏する風光明眉な田園に住んで、稲作を主業としている。首都のタナナリーヴというところは、フランスが植民地経営していた時代から首府であったが、それ以前のメリナ王国のころからの首都でもあった。
この国の住民たちは、この国の温和な風物のためか、元来、性質がおとなしい。しかし、何でもかでも従順であるというわけではない。それには証拠がある。1948年、フランスの圧政に抗して叛乱したとき、島民は貧弱な武器をもってたたかった。結局はフランス兵に屈せざるを得なかったものの、そのとき8万人の犠牲者を出している。また、つい最近では、1972年5月、反仏の暴動に立ち上った学生・労働者はフランスべったりの政府を瓦解させた。その時も、30人を超える死者を出している。
次に、この国の代表的な詩人二人を紹介することにする。もちろん、若い人たちがこのほかにもいるが、歴史的な見地から定評ある二人にしぼることにした。
ラベアリヴェロ (J.J.Rabearivelo)
ジャン・ジョゼフ・ラベアリヴェロは1903年3月4日、タナナリーヴで生まれたが、1937年6月22日自殺をとげている。34歳の若さである。
この詩人はなぜ自殺したのか。この疑問に答えるために、マダガスカルに住んでいた詩人の友のフランス人ロベール・ブードリイの語るところに聞いてみよう。《彼の境遇は彼が得た教養と合致しなかった》からだという。
《彼が詩についてもっていた知識は、植民地に往くフランス人でさえも持ち合せていないようなものだった……だから、植民地のフランス人にも気の合う人をみつけることができなかったのだ》と、ブードリイは書く。じっさい、彼の生のドラマは、すさまじい早さで西欧文化を追った低開発の国の知識人のドラマであったといえるだろう。彼は、白人と同等となろうと、死にものぐるいで努力した。しかも、マダガスカル植民地に見かけられるような商売人や農業をいとなむ白人でなく、高い教養のある知識人としての白人と比肩することをのぞんだのだ。そこで、彼はその生国に住みながら、自らを流刑人とせねばならなかったのである。
フランス文化を追及し、知識の混血児となっている自己を発言[信?]すること、それは日常の生活のなかでも耐えがたいものとなったらしい。彼の妻は、メリナ族の言葉であるホバ語しか話せなかった。妻は、彼の精神生活の発展については行けなかったのだ。彼がその悩みを打ち明けたくても、妻は慰めを与えることができなかった。彼は、その孤独に耐えるほど強くなかったのだといえよう。
では、日本での作家の自殺者の場合にみられるように、その自殺の直接の原因は、ノイローゼとか麻薬による乱心であったろうか。
パリのメルキュール・ド・フランス社から発行された彼の『青い手帖』のなかにおさめられている「最後の日記」は、死を前にした冷静な若い男の姿が読みとれる。
《14時――頭を鈍くするためキニーネを飲む。それと飲み下だすための水少量。
キニーネの効果が出はじめる。もうすぐ、10グラムの青酸カリを飲まねばならぬ。少量の砂糖を入れて。》
それから、次の紙にこうかかれる。
《時計が鳴っている。――眼をつむろう、ボアハンギー (1933年に死んだ娘の名である) を見るために、そして生きている親しいものに別れを告げるために、眼をつむろう。家族たちよ、友よ。今、午後3時だ。時計が鳴っている。ぼくは横になろう。何も考えが浮ばなくなった。》
次に最後の紙片がある。15時02分の日記だ。
《家族のアルバムにキッスしよう。隣の部屋にあるボードレェルの本ヘキッスを送ろう。――さあ飲むんだ――飲んだぞ――マリーよ (彼の妻)子供たちよ。お前たちにぼくの最後の思いを――砂糖を少し飲む――吐きそうだ。さあ眠るんだ》
詩人の自殺の知らせが広がると、こういう不自然の死が常に出食わすような噂がひろがった。ラベアリヴェロの性格が話題になるのだった。高慢ちきだとか、とどまるところを知らぬ野心家だったとか、煙草の吸いすぎ、酒ののみ過ぎが噂される。いや借金追われていたんだ、ヨーロッパ人とアジア人 (これはインド人だろう) の債権者が、彼を相手どって裁判にかけたばかりであった。しかるに、彼の詩作は、まだ彼を栄光の座につけるには至っていない。だから、死んだのは、自分で自分を死なせたのは、勇気がなかったからだ。周囲の人びとはそんな風に彼の自殺を受け取っていたらしい。
だが、彼に人種の垣をこえて常に手をさしのべていたフランス人の友ロベール・ブードリイは、《この死は三面記事と同じに取扱うことはできない異常なものである》と解釈する。《(彼の死は) 文学史上の事件であり、彼がどっぷりひたっていた戦後のロマ (ン?) ティスムの歴史 (シュールレアリズムなどを指す) のなかで捉えらるべきものであると同時に、植民地住民と彼らに文明を与えようとするものとの間の関係の、非常に微妙な問題を含むものである。》
この微妙な問題こそ、20年後に、マルチニックの奴隷の子孫である黒人作家フランツ・ファノンが提起した問題であった。ファノンが、「暴力論」のなかではもちろん、その最初の著作、「白い仮面、黒い皮膚」のなかで執拗に追及した問題であった。それは黒い肌と文明との問題だったのだ。
ファノンは次のように書く。
《問題は重大である。目的とすることはただ、黒い皮膚の人間を、彼自身から解放するということだけである。われわれはごくゆっくりと進むことになろう。なぜなら二つの陣営があるからだ。白人と黒人との。》(ファノン「黒い皮膚と白い仮面」みすず書房『フランツ・ファノン著作集』第一巻)
この論法でいけば、ラベアリヴェロは、皮膚の色の濃い自分を自分から解放しそこなったといえよう。1937年といえば、アフリカの植民地が独立する23年も前のことだ。まだ黒人たちの歌声は起っていなかったのだ。
もっとも、正確にいえば、そのころ、パリでは黒人学生の運動がはじまろうとしていた。マルチニック出身の詩人エーメ・セゼールや、セネガルのサンゴールたちは文芸誌を発行しはじめていた。サンゴールの「ネグリチュード」という黒人の価値を肯定しようという思想がすでにその萌芽をみせはじめていた時代であった。しかし、マダガスカルは、海をへだてて孤立していた。語る友もないラベアリヴェロの孤独感、それが絶望へとかりたてたのだ。
彼は同朋のあいだに語りかける相手をもたなかったので、フランスやスペインの友と文通してなぐさめていた。メルキュール・ド・フランスに拠っていた批評家のアンドレ・フォンテナもその一人だった。
死の直前、失意を与える出来ごとが相次いでいた。彼が期待していた文学賞は他人にもって行かれた。彼が得ていた印刷所の校正係の職よりも、もっと楽な図書館の司書の職はことわられてしまった。またパリで当時開かれていた「芸術と技術博覧会」へ彼を派遣してくれるように申し込んでいたにもかかわらず、彼は外されて、その代りに四人の工芸家が行くことになった。彼は失望した。しかもそれに母と妻と三人の子供を養ってゆく生活にも疲れた。四年まえに愛する四歳の娘を失ったことも彼の絶望を深くした。
自殺の一時 (間?) まえに書いた題のない時のなかで、彼はこうかく。
ゲランもドーベルも同じ年齢[とし]だった、
あのランボオは少しばかり年上だった、
だってこの世は俺たちに余りにも酷[むご]く
蜂はすでに花粉を散らしてしまっていたのだ。
何を議論することがあろう期待することがあろう、
樹の下の、砂か石の上に伏し、
葬式のあとに来るべきものすべてに
やさしい服なざしをそそぐのだ、
やさしい眼なざしをそそげ、虚無のなかの、
俺が信じてもいない虚無の、うつろのやさしさに。
だが、お前が在るというこの存在よりも、
純粋なものがあろうか、おおやさしい母よ、おお大地よ。
太洋のようにざわめき しかも空しい
お前の孤独と同じ孤独を人は生きる
はるか彼方の高みで南の風が吹けば
下の方では生き残ったものが語り合う。
…………………………………………………………………………………………………………
ざわめきよ、人の世のざわめきよ
地上の眠を眠る船乗りにとっての貝殻たちの空しい繰りごとよ!
ざわめきよ、人の世のざわめきよ、いつの世も同じことだ
死者だけがこの世の貧困から脱れるのだ
だがいまやの句がにおってくる
木の葉の匂が匂う、娘が俺を呼んでいる。
地に生きるお前の眼を忘れることのないよう
洞穴のしじまに生きる俺たちをたまには思い出してくれ。
沈黙で閉じられた扉のすぐそばで
涙を流すためでないことを。
大いなる目的に向って導かれることは、
いつの日か魅惑あるものとなることを悟るためであることを思い出してくれ。
ラベアリヴェロは13歳の年で学業を捨てねばならなかった。そのあとはすべて独学であった。彼が自分の文学的天分にめざめてからは、マダガスカルで発行されていた新聞雑誌に寄稿したばかりでなく、世界中に原稿を送った。
1926年には『灰のコップ』、27年には『詩選』、28年には『詩稿』と、たてつづけにクラシックな定律詩の詩集を発刊している。そのなかから、次のソネットを訳してみよう。
フィラオ (Filao)
フィラオ、フィラオ、わが悲嘆の友よ、
遠い海辺の国から来た友よ、
イメリナの土は君のしなやかさにとって
ゆたかな土であったのか。
海の娘と、微風と砂の娘の
岸辺の舞踊に君は想いをはせる
そして君はあの静かな朝の夢をみる
乾くことのない君の樹液の誇り高い朝の夢を
流刑のおかげで君の外皮は今やささくれてしまった
君は力つきて弱々しく投げかえしみるが
僅か鳥たちに希望を与えるだけのことだ
異様なリズムとその影から生れたとしても
わたしの血管を流れる血で生きないなら
わたしの歌も気狂じみて空しいものとなるだろう
遠いメリナ族の先祖への思慕の歌である。伝統を超えて現実の力が何をなし得るのか、ラベアリヴェロの詩操にはつねに無力感がただよい、力つき果てて自らの命を絶つ運命を暗示しているかのようである。
もう一篇、ソネットを読んでみよう。
ピエール・カモに
幾世紀を経た王座へと向って
丘陵[おか]が誇る黒のきざはしを登るとき
波うつ野原をあなたの名がひびき渡り
一隻の美しい船が波をけだてて行く
生れ故郷のアルベールの村へ向えば
フランスに持つあなたの友らは岸辺に立ち
流島と旅うたうあなたの歌を聞くだろう
南の島の栄光に輝く歌のひびきを。
されど王たちの庭 見晴し台の上では、
火の如き陽の光が柘榴をむさぼり、
うかれ女の心臓までも灼きつくす、
樹の切り株から匂う強い香気にまじり、
カモよ、花々は淋しさをかこつ、
行きて還らぬ旅立ちであってみれば!
これは別離の歌である。フランス人で、彼の友であったピエール・カモは植民地行政府の勤務を終えて本国へと去って行った。多分、タナナリーヴの郊外にある旧王宮の庭では、祭りが行なわれていたのだろう。桃色の長い布を振りかざして少女たちが舞う。親友カモは島を去って行く。そしてラベアリヴェロは、ひとりとり残されるのである。文化の祖国、フランスへ彼は行くこともないだろう。
ラベアリヴェロは、その後古典的韻律を捨て去って自由律詩へと向う。1934年には『夢さながら』を出版し、35年には『夜をひもとく』がテュニスで発行され、37年には「アベオンのための唄』が刊行される。
ぼくは君たちを知らぬ
ぼくは君たちを知らぬ、おう、ぼくの昔の嘆息よ! ぼくのなかで新しい生命が生まれたのだ!
ぼくは君たちを知らぬ、おお、桜くの昨日までの悲 いまぼくを責[さいな]めているのは今日の幸福[しあわせ]だ!
ぼくは君たちを知らぬ、おお、死んだ恋よ! ぼくの心のなかには別の恋が生まれたのだ。
ぼくは君たちを知らぬ、(他分忘れてしまったのかも知れぬ) おお、ぼくから逃げて行った姿よ! ぼくの心に悔いを残して去ったものよ!
ぼくは君たちを知らぬ、おお蒼めた?よ! ほかの色どりの紅い頬たちがやってくるのだ!
ぼくは君たちをかまっていられないのだ! ぼくを忘れてくれさえすればいいのだ!
おお、嘆息も、すすり泣きも、ぼくの知ったことじゃない! 悲しみの歌も!
??すべてを忘れてしまったんだ!
もしかしてあのひとがその訳を尋ねたら、こう答えるだけのことだ。
新しい心ができたのだ。ぼくは君たちに用はないのだと。
黒人のガラス屋
黒人のガラス屋
そいつの無数の瞳を見たものはまだない
いくら背伸びしてみてもその肩までとどいたものはない
ガラス製の真珠の首飾で着かざったこの奴隷、
アトラスのように頑丈なこの男は
頭上に七つの天をいただいている、
雲がたてこめた河が、そいつの腰布をぬらした河が、
そいつを運び去るだろう、と人はいう。
その手からおびただしいガラスの
破片がとび散るだろう。
風が生れる
山々によって打ちくだかれた
そいつの額にはね飛ぶだろう……
そして君はそいつの日毎の責め苦に
果つることもない労働に 立ち会う。
そして東方の壁に海のほら貝が鳴り亘るや
君はその轟く死の床に立ち会うのだ――
だが君は奴のことを憐みはしない
太陽が転落するそのたび毎に
奴が苦しみもがくことを思い出しもしない。
正直なところ、この詩は私の理解の枠をこえるものである。黒い巨人が苦しめられているイメージは、白人の支配に悩むアフリカのことであろう。しかし、なぜガラス屋、またはガラス製造人でなければならないのか。強いてこじつければ、15世紀から3世紀半のながきにわたって続けられた奴隷貿易の時代を通して、白人がアフリカに売り渡したガラス玉の首飾りに埋もれたアフリカ人の比喩に通じるものであろう。
新墓[にいばか]
ぼくの墓はぼくの墓でありつづけるだろうが、ぼくの心はそれとは別もの
それは地上のそとの墓、いわばぼくの第二の墓だ。
この墓には蔭をおとす茂みもなく、まして男らしい石もない。それを覆っているのは、不安におののくぼくの肉なのだ。
震える嘆息、涙、せき上げるすすり泣きが幽霊のようにぼくを訪ねてくる。
そこには思いあぐねた夢があるが、あっという間に消え去って行く。そこには希望の船の破片がある。
そこにはむかしの韻律の名残りが、ぼくの青春の歌が埋められたまま眼覚めることもしないでいる。そしてその谺[こだま]さえきこえてこない。
そこには失敗のうちに忘れられた計画がある。そこには遠い日のぼくの骨と無為の時とがある。
そこではゆっくりと肉が分解する。そこでは、肉はまだ若いのに色あせて落下する。そこには死がある、あらゆる死がある。