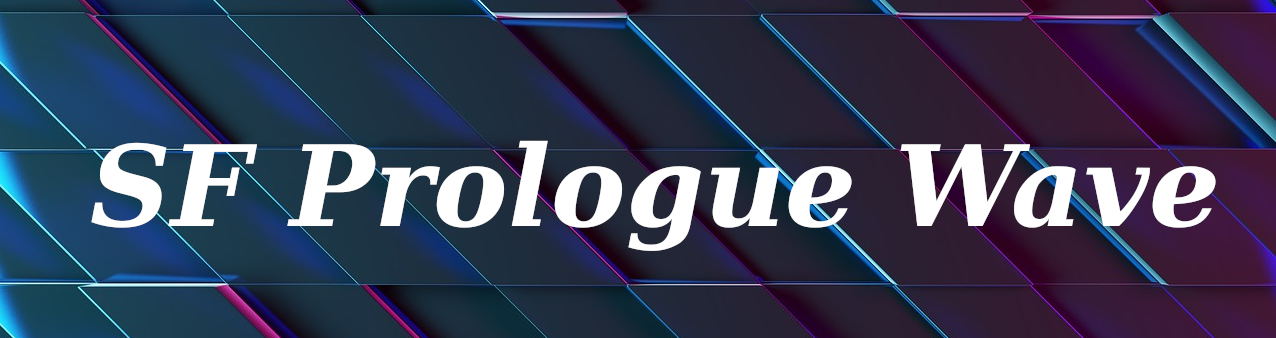●はじめに(岡和田晃)
今回はお酒の話なんですが、ここで語られるコニャックの逸話は、なるほどピリリと辛いもの。そう、中曽根康弘首相(当時)が、アイヌ否定の一種として単一民族国家論を国会でぶったとき、その「驕り」を鋭く批判しえているわけです。
「日本人」はいい加減、なまなかな日本特殊論の上にあぐらをかくべきではない、というメッセージが伝わってきます。
特殊から普遍へ
——コニャックが辿った途——
服部伸六
フランスの西海岸に注ぐシャラント河が、ゆったりと流れる川下のシャラント地方は、むかしからブドウ作りが盛んだったが、土質に多くの白亜質が含まれているので、それから出来たワインは酸味が強くて、評判は今ひとつ、すぐ隣りのボルドー産のワインに比べると低かった。ところが偶然、このあまり評判のよくないワインを蒸留して濃度の高いアルコールを作ることが発見され、これをフランス語で eau de vie と名付けることになった。「生命 [いのち] の水」ということであるが、当時、これはその名の通りクスリとして製造が許可されたのである。
ところがこのクスリ、はじめのうちは戦場の傷病兵向けに売られた薬品だったが、次第に「疲れをいやす」クスリに変身、海上や戦場の荒くれ男たちの愛用するところとなった。ワインを蒸留するのに火が用いられたので、「焼く」という語が使われた。今日の英国のブランディ、すなわち焼き酒の誕生である。奇しくも、日本では焼酒すなわち焼酎[ショウチュウ]がこれに対している。
ところがである。一八世期末の戦乱と革命の時代になって、樫の樽の中に忘れられたまま何年か放っておかれた生命の水が、コハク色の香り高い液に変身しているのが、これも偶然から発見されたという。これは伝説だからあまり信用できない話ではあるが、こうしてコニャックがお目見えすることとなったのである。だが、なぜコニャックという、この地方の名が商品名となったのだろうか。
それは、この飲みものの地域的な特殊性を強調したからなのである。コニャック地方を中心とした白亜質の特殊な土壌に育ったブドウから作られたワインを蒸留したアルコールが、シャラント河の、コニャックからさして遠くないリムーザンの森から伐り出されて、川を下って来た樫の材を使った樽に詰められた上、何年か眠らされた揚句に出来上がった、まさに特殊な条件のもとに仕上げられたのが、コニャックと総称される世界の酒なのである。これを日本の場合にあてはめてみると、灘 [なだ] に当たるかも。兵庫県の一地方の名が酒の銘柄を代表するように、コニャックはヘネシー、マルテル、カミュの総称となるわけだ。
以上、きわめて特殊な地方の酒が、普遍的な酒となる過程を簡単にあとづけてみたのであるが、このウラにある政治・経済の歴史を見落とすことはできない。それは英雄ナポレオンの欧州制覇と時代を同じくしているのである。これは特殊が普遍へと変身する過程が国力の消長の過程と一致していることを語っている。
さて、ここで気になるのは、自由世界第二の経済大国に成長した日本のことである。日本人は、日本という国が特殊な国で外国人には理解できるはずがないと思い込んでいるらしい。日本でとれるコシヒカリやササニシキのネバネバした味わいは、日本人だけにしか分からないと思っている。米の自由化をしたところで外国のパサパサした米は食えるものかと思って、それを相も変らず食管法を外さない理由のひとつに取り上げるのである。
だが、ほんとうに日本は特殊な国なのだろうか。中曽根首相は日本人の lieu commun (ありふれたキマリ文句) の見本みたいな人であるが、この人が世界にマレなる単一民族国家といって誇らしげに語るのを聞くと、その「驕り」には気恥ずかしくなる。日本文化が特殊であることには異存はないが、いま大切なことは、この特殊をいかにして普遍化するかということではなかろうか。
フランスの片隅の特殊な産物が世界に誇る商品となった道を学んで、特殊な国日本の普遍化の道を探究するのが今後の課題であろう。
(はっとり しんろく エッセイスト・詩人)
CUE 1987−07ー01 ジャパンタイムズ 第21号