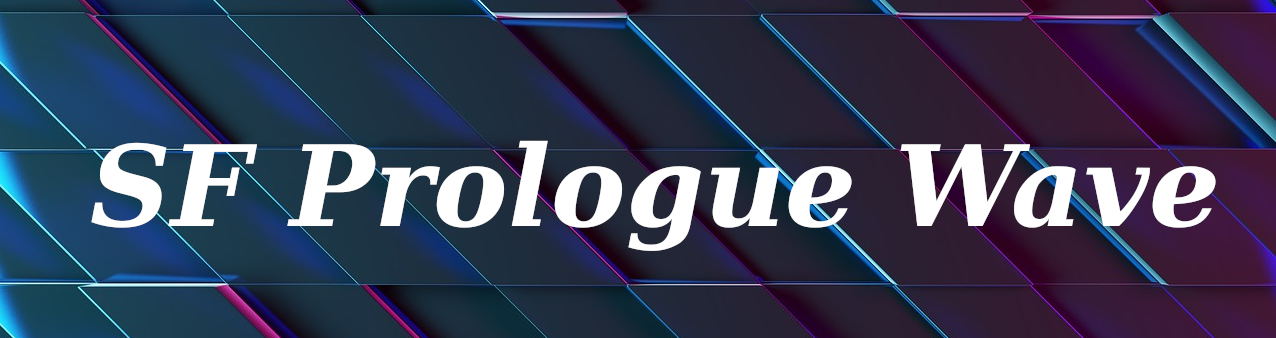「書痴の幸福なる死」余談
仁木稔
SF prologue waveに「書痴の幸福なる死」を掲載していただいております、仁木稔です。この作品は「歴史エッセイの体裁を取った小説」なのですが、そのことがSFPW上で明記されていないことが気に掛かっていました(もちろん、ジャンルは正しくショートショートに分類されていますが)。個人ブログでは説明していたのですが、何しろアクセス数が少ないので、改めてこの場をお借りして、上記の件を含め、本作についての余談を少々書かせていただきます。二回に分けたブログ記事を大幅に改稿、再構成して一つにまとめたものです。
本作は小説ですが、嘘(フィクション)は一つだけです。残りの部分は本当にに歴史エッセイとして通用するくらい、がっつり文献に拠っています。もっとも私(今、この文章を書いている仁木稔)が実際に歴史エッセイを書く場合は、こんなに主観と推測を前面に出したりはしませんけどね。「仁木稔ではない、どこかの誰かが書いた歴史エッセイ」という設定の小説です。この設定も含めると「嘘(フィクション)」は二つになりますが。
古代・中世の中東文化に興味を持って本格的にリサーチを始めてから、かれこれ二十年以上になります。だから本作の「主人公」であるジャーヒズのことは十数年前から知っていたのですが、取り立てて関心はありませんでした。『千夜一夜』に収められた幾つかの物語の元ネタと思しき作品の著者であることと、自らの蔵書に埋もれる最期を遂げたほどの愛書家だということで記憶に残っていた程度です。
それが三年ほど前でしたか、ひょっとして彼はイスラム史のみならず世界史全体で見ても、「自らの蔵書に埋もれて死んだ史上初の愛書家」だったのではないか、と不意に思い至ったのでした。エッセイにしたらおもしろいな、と漠然と思いつつ、なかなかそんな機会にも恵まれませんでした。
時は経って今年(二四年)四月。『SFマガジン』六月号に掲載する中篇「物語の川々は大海に注ぐ」の最終ゲラのチェックを終えて時間が出来たので、以前から読みたかった陸秋槎氏の短篇集『ガーンズバック変換』を読んだのでした。収録作のうち「インディアン・ロープ・トリックとヴァジュラナーガ」と「ハインリヒ・バナールの文学的肖像」はすでにアンソロジーで読んでいたのですが、陸氏の他の作品と併せて読むことで、いっそう深く印象付けられました。この二作と「三つの演奏会用練習曲」の一つ目が特に気に入って、数日後、「おもしろかったなあ」と反芻していたその時、卒然と「例のネタは歴史エッセイを装った小説として書けばいいじゃないか」というアイデアが「降ってきた」のでした。
だから本作が書けたのは、『ガーンズバック変換』のお蔭です。ブログでも書きましたが、改めて御礼申し上げます。我非常感謝您。
さて、一つだけ嘘(フィクション)が混ぜてあると述べましたが、作中で想像や推測として書かれている事柄は、それには該当しません。「事実」(資料に基づく)として書かれている事柄の一つです。それがなんなのかは、ネタバレになるので公開はしません。ゴリゴリに史実で固めた上で、たった一つの嘘(フィクション)を軸に展開させるスペキュレイティブ・フィクションです。
そしてまた本作は、テーマ的には「物語の川々は大海に注ぐ」の続編でもあります。もちろん物語、設定等はまったく繋がっていません。どちらも史実に基づいた小説とは言え、フィクションの度合いは「物語の川々」のほうが遙かに大きい。それでも同作は、そのままなら歴史小説に分類できるほど史実に即しているのですが、敢えて固有名詞や術語を日本人には馴染みのないものに換えています。
わざわざそうした理由は幾つかありますが、「書痴の幸福なる死」との関連という点から一つ挙げると、「物語の川々は大海に注ぐ」はある種のディストピアものでもあるからです。
現代日本において小説、漫画、アニメ、実写作品、ゲーム……媒体はなんであれ、フィクションを愛好してきて、単体の作品やジャンルではなくフィクションそのものを否定する言説に一度も遭遇したこともない人はいないでしょう(間接的にすら一度もない人は、幸運というよりむしろ環境が特殊でしょう)。そうした否定的言説はいずれも、「役に立たない」「現実じゃない(類似のものとして「ただの作り話」等。要するに「実話より劣る」ということらしい)」「学びを得られない」「時間の無駄」「現実逃避」等々、ただただ無益なものとして見下し、「有害」と断じるにしても、そんなものにリソース(時間や金銭および思考や感情)を割くのは無駄を通して有害、健全な精神の育成のを妨げるといった観点からです。フィクションが体制や権威、多数派、社会規範へのカウンターとして恐れられているから否定され、迫害されているのでは、まったくありません。
そのようなフィクション蔑視が強固な社会通念となっているディストピアが、「物語の川々」の世界です。フィクションの愛好者にとってのみのディストピア、それもただただ蔑視され軽視されるだけで迫害されたりということはまったくない、「うっすらとしたディストピア」ですが。
ところで「ディストピア」は「ユートピア」の反語として造語されましたが、「ユートピア」の綴りにはeutopia(理想郷)とutopia(どこにもない場所)の二種類があって、後者ならディストピア(暗黒郷)もまたユートピアの一種ということになります。というわけで「フィクションの蔑視・軽視が強固な社会通念となっているが別に迫害はされない社会」ですが、わざわざ「どこにもない場所」utopiaを創造しなくても、かつて現実の歴史において、そっくりそのまま存在しました。それが「前近代のアラブ世界」です。
しかしこれを「歴史小説」としてしまうと、読者が「自分とは無関係の遠い場所、遠い時代の話」で片付けてしまいかねません。「フィクションがフィクションというだけで蔑視・軽視された経験を持つ読者」の「ささやかな共感」を得るためには、「どこでもない場所」の物語としたほうが相応しいのです。加えて、「中世イスラム世界」という舞台設定を明示してしまうと、「専制」「狂信」といった悪しきオリエンタリズムを重ねられ、「ただただ蔑視・軽視されているだけのフィクション」という「ささやかな共感」が「専制・狂信に危険視され弾圧されるフィクション」という「ヒロイズム」に塗り替えられかねないからです。そんな社会は現実の人類史において、ただの一度も存在していません。
この先、「物語の川々」と同じ世界を舞台にした作品が書かれることは、まずないでしょう。上記のとおり、前近代のアラブ世界ではごくわずかな例外を除き、フィクションは蔑視・軽視され続けた上に、現代に至っても完全に解消されたとは言えません。だから「あの世界」において、これ以上「物語」に触れるとなると、現実のアラブ文化をディスることになりかねない。
では「書痴の幸福なる死」がテーマ的に続篇だというのはどういうことかと言うと、「物語の川々」のテーマが「物語」(厳密には「書かれた物語」)であるのに対し、本作のテーマは「読書」だからです。「物語の川々」は「ある種のディストピアもの」なので、スペキュレイティブ・フィクションかつ「広義のサイエンス・フィクション」ですが、「書痴の幸福なる死」はスペキュレイティブ・フィクションである一方でサイエンス要素は皆無なので、SFPWに掲載していただいたのでした。
ちなみに同じイスラム世界でも、フィクションの地位が低かったのはアラブ世界(アラビア語圏)だけで、ペルシア語圏をはじめ他地域ではそんなことはありませんよ。
余談は以上です。「一つの嘘(フィクション)」がなんなのかはネタバレできませんが、書物や読書の歴史、本作の「主人公」であるジャーヒズ、アッバース朝の文化や政治等に興味のある方は、以下のテキストをどうぞ。本作の主な参考文献です。
書籍(タイトル:『』は書籍名、「」は収録論文等のタイトル 著者名 出版社名)
『図書館の誕生 古代オリエントからローマへ』L.カッソン 刀水書房
『声の文化と文字の文化』W.J.オング 藤原書店
『ギルガメシュ叙事詩』月本昭男・訳 岩波書店
『紙の世界史 PAPER 歴史に突き動かされた技術』(第一章および第三章のみ参照)マーク・ランカスキー 徳間書店
『紙と羊皮紙・写本の社会史』(Ⅱ章およびⅣ章のみ参照)箕輪成男 出版ニュース社
『書物の文化史 メディアの変遷と知の枠組み』(第一章「東洋の書物史」のみ参照)加藤好郎ほか 丸善出版
『中国出版文化史 書物世界史と知の風景』(第四~六章のみ参照)井上進 名古屋大学出版会
『イスラーム 書物の歴史』小林泰/林佳世子・編 名古屋大学出版会
『ギリシア思想とアラビア文化 初期アッバース朝の翻訳文化』D.グダス 勁草書房
『イスラーム社会の知の伝達』湯川武 山川出版社
『イスラーム全史』(第2章のみ参照)余部福三 勁草書房
『イスラームの国家と王権』(第2章のみ参照)佐藤次高 岩波書店
『聖なる学問、俗なる人生 中世のイスラーム学者』(第2章「学問修得の方法」のみ参照)谷口淳一 山川出版社
『イスラームの生活と技術』(第2章「知識と技術の伝達 紙を中心に」のみ参照)佐藤次高 山川出版
「製紙法の西伝」(『シルクロードの文化交流 その虚像と実像』所収)藤本勝次 同朋舎
「住宅と住宅地」(『イスラーム世界の都市空間』所収)陣内秀信 法政大学出版局
『アレクサンドロス変相 古代から中世イスラームへ』(第3章「イスラーム以前のイランにおけるアレクサンドロス」のみ参照)山中由里子 名古屋大学出版会
『ペルシア語の話』(Ⅲ、Ⅳ章のみ参照)黒柳恒男 大学書林
『中世思想原典集成Ⅱ イスラーム哲学』(竹下正孝「総序」のみ参照)上智大学中世思想研究所・編訳 平凡社
『イスラームの人間観・世界観 宗教思想の深淵へ』(第二、三章のみ参照)和子 筑波大学出版会
『イスラームの世界観 ガザーリーとラーズィー』(序章、第一章、第五章のみ参照)青柳かおる 明石書店
『イスラームから見た世界史』(第七章のみ参照)タミム・アンサーリー 紀伊国屋書店
『宗教の世界史11 イスラームの歴史1 イスラームの創始と展開』(第3章 堀井聡江「生活の指針シャリーア」のみ参照)佐藤次高・編 山川出版社
『アラビア科学史序説』(「付録Ⅳ アル・ジャーヒズの『動物の書』について イスラムのアダブの書の典型」のみ参照)矢島裕利 岩波書店
「けちんぼども」(『世界文学大系68 アラビア・ペルシア集』所収)ジャーヒズ 筑摩書房
雑誌論文
「ジャーヒズとアラブ修辞学の形成過程」濱田聖子(『日本中東学会年報』14)
「ジャーヒズ著『けちんぼども』における逸話と登場人物 文人譚を手がかりに」濱田聖子(『日本中東学会年報』37-2)
「アダブ考 アラブ文化におけるアンソロジーの思想」岡﨑桂二(『四天王寺大学紀要』51)
「アラブ文学における論争ジャンル 「マカーマート」の周縁」岡﨑桂二(『四天王寺大学紀要』48)
「アッバース朝期のセクシュアリティと同性間性愛 ジャーヒズ著『ジャーリヤとグラームの美点の書』の分析を通じて」辻大地(『東洋学報』98-4)
「紙の伝播と使用をめぐる諸問題」清水和裕(『史淵』149)
「イスラム世界における紙の伝播と書籍業 バグダードのワッラークを中心として」後藤裕加子(『日本中東学会年報』7)
「マームーンとムウタスィムの新軍団」余部福三(『史林66-6』)
英文(Web記事)
Al-Jahiz Master of Arabic Prose(https://www.alshindagah.com/julaug2005/jahiz.html)
Jahiz: Dangerous Freethinker?(https://criticalmuslim.com/explore/issues/dangerous-freethinkers/jahiz-dangerous-freethinker)
Al-Jahiz Bibliography(https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jahiz_bibliography)
al-Fatḥ b. K̲h̲āḳān(https://referenceworks.brill.com/display/entries/EIEO/SIM-2320.xml)