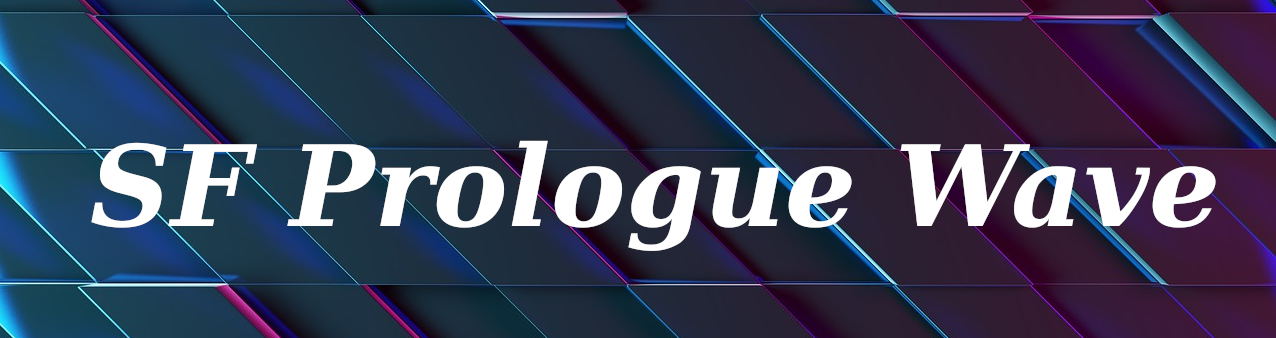天沢童話の源泉――天沢退二郎『夢でない夢』書評 思緒雄二
読む人を選ぶ本です。
あえてタイトルを原型でなく元型でもなく源泉としたのには意味があります。
さらっと最初によんだとき、これは散文詩集ではないかな、という印象をもちました。
ミームな言い方をすれば「考えるな。感じるんだ」です。
おはなしを、物語としてだけでなく、現象、風景としてながめるだけでもたのしめるという方には退屈しないでしょう。
ただ、自分がおもうに、それができるのは、かなりの読書の達人です。いちいち考えはじめたら、たぶんイライラしはじめる人も少なくないかも。
あと(これは二次的たのしみかたといえますが)天沢作品を研究したい、もしくは文学作品を心理学や精神分析的にアプローチしたいという方などには、興味深い作品でありましょう。
また、シュール系の小劇場、アングラ演劇、唐十郎の状況劇場などが好みな人とかなら、すんなり作品世界を徘徊できるかもしれません。つげ義春『ねじ式』などの不条理ワールドが合う方にも、おすすめできるでしょう。
日常的素材(街、人々)を用いつつ、少年少女らがくりひろげ、関わっていく非現実、非日常。
不確かでゆらぎつづける世界、唐突な場面転換の連続―
因果関係という物語性の担保は希薄なレベル、なんとかギリギリのところで相関関係が物語的風景を支えている・・・
言わば〝時間〟すらゆらいでいる世界。
そんな奇妙な、おはなしがあつめられています。
(意外と量子論とかが好きな人には、すんなりと入っていける?)
この本は翻訳家、詩人、宮沢賢治研究家、児童文学作家として知られる天沢退二郎さん二十代の作品群。
復刊にあたって寄せられたあとがきに、
>一種の自動記述的方法で〈童話〉という私好みの様式を操縦したもので(中略)
>作者自身にも意外な展開が続出する
とあり、この本の特徴的制作方法が示唆されています。
〝自動記述的方法〟、これがキーワードになりましょう。
自動記述とはオートマティスム。「自動書記」「自動筆記」などとも言われます。
オカルト的な興味から面白おかしく取りあげられることが多いのですが、心理学で使われる用語。
天沢さんは東京大学のフランス文学科を卒業されています。
当時、フランスの文学者に『シュールレアリスム宣言 溶ける魚』で有名な、アンドレ・ブルトンという人が健在でした。
そして、そのブルトンが以前より詩などをつくる実験として試みていたのが〝自動記述的方法〟なのです。
当時注目をあつめていた精神分析的手法を取りいれ、うたたねしながら書く、超高速で書くなどなど―覚醒時の意識レベルをあえて低下させ、言葉を羅列させていくのがポイントとなります。
KJ法など、いわゆる発想法で取りいれられている連想手段のブレーンストーミング(ブレスト)と似てますが、こちらのほうが、より低下した意識レベルのもとでおこなうことを目的にしているとみてよいでしょうか・・・。
とにかく、こうして得られた言葉、文章の世界は、ふだんわたしたちが〝めざめて〟活動しているときに縛られる既成概念、意識偏向というタガを越えて深層のあらわれることが期待でき、そこから、また現実をながめる新たな視座、ヒントが得られる・・・ザックリしすぎな言い方かもしれませんけれど、そんなカンジでしょうか(めんどいので、ブルトンがなぜこうした精神分析的手法を取りいれたか、精神分析学という衝撃が当時の精神医学や心理学のみならず、一種の宗教的〝くびき〟を破壊するものとして、たとえば少しまえのダーウィンのよう、どう思想的、文化的影響力をもったかとかまでは、ここでは踏みこみません)
「んだよ、ただの夢日記かよ」とか言わないように。
夏目漱石の『夢十夜』を夜の夢、『永日小品』にある作品のいくつかを昼の夢(白日夢)としたら、わたしは、この作品に、ブルトンのしたフロイト流の自動書記よりは、ユング流の能動的想像に近い影を感じました。
そして、それは後に書かれる天沢さん最初の長編児童文学『光車よ、まわれ!』において、より強く感じたのです。
宮沢賢治の童話が『銀河鉄道の夜』でみせた「星々きらめく宇宙へと、どこまでも高くはるかに」とは、またちょっと異なる「水や深みの周辺」・・・水、水底、水鏡、水平線、そしてユング的〝中心のモチーフ〟が、天沢童話のイメージとして産声をあげている――そこにブルトン『溶ける魚』と似たカケラを感じるのは、自分だけでしょうか。
わたしにとって『夢でない夢』の作品群は、あたかもそうした天沢水源のごとくに感じられるのでありました。
(初出:シミルボン「思緒雄二」ページ2016年1月8日号)
採録:川嶋侑希・岡和田晃