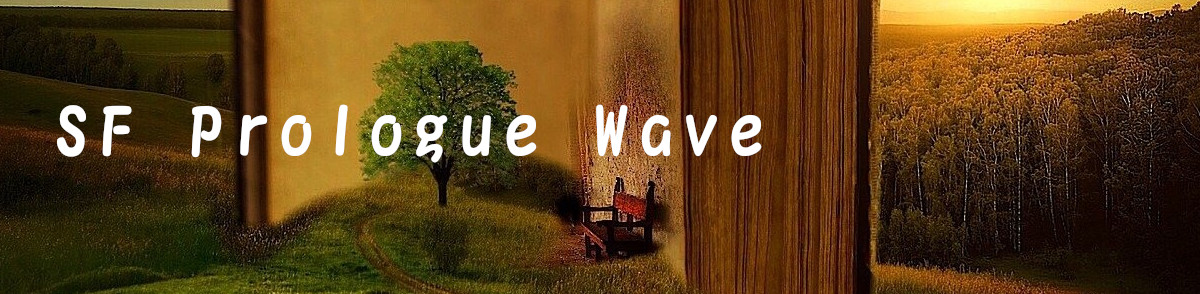●はじめに(岡和田晃)
服部伸六氏の仕事を再録していく企画の第5回は、「詩学」1979年7月号に発表された「詩人・大統領サンゴールの日本訪問」をお届けします。この号には、インゲボルク・バッハマンやマリヤ・ルイゼ・カシュニッツ、ギュンター・アイヒら「ドイツ詩人による原水爆の詩」(鈴木俊訳)が掲載されているのが印象的でした。
詩人にして大統領のサンゴールについて、服部はたびたび言及してきましたが、そうした関心は、「外務省の役人」でありながら詩人という、服部氏自身の経歴に由来するところも大きいでしょう。ネグリチュードについての解説は明快ですし、「なぜ詩人にして大統領という人物が成ったのか」という氏の仮説には、コロンブスの卵というところがあります。これまでと同じく、文字起こしと注釈は大和田始氏が担当しておいでです。
詩人・大統領サンゴールの日本訪問
服部伸六
アフリカのおデコのところにある黒人の国のセネガル共和国の大統領、レオポール・セダール・サンゴールは、詩人として有名である。
その詩人大統領が、4月16日から約1週間、日本を公賓として公式訪問を行なうことになり来日した。今この文章を書いている19日現在、セネガルからのお客さんの一行は、新幹線に乗って関西へ向けて旅の途中であるはずである。
わたしも、外務省の役人として、たびたびアフリカへ出かけたことある関係で、今回三回ほど詩人大統領にお目にかかる機会を与えられたので、この詩人の印象などを少しばかり書き残すことにする。
サンゴールの生い立ち
しかし、その印象を書くまえに、サンゴールの生い立ちから、詩人サンゴールの誕生について書いておかねばならないであろう。
サンゴールは1906年、当時フランス領西アフリカの総督府のあったダカール市の南方約100キロの地点にある、ジョアルと呼ばれる海辺の村に生れている。父は富裕な家畜商で、詩人はその伝統的アフリカ社会の暖い雰囲気のなかで成長しているが、この幸福な幼時の思い出は、絶えずサンゴール詩の主題となっている。
家がカトリック信者であったことから、幼時はカトリックの神父の下で教育をうけるが、中学へ進む年ごろから、ダカールの学校へ送られる。大学入試資格(バカロレア)を取るのは22歳のときで、これは比較的遅れているといわねばならない。彼はそれからフランス政府の奨学金を得て、パリの名門校ルイ・ルグラン校へ進み、そこで友人として、のちフランス大統領となることになるジョルジュ・ポンピドゥや、アカデミー会員となるティエリー・モオニエなどの友人を得る。ソルボンヌへ進んだサンゴールは、教授資格試験を受けるためフランス国籍をとることになるが、これがたたって(というべきかどうか)のち、第二次大戦へ参加することになる。しかし、当時はセネガルは仏領であったのであるから、理論的には、すでにフランス国民でなければならなかった筈であるが、セネガル人でもフランス国籍をもつことのできたものはく一部であったということである。彼の属するウーロ族には、これが与えられなかったという。
1939年、ドイツのヒットラーの軍がマジノ線を破って侵入をはじめるや、詩人は動員せられ、陸軍二等兵として大戦に参加することになるが、間もなく1940年6月には捕えられてキャンプに入れられて虜囚の身となる。だが、この二年間のキャンプぐらしは詩人にとって反省のよい機会となった、と後年彼は回想してのべている。彼にとって、この二年間は、古典をよみ、ドイツ語を学習し、ヨーロッパ文明について、新しいアフリカの未来について、思いをめぐらせるよいチャンスであったのであろう。
ネグリチュードの誕生
パリでの学生の時代、彼はアフリカやカリーブ海出身の学生と接触するが、とくに、カリーブ海からやって来た、エーメ・セゼールとレオン・ダマとの交友は、ネグリチュード運動を生むことになった。
この二人を合わせて三人で発行した詩誌「黒人学生」や「正当防衛」で、はじめて「ネグリチュード」なる語が用いられるようになる。1945年に、サンゴールの編集になる「黒人詩華集」は、そのころ世界の思潮のうずまきの中心にあったジャン=ポール・サルトルの序文「黒いオルフェ」によって注目を集めたが、サルトルはそのなかで、黒人詩人にとって異国語であるフランス語に、新しいリズムを与えたことを強調している。まさに、ヨーロッパ流の客観的合理性に対して、主観直感性のアフリカ詩人のリズムはショックを与えたにちがいない。
しかし、アフリカ人のヨーロッパ文化に対する寄与は、これが初めであったわけではない。すでに20世紀のはじめ、ピカソやブラックは黒人彫刻に啓発されて立体派を創始していたし、詩の分野では、サンドラルスが編んだ「黒人詩華集」があり、アポリネールの「カリグラム」や「アルコール」があった。また、アメリカでは、黒人による音楽の革新がはじまっていて、そのジャズやブルースは世界を風靡していた。
だから、サンゴールの「詩華集」は、「はじめ」ではなくて、彼ら黒人学生が30年代にはじめていた第一期黒人文化運動の結論であったといえよう。
1945年はまた、サンゴールが第一詩集「陰(かげ)の歌」を出版した年でもあった。48年には、第二詩集「黒いいけにえ」が出版される。サンゴールの時には、ポール・クローデルや、サン・ジョン・ぺルスの影響が深く、いわゆる唱詩(ベルセ:註1)の様式が用いられているとの評を得ている。しかしサンゴール自身は、これを否定して、西欧流の「抽象概念」には、彼の詩は無縁であるとのべている。そして「芸術のための芸術」には嫌悪を示すのである。
今回の日本訪問にあたって、赤坂迎賓館で行なわれた日本文化人との懇談の際も、このことを確認して、「だから、ポール・ヴァレリーの詩は、わたしは評価できません」と、のべていた。
サンゴールの詩法は、だから、具体的な物のイメージを通じて、リズムと音楽によって芸術を創造するという道がとられるのである。
「イメージというものは、黒人にあっては、リズムを伴わないならば、何らの効果も生まない」(「ネグリチュードとユマニズム」)とのべているが、じじつ、サンゴールは、その時のほとんどに、伴奏となるべきアフリカ楽器を指定しているのである。
ネグリチュードとは何か
サンゴールら黒人学生が作り出した文化運動「ネグリチュード」とは何であろうか。
この語は、文法学者であるサンゴールの造語であるかも知れないが、黒人を意味する「ネグロ」と、状態を意味する「チュード」という語尾から成っている語で、訳すれば、「黒人であること」ということになろう。
今回、来日中に、明治大学から「名誉博士」号が贈られ、その記念講演のなかで、詩人はこれを説明して次のようにのべた。
「このネグリチュードという語は、わたしの国のマリンケでいうところの人間の定義に対応した言葉、「モ・キン・リン」(この語は、サンゴールの口からいわれた言葉を移したものであるが、あるいは聞き方が悪く、原語とは異った表記になっているかも知れない)という言葉、つまり「小さな 黒い 人」という意味の翻訳であります。小さいというのは、体格が小さいという意味ではなく、神に対して小さく、力弱いものという意味であります。」
つまり、全能の神に対して卑小なる存在にすぎぬ人間、それも黒人存在という意味にほかならないのであろう。
もうひとついえば、ここでは、西欧人が、神様をさぐり当てるにも、論理を使って、推論的に神をつくり出すのに反して、アフリカ人は、直感で神をさぐり当てるという、認識の仕方の差異を強調しているのだと、わたしは理解するものである。
サンゴールは、こういう語の名人であって、フランスらしさを「フランシテ」と呼び、アラブ文化を指して、「アラビテ」と呼び、アフリカ人の像を「アフリカニテ」と呼んでいるが、日本について何と呼ぶであろうかと、実は、わたしは興味をもっていたのだが、「ニッポニテ」という語が飛び出したので、想像はしていたものの、さもありなんという感を抱いたものである。
諸文明の交流
詩人サンゴールは、同時に一国の元首であり、政治・経済においても国民の運命を背負っている人であり、当然、物質文明、精神文明全体に対して関心を持っており、人類の未来についても思索を重ねている筈であり、そういう発言もあったのであるが、ここでは、こと詩文学のことだけに限ったわけである。
18日、赤坂迎賓館で行なわれた日本文化人との懇談会は、途中、フランス料理の中食を含んでの、いわゆる「デバ・デジュネー(註2)」であったが、ここで親しく詩人に接することができたのは、楽しかった。大統領は、予想に反して全く親しみ深い話し口で、個人的な想い出話など混えて話してくれた。話し相手の日本側には、フランス語の大家で、現在国際文化会館の専務理事の前田陽一氏、作家の辻邦生氏、美術史家の秋山光和教授、アフリカ文学の土屋哲明大教授、アフリカのフィールド・ワークで有名な文化人類学の川田順造氏など、末席に変な詩人のわたしを含めて八名であった。
サンゴールは席上、日本の俳句を引用して、日本の文化が、西欧の文化と質を異にしており、アフリカの文化に似たところのあることを指摘して、今や、西欧中心の文化は行きづまり、新しい文化、新しい発想による哲学が生れねばならないことを強調し、そのためにも、諸文明が、それぞれの異った文化が、新しい文化を求めて協力すべきであると、結んでいたのが、極めて印象的であった。
なぜ 詩人大統領か
おそらく読者は、アフリカで何故詩人の大統領が生れたか、いや、生れねばならなかったか、という疑問を持たれるにちがいない。そこで、この疑問に答えるわたしの回答を書いて、この短かい文章を終ることにする。
フランスにしても英国にしても、その植民地を統治するに当って、現地人のなかから、統治行政の職員を育てる必要にせまられていた。そこで、出来のよい現地人を本国へ呼んで教育を与えたのだ。パリやロンドンへの留学生は、こうして生れたのであるが、この留学生たちにとって自己を表現する道は、文学へ近づくことが、それも詩文学へ進むことが、もっとも手取り早く、且つネグリチュードを発揮することのできる道であった。科学や軍事やという道は、自然であるアフリカ人には困難であったばかりでなく、宗主国にとって、文明の技術を被支配の民に教えこむことは得策でないと考えられたのである。
そこで、多くの学生が詩人となったわけである。1960年の当時、新たに独立したアフリカの国の指導者のなかには、何と多くの文人がいたことであろう。当時、ダホメといっていた現在のペナンの最初の大統領アピチイ(註3)も詩人なら、コンゴーの動乱で死んだ独立国コンゴーの英雄パトリス・ルムンバも詩を書いていた時代があり、最近独立したアンゴラの大統領アゴスチノ・ネトも詩人として有名である。
サンゴールの同志であった、エーメ・セゼールは、最近はフランスからの独立は断念したものの、初期においては反植民地主義の闘士であり、一時はフランス共産党に加入していたことがある。しかも現在、故郷マルチニック島のフォール・フランス市の市長であり、フランス国会に議席をもつ政治家である。
レオポール・セダール・サンゴールは、これら詩人政治家たちのなかにあって、最もすぐれた詩人であり、哲学者であり、政治家であり、1960年の独立から、現在に至る19年間、一貫してセネガル共和国の運命を背負ってきているのである。
彼はアフリカの伝統を身につけると同時に、フランス文化についてもフランス人以上の含蓄があり、とくにマルクシズムを克服するものとして、チャール・ド・シァルダン(註4)の哲学に心服していることを隠さない人である。
彼の説く「社会主義へのアフリカの道」というのは、地方組合主義を基盤とする共同体の完成である旨、来日しての談話のなかにしばしば言及したが、この社会主義は同時に、世界の他の国の政治、文化、思想と交流し、「混血」を行なうべきことを強調したが、この感想は、あながち、日本へ来たための、招待国への讃詞として聞き流すだけのものではないと、わたしには思われた。
註釈:
註1:唱詩(ベルセ)verset 〖詩法〗一呼吸をリズム単位とした詩、その一節。
註2:デバ・デジュネー débat déjeuner 父の書架に辻邦生さんの『背教者ユリアノス』があり、川田順造さんには著作が出るたびに送っていただいたのはこの時の縁だろう。
註3:アピチイはアピティの誤植か。ただしダホメ共和国(1958年〜1975年)の初代大統領はユベール・マガとされている。
註4:チャール・ド・シァルダンはテイヤール・ド・シャルダンのことであろうか。