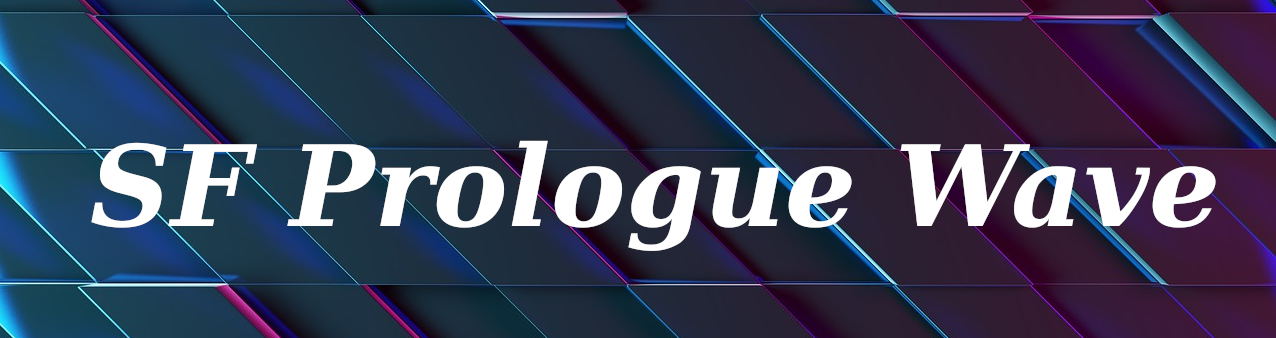五時間目は理科。私たち二年三組は今、「生物の体のつくりと働き」の単元を習っていて、今日はイワシの蘇生(そせい)実験をする。
実験に使うのはカタクチイワシの幼魚を乾燥させたもの――つまり煮干しだ。
四人の班ごとに一匹の煮干しが入った蓋つきのペトリ皿が配られる。昨日の理科の時間に、人間用よりも少し濃い生理食塩水と蘇生液Aを入れて浸しておいたものだ。
「では、まず、イワシの様子を観察してノートにメモしてください。昨日の状態からどこがどう変わったかな?」
かなえ先生が注目ポイントを黒板に書き出す。
・体の表面の様子
・触ってみた体のかたさ
・あごやヒレなどが動かせるかどうか
「体が大きく傷つくと蘇生がうまくいかないから、やさしく触ってね」
昨日はカラカラに乾いて硬くてちょっとねじくれたようになっていて、生き物っぽい感じは無かったのに、まる一日溶液に浸けたあとの煮干しはツヤと柔らかさを取り戻し、体も真っ直ぐに伸びている。ちょっと触るだけで折れそうだったヒレやあごも少し動かせるようになった。
「だけど、まだ死んだままだな」
同じ班のハシケンが雑な字でノートに「白目をむいてる」と書いた。
確かに煮干しの目は白い。通りがかった先生がそれを見て「ああ、林君はいいところに気がついたね」とクラスみんなに向かって言う。
「イワシの目には、みんなのと同じように真ん中に虹彩と瞳孔があるから、生きているときは黒く見えるんだけど、ヒトだとその内側に水晶体って透明な部分があるって覚えてるかな? 厚くなったり薄くなったりするレンズの役割をするところだよね? 魚類にも同じく透明な水晶体があるんだけどボールのような球形で、ヒトのよりずっと前に飛び出ています。で、この水晶体はタンパク質でできているので、熱を加えると白くなっちゃうのね。煮干しは一度煮てるので、その時に目が林君の言うように白目になっちゃうわけです」
思わぬところで誉められたハシケンはちょっと赤くなっている。かなえ先生は美人でかっこよくて生徒に人気があるのだ。
「じゃあ、イワシに針を刺すので、観察が終わった班から前に持ってきて」
点滴の針を刺すのは中学生には難しいので、先生がやってくれる。
実体顕微鏡のステージに乗せたイワシに、下から強いライトを当てて、尾の付け根にある太い(と言っても直径一ミリもない)静脈に針付きのプラスチック管を刺し、うまく刺さったのを確認したら針は抜いてプラスチック管だけが血管に入っている状態にする。管の外に出ている側の端に輸液ルート(これも柔らかいプラスチックの管)をつないで点滴の準備が完了する。
「人間の病人の場合は、一秒間に一から五滴くらい入れたりするんだけど、イワシは小さいので、二十秒に一滴くらいのゆっくりペースで入れます」
最初の十分間は生理食塩水と蘇生液Aの混合液を、次に五分ほど間を置いてから代替血液と蘇生液Bの混合液をまた十分点滴する。
「みんなの中でもし看護師さんになる人がいたら、これが上手にできないと困るんだよ」と先生が言うと、「うちのお母さん毎日やってる」とヨッシーが言って「うちもー」「うちはお父さん」「新人の時できなくて泣いたって言ってた」と三、四人が続いた。
「そっか、おうちの人が看護師さんやってるって人、結構いるんだね」
「うちは介護士」
「あー、介護士さんも多いよね」
点滴している間は暇なので、あちこちで雑談が始まる。小さなイワシはペトリ皿の底に体の右側を下にして静かに横たわっている。アラームが鳴って点滴の時間の終わりを告げる。
「はい、じゃ、管を抜きます。血管と平行になるように尾ビレの方に向けてゆっくり抜いてください」
私たちの班では、手が器用そうだからという理由で私が抜くことになった。青い実験用ゴム手袋をはめて、先生が図解した通り、片方の手でイワシを押さえ、もう片方で横に管を引っ張ると特に抵抗もなくするっと抜けた。
「次に、二百ミリリットルの生理食塩水を入れたビーカーにイワシをうつして、図のように電極をセットしてください。水溶液の電気分解の時と同じだからわかるよね?」
ピンセットでイワシをつかみ、ビーカーに入れて、その上に電極の炭素棒が刺さった発泡ポリスチレンの板を乗せる。電源装置と電極をクリップ付きの導線でつなぐ。
「いい? 今回は電気分解が目的じゃないので、電流を流すのは約〇・一秒だけだからね。電源装置のスイッチを入れたらすぐ切ってね」
先生は念の為コンセントを差さない状態で、スイッチのオンオフをみんなに練習させた。カチカチッと入れてすぐに切る。
「電流を流してから三十秒くらいイワシの様子を見て、動かないようならまた同じように電流を流します。じゃ、やってみて」
ハシケンが電源装置のコンセントを差して、スイッチを素早くオンオフすると、イワシは一瞬浮き上がって、それからまたビーカーの底に横たわってしまった。教室のあちこちから「あ、動いた!」とか「だめだ」とか声がする。
三十秒待って、もう一度ハシケンがオンオフする。イワシは浮き上がったあと底に沈まず、尾ビレを左右に動かした。
「やった」
「生き返った!」
電極を抜くとイワシは狭いビーカーの中でクルクルと泳ぎ回った。少し体が右に傾いている。
「メダカみてえ」
「メダカより大きいよ」
「目は白いままだな」
「でも、真っ白って言うより半透明になってない?」
班のみんなが口々にいろんなことを言う。
「はーい、どの班も実験成功したようですね。次の授業では、『命とは何か』について考えます。昔は、生きてるか死んでるかっていうのは見たまんまっていうか、動ければ生きてるし、動かなくて息もしてなきゃ死んでるよねってことでよかったんだけど、現代ではこのように完全に死んでるって思えるような生き物でも一応、蘇生が可能になったでしょ? だけど、じゃあ、このイワシは生きてるって言えるのかっていうと、そう単純じゃないよって話です。……ということで、今日はここまで。各班片付けに入ってください。イワシはビーカーごとこっちに持ってきて」
「このイワシ、どうするんですか?」
教卓に持ってきたビーカーのイワシを見ながら、私は先生に聞いてみた。
「せっかく生き返ったのに可哀想なんだけど、先生の方で処分することになってるの。自然には帰せないし、厳密には生きてるとも言えないし」
先生は低い声で、そうはっきり言った。
「あの、私、この子うちで飼ってもいいですか?」
先生は驚いたようだったけど、じゃあ飼育用の水槽と餌と海水の素を用意しておくから放課後に取りにおいでと言ってくれた。
「ただいま」
家に着くと、すぐにシャワーを浴びて滅菌服に着替える。お母さんに許可をもらって、先生が貸してくれた水槽の外側を丁寧にアルコールで拭いて消毒する。
「おかえりー」
子ども部屋に入ると、床でお絵描きをしていたお兄ちゃんが、クレヨンを放り出して私にしがみつく。
「お魚持ってきたよ。イワシだよ」
「おさかな?」
「そう、お魚」
科学は進歩して、一度死んだ生き物が蘇生できるようになった。だけど、今のところ、蘇生されたものは完全にはもとの「生きている」状態には戻らない。
大人では成功例がほとんどないし、希望する人もまずいない。
子どもの場合は成功率が高いけれど、成長が止まり、知能は退行するか停滞して、免疫機能もほとんど働かなくなる。
蘇生された煮干しはいつまでも幼魚のままで、自然界に帰せばたちまち病気に感染してしまうし、三歳の時にトラックに轢かれたお兄ちゃんは、いつまでも三歳児のままで、クリーンルームの中でしか生きられない。
こんな状態で生かしておくのは残酷だとか、不幸だとか言う人が多いのも知っている。それでも、お母さんとお父さんは蘇生を望んだし、私もお兄ちゃんがいるのが嬉しい。
科学は進歩して、いつかお兄ちゃんを完全に「生きている」状態に戻せる日がやってくるかもしれない。それをうちの両親は、待ち焦がれている。
だけど、本当に本当に正直に言うと、私は今のままでも別にそう悪くないかもと思っている。
「おさかな、おさかな」
小さなお兄ちゃんは小さな手のひらを水槽に押し付けて、歌うように繰り返す。
「生きていると言えるかどうか」なんて、本人たちにとっては、どうでも良いことだ。
ぎこちなく泳ぎ回る煮干しも、少し濁った目でそれを見つめるお兄ちゃんも、けっこう幸せそうに、私には見える。