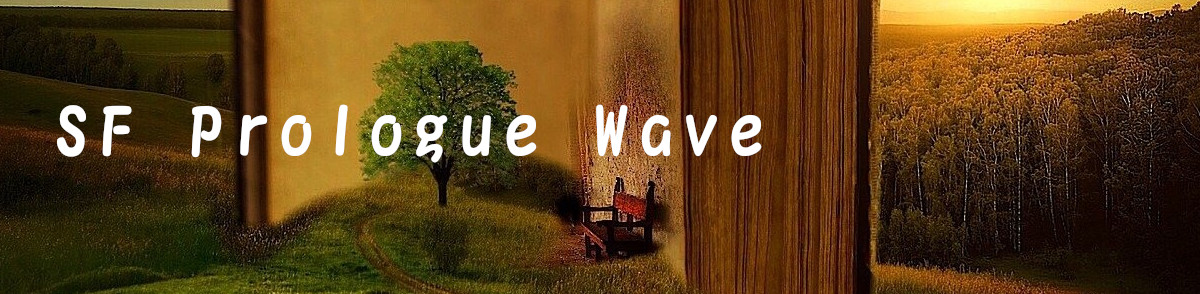書痴の幸福なる死
仁木稔
0
――本に埋もれて死にたい。
最初に、そう言ったのは誰だろう。実在であれ架空であれ度を越した愛書家――本の虫、書痴――が、理想の死を語る文脈で発せられる台詞である。だが考えてみてほしい。雪崩落ちてきた大量の本で生き埋めなんて、最初に失神でもしない限り、長く苦しい死に様だ。地震などでそうして亡くなった人のニュースに接することもあるが、ただただ痛ましい。
とはいえ、〝埋もれたら死にかねないほどの大量の本〟に囲まれた暮らしが、愛書家にとって一つの理想なのは間違いない。部屋は狭くていい。床から天井近くまで、三方ないし四方の壁面を埋め尽くすのは、私が愛する本、本、本、本、本――紙の本ならではの、圧倒的〝実体〟だ。
しかしそんな環境で大往生できたとして、気掛かりなのは遺された本たちの行方である。後を託せる家族や友人に恵まれるのは僥倖(ぎょうこう)だ。そうでないなら理想の晩年は諦めて、元気なうちに自身で納得の行く処分をすべきなのか。いや、若く健康でも明日死なないという保証はない。どうせあの世には持っていけないのだから、死後のことなどどうでもいい――そう考える人も、本を愛していないとは言えないだろう。
ところで、自らの蔵書に埋もれて死んだ最初の愛書家は誰か。最古の記録は明確だ。今から一一五〇年余り前、より正確にはAD八六八年十二月または八六九年一月のイラク南部、ジャーヒズと呼ばれた九〇代の老人である。この通称は、アラビア語で出目を意味する。つまりそういう風貌の持ち主だった。極貧から身を起こし、長短併せて二四〇点余りの著作をものした、人類史上空前のヒットメーカーだ。
私見だが、彼は単に記録の上で自身の蔵書に埋もれて死んだ最古の愛書家というだけでなく、実際にそうである可能性が高い。以下、この仮説を検証していきたい。
1
本、書物と呼べるだけの、まとまった内容と情報量の文書が誕生したのはいつか。紀元前三五〇〇年頃、メソポタミアに経済や行政に関する記録が登場する。多くは縦横数センチの粘土板だった。五〇〇年ほど経って、神話、神や王たちへの讃歌、歴史なども記されるようになった。粘土板も縦横十数センチと大型化したが、二〇センチを超えるものは少なかった。厚さは数センチ、裏表に刻まれた。長い作品は複数枚にわたり、たとえばギルガメシュ叙事詩は、最も欠落が少ない三三〇〇年前のもので全一二枚だった。一枚あたりの情報量は、日本語訳で七千~一万字程度になる。内容はもちろん分量からも、本と呼んでいいだろう。読書という行為の誕生だ。こうした大型粘土板は、棚に立てて並べられた。一枚落ちてきただけで、打ち所が悪ければ死にそうである。
紀元前七世紀半ばには、神殿や王宮といった公的機関だけでなく、書記や神官、悪魔祓い師ら平民の個人もそれなりの規模の蔵書を有していた。空前の文書蒐集家だったアッシリアのアッシュルバニパル大王が、彼らからも蔵書を接収している。だが残念ながら大王その人も含め、彼ら蔵書家たちは誰一人として愛書家ではなかった。
古代メソポタミアでは、文書はすべて実務用だった。大王、神殿、個人の蔵書いずれにおいても、最も大きな割合を占めていたのは前兆の書である。国家も個人も、前兆によって導かれていた。次に多かったのは宗教や魔法の技術書、三番目が読み書きの訓練に必要な教材類だった。叙事詩や讃歌といった文学作品はわずかで、それらも安産祈願など特定の目的のために特定箇所が読み上げられるだけだった。つまり二番目の技術書に該当する。ギルガメシュ叙事詩は素晴らしい物語であり、感動した読者はいたに違いないが、感動が目的で読んだ者はいなかったのだ。
アッシュルバニパル大王と同時代のエジプトにも、大規模な図書館があったことが記録されている。しかしパピルスの蔵書はすべて失われ、実態は明らかではない。愛書家のエジプト人が存在していたかも不明だ。
愛書家の登場が確実なのは、古代ギリシアである。紀元前五世紀、ソクラテスは書物を記憶力も思考力も損なうとして嫌った。同時代の悲劇作家エウリピデスは、両腕に抱えるほどの本を所有する変わり者、と年下の喜劇作家アリストパネスに揶揄された。しかし読書人口は着実に増加しつつあり、この時代には書籍商の存在が確認されている。人々は愉しみのために読書した。詩や戯曲など、愉快な内容で笑うのはもちろん、悲しみで涙を流すのも娯楽だった。哲学(フィロソフィ)書を読んで知への愛(フィロソフィ)を高めた。ソクラテスの思想も、弟子たちによって書き残された。
前四世紀前半には、大きな書架を並べた書斎を所有する者も現れた。彼らの中に、自らの蔵書に埋もれて死んだ者はいるだろうか。書架ではなく本だけで、圧死または窒息死した者である。ここで問題になるのは情報の容量だ。この時代のギリシアの書籍は、パピルスの巻物だった。縦およそ三〇センチ、長さは自由だが、『イーリアス』と『オデュッセイア』はそれぞれ二四巻だった。日本語訳はどちらも文庫二巻本である。
同じ本を繰り返し読むのも、愛ではある。しかし大量の蔵書に埋もれて死ぬような愛書家は、すなわち濫読家だ。やはり本一点当たりの容量も重視したい。文字どおりの万巻の書も現代の冊子体に換算すれば、情報量はせいぜい十分の一だろう。書物が巻子体だったのは、パピルスが片面しか使えない上に脆くて折り畳めなかったからだ。冊子体の原型は、蝋を塗った木板を数枚重ねて綴じたもので、メモ帳として使われてきた。両面が使える獣皮紙が普及したことで、この形態の書物が生まれた。皮革は四千年以上前から書写に利用されていたが、これは片面しか使えなかった。伝説によれば獣皮紙の発明は紀元前三世紀、現トルコのペルガモンにおいてである。
獣皮紙の冊子体は当初、数枚を二つ折りにして綴じただけのものだったが、巻子体より遙かに容量が大きかった。膨大なウェルギリウスが、なんとちっぽけな書冊に収まっていることか――紀元八〇年代、ローマの詩人マルティネスの言葉である。製本技術が向上すると、さらに多くの紙葉を綴じられるようになった。例えば目次を付けられるかどうかという一点だけを取っても、冊子体はハードウェアとして巻子体より遙かに優れている。読む速度は上がり、さらなる多読を可能にする。獣皮紙自体、パピルスより耐用性が高く、生産地も限定されない。
それでも大量の仔牛または羊の皮を加工するのは、金も手間も掛かった。しかも実は、容量の問題は解決していない。嵩張らないが重いのだ。時代は下るが八世紀初頭、英国の『リンディスファーン福音書』は仔牛の皮一二八頭分を要し、金銀宝石を使った装丁込みとはいえ、八・七キロもあった。因みに今、手許にある岩波文庫版福音書――解説その他付き――は二二六グラムである。獣皮紙は高級なほど薄い。最高品質を用いたはずの『リンディスファーン』でさえ、こうである。四世紀、ローマの哲学学校における学生の喧嘩では、教科書が強力な投擲武器として活躍したという。
ローマとその文化は衰退し、識字率は低下した。読書の喜びは、一握りの知識人だけのものとなった。彼らの大半はキリスト教徒だったので、異教徒の著作を愉しむことに罪悪感を抱いた。その他の信徒たちは、喜び勇んで異教を排斥した。五二九年にはアカデメイアが閉鎖される。プラトンが創設した学園だ。古代ギリシア以来の学問は、東ローマ帝国とサーサーン朝ペルシアの狭間に位置する都市ハッラーン、およびペルシア領内でかろうじて命脈を保つことになる。
サーサーン朝の皇帝たちは、ギリシア語とサンスクリット語の書物を熱心に蒐集し、ペルシア語に翻訳させた。宗祖ザラシュトロは、光明神アフラマズダから授かった知識を書物に著した。だがその書は侵略者アレクサンドロスに奪われ、知識は世界に拡散した。奪われたものは取り戻さなければならない――それは皇帝たちの悲願だった。
数多くの学術書と若干の文芸書が翻訳されたが、ペルシア文化への影響は医学を除けばわずかだった。歴史書、教訓書、『千夜一夜』の原型となる物語集など独自の作品もペルシア語で書かれたが、あいにく読者は少なかった。ペルシア語の表記体系は極めて不完全な上に複雑で、習得は非常に困難だったのである。
現代の本、すなわち植物繊維を原料とした紙の冊子体は、それまでのどんな形態の本よりもサイズと重量に対する情報量が大きい。植物繊維紙は紀元前に中国で発明されたが、それが冊子体として製本されるようになったのは七世紀以降、おそらく八世紀だった。東アジアにおける冊子体の原型は、巻物をアコーディオン状に折り畳んだ折帖である。冊子体の誕生に先んじて木版印刷も発明されており、多くの情報が収録され、扱いやすく、かつ安価な本の大量生産が可能となった。
にもかかわらず印刷された冊子体が普及したのは、九世紀半ば以降のことである。それらはすべて、科挙の受験参考書だった。この状況は一〇世紀以降も続く。
もちろん中国でも、趣味の読書は行われていた。その歴史は古く、四、五世紀には詩作や著作が書道、碁などと並んで貴族の嗜み、教養の一つとされていた。だがやがて教養は競い合うものとなり、古典クイズのような遊びが盛行した。詩も文章も、独創性ではなく如何に古典を切り張りできるかで評価され、原典を直接確認しなくても済むよう、事典の類も多く作られた。
このような遊戯に興じる貴族たちは当然、千巻、二千巻といった個人蔵書を抱えていた。六世紀以降は万巻、二万巻の蔵書を誇る者も現れた。書籍商の類は存在しなかったから、蔵書を増やしたかったら人に頭を下げて写させてもらわねばならず、そこに力関係が発生する。蔵書家の誰も、書物の大量生産など望まなかった。冊子体の利便性も軽蔑の対象だった。
貴族にとっても平民にとっても、教養は出世のための武器であり、読書はその獲得手段だった。果たして彼らは、読書そのものを愉しんだのだろうか。
九世紀中葉、ドイツ、ロルシュ修道院…五九〇冊
九世紀後半、スイス、ザンクト・ガレン修道院…四二八冊
十世紀、ある司教…五七冊
九世紀、コルドバの図書館…四〇万冊
十世紀、バグダードの高官…一万冊
修道院は中世を通じて西洋文化の中核だったが、一三世紀に至るまで数百冊という蔵書数は突出した規模だった。個人蔵書五七冊は、当時の常識を超えていた。一方、バグダードの一万冊は、最大級ではあるものの随一ではなかった。
七五一年、現キルギスのタラス河畔で唐とイスラムの大軍が激突した。この時の捕虜に紙工がおり、イスラム世界に製紙法を伝えた――一〇世紀のアラビア語文献を根拠とした通説だが、これに疑義を呈する研究者は少なくない。中東では八世紀末までに亜麻の襤褸(ぼろ)を原料とする紙が大量に生産されるようになっていたが、中国の紙は草木を原料とする。また現ウズベキスタンのソグド地方では、八世紀初めに書かれた紙の現地語文書が発見されている。残念ながら研究が進んでおらず原料は不明だが、中国からの輸入品ではなく地元産なのは確実なようだ。
いずれにせよ出目のジャーヒズが筆一本で身を立て、自らの蔵書に葬られるためには、安価な紙の普及が絶対不可欠だった。なおイスラム世界の本は、最初期から冊子体である。亜麻布紙はインクが滲みやすいため小麦澱粉で表面を処理する必要があり、また装丁も革だった。同じ頁数、同じ縦横サイズでも現代のハードカバーより重い。それでも獣皮紙冊子体とは比べ物にならないほど軽かった。
ジャーヒズは七七六年頃、イラク地方随一の文化都市バスラに生まれた。本名は重要ではない上に長いので割愛する。解放奴隷、すなわち非アラブを両親とする彼の肌の色はかなり濃く、祖父が黒人だとする史料もある。家は非常に貧しかったが、学校で読み書きを学び、モスクや市場で行われる学者の講義を聴いた。講義後に行われる討論にも参加した。
バスラから数百キロ北上すると、当時の首都バグダードに至る。ジャーヒズが生まれる十年前に完成した円城都市だ。ペルシアやハッラーンで保持されていたギリシア・ローマの学術書は、カリフの命によってここで翻訳、研究されていた。ジャーヒズは講義や討論を通じ、蘇った古代の知識を身に着けた。親しくなった文人たちから本を貸してもらうこともあっただろう。ある日、ジャーヒズが帰宅すると、母親からたくさんの――彼自身の言によれば〝盆に山盛りの〟――ノートを与えられた。「これを活計(たつき)としなさい」
当時の一般的な書籍刊行の手順は、次のようなものだった。作家は作品をモスクや市場で読み上げる。好評を得ると、書籍商が買い取って書写、製本を経て発売する。書籍商は売れそうな作品を常に探しており、作家を兼ねている者も少なくなかった。同時代の中国と異なり、各部数は少ないが作品数は多かった。
巷に本が溢れている――それは、人類が初めて目にする光景だった。しかもその一五〇年足らず前まで、アラビア語の書物はこの世に一冊も存在しなかったのだ。その後も半世紀以上、アラビア語作品は一点しか存在しない時代が続いた。たった数十年でこの変わりようである。
ジャーヒズの死より一世紀ほど後、バグダードの書籍商イブン・ナディームは『目録の書』を著した。当時バグダードで入手可能な書籍、および入手困難だが存在は知られていた書籍六六〇〇点余りが記載されている。題名だけでなく、その概要と著者の略歴までが記された貴重な史料だ。六六〇〇は作品数であり、複数巻にわたる大著は珍しくなかった。例えばジャーヒズの『動物の書』は全七巻だ。彼以前の作品はそもそも数が少なく情報も乏しいが、『目録』までに刊行された作品を挙げれば、翻訳書『ナバティア人の農書』が七巻、西洋ではラーゼスの名で知られるラーズィーの医学書が二三巻、タヌーヒーの逸話集『座談の粋』一一巻、マスウーディーの歴史百科事典『時代の情報』三〇巻等々となる。したがって『目録』と同じ一〇世紀の、個人蔵書一万冊という数字は信憑性が高い。九世紀のコルドバの図書館蔵書四〇万冊は、さすがに眉唾だ。
同時代の文人たちが伝えるところによると、ジャーヒズはある時期、本屋の二階に間借りしていた。夜番を任されたのをいいことに、本を読み耽っていたという。文筆家としての下積み時代のことだろう。彼は一度読み始めると、読み終えるまで本を離すことがなかった。己の死後も刊行され続けるであろう多くの本を想い、それらを読めないことを嘆いていた。
2
ここからは、ジャーヒズが如何に本を愛したかを見ていこう。彼が初めて文名を揚げたのは八一六年、四〇歳頃とだいぶ遅い。信仰と理性についての小論が時のカリフ、マアムーンの目に留まったのだ。これ以前の作品は、まったく知られていない。
これを機にジャーヒズは、バグダードに移住した。カリフに招聘されたわけではない。マアムーンはその三年前、カリフだった兄を処刑して即位したものの、支持基盤のある東ペルシアに引き籠っていたのだ。内乱で荒れ果てた円城都市に、ジャーヒズはカリフお墨付きの小論一本を頼りに乗り込んだ。
三年後の八一九年、カリフがようやくバグダードに戻って来た。ジャーヒズはすでにある程度の名声を得ていたようで、文書庁の書記に登用された。そして不明の理由によって三日で辞めた。次いで王子の家庭教師に任じられたものの、すぐに罷免。幼い王子が彼の顔を怖がったからだという。出目に加えて色黒というのは、確かに伝統的なアラブの美意識にはそぐわない。それから半世紀、文筆業に専念した。著作は書籍商に売るだけでなく、しばしば有力者に献呈し、その返礼は時に金貨数千枚に達した。
アラブ文学史上、ジャーヒズは〝散文文学の確立者〟と位置付けられている。アラブの伝統では、散文は芸術と認められていなかった。その地位を引き上げ、かつ幾つものジャンルを開拓したのがジャーヒズである。現存している作品は三〇点。散逸した二一〇点余りも、イブン・ナディームの『目録』から題名と概要を知ることができる。
ジャーヒズは自らの作風を〝真面目と冗談〟と呼んだ。真面目な主題に冗談を織り交ぜて、読者を飽きさせない手法である。その結果、網羅的な話題と短い逸話や蘊蓄(うんちく)の集成が、彼の作品の特徴となった。この形式は、後に教養(アダブ)文学と呼ばれるジャンルへと発展する。現存作品では、博物誌『動物の書』とアラブ修辞学の嚆矢(こうし)『雄弁と明解の書』が、その典型とされる。〝冗談〟だけの作品もあり、唯一邦訳のある――ただし全体の三分の一――『けちんぼども』は実在人物たちの吝嗇(りんしょく)譚を中心に、当時横行していた詐欺の手口などもおもしろおかしく紹介する。また架空の人物たちが議論する形式のフィクションも著し、論争文学というジャンルの基礎を築いた。これも多くは真面目な主題を扱ったが、現存する『ジャーリヤとグラームの書』は、女奴隷(ジャーリヤ)と稚児(グラーム)のどちらが性交の相手として優れているか女色家と男色家が議論するというものだ。内容はもちろん、表現もだいぶ露骨らしい。
八三三年、カリフ、マアムーンは死去した。弟のムウタスィムが即位し、三年後にバグダードの北一二五キロに新都サーマッラーを建設した。ジャーヒズも移住し、以後はそこを活動の場とする。
このサーマッラー時代、ジャーヒズは当世三大愛書家に数えられていた。後の二人のうち、イブン・イスハークという名の判官については何も知られていないが、ファトフ・イブン・ハ―カーンは第二王子の腹心だった。可汗の息子(イブン・ハーカーン)という名からも明らかなように、父親はトルコ系部族の長(ハーカーン)で、カリフ、ムウタスィムの将軍を務めた。ムウタスィムは兄マアムーンの時代から続く政情不安に対処すべく、中央アジアのトルコ騎兵から成る新軍団を設立していたのである。ファトフ自身は長じて当代随一の文化人となり、多くの学者や作家を支援した。四〇歳ほど年長のジャーヒズもその一人である。ファトフの邸宅には広大な私設図書館が併設され、文化人が集うサロンを形成した。
新設の軍団に対し、旧来の軍は激しく反発した。バグダード市民も、辺境の騎馬民族を蛮族として恐れ憎んだ。サーマッラー遷都の理由である。新都のトルコ人たちはカリフの庇護に驕り、まさに蛮族の振る舞いを見せた。こうした中、ジャーヒズは彼らを擁護する小論『トルコ人の美徳』を執筆した。ファトフを通じてカリフに進呈されるはずだったが、ジャーヒズ自身の言によると〝その説明が長くなる理由〟によって差し止めになってしまった。執筆の労を無駄にしたくなかったのか、後日しれっと刊行している。
八四七年、ジャーヒズが七〇歳の頃、第二王子がカリフ、ムタワッキルとして即位し、ファトフの権勢はさらに高まった。しかしトルコ人の扱いには苦慮することになる。彼らの力を削ごうとした結果、ムタワッキルとファトフは八六一年に暗殺された。
政変後、ジャーヒズは故郷のバスラに帰った。伝えられるところによると、自邸で〝女奴隷――すなわち妾――一人、下女一人、下男一人、驢馬一頭〟と共に暮らした。中東の住宅は中庭が基本であり、ジャーヒズの書斎も中庭に面していただろう。優美な飾り格子の窓は大きく、三面の壁は造り付けの書架が占め、床にも背の高い独立書架が並ぶ。一三世紀前半の写本挿絵には本を平積みにした書架が描かれているが、九世紀のジャーヒズもそのように収納していただろう。
……小さな地震だったのだろう、平積みの本が落ちてくる程度の。イラクは地震の発生が少ないが、東隣のイランは世界でも有数の地震多発国である。バスラはイラン国境に近く、たびたび余波を被っている。
アラブ文学史に偉大な足跡を残したジャーヒズだが、後世の少なからぬ学者、文人からの評価は低い。最も酷評されたのは、詩才の乏しさだ。現代に至るまで、詩はアラブの文学、いや芸術の粋である。なお欧米および日本では彼の詩はまったく研究されていないが、アラビア語の論文が一本だけ、一九七四年に書かれている。現存作品はあるのだろうか。
散文への批判は、その独創性の欠如に集中している。古来の伝承や他者の著作からの引用を並べるだけで彼自身の言葉はほとんどない、というのだ。『目録』のイブン・ナディームに至っては、一切の引用なしで長い文章を書けるマアムーンが、ジャーヒズを称讃するはずがない、とまで言う。
『けちんぼども』の序文でジャーヒズは、広く知られた話のほうが読者は喜ぶが、敢えて知られざる、文字どおりの逸話だけを収録した、と述べている。実際にそうなのかは、彼以前の同類作品が残っていないので確かめようがないが、少なくとも収められた話のほとんどは、ジャーヒズ自身か身近な人物の目撃談の体裁を取っている。『動物の書』も、彼自身の観察に基づく記述が多いという。一方で『雄弁と明解の書』は確かに引用が多いようだが、これは後期の作品だから、考えを改めて読者の好みに合わせたのかもしれない。
ジャーヒズを批判したのは、彼がまだ生きていた九世紀後半から一一世紀にかけての人々だ。教養(アダブ)文学が興隆し、隆盛した時代である。アダブとは元来、宴席で披露される小咄や短い蘊蓄のことだった。それらを書籍としてまとめたものがアダブの書であり、まさにジャーヒズが確立した形式である。教養人(アディーブ)と呼ばれる人々は、教養(アダブ)書で得たアダブを宴をはじめ社交の場で開陳した。教養(アダブ)とは、そういうものになった。
やがてアダブ書は著述されたものではなく、他者の書物からの抜粋を編纂した撰文集が主流となる。ジャーヒズの批判者たちは独創性を重視したが、教養人の多くはそうではなかったのだ。一〇世紀後半、つまり批判者たちと同時代のある文人は、思うままに書き散らせばいいだけの作文よりも、理性に基づいて行う撰文のほうが優れている、といった主旨のことを述べている。新奇なもの、独創的なものは好まれなくなった。誰も読まないのであれば、誰も新たな文章など書かなくなる。
この退行は突き詰めれば、社会の保守化が原因だ。社会の保守化の原因は、二つないし三つに絞れる。まず、トルコ人軍団の専横。彼らはカリフの権威を地に堕とした。次に、ムウタズィラ派の専横。九世紀前半に勃興した彼らが旧来の神学を弾圧した反動で、イスラムは急激に保守化した。
ムウタズィラ派と守旧派の争点は、端的に言えば〝創造された聖典(クルアーン)〟である。唯一神が全存在を創造した以上、聖典も被造物である。現代の異教徒には妥当と思えるこの考えに、聖典を神聖視する信徒たちは激烈な拒絶反応を示した。ムウタズィラ派神学を生み出し信奉したのは、ギリシア哲学によって論理的思考を身に着けた人々である。同じく外来思想を愛好するカリフ、マアムーンに取り入り、勢力を伸長した。彼の治世の末期には、自派以外を弾圧する機関、異端審問所を創設させるに至る。
続く数代のカリフの下で、ムウタズィラ派は権勢を振るった。修辞学を知らない守旧派は議論で敵わず感情的に反発するばかりだったが、民衆は彼らに同情し、犠牲者として崇敬した。それは裏返せばムウタズィラ派とカリフへの反感であり、アッバース朝が推奨してきた外来の学問への反感でもあった。
ジャーヒズの晩年までに、イスラム世界は外来の学問を吸収し終え、新たな知と技術を生み出す段階に来ていた。しかしその動きはすぐに減速し、停滞してしまう。一〇世紀の前半にはアシュアリーという神学者が聖典の記述を基に、世界は神によって一瞬ごとに破壊と再生を繰り返していると説いた。つまり如何なる物理法則をも否定することになり、科学が発展する余地は皆無になる。皮肉なことにこの理論は九世紀のムウタズィラ派神学者、ナッザームの理論を発展させたものだ。アシュアリーはムウタズィラ派からの転向者で、かつての宗旨を徹底的に攻撃し、その衰亡を速めた。
ナッザームは、ムウタズィラ派神学を確立したアブー・フザイルの甥である。異端審問を主導したのは、この二人だった。ジャーヒズはバスラ時代、彼らに感化されてムウタズィラ派となった。著作からは、特にナッザームへの深い尊敬と友情が窺える。彼はジャーヒズより十歳ほど年下だが、没したのは二十年余り早い八四五年頃だった。その後の数年で異端審問所は廃止され、ムウタズィラ派はカリフの庇護を失った。しかし守旧派はムウタズィラ派のような異端を生む要因として、外来思想だけでなく読書という行為をも危険視した。学生が本一冊読むにも、好き勝手な解釈をしないよう教師の指導が必要とされ、書物に耽溺する文化は失われていった。
アッバース朝の下、イラク地方に咲き誇った文化の名残りは一二五八年、モンゴル軍によって完膚なきまでに踏み躙られる。モンゴル人の興隆は、トルコ人の西進によって生じた勢力の空白が一因である。そしてトルコ人の移動を加速させたのは、アッバース朝のカリフたちだった。
本を愛し本に死んだジャーヒズが、書籍文化衰退の原因一つ一つに多少なりとも関わっているのは、奇妙な偶然であり大いなる皮肉だ。彼は教養書が撰文集と化す道を付けた。その著書によって、外来思想を広めるのに貢献した。ムウタズィラ派の中心人物と親しく、教理書も幾つか書いている。『トルコ人の美徳』をファトフが却下したのは、保守勢力をかえって刺激したり、トルコ人たちを増長させることなどを恐れたからだろう。しかしジャーヒズは自著の公表を選んだ。当代一の蔵書家だったファトフの暗殺は、書籍文化の衰微の始まりを象徴する。
こうしてジャーヒズの死後、新たに刊行されるアラビア語書籍は量も質も低下していった。入れ替わるようにしてペルシア文学が興隆し、優れた学術書や文芸書が次々と著されるのだが、それらがアラビア語に訳されることもなかった。
x
以下は、ただの想像だ。死後も刊行され続けるはずの書物を読めないことを、ジャーヒズは嘆いた。それは言い換えれば、書籍文化の衰退を望んだことにならないだろうか。彼はアラビア語しか読めなかったから、その望みは叶ったことになる。ただの想像だ。百年、二百年先を見通せる者はいない。だが予兆をことごとく見逃すほど、なんの予測もできないほど、彼は愚かだったのだろうか。
四〇も年下の青年の政治的配慮が、彼には理解できなかったのだろうか。読者の嗜好に迎合し、それを助長することが、どんな結果を招くか予測できなかったのだろうか。外来の学問やムウタズィラ派への反感が反動を呼ぶことが、予測できなかったのだろうか。師であるナッザームとその叔父に、彼からなんらかの影響を及ぼしてはいないだろうか。
疑う余地なく明らかなのは、彼の本への愛だけだ。その死が速やかで苦痛が少ないものだったことを、ただ願う。最後に目に映った光景は、一面に降り注ぐ、彼が愛した本、本、本、本、本――