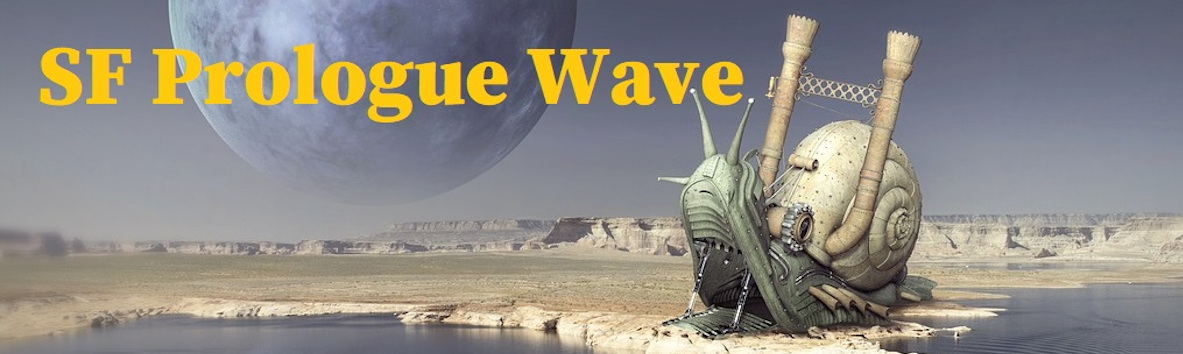「青の炎が気付かせてくれたもの――貴志祐介『青の炎』書評」 アカリ
炎と言えばまず何を思い浮かべるだろうか。赤色、灼熱、火事、熱…。人によって思い浮かべるものは様々だろうが、私は真っ先に赤く燃え盛る火が脳裏をよぎる。私と同じものが思い浮かぶ人はきっと大勢いるはずだ。
しかし、この作品のタイトルは『青の炎』。実際に青い火は存在している。赤色の火より、更に温度が高い。赤色の火は500度~1000度、青い火は1000度~1500度といわれており、硝子を溶かすほどの熱を持っている。青の炎は、静かに燃え滾る主人公櫛森秀一の鮮烈な怒りを、そしてこの物語の結末を表している。
『青の炎』のあらすじをここで紹介しておこう。
主人公の櫛森秀一は、湘南の高校に通う十七歳だ。父親はいないが、母と妹の遥香との三人で平和な生活を送っていた。そこへ、母が10年前再婚してすぐに別れた曾根という男が現れた。曾根は傍若無人な性格で、母と体の関係を持ち、妹の遥香にまで手を出そうとしていた。幸せだった日々を取り返すため、秀一は曾根を誰にもばれないように殺すことを決意するのだった。
以上が『青の炎』のあらすじである。秀一は綿密に計画を立て、実験を繰り返した。そして遂に曾根を殺害することに成功する。最終的に警察に追い詰められ、逮捕一歩寸前で、秀一は決意する。
マスメディアの餌となって、センセーショナルに報道されれば、家族のプライバシーはないに等しい。自分に残されたのは、被疑者死亡というシナリオだけだ、と。
作品の最後のシーンに、「自分が、今、終着地点に達しようとしていることを思う。(中略)目的を遂げようという意志を支えているのは、脳裏に燦めく青の炎だった。」(487ページ)という文がある。この場面は彼が、明らかな自殺ではなく、自殺とも事故ともとれる状況として、ロードレーサーで大型トラックにハンドルを切る直前である。秀一はこの苦しい状況から解放されたかった。そして、今まさに彼は完全燃焼しようとしているのである。全てを燃やし尽くす、青の炎によって。不完全燃焼である赤い炎ではなく、完全燃焼を表す美しい青の炎が、この作品の結末を彩っている。
『青の炎』は、秀一の家族を守りたいという思いからの切なさを極める殺人の物語と捉えることができる。しかし、見方を変えるとこの作品の新たな側面が見えてくるのである。秀一は本当に家族思いで勇敢な、孤独な戦士だったのだろうか?
『青の炎』は秀一の一人称で語られている。曾根に対する感情や推測は、もしかしたら秀一の一方的な思い込みであるかもしれないのだ。曾根は遥香に対し、自分はガンであり、もう命が長くないから遥香に会いに来たと話していた。それに加え、どんなに曾根が傍若無人な態度をとろうとも、家から追い出そうとしなかった母の姿。これらを考慮すると、曾根は本当のことを言っており、最後くらいは家族と過ごしたいという願いを叶えたかっただけなのだととれる。実際に、曾根は末期ガンであったことが判明し、秀一が曾根を殺したのは全くの無意味な行為であったことがわかる。
また、秀一の行動の端々に他人を見下すような一面があり、彼の傲慢で思い込むと止まらない性格を表している。
秀一が、家族思いで勇敢な、そして孤独な戦士だったというのはまやかしで、実は独りよがりな愚かな犯罪者だったという読み方もできる。そして最後は責任から逃れ、安易な道を選ぼうとしている。紀子に秘密を守ることを強いて。櫛森秀一の一人称で語られているから、読者はその思いや考えに共感し同調する。しかし、少し視点を変えてみるだけで、私たちは新しい物語と邂逅することができるのだ。たった一冊の本で、何度も美味しい思いを味わえる。
是非、『青の炎』を読んで、そのことを体感してほしい。
(初出:シミルボン「アカリ」ページ2018年12月2日号)
※本作は東海大学文芸創作学科で岡和田晃が2018年度秋学期に開講したSF・幻想文学論で提出されたレポートの優秀作。アカリ氏は当時の受講生。
採録:川嶋侑希・岡和田晃