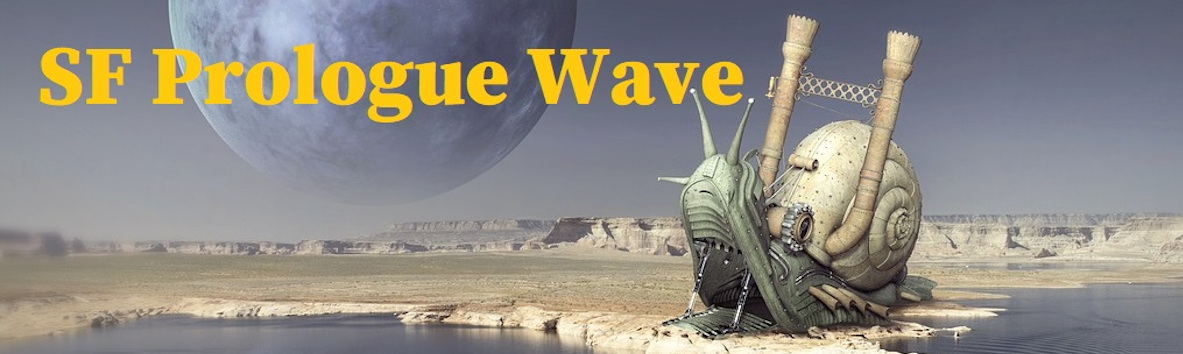高齢者施設に暮らす百歳になるおばあさんは、昨日のことは忘れてしまうが昔のことはしっかり憶えている。
――わたしが娘のころは、村の神社の祭礼があると、行商人がやってきて参道に店を開いたものじゃった。一人か二人で葛籠(つづら)のようなものを背たろうて、あちこちの家に雨戸を借りにくるんじゃ。
なんで雨戸なのかいなあって? 雨戸を二つ離した葛籠に渡したり、地べたに直接置いたりして、品物を並べる台にするのよ。神さんのお祭りじゃから、どの家も昔からの習わしで気持ちよう貸してあげるのさ。
どの行商人がどこの家から借りるかは決まっておって、雨戸を返しにくるときにそれぞれ自分の商いの品物を、御礼に置いていった。
戦争が始まった年に、わたしは同じ村の若者のところに嫁いだ。
わたしの家では、雨戸を貸したのは小間物を商っている人だったから、御礼は小娘が喜ぶような飾り紐や袋物をもらえるのでうれしかったけれど、夫となった人の家はそうではなかった。
そこに雨戸を借りにくるのは、魔除けのお札や置物を商いしている行商人であった。おやじさま――夫の父さまが雨戸の御礼に貰っていたのは、そんな品物ではなく、「目」じゃったのよ。
雨戸についた「目」。
祭りのあいだ、上に並べた魔除けの道具の効き目が雨戸に移り、板の節穴が目の働きをするようになるそうなのさ。おやじさまは、その節穴の「目」が見ている景色を、自分が見られるようにしてもろうていたのよ。
何のために? まあ、泥棒除けであったろうな。
野良仕事に出ているときや、夜中に家のものが寝静まっているときに、雨戸に怪しい者が近づくと、「目」がおやじさまの目にそれを見せてくれる。さらにはおやじさまが声を出すと、雨戸がその声を伝えて鳴るので、相手はおどろいて逃げ出すという寸法よ。
ただ、その効き目は一年ほどしか続かんのさ。
行商人は年に一度、一番大きな祭りのときにだけやってくるので、雨戸を貸した御礼として、そのたびに「目」の力を回復してもらいよったのじゃ。
戦争が激しくなり、暮らしもしにくうなった年におやじさまは亡くなった。
長男だったわたしの夫が当主を継いで、お姑(しゅうとめ)さまと夫の弟とわたしの四人暮らしとなった。子供はまだ出来ておらなんだ。
その年のお祭りにやってきた行商人には、いつものように雨戸を貸し、御礼に「目」をおやじさまの代わりに夫が貰うことになったのじゃ。
ところが祭りが終わるとすぐ、夫に赤紙が来た。兵隊にとられたのさ。
夫は出征していった。南方ということだけ知らされて、どこに行ったかなどわからぬ。
安心しろ、雨戸からいつも見張っておいてやる。夫はそう言い残した。
少なくとも次のお祭りまでは泥棒の心配は減ると、お姑さまと言いあったものさ。
ある日、夫の弟とわたしが座敷にいると、ふいに雨戸から夫の声がした。
おどろいて雨戸を向くと、そこに夫の姿があった。痩せこけて、ぼろぼろの軍服を着て、こちらに向けて銃を構えておった。
夫はまた何か叫んだが、同時にのけぞるように崩れ落ちると、それきり姿は消えてしまった。
それから半年ほどして、夫の戦死公報が届いたのじゃ。遺骨は帰ってこなかった。
終戦後、夫の戦友だったという人が訪ねてきた。夫が戦死するときに一緒にいたという。
その人から聞いた日付や時刻は、あの雨戸から夫の姿が現れたときと違っていたが、新しいつれあいが戦場と日本の時差を計算すると、ほとんど同時であったということじゃった。
つれあい――いまの夫は、戦争が終わったときに結ばれた、戦死した夫の弟なのだけれど、当時はよくあることだったのよ。
戦友のお人は、夫の死にざまも教えてくれた。
敵と遭遇したときに、夫は何か別のものを見ているようで、誰もいないジャングルに向かって銃を構えたときに撃たれたそうな。
一緒に話を聞いていたお姑さまは、戦地に行っても雨戸からわが家の外を見張っていて、怪しいものを見つけたのでそっちに注意が向いて、油断したのじゃろうと涙を流した。
何年かあと、戦争で途絶えていた神社のお祭りが再開されても、行商人が雨戸を借りにくることは、もうなかった。家も、戦後に生まれた息子の代になって修繕して、雨戸もなくなってしまったのよ。
それもずいぶん昔のことじゃが、一度だけ、雨戸を貸していた行商人に、道端で会ったことがある。その後の暮らしぶりを簡単に伝えあってから、その行商人はふいにこんなことを言ったのじゃ。
亡くなったおやじさまの代わりに、雨戸の「目」を自分に付けるときに、夫は、「目」が見る向きを逆にしてほしいと願ったと。