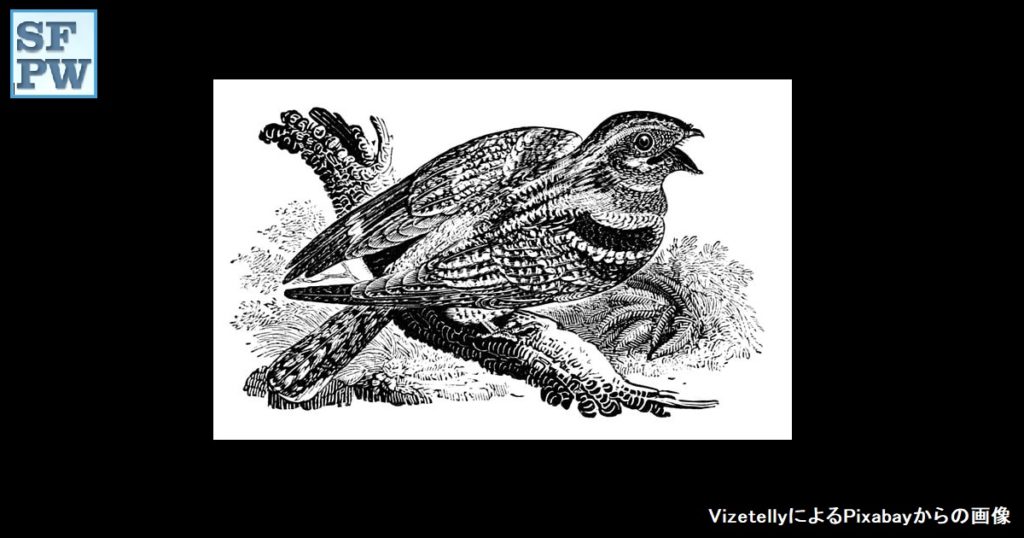
「よだかの息子の僕が鷹の改名要求を呑まざるを得なかった件」尾車れふ
(注:この作品は、書評SNS「シミルボン」に、宮澤賢治「よだかの星」の書評として発表されたものの再録です。)
十歳くらいの時だったんだろうか。夕食中、鷹がいきなり家に来て怒鳴ったんだ。
「おい。居るかい。まだお前は名前をかえないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな」
おびえた妹が泣き出した。父は鷹の前に立ちふさがって、僕たちをかばうようにした。父の後ろに立とうとした僕は、母に「妹をつれて奥の部屋に行きなさい」と言われた。
なだめても、妹は泣きやまなかった。鷹のわめく声は、近所にひびきわたっていた。
「お前とおれでは、よっぽど人格がちがうんだよ。たとえばおれは、青いそらをどこまででも飛んで行く。おまえは、曇ってうすぐらい日か、夜でなくちゃ、出て来ない。それから、おれのくちばしやつめを見ろ。そして、よくお前のとくらべて見るがいい」
父は、落ち着いた声で応対していた。
「鷹さん。それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神さまから下さったのです」
「いいや。おれの名なら、神さまから貰ったのだと云ってもよかろうが、お前のは、云わば、おれと夜と、両方から借りてあるんだ。さあ返せ」
「鷹さん。それは無理です」
「無理じゃない。おれがいい名を教えてやろう。市蔵というんだ。市蔵とな。いい名だろう。そこで、名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか。それはな、首へ市蔵と書いたふだをぶらさげて、私は以来市蔵と申しますと、口上を云って、みんなの所をおじぎしてまわるのだ」
「そんなことはとても出来ません」
「いいや。出来る。そうしろ。もしあさっての朝までに、お前がそうしなかったら、もうすぐ、つかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。おれはあさっての朝早く、鳥のうちを一軒ずつまわって、お前が来たかどうかを聞いてあるく。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ」
「だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをする位なら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺して下さい」
「まあ、よく、あとで考えてごらん。市蔵なんてそんなにわるい名じゃないよ」
鷹が帰って、妹が泣きやんでも、僕はしばらく奥の部屋から出なかった。母と父との激しいやりとりが、はじまっていた。
しずかになってから、行ってみた。
「おなか、すいた」と、妹が言った。
「ごはんの続き、食べようか」と、妹に向かって笑ってみせた母の眼は赤かった。
父は目をつぶって考えこんでいた。
○
父が星になってしまったことについては、宮澤賢治という人が既に書いてくれている。『よだかの星』という作品だ。
この作品は父が星になったところで終わるが、僕の物語はそこから始まる。
父が星になった翌日、鷹はまたやってきた。
「おまえが、あいつの跡継ぎか。ちょうどいい。跡継ぎの挨拶といっしょに、改名の挨拶をして回るといい。今日からお前の名前は市蔵だ」
母と妹のために、僕はそうするしかなかった。
○
好きになった女の子がいた。
友人の妹だ。友達の家に遊びに行ったら、玄関に出てきてくれたんだ。すごく可愛い子だった。ひとめぼれだった。
その顔が見たくて、毎日、友人の家に遊びに行った。
ある日、彼女が悲しそうに言った。
「あのね、見たい映画があるんだけど、お兄ちゃんが嫌だって言って、一緒に行ってくれないの」
「じゃ、僕が一緒に行ってあげるよ。次の日曜日でいい?」
「うん!」
極上の笑顔に、僕は有頂天になった。
しかし、次の日曜日、待ち合わせ場所に彼女は来なかった。少し遅れてやってきたのは「お兄ちゃん」のほうだった。
「悪いけど、もう俺の家には来ないでくれるかな」
きまずそうに、友人は言った。
「妹は父ちゃんにすごく怒られて、泣いている」
「なぜ?」
「父ちゃんは、おまえのもとの名前を知っているんだ。家に遊びに来るくらいはいいだろうと、甘い顔をしてしまったことを後悔しているってさ」
○
その後、いろいろな女性とつきあった。みんな、僕が本当の名前を打ち明けると去っていった。
「悪いことをさんざんやって嫌われたあげく、それをごまかすために名前を変えたんだって聞いたわ」
いくら「そうじゃない」と言っても、無駄だった。
「だって、みんな、そう言っているわよ」
「悪いことをしていないのなら、どうして名前を変える必要があるの? 変えたってことは、後ろ暗いところがあったからでしょう?」
「よくも、今までだましてくれたわね」
「あたしとつきあってたなんて言わないでね。皆に知られたら、あたしまで仲間はずれにされちゃう」
僕は、僕の真実を相手に見て欲しかった。そこを隠しているのは、不誠実だと思ったんだ。
だけど、それは間違いだった。真実なんて、何の価値もないんだ。何の力もないんだ。だんだん僕はそう悟っていった。
僕は真実の僕を隠すことにした。いや、殺すことにしたんだ。
おまえが二度と出て来ることができないように、僕が墓に葬ってやる。墓碑銘は「真実になんか、何の価値もない」とでもしようか。
何の価値もない?
僕はドキッとした。
では、価値のあるものとは何だろう?
真実に価値がないのなら、嘘には価値があるのか?
あるのかもしれない。僕はそう思った。
だって、こんな時に僕の心をなぐさめてくれるのは、「嘘話」としてさげすまれているような、読み物だけだったから。
○
彼女と出会ったのは、そんな時だった。
旅先で知り合って、二度と会うこともないだろうと思っていた。そしたら、手紙がきた。変化のない生活が退屈だと言う。
ただならぬ関係になるまで時間はかからなかった。「こんなこと、初めてだわ」と彼女は言った。もちろん、僕だって、初めてだった。
誰にも知られずに愛し合っている。その幸福だけで僕は充分だった。
「あなたって、いつも冷静よね。強引な人が現れたら、私、そっちについていってしまうかもしれないわ」
「私みたいなつまらない女、あなただって本気じゃないんでしょ」
そんなふうに言われ、ぼくは強く否定した。
「本気だよ」
「でも、どうせ結婚する気なんてないんでしょ?」
「そんなことはない。愛している」
「あなたの愛が永遠だという保証があるの?」
「永遠の保証なんて、この世にはありえないさ。だからこそ、今、真剣に愛せるんだ」
「嬉しいわ。私なんかと結婚してくれるのは、きっとあなただけだわ」
そう言われて、僕も決意を固めた。
「でも、結婚となると、君のご両親の許可が必要だ」
僕はちょっと暗い気持ちになった。
「僕との結婚に、ご両親が反対なさったら、君はどうする?」
「そんなこと、あり得ないわ。母は私に『誰とでもいいから、さっさと結婚しなさい』って、いつも言っているし、父はいないし」
「えっ、お父さん、いないの?」
「ええ、家にいないの」
「僕と同じだね。じゃ、母と妹に君を紹介するよ」
僕は彼女を家に招いた。母も妹もきっと喜んでくれると、僕は思い込んでいた。
母は彼女に家族のことを尋ねた。僕に言ったのと同じことを、彼女は答えた。
彼女が帰った後、母は言った。
「あの娘はダメよ。あなた、わからないの? まともな家の娘ではないわ。まんまと、たらしこまれたわね」
母が彼女を毛嫌いする理由が、この時の僕には全くわからなかったんだ。
○ それでも、僕は彼女を愛していた。
母に反対されても、僕は彼女と結婚するつもりだった。
でも、彼女はこう言い出したんだ。
「ねえ、父に会ってもらえない? 母がね、やはりあなたに父と会ってもらわないとダメだって言うの」
「え? お父さん、いないんじゃなかったの?」
「家にはいないわ。でも、他の家にいるのよ」
わけがわからない。
母に話したら「やっぱりね」と言った。そして、その意味を教えてくれた。
それがどうだというんだと、僕は思った。そんなことで、僕の彼女に対する愛は変わらない。むしろ、以前より彼女をいとおしいとさえ思う。きっと今まで、つらい目にあってきたに違いない。
しかし、何ということだろう。
神様は、とことん僕に意地悪だった。
彼女の父親は、僕を見て、「おお、市蔵か」と言った。
「市蔵っていい名前だろう? おれが考えてやったんだ」
彼女の父親は、鷹だったんだ。
「おまえが、おれの娘と結婚? とんでもない」
○ 彼女の父親と会った翌日、僕は彼女にデートを申し込んでみた。彼女が僕をどう思っているのか、知りたかったんだ。
彼女はデートに応じてくれた。態度も変わらなかった。嬉しかった。
鷹の娘であることは、彼女の責任じゃないんだ、僕らは愛し合っているんだ!
彼女から、手紙が来た。「いつか結婚できるときが来たら、結婚しましょう。結婚しても、あなたと浮気をしましょう」
ぼくは感動した。いつか結婚して、そして、その後も常に相手に対して新鮮な気持ちを持ち続ける…そんな夢みたいなことができるんだろうか。ああ、そんな日がくればいいんだが……。
こうして、三年の月日が過ぎ去った。
ある日、鷹がいきなり僕の家にやってきた。
「おまえ、責任は取ってくれるんだろうな?」
「何のことですか?」
「娘が雛をかえしたんだ。お前の子だろう?」
「え?」
驚いた。そんな話は初耳だった。
「ちょっと待って下さい。うちの息子の子だって、どうしてわかるんですか?」と、母が言った。
「なんだって?」
鷹は、母に襲いかかろうとした。母をかばった僕は、鷹に押し倒された。
「娘が、そう言っているんだから、確かだ!」
「責任をとれって、どういうことですか?」
「結婚に決まっているだろう!」
「結婚には、ご反対なさっていたんじゃないんですか?」
「こうなったら、話は別だ。ただし、娘をここに嫁入りさせるわけにはいかないから、おまえが娘とその母親の家に入れ」
「そんな…」
「そしたら、もう市蔵じゃないぞ。鷹と名乗っていいぞ。嬉しいだろう?」
僕には、何が何だかわからなかった。
「息子を奪われて、私たちはどうしたらいいんですか?」
母は、妹と抱き合いながら、ふるえ声で言った。
「そうだなぁ。仕方がない。毎月、この家に金を届けさせてやる。娘の母親に頼もう。それで何とかなるだろう。ただし、このことは、娘には絶対に内緒だぞ」
さすがに、カッとした。
「僕はお金で買われるんですか?」
「何を言う! ここでお前がこの条件を呑まなければ、娘は死ぬぞ!!」
「死ぬって……?」
「頼む。娘を助けてくれ」
鷹の懇願に、僕はうなずかざるをえなかった。
出て行こうとする鷹の背中に、母が「カッコウ…」とつぶやいた。
鷹は、ちょっと振り返るようにしたが、そのまま出て行った。
その意味も、その時の僕にはわからなかったんだ。
○「ホントに、私、死んじゃおうかと思ったの」と、彼女は言った。
「よかったわ。ママの言ったとおり、パパと相談して。パパが何とかしてくれるからって。そのとおりだったわ」
どういう意味なのだろうと、僕は思ったが、深くは考えなかった。
愛する女性と結婚できるし、僕たちの間には既に子供がいるんだ。前向きに考えよう。
僕は必死で稼いで、妻子を養おうとした。
「こんなんじゃ、ぜんぜん足りないわ」と、妻は言った。
「いいわ。パパからお金、もらうから」
ピヨピヨと鳴く雛たちに、妻が言いきかせているのが聞こえた。
「おじいちゃんみたいに、立派な鷹になるのよ」
僕が実家に顔を出そうとすると、妻はひどく不機嫌になった。もちろん、絶対に一緒に行こうとはしなかった。
妻は、僕とトラブルになると、必ずこう言った。
「ここは鷹の家よ。パパは、そうしなかったわ。こうしていたわ。こうしてちょうだい」
こうして、僕はだんだん気がついていったんだ。
妻が、ずるい女だということ。
だらしがなくて、精神的な規律に欠けているということ。
僕が感動した「あなたと浮気をしましょう」というのは、僕が考えたような意味じゃなかったこと。
だけど、僕はそれでも彼女のことを愛していたんだ。
彼女は、寂しい人だ。悲しい人だ。その意味では、僕と同じ人なんだ。
○ そんなある日、職場に電話がかかってきた。同人誌を主宰している男からだった。結婚前に知り合い、その同人誌に、自分の書いた「嘘話」を載せてもらったこともあった。
「発送作業を、ちょっと手伝ってほしいんだけど」
「ああ、いいよ。帰りに寄ろう」
家に帰りたくなかったから、渡りに舟だった。男の家は、職場から歩いて十分くらいの場所にあった。
「君の作品、人気があったんだよ。また載せたいな。書いてくれよ」
「無理だよ。もう書けない。書く場所がない。小さい子供がいてさ、家では全く落ち着けないんだ」
「そうなんだ。じゃ、ここで書けばいいよ」
「えっ、ここで? この家で?」
「帰りに寄ればいい。奥さんには残業だって言っておけば?」
「そ、そうだな」
僕は乗り気になった。
「前に話してくれたの、面白かったな。あれを書けばいい」
「あれより、もっと面白い話もあるよ」
「おお、すばらしい。ぜひ読みたいな。すぐ書き始めなよ」
「え? 今?」
「善は急げ、だ」
原稿用紙とペンが差し出された。思わず、手にとって、書き始めた。
だんだん、気分が高揚してきた。高く叫びながら飛んでいるようだ。
時間がたつのを忘れた。
「今日は、泊まっていくよね」
男の声に、我に返る。
「あと十分で出ないと、終電に間に合わなくなるよ」
「え? いや、帰るよ。帰らなくては」
あわただしく飛び出し、駅へ向かった。頬に何やら暖かいものが流れてくる。
僕は嗚咽をもらしながら、走った。
○
この時に書いたのは、遠い未来の、地球ではない星の物語だった。主人公の種族を滅亡寸前まで追い込んだ強大な敵が守ろうとしていたものは、弱々しい1本の草だったという話だ。
この頃には、鷹の「事情」もわかってきていた。この話がそれの反映であることは、僕だけが知っていることだった。
ペンネームは、僕の本当の名前と同じイニシャルのものにした。そして、イニシャルでサインをした。
「すごいな。読者アンケートで、ダントツの一位だ」
そう言われて、嬉しくないはずがなかった。
男の主宰する同人誌は、プロ作家を輩出していることで有名だった。その理由が彼にあることを、僕は知っていた。彼の的確なアドバイスで、僕は商業誌に連載を持つようになって行った。
こうなると、さすがにいつまでも彼の家で書かせてもらっているわけにいかない。
僕は、職場にも彼の家にも近い場所に部屋を借り、そこで書いた。
時々はそこに泊まったが、基本的に家に帰るようにしていた。妻は気づいていないようだった。
書いていると、どこまでもどこまでも、まっすぐに空へのぼって行くような気分になった。
キシキシキシキシキシッと、原稿用紙の中で、僕は叫んだ。
○
妻の母親が死んだ。 ほどなくして、妻の父親も死んだ。
ある日、妹が訪ねて来た。妹はずっと独り身を通し、母と一緒に暮らしていた。
「お金が届かなくなって、困っているのよ、お兄ちゃん」
妹は、妻を恨んでいた。妻に兄を取られたせいで、妹が更に縁遠くなってしまったのは確かだったから、仕方がなかった。
僕は妹に金を渡した。僕の書いた「嘘話」で得た金だった。
もちろん、妻には内緒だった。
○「嘘話を書くあなたは、もともと嘘つきなのよね。私を『愛している』って言ったのも、全部、嘘だったんだわ」と、妻が言った。
「私、知っているのよ。お金が欲しかったから、私と結婚したんでしょう? あなたの妹が教えてくれたわ。母が毎月、お金を届けに行っていたんですって? みんなで、そうやって私をだましていたのね」
妻は、僕が妹にお金を渡していることに気づいたのだ。そして、妹を責めたのだろう。
僕は何を言うことができなかった。
「それに、私と結婚すれば、鷹でもないくせに、鷹としての特権が享受できるものねぇ」
僕がいくら弁明しても、その言葉を妻が信じるはずがなかった。
それでも、僕は嘘話を書くのをやめなかった。
むしろ、狂ったように書き綴った。
僕はやっと気がついたんだ。自分が何を書いていたのかに。
墓碑銘だ。僕が書いていたものは、全部、僕の墓碑銘だったんだ。「真実になんか、何の価値もない」の続きを、ずっと僕は書いていたんだ。
○
勤め人をやめて、執筆に専念することにした。
いろいろな作品を書いた。
特に人気を集め、有名な少女マンガ家によってマンガ化もされた「代表作」の主人公は、美しい少女だった。絶対に勝てない戦いの中に投げ込まれ、仲間もすべて失い、孤独の中に立ち尽くす少女……それが、かつて僕によって殺された、僕の魂の姿であることを、僕はよく知っていた。
僕の死後、僕の妻は自分に都合がいいように、僕たちの結婚のことを語るかもしれない。あるいは、僕の手紙や日記を、そのために利用するかもしれない。
だけど、僕は信じている。僕の書いた嘘話をきちんと読めばわかるはずなんだ。
僕の書いた嘘話だけが僕の真実だ。
僕は、僕の書いた嘘話の中に生き続ける。
「よだかの星は燃えつづけました。いつまでもいつまでも燃えつづけました。今でもまだ燃えています。(宮澤賢治『よだかの星』)」
