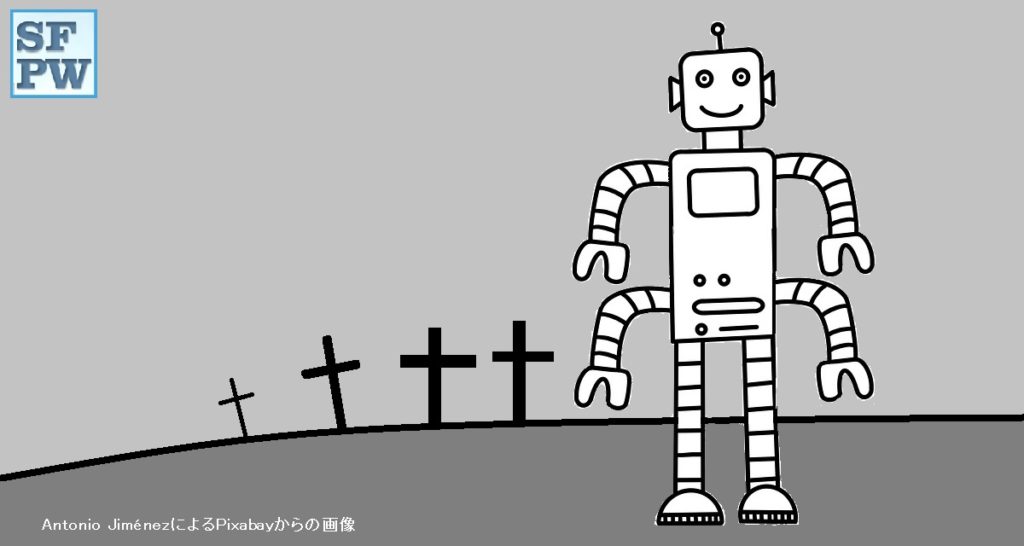
それを《彼》と呼ばせていただこう。
正確には性別はないのだから、彼でも彼女でも一向に構わないのだが、それは男性と見なされる事が多かった。
誕生、生命に関わる事象は女性になぞらえる事が多い。そうなると男性はどうしても死や滅びに結びつけられる。
そうだ。それは命の終わりに関する仕事の為に作られたのだ。
彼は墓掘りロボットなのだ。
姿はあまり人間には似てない。墓を掘る為に特化した姿だ。腕は四本。必要に応じて左右一本ずつに束ねる事も出来る。腕の先には掘削用の装置が取り付けられている。
本来頭部は必要ないはずだが、帽子の鍔がついたような円筒形の頭部を持つ。これは墓に遺体を埋葬する際、彼は死者を送る葬送者の役目をする事もあり、このように作られたのだ。
同類を埋葬する事を覚えた時、人類は文化を得たという人も居た。もはや滅びが確実な人類の遺体は誰が埋葬するのだろうか。最後の一人になった時、その遺体は誰が埋葬するのだろうか。
最後の遺体をきちんと埋葬する事。それこそが人類が文化を持っていた証明であり、人類という種の尊厳を守る行為だ。
そう考えた人間によって彼は、いや彼らは作られた。
今日も彼は瓦礫の中で遺体を探し回っていた。墓掘りロボットというものは、遺体を探して墓を掘り遺体を埋葬するのが役割だからだ。
人間がやればいいではないかという指摘はまさにその通りだ。しかし彼はしばらく人間を見てない。彼にとってはどうでもいい、そして認識しがたい概念である時間でいうと、もう30年くらい生きた人間は見てない。
彼にとっては人間とは死体の事なのだ。
今日も転がっている遺体の為に墓を掘り埋葬した。
これでこの辺りにある遺体はすべて埋葬した。
彼は次の遺体を探して別の地へ向かった。
同類がどれだけいるのかは分からない。彼と同じロットが3000体作られた事は分かっている。しかし他のロットも含めた墓掘りロボットがどれくらいあるのかまでは分からない。彼のロットは10番目だ。最低でも3万体はあると考える事も出来る。彼のロット以降も墓掘りロボットは作られ続けた。
全体で30万だろうか、300万だろうか。もっとあるのかも知れない。
効果的に埋葬を行う為、同類と連携を取りつつ行動していたが、その同類とも最近連絡が取れない。
最後に連絡が取れたのは2年前。他の大陸で作業していたが、すでに目に付く遺体は無くなったと言ってきた。山脈の方へ行ってみる。高地にはまだ埋葬されていない遺体があるかも知れない。
それが最後の連絡だった。
同類は高地へ行けたのだろうか。今でも人間の遺体を捜し、埋葬を続けているのだろうか。
しかし彼には同類の行く末に思いを馳せる機能は無い。ただ同類が山地から落ちれば機能が停止するだろう。経年劣化の為、自分も歩行機能に障害が出ている。山地に行くのは出来るだけ避けよう。足下が悪い地形には気をつけよう。彼が考えるのはそれだけだ。
あくまで遺体を捜して墓を掘り埋葬するのに必要な能力、機能に特化した存在なのだ。 そして彼はロボットだ。眠らない。疲れも知らないが、動力源のバッテリーや手足のモーターは徐々に劣化している。それでも彼は人間の遺体を求めて大陸を歩き回った。
都市の跡を訪れてみたが、大抵、同類が作業を終えていた。朽ち果てたビルディングの合間にある道路のアスファルトを剥がしたり、公園の跡地を利用したりして広大な墓所が作られていた。
そしてその墓所の脇には、役目を終えた彼の同類が転がっていた。
彼は墓掘りロボットだが、スクラップとなった同類の為に墓を掘る事はしなかった。そういう役目は課せられていなかったのだ。
彼はあくまで滅びが確実となった人類の為に墓を掘り埋葬するロボット。同類のロボットの処分は彼らの仕事では無い。
しかしスクラップとなった同類を放置する事もしなかった。使える部品をいただくのだ。
その行為は最初から想定されていた仕様だ。人類文明が滅んだも同然の状態で運用されるロボットだ。メンテナンスなどしてくれる人間もいない。メンテナンス専用のロボットも作られたようだが、とうの昔に機能を停止してしまっている。
そこで彼らは機能停止した同類から、使える部品を貰う、所謂共食い整備で自らの機能を維持していくように設計されているのだ。
もっともそれには限界もある。劣化の少ない外装やフレームは簡単に手に入るが、もともとそれらはさほど交換を必要としない。反面、記録媒体や土を掘る作業腕、そして現状、彼が支障を来している歩行脚の部品は劣化が激しく、スクラップ状態の同類から状態が良いものを入手出来る可能性は少ない。
今回も彼自身に使用されている部品より状態の良いものを手に入れる事は出来なかった。
落胆を覚える機能は彼には無い。ただ自分の耐用期間がとうの昔に過ぎており、このままでは残った人類の遺体をすべて埋葬できない。そう考えると焦りのようなものを覚えたのは事実だ。
再び彼は人類の遺体を捜して旅に出た。
かつて同類から得たデータを元に、西の方角へ行ってみる事にした。十数年前、そこでわずかに生き残った人類と、彼の同類が遺体の埋葬を行っていたのだ。同類とはすでに連絡が付かなくなっている。ロットは彼よりも前だ。おそらく機能停止してしまったのだろう。その時点で生き残っていた人類が生存していたかどうかも怪しいが、仮にロボットよりも長く生存していたならば、放置された遺体が残っていてもおかしくない。
彼は空を飛ぶことも、水中へ潜る事も出来ない。出来るのは歩く事だけだ。ならば多少なりとも可能性のある場所へ行くしか無い。
それが、墓を掘り人類の遺体を埋葬するという彼の存在意義なのだ。
数ヶ月か数年かが過ぎ、ようやく大陸の西の果てに近づいた。それに連れて人類が生活していた気配がちらほら見えてきた。
彼ら墓掘りロボットの規格ではない墓地。人間の手によって埋葬されたのだろう。彼と同類のスクラップもいくつか転がっていた。同類は己の使命を全うできずに機能を停止したのだろう。そして住居や火をおこした跡も見つけた。
もっともその痕跡も数十年前のものだ。まだ人類が生き残っているかどうかは定かでは無い。
しかし西へ行くにつれて、人類の痕跡が増えてきたのは確かだ。
海が近づいてきた。まだ海そのものは見えないが、風に海水の成分が含まれるようになってきた。対策はほどこしてあるとはいえ、彼も機械には違いない。海水に含まれる塩分には弱い。
その一方で人類の痕跡は徐々に新しくなっていく。放棄された耕作地。木製の柵も残っている。放棄されたのはほんの十数年前といった所だろうか。
逸る心等というものは彼にはない。だから移動速度は今まで通り。足が軽くなると言う事も無い。歩行脚に無駄な負担を与えるわけにもいかない。
それでも着実に人類の痕跡が新しくなる方向へ進んでいた。
ついに痕跡は痕跡では無くなった。
雑な作りではあるが、明らかに手入れされている耕作地。栽培されているのは人類が食用にするものだ。そして彼方に見える廃墟から比べると、みすぼらしい事この上ないが、人が住んでいるとおぼしき小屋が建っていた。ぼろぼろの洗濯物が干してある。人間が住んでいるのは間違い無い。
彼は周囲を見回す。小屋から少し離れたところに、彼にとっては見慣れた施設があった。
墓場だ。しかし彼のような墓掘りロボットの規格に沿って作られた墓では無い。大きさ、形もまちまち。間違い無く人間が、自らの同胞を葬ったものだ。
そして彼が到着した時も、そこで墓を掘っている人間がいた。
彼が姿を現した事に、人間の方も気づいたようだ。墓を掘る手を休め、彼が近づいてくるのを待った。
人間は子供というか少年のようだ。声が届く頃合いになると、少年の方から声を掛けてきた。
「やあ、墓掘りロボットだね。子供の頃にはこの村にも何体かいたよ」
彼は答えた。
「埋葬作業中ですか? お手伝いいたします」
「頼むよ」
少年は笑いながらそう言った。少年が埋葬しようとしている遺体は、すでに死後数年は経過しているようでミイラ化していた。
その遺体を埋葬しながら少年は彼に言った。
「君が来てくれて助かる。埋葬しなきゃいけない遺体はまだたくさんあるんだ」
どうやらまだ自分の存在意義は失われずに済みそうだ。彼は少年に言われるまま、埋葬の手伝いを始めた。
「故人とはどういうご関係で?」
彼は少年へ訊ねた。
「いや、知らない人だ。僕が物心つく頃にはすでに他界していた」
なるほど。ミイラ化しているのも無理は無い。死後十年くらいは経っていそうだ。
「何故いままで埋葬しなかったのですか?」
「手が足りないんだ」
少年は苦笑した。
「ここで生き残っているのは僕だけだからね。時間を見て少しずつ埋葬してきた。でもまだ野ざらしになっている遺体は百体以上はあるだろうね」
埋葬をしながら少年はぽつりぽつりと、この集落の跡地について語った。
少年が産まれた頃には、まだ集落として機能しており、人口も二百人程度はいたらしい。家畜の飼育や耕作も順調だった。
しかし十年くらい前、突然、この集落を感染症が襲った。なけなしのワクチンや薬を使ったが、いかんせん長年不適切な状態で保管されたものだ。生憎と効き目は限定的だった。
集落の人口は数年で十分の一程度まで減少した。若年層の被害は特に大きく、新しく産まれてくる子供もいなくなった。
当然、人口は減る一方。農業生産や家畜の飼育もたちいかなくなり、耕作地も放棄された。
数年前、最後まで少年の面倒を見てくれた老夫婦も相次いで世を去った。以来、少年はこの地で一人きりなのだ。
もっとも彼は少年の生い立ちには興味が無い。彼は遺体を埋葬する事だけが存在意義なのだ。
「なんでしたら、私が残りのご遺体を、責任をもってすべて埋葬いたします。貴方は他に人間がいないか、捜索に向かってはいかがでしょうか?」
埋葬を終えた彼は、少年に向かってそう提案した。
少年はちょっとはにかんだような笑みで答えた。
「いや、ここにいる人たちは、僕が責任を持って埋葬する。君にも手伝って欲しいけど、僕はみんなをちゃんと埋葬する所まで見届けたいんだ」
そして少年はまだ野ざらしになっている遺体へ目をやりながら言った。
「今となっては分からなくなっているけど、あの遺体の中には僕の両親や兄弟、友達もいるはずなんだ。その人たちがきちんと眠りに就くのを確認したい」
「なるほど。良い志です」
彼の返答に少年は笑う。
「そう思うのは君が墓掘りロボットだからなのかい?」
「もちろんそうですが、死者を悼み見送るのは人間らしい心がけだと思います」
「ありがとう」
「どういたしまして」
その日から彼は少年と協力して、集落とその周辺にうち捨てられた遺体の埋葬を始めた。
彼には遺体を確認して、それが人間かどうか、同一人物かどうか、性別、年齢まである程度推察する機能が付加されている。
その機能で同一人物として推測された遺体はまとめて一人分として埋葬した。それが死者への礼儀だ。
当然だが、少年が一人で埋葬していた時よりも、作業ははかどった。彼は墓掘りロボット、つまりプロなのだ。多少、機能に不安があっても、以前より効率良く埋葬作業を進めていけるようになった。
彼は機械だ。少年が寝ている間や農作物の世話をしている時にも、休まず埋葬作業を続けられる。ある程度の人数を埋葬し終えたら少年を呼びに行き、一緒に死者の冥福を祈る。
来る日も来る日も少年と墓掘りロボットである彼の作業は続けられた。
いつまで続くのかと思われた埋葬作業だが、さすがに終わりが見えてきた。状態の良い遺体はほとんど埋葬を終え、残りは集落の周辺に散らばった骨片などの回収だけになった。
人口が劇的に減少した際、周辺にうち捨てられたまま、野犬や野鳥などの餌食になった遺体だ。
同一人物の骨は出来るだけ一つにまとめるが、わずかな骨片しか見つからない個人もいた。そういう場合はやむを得ない。一つの墓穴に数人分の骨片をいれて、一緒に埋葬する。故人も他人と一緒くたにされるのは嫌だろうが、野ざらしのまま風雨にさらされているよりはましだろう。
そう思うしか無い。
そんな作業に移る頃には、少年も成長してもう青年と呼ぶ方が相応しい程になっていた。
しかし彼は墓掘りロボットだ。成長はしない。老化もしないはずだが生憎と劣化はする。海は見えないとはいえ、塩分を含んだ風が寄せてくる場所だ。本来ならばその程度は本体のシール機能で充分防げるはずだが、それも経年劣化には勝てない。シール部分は剥がれ、ひび割れ、そこから塩分、水分を含む空気が入ってきて、内部の機能を侵食していた。
青年に機能劣化を相談した所、周辺を回りスクラップになった墓掘りロボットから使えそうなパーツを持ってきてくれた。
しかしそれらも長年、この環境に晒(さら)されて来ている。到底、根本的な解決にはならなかった。
この集落にある遺体はすべて埋葬できそうだ。しかしそれが終わったら自分はどうする? 生きている人間、あるいは遺体がある場所まで、また移動できるとは思えない。
この地で機能停止して最後を迎えるのか?
それでいいのか? まだやるべき事が残っているのでは無いか?
彼は自問していた。しかしどう自問しても答えは出てこない。その一方で何かを見落としているような違和感があったのだ。
その違和感のようなわだかまりを残しつつ、彼と青年は最後の遺体の埋葬を終えた。
「これで最後だね。長い間、有り難う」
さすが青年は感無量のようだ。
「私はプログラムされた通りの作業を行っただけです。礼ならば私をプログラムした開発者に言って下さい」
そう言う彼に青年は重ねて礼を言った。
「いや、埋葬を手伝ってくれたのは、他でも無い君だ。亡くなった人たちもきみに感謝しているだろう」
そう言うと青年は西の方を見つめた。青年に彼は尋ねた。
「これからどうなさいますか?」
「そうだな……。西の方にでも行こうか。海に行けば魚も捕れるだろうし、舟を作れれば遠い所へ行けるかも知れない」
「海ですか」
彼はつぶやく。今の自分の状態では海には行けない。ここで青年と別れるしか無い。しかし青年と別れてどうする? 今の自分の状態ではあと数年、いや数ヶ月しか稼働できないだろう。
この集落で機能停止してスクラップになるしか無いのか?
「君もどうだい? 一緒に来るか」
「いえ、私は……。まだ仕事が残っていますので」
あぁ、そうだ。私にはまだ仕事が、最後の仕事が残っていたのだ。彼がそれをやらなければ、誰がやると言うのだ。
「そうか。僕は……」
青年は海の方へ向き直り、彼に背を向けた。そんな青年に彼は一本に束ねた作業用アームを振り下ろした。
太い金属製のアームは青年の後頭部へ直撃した。鮮血がほとばしる。
「い、一体、なにを……」
青年は呻きながら振り返ったが、彼は有無を言わさず作業アームを、右左と次から次へと振り下ろした。
やがて青年は動かなくなった。死んだのだ。
つまり遺体だ。
彼に仕事が出来た。おそらくこれが最後の仕事だ。
青年が死んだら、誰が埋葬するというのだ。私しかいない。ならばその行為にためらいがあるだろうか。
彼は青年の遺体を丁重に埋葬した。最後の仕事が終わったのだ。おそらく青年は地球上で最後の人類だったのだろう。そうでなくとも彼が残り少ない稼働時間で出会える最後の人類なのはほぼ間違い無い。
そしてその最後の一人の埋葬を終えた。人類の尊厳は守られたのだ。彼はロボットとして最後まで人間に奉仕できた事に深い満足を覚えていた。
