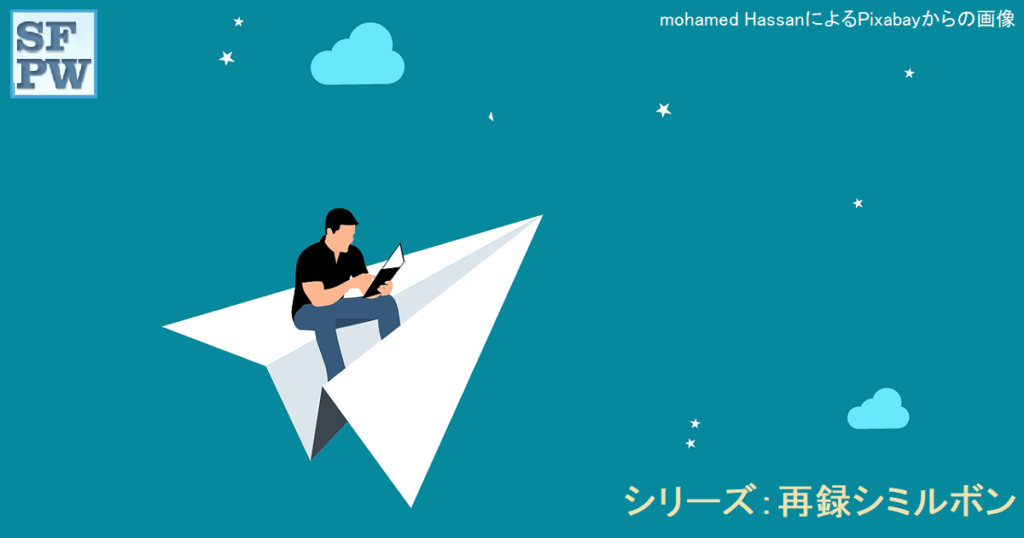
『ドン・キホーテ』再入門 その4 樺山三英
受容の変遷
作者の死後『ドン・キホーテ』は主にスペイン国外で評価されていきます。パロディとしての側面が後退し、作品自体の独り歩きが始まるのです。もっとも典型的なのはロマン主義的解釈でした。「ロマン主義とは何か?」というのはたいへんややこしい問いなので、ここは教科書的なまとめで勘弁してください。フランス革命以降、理性や普遍性に対して個性や感受性の優位を説いた立場、といったところでしょうか。そうした文脈のなかで、近代社会が抑圧してきた中世精神をリバイバルしようという動きが盛んになってくる。そこで浮上してきたのが、この時代錯誤の騎士の物語でした。たしかに『ドン・キホーテ』には、現実に対する強烈な異議申し立てがあります。周囲の嘲笑にも負けず、自身の信念を貫く強さもある。反抗の果ての死という、劇的な最期まで持っている。しかも作者のセルバンテス自身が、相当に波乱万丈な生涯を送っています。ここから、作者と主人公を重ね合わせたロマンティックな読解も生まれてくる。結果『ドン・キホーテ』は「失われゆく騎士道精神を描いた悲劇」として受け止められ、憂い顔の騎士はロマン主義的英雄の典型となっていったのです。
もっともロマン派の人々がすべて、上記のような見方をしていたわけではありません。たとえばハイネ。彼はドイツ語訳の序文のなかで、少年の頃、夢中になって『ドン・キホーテ』を読み耽ったことを綴っています。しかし他方、長じるにつれて次第に冷淡になっていったこと、ついには馬鹿げた喜劇としか受け止められなくなってきたことを告白しています。結局ハイネは、ドン・キホーテを英雄視することを止める。その一方で『ドン・キホーテ』という書物がすばらしい点は、一人の英雄の姿ばかりでなく、市井の人々(床屋や司祭、得業士ら)も併せて描いていること、そしてその両者のせめぎ合いを主題化しているところにあるのだと結論づけます。そこに近代的市民社会の形成を見るわけですね。これはなかなかユニークな視点だと思います。
市民社会とのかかわりで言うと、ツルゲーネフの指摘も重要です。『ハムレットとドン・キホーテ』と題された有名な講演があります。このなかで彼は、ヨーロッパ文芸に現われる二つの性格類型を定義しています。自己懐疑ばかりでなかなか行動に移らない「ハムレット型」と、考えなしで突き進む猪突猛進の「ドン・キホーテ型」というわけですね。これは今日でもしばしば引き合いに出される分類なので、聞いたことがある人も多いかと思います。ですが実際に読んでみると、どうもハムレットばかりを非難し、ドン・キホーテを称揚する論調が目立つ。おそらくツルゲーネフ自身の置かれた状況も関係しているのでしょう。ヨーロッパ発の利己的な市民像をハムレットに当てはめ、利他的で無私なロシア的人間をドン・キホーテに投影させているような気配があります。ちょっとフェアではない気もするのですが、これもまた興味深い見解です。
こうした反近代的人間像を極限まで推し進めたのは、言うまでもなくドストエフスキーです。彼は『作家の日記』のなかで『ドン・キホーテ』を絶賛しています。「世界中さがしても、この書物より深く力強いものはない。これは今のところ、人類の思想の最も偉大な、最後の言葉である。人間が表現しうる最も辛辣な皮肉である」――ここまで言うのだから相当なものです。また『白痴』のムイシュキン公爵は、キリストとドン・キホーテの系譜に連なる人物として造形されています。あまりにも無垢、純粋であるがゆえに、狂気に近づいていく聖なる愚者というわけですね。近代的人間観が抱え込んだ矛盾を、そのもっとも深い場所で打ち破ろうとするとき、かの遍歴の騎士が姿を現わす。この事実には何度も立ち返る必要があるでしょう。
そのドストエフスキーと同時代人だったのがフローベール。彼もまた『ドン・キホーテ』の愛読者として知られています。「文字を覚えるより前から聞き知っていた」というこの騎士の物語は、彼の作品にも深い影響を残しています。恋愛小説に読む耽るあまり、凡庸な現実に耐えられなくなった女性――『ボヴァリー夫人』の物語は、19世紀版『ドン・キホーテ』と言えるものかもしれません。彼女はしばしば「スカートを穿いたドン・キホーテ」とも呼び称されます。また未完に終わった最後の作品『ブヴァールとペキュシェ』は、本を読み蓄えた知識を実践することで、ままならぬ現実に立ち向かおうとする奇妙の二人組の物語です。でも彼らの道行きは逸脱と幻滅を繰り返すばかり。滑稽で狂気を孕み、しかしどこか物悲しいその姿は、ドン・キホーテの面影を感じさせるものです。
以上、19世紀までのスペイン国外の受容を追ってみました。さて。では本国スペインではどうだったのか。さきほど述べたように、騎士道物語のコードが失われていくにつれて、作品の評価は下火になっていきました。スペイン国内では18世紀以降、ほとんど忘れ去られていたというのが実情のようです。それが再燃したのが20世紀に入るころ。きっかけになったのは「98年世代」と呼ばれる人々の登場でした。当時、スペインは米西戦争に敗れ、結果として国外の植民地をすべて失ったところでした。過去の栄光のすべてを失い、発展からも取り残された国家。スペインはこれからどこへ行くのか? そうした問題に直面したのが彼らの世代でした。
この世代の代表格がミゲル・デ・ウナムーノ。南欧のキルケゴールとも呼ばれる、実存主義の先駆的人物でした。彼の代表作に『ドン・キホーテとサンチョの生涯』という本があります。これは『ドン・キホーテ』を頭から終りまで読み解き、どこがどうすばらしいのかを延々と語る、かなり破格の書物です。彼は自らの立場を「キホーティズム」と名づけました。真に偉大なのはドン・キホーテただ一人。作者でさえ、その偉大さを理解していなかった。セルバンテスは単に、騎士道物語のパロディを書こうとしただけだ。にもかかわらず、図らずも「スペインの真の魂」を露呈させてしまったのだ――。こういう調子でドン・キホーテを、イグナチオ・デ・ロヨラや聖テレサといった、宗教的偉人たちに重ね合わせて読解していきます。ちょっと強引で手前勝手なところもありますが、たいへんパッションに満ちたユニークな著作です。
このウナムーノの立場を引き継いだのがオルテガ・イ・ガセット。『大衆の反逆』で有名な哲学者です。彼にも『ドン・キホーテをめぐる考察』という著作があります。ゲルマンの森と地中海の対比から始まる、文明史的視座に貫かれたスケールの大きな評論です。彼によれば人間の生の「英雄性」は、不条理な周辺世界に意味を与え、自らの生きる世界をかたちづくるべく、不断に闘い続けるところにあります。そしてドン・キホーテこそが、その象徴であると言うのです。敗北が避けられない闘いを、それでも戦い抜く不屈の闘志。それが『ドン・キホーテ』の主題なのだと。こうした「英雄性」を欠いたとき、人は無責任で自己判断ができない「大衆」に堕していくことになる――。後に展開されるオルテガ独自の生の哲学、そして大衆論の萌芽が、ここにはすでに現われています。
もう一人、アメリコ・カストロという人も重要です。彼の『セルバンテスの思想』は、それまで「キホーティズム」に偏っていたウノムーノ的視点を退け、作家セルバンテスの積極的評価に向かいました。彼がエラスムスの流れを汲むルネサンス思想の深い影響下にあったことを、詳細な研究を通じて明らかにしたのです。もう一点重要なことして、スペインの宗教的混淆性を強調したことも挙げられます。15世まで、キリスト教とイスラム教とユダヤ教が共存していた、スペインという国の特異な成り立ち。それが作品に与えた影響を追求することで、ウナムーノらのスペイン一国主義に対する批判を行いました。賛否もありますが、今日のセルバンテス研究は、おおむねこのカストロの議論に方向づけられたものと言えるようです。
(初出:シミルボン「樺山三英」ページ2016年10月7日号)
採録:川嶋侑希・岡和田晃
