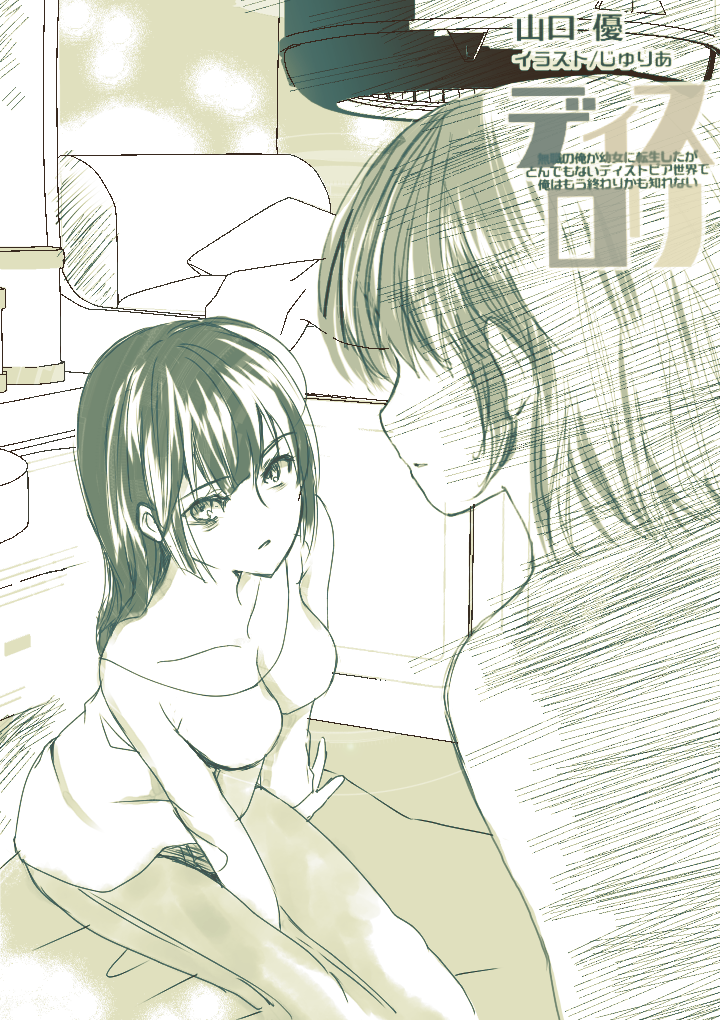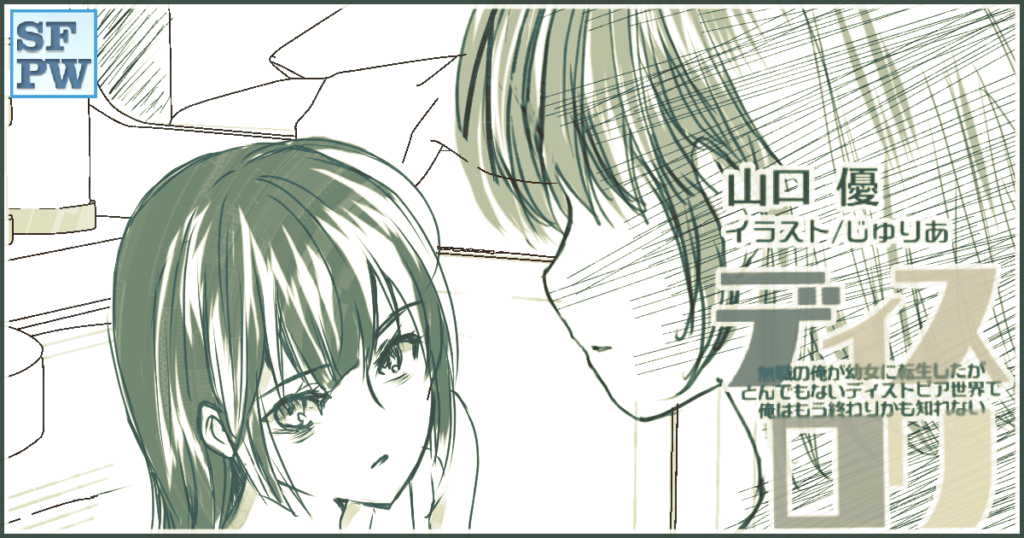
<登場人物紹介>
栗落花晶(つゆり・あきら)
この物語の主人公。西暦二〇一七年生まれの男性。西暦二〇四五年に大学院を卒業したが一〇年間無職。西暦二〇五五年、トラックに轢かれ死亡。再生暦二〇五五年、八歳の少女として復活した。
瑠羽世奈(るう・せな)
栗落花晶を復活させた医師の女性。年齢は二〇代。奇矯な態度が目立つ。
ロマーシュカ・リアプノヴァ
栗落花晶と瑠羽世奈が所属するシベリア遺跡探検隊第一一二班の班長。科学者。年齢はハイティーン。瑠羽と違い常識的な言動を行い、晶の境遇にも同情的な女性だったが、最近瑠羽の影響を受けてきた。
アキラ
晶と同じ遺伝子と西暦時代の記憶を持つ人物。シベリア遺跡で晶らと出会う。この物語の主人公である晶よりも先に復活した。外見年齢は二〇歳程度。瑠羽には敵意を見せるが、当初は晶には友好的だったが、後に敵対する。再生暦時代の全世界を支配する人工知能ネットワーク「MAGIシステム」の破壊を目論む。
ソルニャーカ・ジョリーニイ
通称ソーニャ。シベリア遺跡にて晶らと交戦し敗北した少女。「人間」を名乗っているが、その身体は機械でできており、事実上人間型ロボットである。のちに、「MAGI」システムに対抗すべく開発された「ポズレドニク」システムの端末でありその意思を共有する存在であることが判明する。
団栗場
晶の西暦時代の友人。AGIにより人間が無用化した事実を受け止め、就職などの社会参加の努力は無駄だと主張していた。
胡桃樹
晶の西暦時代の友人。AGIが人間を無用化していく中でもクラウドワーク等で社会参加の努力を続ける。「遠い将来には人間も有用になっているかも知れない」と晶を励ましていた。
ミシェル・ブラン
シベリア遺跡探検隊第一五五班班長。アキラの討伐に参加すべくポピガイⅩⅣに向かう。
ガブリエラ・プラタ
シベリア遺跡探検隊第一五五班班員。ミシェルと行動を共にする。
メイジー
「MAGIシステム」が肉体を得た姿。晶そっくりの八歳の少女の姿だが、髪の色が青であることだけが異なる(晶の髪の色は赤い茶色)。
<これまでのあらすじ>
西暦二〇五五年、コネクトーム(全脳神経接続情報)のバックアップ手続きを終えた直後にトラックに轢かれて死亡した栗落花晶は、再生暦二〇五五年に八歳の少女として復活を遂げる。晶は、再生を担当した医師・瑠羽から、彼が復活した世界について教えられる。
西暦二〇五五年、晶がトラックに轢かれた後、西暦文明は滅び、「MAGI」と呼ばれる世界規模の人工知能ネットワークだけが生き残り、文明を再生させたという(再生暦文明)。「MAGI」は再生暦の世界の支配者となり、全ての人間に仕事と生活の糧を与える一方、「MAGI」に反抗する人間に対しては強制収容所送りにするなど、人権を無視したディストピア的な統治を行っていた。一方、西暦文明が滅亡する前のロシアの秘密都市では、北米で開発されたMAGIとは別の人工知能ネットワーク「MAGIA(ロシア側名称=ポズレドニク)」が開発されていた。
MAGIによる支配を覆す秘密組織「ラピスラズリ」に所属する瑠羽は、仲間のロマーシュカとともにアキラを彼女らの組織に勧誘する。晶はしぶしぶ同意し、三人はポズレドニクが開発されていた可能性のある秘密都市遺跡「ポピガイXⅣ」の探検に赴く。そこで三人はポズレドニクに所属するソーニャと名乗る人型ロボットと出会う。ソーニャは自分達(ポズレドニク勢)の「王」に会わせると語る。ソーニャの案内でポピガイⅩⅣの地下深くにあるポズレドニクの拠点に赴いた晶らは、そこで晶と同じ遺伝子、同じ西暦時代の記憶を持つポズレドニクの「王」と名乗る人物と出会う(晶は彼女をカタカナ表記の「アキラ」と呼ぶことにした)。MAGIを倒す目論見を晶に語り、仲間になろうと呼びかける晶。が、人と人のつながりそのものが搾取を産むと語るアキラは、MAGIを倒した後には、人と人のつながりのない、原始時代のような世界にするつもりだと示唆する。晶はアキラの目論見に加わることを拒否、アキラと自分が同じ生体情報を持つことを利用してポズレドニク・システムのセキュリティをハックし、アキラに対抗する力を得る。
アキラは晶が自らに従わないことを知ると、身長一〇〇メートルに達する岩の巨人を出現させ、晶と仲間たち、そして新たに支援に駆けつけたガブリエラ、ミシェルをはじめ多くの冒険者たちを攻撃する。攻撃は苛烈で、晶たちはいったん撤退を決意する。
一方、自身がポズレドニク・システムとして作られたことを思い出したソルニャーカ・ジョリーニィも、晶たちに味方し、彼女等をポズレドニク勢として受け容れていた。
それを知ったMAGIシステムは、晶たちと敵対することを決意し撤退する。MAGIシステム撤退の後、再びアキラとの交戦が始まる。晶は仲間たちの支援を受け、アキラを倒すことに成功、MAGIシステムを倒すために手を組むが、人と人のつながりを大切に思う晶は、MAGIを完全破壊する意思はなく、「MAGIを倒したときにそこにいた方がMAGIを完全破壊するかどうか決める」ということで、アキラとの共闘を取り付ける。晶は「ラピスラズリ」にも協力を求めるため、瑠羽の部屋を訪問した。瑠羽はこれまでの経緯をあらためて彼女の視点から語ろうと告げる。
西暦二〇五五年。
「瑠羽先生、終わりましたよ」
病院内の設備で石英記録媒体へのバックアップを終えた私は、電磁気遮断チャンバーからせり出してくるベッドの上で、大きく息をついた。上半身を起こす。
正面の鏡を見た。
Tシャツにジーンズというラフな格好の女が目の前にいる。
青みがかった髪は肩まで伸び、くりっとした双眸の眼光は強い。目の下にクマがあるのは、彼女の寝不足を象徴している。よく引き締まり、出るところは出ている体型なのはよいが、実際にはやたらと暴飲暴食のくせに、淡々とジョギングすることで新しい発想を求めている普段の生活パターンを反映しているにすぎない。
そして、その姿は、この機械に入れられたときと同じ。年齢は二〇代半ばといったところだ。
(……元のままか。いったん死んで甦ったわけではないようだね……)
この鏡はそれを確認する為にあるのだ。
「はいこれ、どうぞ」
装置の傍らに控えていた、人型のMAGIから渡されたカップを受け取り、一気に飲む。脳血管関門を通過し、脳内に配置されたNLAM(ナーヴセル・リンク・アンテナ・ナノマシン)を脳から追い出し、排出させるための薬だ。
人型のMAGIは、身長一四〇センチぐらいの小柄な少女の形をしていたが、特徴的なのはその頭部にドーナツ型のMAGIが浮かんでいることだ。
MAGI、つまり、モバイル汎用人工知能は、浮遊能力を持つ筐体に納められた汎用人工知能を意味する。直径三〇センチ程度、ドーナツ型の穴の部分に二重反転プロペラがあり、極めて静かな音で、少女型アンドロイドの頭部の上一〇センチぐらいのところに、静止するように浮かんでいる。目をこらせば、少女の黒髪がわずかに風になびいているが、目立つほどではない。
少女の顔は、いわゆる平均顔で、整っているが特徴がない。体型もスリムで特段の特徴なし。まあ私は、美少女だろうがそうでなかろうが、性格がおもしろくてかわいければ好みではある。が、このアンドロイド少女の場合、その実質的な脳髄は上に浮かんでいるMAGIのほうにあり、その判断基準はクラウドにあるので、面白みもかわいげもないのは残念なところだ。
「ねえMAGIちゃん、君は人類をどう思うかね」
「私たちは人類の幸福を心の底から願っていますわ、瑠羽先生」
「それは光栄だよ。あー、今日はもう休みたいなあ。私の仕事、君たちが代わりにやってくれるかい? その方が幸福な気がしてきた……」
私は冗談っぽく続ける。
「――可能ですが、本当に幸福ですか?」
MAGIは意外に真面目で真摯な瞳を私に向けてきた。平均的な瞳が、平均ではない非凡な知性をその後ろに感じさせつつ、私の真意をのぞき込もうとしている。
「さてね。刺激があればそれでいいんだけどね。例えば君がデートにつきあってくれるとか」
「考えておきます」
MAGIはそつなくそう答えた。
「ほんとかい? 夜も帰さないよ?」
「クラウドにつながっていますので、私はいつも家にいますよ」
(まあこの世界そのものが君の「家」といえばそうか)
私は立ち上がり、白衣を羽織ってそのポケットに両手を突っ込む。
はかったようなタイミングで、ポケットの携帯端末が鳴った。
「世奈先生、ちょっと来てください。妙な患者が」
かけてきた相手は人間だ。人間でなければ、つまり、MAGIネットワークであれば、私に用があれば、今、私の目の前にいる少女型アンドロイドを操作しているMAGIに要件を転送し、そのまま言葉に出していただろう。
「はいはい。私には妙な患者の相談ばかり来るね。類友ってやつかな」
「自覚あったんですか?!」
*
私の職場――つまり、夢島区第一区民病院には、石英記録媒体の電磁気遮断チャンバーが二つある。一つは私の担当で(つまり私は自分の職場で自分のバックアップをしていたわけだ)、もう一つを担当しているのが、私の電話相手だ。
私は足早に院内を歩き、第二チャンバー室に到着した。
「姫子(ルビ:ひめこ)先生、どうしたんだい? 妙な患者って?」
操作室の中に入りつつ、声を掛ける。
私に声を掛けられた相手――冷川姫子(れいぜん・ひめこ)が振り向く。
彼女は、小柄で整った顔立ちで、どことなくさっきまで私が相手にしていた少女型アンドロイトに似ていた。初対面のときは、MAGIの制御下にない素体(ルビ:そたい)かと思って若干失礼なことを口走ったら、ハイヒールのつま先で思い切り向こう臑を蹴飛ばされた思い出がある。あれは痛かった。
姫子先生をアンドロイドと区別するポイントは髪型だ。後頭部にシニョンにまとめており、かつ、桃色の控えめな髪飾りがついている。年齢も少女型アンドロイドと変わらないように見えるのは驚くべきことだが、実際には私より一つか二つ下であるにすぎない。
そしてもちろん、頭上にMAGIは浮いていない。
「走査しようとしたら、反応しないんですよ」
遮断チャンバーの中に寝かされている人体のデータが、操作室のディスプレイに映っている。髪は金髪、年齢は四〇代ぐらいか。
(美人だ。幸先がいい)
――と、言葉に出してはもちろん言わない。私にも多少の節度がある。それに、これ以上姫子先生に嫌われるのはいやだ。
「……この人は?」
「旅行者だそうです。パトソール・リアプノヴァ氏。定期バックアップだそうで」
定期バックアップは全世界の市民の権利であり、各国は互いに協定を結んで、どの国でも定期バックアップを受けられるようにしている。旅先で不意の事故に遭うこともある。旅先の記憶だって残したいだろう、ということだ。
それで彼女は遮断チャンバーの中で眠っているわけだ。バックアップの時は眠らせるのが通常である。
「ふうむ。全く走査できない、か。機械の故障でもなさそうだ。そうだね?」
最後の言葉は、バックアップシステムの上に鎮座しているMAGIに話しかけたものだ。
「間違いありません。機械システムに問題はありません。推測としては、患者本人の頭蓋または脳内にNLAMの電波を阻害する仕組みが入っていることが考えられます」
MAGIに内蔵されたマイクの合成音声がそう告げる。素体を操っているときは、その人工声帯を使うが、そうでないときはMAGIはこうやって話す。
「わお。なんだそりゃ」
私は小さくつぶやいた。そして、顎に手を当てる。
「面白いね……」
「この人がわざとやっているんでしょうか? でも、だったらなぜ定期バップアップに来たのか……。そもそも、死んでも復活するというのはみんな望んでいることなのに」
姫子先生が言う。
「――全く何も分からないね。でもいったんこの人をチャンバーから出そう。入れていても何にもならない。目が覚めるのを待って、話を聞いてみようか」
姫子先生も頷いた。
*
「さて、ガスパジャー(ロシア語での「Ms.」の意味)・リアプノヴァ。あなたの要請通り、電磁波遮断実験室で面会をしているわけだが……これで話してくれるかい?」
「けっこうです。流ちょうな英語ですね。よかった」
我々は英語で会話していた。例の患者――パトソール・リアプノヴァ氏、姫子先生、私の三人だ。電磁波遮断でないと何も話せない、と言い出したのはリアプノヴァ氏だ。彼女の話など聞く必要はなく、さっさと帰ってもらってもよかったのだが、私は好奇心が強いタイプだ。
姫子先生は渋々付き合っている雰囲気だった。それでもこの場にいるのは、彼女の、自分の患者に対する責任感ゆえだろう。
電磁波遮断実験室は、現代の病院にならどこでもある部屋だ。遮断チャンバーの環境と同じく、外部との一切の通信が不可能な作りになっていて、この中でNLAMを飲ませた患者が発する微弱な通信波を走査する実験をしたりする。遮断チャンバーで反応がなかったリアプノヴァ氏を、我々二人がここに連れてくることは、全く不思議なことではなく、誰も疑問に思わなかった。
定期バックアップ業務はMAGIたちに任せている。寧ろ、彼女らの方がうまくやるかもしれない。
「単刀直入に言います。この世界は崩壊します」
「な、なんだって……?!」
私は思わず典型的な反応をしてしまった自分に苦笑した。姫子先生は、(ふざけてるんですか?)という冷たい目で私を見ている。
パトソール氏は私の反応を半ば予期していたようだ。次に言う言葉も決まっているようだったが、言うタイミングを計っている様子だ。
「もし冗談でないとしたら、真意を聞きたいね……」
私が言葉を続ける。
「現在、MAGIシステムが制御していないのは各国の軍事システムだけですが、MAGIは間接的な方法でこれも制御しようとしています」
「間接的な方法?」
「二つの世論操作が同時に進行しています。一つは、MAGI脅威論です。そして、もう一つは、それに乗っかって、『他国がMAGIを自国よりももっと推進している』という論です」
「……馬鹿馬鹿しい、と言いたいところだが、『二つ組み合わせている』というのは興味深いね。他国脅威論だけなら人類は慣れっこだからね。だが、MAGI脅威論をそれに組み合わせることを、とうのMAGIがやっているとは気づきにくい、と。どうやってそれをやる?」
私は一応、信じているふりをして聞いてみた。
「MAGIの目的は軍事関係者に信じさせることです。各国の軍事システムをMAGIの制御下に起き、自動的にあらゆるレベルの攻撃が行えるようにする計画がある、という情報が密かに各国の軍事諜報システムに流されています」
「やれやれ……システムとしての規模はMAGIの方が上だから、人間が制御している軍事システムが手玉に取られているという構図かい?」
「おそらく」
パトソール氏はそこで口をつぐんだ。
「知っていますよ。私があなたがたにどのように見えるかは。しかし、私は各国で仲間を集めている最中なのです。多ければ多いほどいい。そして、話をするにはこのような場所しかないので、病院で勧誘しています」
「冒険者のようだね。仲間を増やして敵を倒す、か」
私は肩をすくめた。
「世奈先生」
それまで黙っていた姫子先生が、私の白衣の袖を引っ張り、部屋から出るように促す。
「ちょっと失礼」
私はパトソール氏に微笑んでみせ、それから二人で部屋を出た。
*
「まずいですよ。あの人、我々精神複写科じゃなくて心療内科のほうがよくありません?」
姫子先生は小声で言った。
「――まあそうだよね」
私は頷く。
「でも、あの人が全く走査できなかったのは事実だ。多分頭蓋骨に何らかの電波阻害剤でも埋め込んでいるんだろうけど、私が知る限り論文でもそんな技術はないよ。それだけでも、あの人がただ者ではないことは分かる」
「……確かに、それはそうですが。しかし科学的に優れた知見を持つ人が、まともであるとは限りません。マッドサイエンティストという例もあるでしょう」
「君の目の前にもいるしね」
「世奈先生! ふざけないでください。また蹴りますよ!」
どうやら、私のジョークは姫子先生には通じないようだ。
「……どうする? 心療内科に回す? それとも帰ってもらう?」
「そうですね……いったん前者、というのが一つの手ではありますが……」
「でもバックアップは条約上の義務だからなあ。どんな人だってバックアップをするのが我々の使命だ」
「それはそうですが……」
こういうところで躊躇するのが姫子先生のかわいいところだ。普段は我関せずといった雰囲気でつんとしているが、患者に対してはいつも本気だ。ツンデレというやつだろう。
「真面目に考えるなら、もっといい設備で、なぜバックアップできないのかちゃんと調べるしかないね」
「――はい。彼女の話はとりあえず聞き流しておいて、もっといい検査設備のある都内の病院を探してみます」
言いつつ、姫子先生は近くを通りかかったMAGIに手招きした。
「はい。冷川先生。どうされましたか?」
「ちょっと都内の病院を探してほしいのだけど」
不思議な光景だ。美少女アンドロイドが二人会話している――。私は不埒な考えを持った。
いいなあ。
「記憶が走査できないのよ。それと、あの人が変なことを言っていてね。何でもMAGIシステムが各国の軍事システムを……」
私は反射的に、MAGIアンドロイドと姫子先生の間に入った。
「おっと。まあ詳細はたいしたことないから別にいいんだけどね、とにかく走査が難しい患者さんがいてね、都内で対応できるところを検索してみて?」
「――了解です」
MAGIは一瞬遅れた後、そう言って頷き、それから、私と姫子先生、そのアンドロイドの間で会話しつつ、最適な病院を見つけ出した。
それからまたパトソール氏との会話に戻り、いろいろと聞き流した後、彼女を検査のために移送する手続きを取った。実際の移送は明日ということになった。
*
「姫子先生、どうしてあのとき遮ったんです?」
私と世奈先生は、帰宅が途中まで同じだ。我々は都営夢島線夢島駅で電車を待っている途中だった。
「ああ……念のためだよ」
「念のため?」
「万が一、MAGIが本当に世界を崩壊させたがっているなら、……教えちゃまずいと思ってさ」
姫子先生はどう反応していいのか分からない、という顔をした。
「世奈先生は、なんとなく浮世離れしたところがありますよね。ここにいながら、ここにいないような……」
「褒めてるの、それ?」
「ある意味では褒めてます。好きですよ、そういう人。なんだか、私にないものを持っている感じで」
「やったね。じゃあ今度デートしよう」
「セクハラしなければもっと好きですよ」
姫子先生はそっぽを向いた。
その瞬間。
駅員の姿をし、上にMAGIを浮遊させているアンドロイドが、勢いよく姫子先生に突撃してきた。私はとっさに姫子先生を抱え、そのままそのアンドロイドの力をまともに受け止めて線路に飛び降りる。
反射神経も膂力も段違いのアンドロイドの力を回避したり抵抗したりするのは無意味だからだ。
電車が迫る中、私はそのままの勢いで姫子先生をひきずって線路を横断、向かい側のホームに彼女を投げ出すように押し上げ、自分自身も必死に飛び乗る。勢い余って私の身体はごろごろとホームを転がった。
直後、風が後ろを通る。電車だ。
姫子先生ががたがた震えている。
私は震える余裕もなかった。心臓が爆発したように大きな鼓動を続けている。
(……殺されかけた……姫子先生が……MAGIに……?)