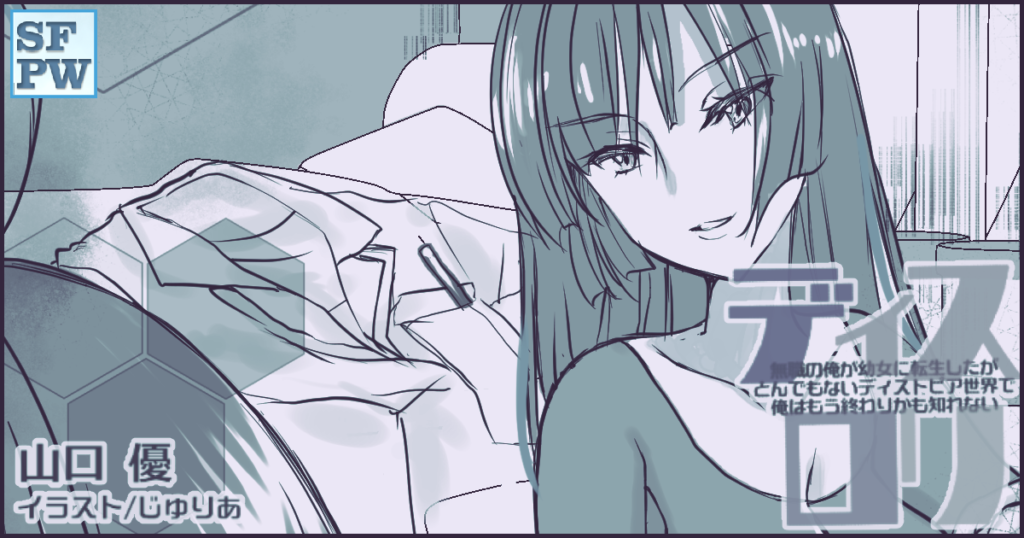
「無職の俺が幼女に転生したがとんでもないディストピア世界で俺はもう終わりかも知れない(略称:ディスロリ):第24話」山口優(画・じゅりあ)
<登場人物紹介>
- 栗落花晶(つゆり・あきら)
この物語の主人公。西暦二〇一七年生まれの男性。西暦二〇四五年に大学院を卒業したが一〇年間無職。西暦二〇五五年、トラックに轢かれ死亡。再生暦二〇五五年、八歳の少女として復活した。 - 瑠羽世奈(るう・せな)
栗落花晶を復活させた医師の女性。年齢は二〇代。奇矯な態度が目立つ。 - ロマーシュカ・リアプノヴァ
栗落花晶と瑠羽世奈が所属するシベリア遺跡探検隊第一一二班の班長。科学者。年齢はハイティーン。瑠羽と違い常識的な言動を行い、晶の境遇にも同情的な女性だったが、最近瑠羽の影響を受けてきた。 - アキラ
晶と同じ遺伝子と西暦時代の記憶を持つ人物。シベリア遺跡で晶らと出会う。この物語の主人公である晶よりも先に復活した。外見年齢は二〇歳程度。瑠羽には敵意を見せるが、当初は晶には友好的だったが、後に敵対する。再生暦時代の全世界を支配する人工知能ネットワーク「MAGIシステム」の破壊を目論む。 - ソルニャーカ・ジョリーニイ
通称ソーニャ。シベリア遺跡にて晶らと交戦し敗北した少女。「人間」を名乗っているが、その身体は機械でできており、事実上人間型ロボットである。のちに、「MAGI」システムに対抗すべく開発された「ポズレドニク」システムの端末でありその意思を共有する存在であることが判明する。 - 団栗場
晶の西暦時代の友人。AGIにより人間が無用化した事実を受け止め、就職などの社会参加の努力は無駄だと主張していた。 - 胡桃樹
晶の西暦時代の友人。AGIが人間を無用化していく中でもクラウドワーク等で社会参加の努力を続ける。「遠い将来には人間も有用になっているかも知れない」と晶を励ましていた。 - ミシェル・ブラン
シベリア遺跡探検隊第一五五班班長。アキラの討伐に参加すべくポピガイⅩⅣに向かう。 - ガブリエラ・プラタ
シベリア遺跡探検隊第一五五班班員。ミシェルと行動を共にする。 - メイジー
「MAGIシステム」が肉体を得た姿。晶そっくりの八歳の少女の姿だが、髪の色が青であることだけが異なる(晶の髪の色は赤い茶色)。
<これまでのあらすじ>
西暦二〇五五年、コネクトーム(全脳神経接続情報)のバックアップ手続きを終えた直後にトラックに轢かれて死亡した栗落花晶は、再生暦二〇五五年に八歳の少女として復活を遂げる。晶は、再生を担当した医師・瑠羽から、彼が復活した世界について教えられる。
西暦二〇五五年、晶がトラックに轢かれた後、西暦文明は滅び、「MAGI」と呼ばれる世界規模の人工知能ネットワークだけが生き残り、文明を再生させたという(再生暦文明)。「MAGI」は再生暦の世界の支配者となり、全ての人間に仕事と生活の糧を与える一方、「MAGI」に反抗する人間に対しては強制収容所送りにするなど、人権を無視したディストピア的な統治を行っていた。一方、西暦文明が滅亡する前のロシアの秘密都市では、北米で開発されたMAGIとは別の人工知能ネットワーク「MAGIA(ロシア側名称=ポズレドニク)」が開発されていた。
MAGIによる支配を覆す可能性を求めて、ポズレドニクが開発されていた可能性のある秘密都市遺跡「ポピガイXⅣ」の探検に赴いた瑠羽と晶、そして二人の所属する探検班の班長のロマーシュカ。そこで三人はポズレドニクに所属するソーニャと名乗る人型ロボットと出会う。ソーニャは自分達(ポズレドニク勢)の「王」に会わせると語る。ソーニャの案内でポピガイⅩⅣの地下深くにあるポズレドニクの拠点に赴いた晶らは、そこで晶と同じ遺伝子、同じ西暦時代の記憶を持つポズレドニクの「王」と名乗る人物と出会う(晶は彼女をカタカナ表記の「アキラ」と呼ぶことにした)。MAGIを倒す目論見を晶に語り、自分に従えと呼びかけるアキラ。が、人と人のつながりそのものが搾取を産むと語るアキラは、MAGIを倒した後には、人と人のつながりのない、原始時代のような世界にするつもりだと示唆する。晶はアキラの目論見に加わることを拒否、アキラと自分が同じ生体情報を持つことを利用してポズレドニク・システムのセキュリティをハックし、アキラに対抗する力を得る。
アキラは晶が自らに従わないことを知ると、身長一〇〇メートルに達する岩の巨人を出現させ、晶と仲間たち、そして新たに支援に駆けつけたガブリエラ、ミシェルをはじめ多くの冒険者たちを攻撃する。攻撃は苛烈で、晶たちはいったん撤退を決意する。
一方、自身がポズレドニク・システムとして作られたことを思い出したソルニャーカ・ジョリーニィも、晶たちに味方し、彼女等をポズレドニク勢として受け容れていた。
それを知ったMAGIシステムは、晶たちと敵対することを決意し撤退する。MAGIシステム撤退の後、再び晶とアキラとの交戦が始まる。晶は仲間たちの支援を受け、アキラを倒すことに成功する。
現在、ポピガイⅩVに所在するMAGI勢は、待機状態となっていた。MAGIがそう指示したのだから仕方ない。そして、俺たちの班にだけは、MAGIは指示を送って寄越さない。多分、ポズレドニク勢だと明かしたことで、MAGIは機械的に俺達を管理範囲外の人間と規定したのだ。
俺達――とは、俺と瑠羽、ロマーシュカ、そして、シベリア遺跡探検隊第一五五班のミシェル・ブランとガブリエラ・プラタだ。班長のミシェルは別のメンバーに一五五班の班長の役割を譲り、俺たちの班に残った。ミシェルはロマーシュカとともに、ゴーレムを生成するMAGIC関数の作成に携わってくれもした。偶然に早く駆けつけ、俺達と共に戦闘に参加してくれただけの仲で、ありがたいことだと言えよう。
俺達は冒険服を着て、俺達とは別のコンテナの「セーブポイント」に入った。そこには培養槽が一つしかなく、その培養槽の脇に、ソルニャーカが佇んでいた。
覗き込むと、そこにアキラが横たえられている。
鍛えられた、筋肉質でスレンダーな肢体だ。俺たちの接近に合わせるように、身を起こした。彼女の赤茶色の髪と上体から、培養槽のしずくがしたたり落ちる。
「……来たか、オレ」
「……確かに俺はお前だが、もはや違う者だ。頭は冷えたか?」
「違う者なら、冷えたところで頭で考える中身が同じになるわけがないさ」
口の端をつりあげ、皮肉っぽく言う。いや、皮肉と言うよりも自嘲なのか。
「しかし、お前ともういちど戦っても、倒せはしないだろうからな。今は仕掛けるのをやめておいてやる」
偉そうにそう言った。ぬれそぼった赤い前髪の後ろからのぞく鋭い眼光は、まだ俺への敵意を消していないことを示している。俺は少し視線を落とした。やつの前髪からしたたり落ちたしずくは前髪から胸に落ち、そこから培養液の液面に波紋を広げる。
俺たちを照らす「セーブポイント」の照明は、天井に張り付けられた塗料発光材料からのものだが、青空色ではなく、アキラと同じ赤色の要素が強く混じった光だ。それがポズレドニク勢の象徴色なのかもしれない。その赤の光の中で、アキラの肢体は不敵なオーラをまとい続けている。
(気圧されるな、俺)
自分に向けてささいやいた。瑠羽が俺の肩に手を置く。激励のつもりか。奇矯なわりには気のつく女だ、と、一応感謝しておく。そして口を開いた。
「……ふん。そんな風に恩着せがましく言われてもな。それはお前の都合だ。俺はいつ仕掛けられてもいいさ。それよりも俺に恩を着せたいのなら、MAGIを倒すのに協力しろ。もともとはお前がやりたかったことのはずだ。俺が主導権をにぎったところで、結果は変わらないはずだろう」
アキラは、俺を探るように見つめた。培養槽から身を起こしたやつの顔は、俺の頭の位置とそう変わらない高さだ。やつにとっては、俺は、培養槽のふちからようやく顔を出す程度のちっぽけな存在に見えていることだろう。それは事実だ。だが、俺の後ろには瑠羽がいて、ロマーシュカがいる。ミシェル・ブラン、ガブリエラ・プラタもついてきてくれている。培養槽のふちにたつソルニャーカ・ジョリーニィも、今やポズレドニク勢としては俺とやつの双方に責任を持つ立場であって、一方の味方ではない。
やつはフン、と鼻を鳴らした。
「変わるさ。お前はMAGIを全て破壊するのか? 何か残すんじゃないか? 現にお前は倒したオレをそのまま生かし続けている」
流石に鋭い。
研究予算申請や就活のような特殊な状況を除き、俺は俺自身を褒める趣味はないが、この場合は俺自身を褒めることにはならないだろう。
やつは俺と同じように幼女の姿で復活してから、初期に仲間と信じていた団栗場、胡桃樹に裏切られてあとは、一〇年以上、一人で生き抜いてきた。そこで身につけた鋭さでもあるのだから。
「……それは状況による」
俺は曖昧に言った。MAGIの全てを否定したいわけではない。仲間を作るということの重要さを俺はすでに知っている。全否定したいアキラとはすでに異なる立場だ。MAGIが俺たちとの対決の末に、強制収容所のような行き過ぎたシステムを改めるなら、やつというシステムを存続させることに俺は決めていた。
「……だろうな。オレはなんとしても滅ぼすつもりだった」
アキラは言う。そのらんらんと光る眼光には、「仲間」について俺とは異なる経験をしたやつの強い意志が感じられる。やつを翻意させることは無理だろう。俺とやつは、所詮は「現在のMAGIのあり方を否定する」というただ一点で協力できる関係にすぎない。
「――では、MAGIを滅ぼすかどうかは、最後に奴の生殺与奪を握った奴に任せよう。俺とお前が力を合わせたところで、奴に勝てるかどうかは分からないからな」
俺は言う。俺の言葉に、彼女はふむ……と言ってから黙り、顎に手を当てた。それから、じっと俺を見る。
「オレはこういうとき、合理的な判断をする。そういう本質的な部分は、オレもお前も変わらないはずだ。違うかな?」
俺は無言で頷いた。
「とすれば、オレがMAGIの生殺与奪を握ったとき、MAGIを倒してしまう、という可能性を容認することは、お前にとって果たして合理的なのかな?」
俺はため息をついた。
「……どちらがマシかという判断だ。このままのMAGIを存続させるのと、いったんMAGIを滅ぼしてでも、よりよいシステムを構築するのと。俺は最終的にMAGIの要素が入ったシステムが構築できればそれでいい。今のMAGIを存続させる必要は、必ずしもない……。その分、手間はかかるがな――しかしお前の助力が得られないことによって、永遠に今のMAGIの体制が続くままの方が、俺にとっては容認しがたい」
それに、と俺は続けた。
「異なる人間同士が異なる考えを持つのは当然のことだ。それを容認できなければ、真の『仲間』など作れないさ」
アキラは虚を突かれたような顔になり、それから大声で笑い出した。
「あっははははは! お前はオレを仲間にしたつもりか!」
ざぶりと立ち上がる。俺を見下ろすように立った。やつの身体からしたたり落ちるしずくが、俺の髪に落ちる。
やつは俺の胸ぐらをつかみ、無理矢理上を向かせた。
「晶ちゃん!」
緊迫した声を出す瑠羽を手で制した。そして、ほぼ真上にあるやつの顔をぐっと見上げる。
「ああ、そうだが?」
アキラは俺の胸ぐらをつかむ手を強めた。
「いい気になるなよ……? この世界はゲームを装っているがゲームではない。倒した敵がそう簡単に仲間になるものか……。よく聞け。オレはお前の仲間になどならん。それだけははっきりさせておこう。お前など、いつかオレが力を蓄えれば倒せるんだからな……それはそう遠い未来じゃない」
俺は俺の胸ぐらをつかむアキラの手の手首を握る。
「こちらもはっきりさせておこう。俺はお前の挑戦を恐れてなどいない。いつでも仕掛けてくればいい。そのたびに倒す。それによってお前が『仲間』の価値を容認するまでな……。本当は議論によって認めさせたいところだが、お前はそんな方法はすでに認めないのだろう。ならば戦いによって認めさせるまでだ。お前が戦いではなく、議論によってよりよい社会とは何か俺と論(ルビ:あげつら)うようになったとき、お前は俺の仲間になっているだろう。俺の言う『仲間』とはそういうものだからだ。そうなる日まで、俺は挑戦を受け続ける」
俺は意識して、激昂せず、淡々とそう言い切った。
「減らず口を!」
アキラは俺を突き飛ばす。だが、俺は数歩あとずさって踏みとどまり、その場で仁王立ちになった。
アキラの前に進み出て、手を差し出す。
「とりあえず、共闘の方針は受け入れたと思ってよいか?」
アキラはその手を乱暴に握った。
「……倒す順番を変えるだけだ。まずMAGI、その次にお前だ。覚悟しておけ」
俺は頷いた。
「それでいい」
本当にそれでいいと思っていた。
不思議な感覚だった。俺だって目の前のアキラのようになった可能性があるのに、同じ人間がここまで変わるとは。
だが、それこそが『仲間』というものの――社会というものの効用であり、欠点でもあるのだろう。
*
ソルニャーカは、ポズレドニク勢仕様のセーブポイントを増設し、そこに俺たちの宿舎も整えてくれた。MAGIのセーブポイントでMAGIを倒す相談をするわけにはいかないからだ。
ただ、「赤い照明」は気分が悪いので、そこは普通の白い照明に変えてもらったが。「今日はもう疲れただろうから、明日作戦会議をしよう」という瑠羽の言葉に従い、俺たちはそれぞれの部屋に引き取った。
だが、俺は思うところがあり、瑠羽の部屋の前に立っていた。
ノックする。
「誰だい? ロマーシュカかな?」
「いや、俺だ」
俺は淡々と言う。
「晶ちゃんか!」
弾んだ声がドアの向こうからする。その一秒後、ドアが開いた。瑠羽がにこにこして立っている。
「いやー、いつか夜這いに来てくれるとは思っていたけどねー。待ちわびたよ。晶ちゃんは本当に遠慮深いんだから。君と私の仲なんだからさ、遠慮なんていらないんだよ? ささ、入ってくれよ。何か飲むかい? コーヒーと紅茶、どっちが好きかな?」
「紅茶。言っておくが、夜這いじゃないぞ。なんでそうなる」
俺は一応そう言い、瑠羽に勧められるままに、椅子に座る。セーブポイントの居室のデザインは、MAGI勢のそれと全く変わらない。ベッドがあり、デスクがあり、チェアがあり、シャワールームとトイレがある。そして部屋の中央にはテーブルが置かれ、それを囲むように椅子がある。その椅子の一つに俺は座ったわけだ。
よく見ると瑠羽は気楽な格好をしていた。Tシャツにホットパンツ、それだけだ。化粧もおとしているようだが、もともと顔はいいので、落としてもそう見た目は変わらない。普段から、ごく薄い化粧しかしていなかったのだろう。
そして、今はトレードマークの白衣を着ていない。それが新鮮と言えば新鮮だった。
「お? その顔は、改めて君の彼女の美しさに感嘆しているな?」
いたずらっぽく微笑んで言う。
「いつ付き合い始めたんだよ。今日は真面目な話をしにきたんだ」
真面目な話以外、こいつとするつもりなどそもそもないが。
「ひどい……この私をだましたんだね……ロリっ娘のくせに年上の女を手玉に取るとは……」
口を覆ってショックを受けたような顔を作る。
「……ったく。手玉に取られてるのは俺のほうだ。恋愛経験のない幼女をからかうな」
「そりゃあ再生された君には恋愛経験などないだろうけど、再生前の君にはあるんじゃないのかい?」
「……ないさ。誰が無職の人間なんかに興味を持つ?」
俺は肩をすくめた。
「……それはやつも……女王アキラも同じだろうさ。だから急に好意を示されても警戒感もなかったんだ」
「ふうん。君は確かにひねくれているけど、よく話を聞いてみれば面白い性格のように思うけどねえ。君の周りの女は見る目がなかったと見える」
つと立ち上がり、食器棚から紅茶カップとティーポットを取り出し、ポットに茶葉を入れて湯を注いだ。さらに、冷蔵庫からジャム、マーマレード、蜂蜜を取り出し、テーブルに置く。
「ロシアンティーか?」
「まあね。ロマーシュカの好物でね。彼女に勧められて私もファンになった。無論君がいやなら、普通の砂糖もあるけど」
「……いや、いただくよ」
俺は紅茶に蜂蜜を入れ、ひとくち、飲んだ。甘い味だ。俺は味にうるさくない。というかそもそも味覚がそれほど鋭敏ではない。だがうまいと感じた。そして暖まった。
「……俺が面白い性格だって?」
瑠羽は頬杖を突き、興味深げに俺をのぞき込んでいる。
「面白いよ? だから私は好んでからかっているわけだし」
「それをやめろと言ってるだろ」
「はっは。やめろと言われてやめるようなら始めからやってないさ。人生というものはね、晶ちゃん、楽しんだものが勝ちなんだよ。あれをやれ、これをするなと人は言うが、そのとおりに生きて楽しめるもんか」
「それがお前の人生哲学か。ならばラピスラズリなんて組織に属しているのも分かるな……。MAGIというシステム自体がお前の哲学に反している」
「その話か。君の言う『真面目な話』というのは」
俺は頷いた。
「そのとおりだ。夜這いなんかじゃないぞ」
「夜這いも真面目にやれば真面目な話になるよ?」
なおも言いつのるが、俺が不快感を隠そうともしないので、瑠羽はひとつ咳払いし、腕を組んで椅子にもたれかかった。
瑠羽の指が彼女の胸のあたりをさまよったが、そこに指しているはずのラピスラズリ色のペンは、今は壁にかけられている白衣の胸ポケットにある。それに、そもそも今や天井も空色ではなかった。
「……ラピスラズリの仲間を作戦に加わらせろと言うことだね」
「ああ。戦力は多い方がいい。今回の俺たちの行動は、お前たちラピスラズリの理念にもかなうものだと思うが。MAGIを破壊したい、そのためにポズレドニク勢の女王、アキラと接触する……それがそもそもお前たちの目的だっただろう。そのために俺を復活させもした。違うか?」
「違わない。しかし、なぜ私を訪問したんだい? ロマーシュカでもよかったじゃないか。彼女もラピスラズリのメンバーだ」
「俺を復活させる――それはお前がやったことだろう。お前の行動であり、動機が、俺の新たな冒険の人生を開始させた要因なんだ。今ここで冒険に幕を閉じる戦いを始めるなら、お前に話をするのが筋だ。違うか?」
「……まあ、間違ってはいないね」
瑠羽は目を閉じ、紅茶をすすった。
「そうだね。君にそもそもの発端から話を聞かせるのも悪くないだろう。ラピスラズリの想い、私の想いを知り、それをMAGIと対峙したときに役立ててもらうためにも。それは確かに、君をこの世界に『召喚』した私の責任だ」
彼女はさきほどのふざけた調子から打って変わって真面目な雰囲気になり、語り始めた。

