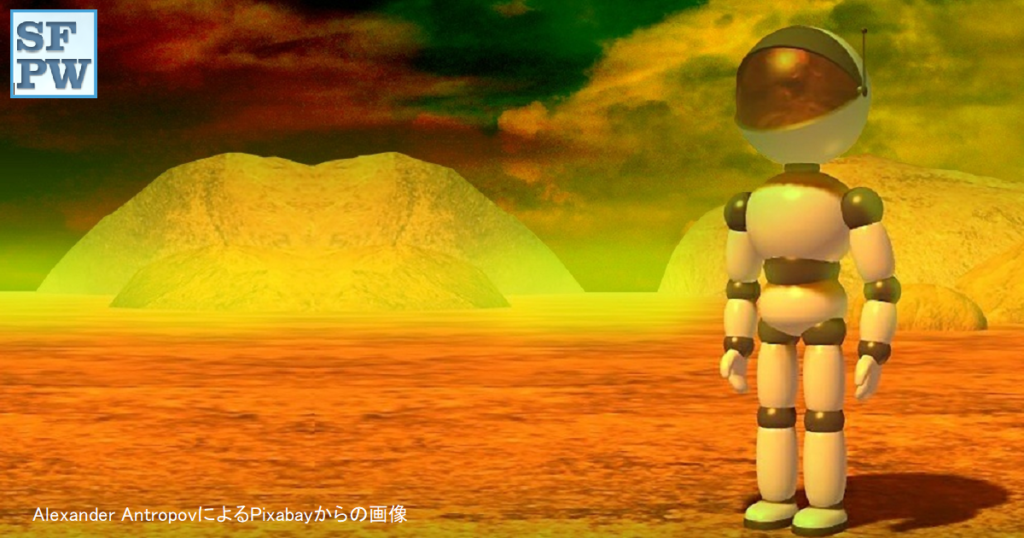
Grandma’s Heartbeat 伊野隆之
訓練期間を終えた僕は、久しぶりに母に会いに家に戻った。二週間の短い休暇が終われば火星行きのための最終的なメディカルチェックがあり、僕は月の軌道上で待機しているマーズトランスポーターに積み込まれることになっている。
搭乗するのではなく、積み込まれる。活動状態の人間を運ぶには、空気や大量の食料、十分に大きな空間が必要だが、コクーンの中に低温保存しておけば必要な資源を大幅に節約できる。マーズトランスポーターは軽くなり、火星に人を送り込むために必要なエネルギーとコストを節約できる。それに運ばれる僕らからすれば、火星に到着するまでの二年の間の暇つぶしを考えなくてもいい。
「もう、そんな時期になったのね。あっという間だったわ」
リビングのローテーブルにコーヒーカップの乗ったトレイを置いた母が感慨深げに言った。母が愛用している白磁のカップと、惑星の絵がプリントされた僕のマグカップに、母はコーヒーをゆっくりと注ぐ。
「そうだね。まだ現実感がないんだけど」
この家に来ると大学に入る前の僕自身に戻るような気がする。実際、二階には僕の部屋があり、今でもハイスクール時代のままに残されている。母もそのままが良いと言ってくれた。
「私の方こそ現実感がないわ。あなたがこの家を出てから、あっという間だった」
修士課程を終え、博士課程に進んだ年に火星入植計画にエントリーした。それから既に五年近い年月が経過している。エントリー、書類選考、ペーパーテストにインタビュー、モハベ砂漠での長期の訓練と試験、最初の入植者になる百人の候補に残ったところで、脱落の可能性は常にあった。
「もう少し、頻繁に帰ってこられれば良かったんだけど……」
火星への旅は片道切符だ。そのことを母と僕は十分に理解している。つまり、母と一緒に過ごす時間はこれで最後だ。
「知ってる? 子供が独立した時点で、親が子供と一緒に過ごせる時間はほとんど終わっているんだって。私はたまに火星の風景でも撮影したメールをもらえれば十分よ」
火星と地球との間では、会話は成立しない。タイムラグは二つの惑星が最も近いときでも三分を越え、遠いときには二十分を越える。直接話すことはできない。
「もちろん約束するよ。それに送るのは風景だけじゃないと思う」
僕たちは最初の入植者だ。次の世代を育てるのも任務のうちだ。
「それは楽しみだわ。もう誰か付き合ってる人がいるの?」
「そっちはまだだけど……」
ちゃんとしたパートナーが見つかるかどうかは別にして、遺伝的な子供を持てる可能性は高い。遺伝的多様性も最初の百人を選ぶ基準の一つだった。
「そうだったわね」
母は精子バンクから提供された精子で僕を生んだ。親一人に子供が一人。僕たちのような家族は、今は珍しくない。だから僕がいなくなれば母は一人になる。もちろん母は一人でやっていけるだろうし、今更心配しても始まらない。
「そう言えば渡したい物があったの」
母は首に掛けたペンダントから小ぶりの卵を扁平にしたようなものを外した。それは、透明感のある光沢があり、ホワイトオパールのようにも見える。
「私がハイスクールの試験の時に母からもらったものよ。ちょっとした電子的なおもちゃね。少しくらいは私物を持って行けるんでしょ?」
母の問いに、僕はうなずく。
「ほんの少しだけだけどね」
個人的に火星に持って行くべき物はほとんどなく、私物用のスペースには十分な余裕があった。
「じゃあ、大丈夫ね。これを火星に連れて行ってあげて」
僕の手のひらに乗せられたその物体は、まるで生きているかのように脈動していた。初めて触るそれはほんのりと暖かく、小石ほどの重さがあった。
「これ、母さんのお守りじゃあ……」
僕は、母がそのオーバル型の物を常に身につけていたことを知っている。表面は滑らかで、電池を入れるための開口部がないのは、放射性物質を使った長寿命の電池を内蔵しているからだろうか。
「いいのよ。もう、私には必要ないから。これが必要だったのは随分前のこと。私は手間のかかる子供で、私の母、あなたのおばあさんには大変な苦労をかけたの……」
祖母は、僕が生まれる随分前に亡くなっていた。古い写真に残る赤ん坊の母を抱いた祖母は、今の母と間違えそうになるくらいにそっくりだった。
「へえ、そうなんだ。ぜんぜんそんな感じじゃないのにね」
母が生まれる前、空軍に勤務していた頃の祖母は、宇宙飛行士の候補にもなったくらいに優秀だったという。僕が火星を目指したのは、そんな祖母の影響かもしれない。家には、祖母の遺した物がたくさんあった。
「分離不安障害ってわかるかしら? 良くあるのが母親からの分離を恐れる症状なの。二歳くらいまでの乳幼児にはごく当たり前で、普通は病気と見なされるようなものではないんだけど、私の場合は不安による症状が強く、それが長く続いたの……」
子供を産むために、祖母は軍を辞めたのだという。母が生まれたのは、軍関連の民間企業で働き始めて三年が過ぎた頃だった。
祖母が育児休暇を取っている間は良かった。一年半の育休があけたその日、会社に出勤しようとした母は最寄りの地下鉄までの五分で出勤を諦めたのだそうだ。ちょうど改札に着いたとき、息を切らすほどの大声で泣く赤ん坊の動画がベビーシッターから送られてきた。それが僕の母だ。祖母は慌てて会社に連絡をいれ、家に引き返した。
家に戻った祖母は、泣き疲れてぐったりした赤ん坊を小児科に連れて行った。病院に着く頃にはすっかり落ち着いていたが、動画を見せられた小児科医は、急いで家に戻った祖母の判断は正しかったと請け合ったという。大声で泣いて十分な呼吸ができなかった赤ん坊の唇は青ざめ、低酸素血症の症状を呈していたらしい。
祖母はシステムエンジニアだった。育児休暇の延長は認められなかったものの、在宅勤務を認められ、家で働き始めた。端末に向かう祖母の横にいる時の母は、扱いやすい、上機嫌な赤ん坊だったらしい。祖母は会社のウェブ会議で同僚たちに幼かった母を見せた。画面越しの母は、祖母と同じ金色の巻き毛の小さな女の子だ。
「母には月に一度だけ出勤日があり、そんな日には母は私を連れて会社に行ったの。二歳になったばかりの私は、母のいるオフィスで若いエンジニアに囲まれ、上機嫌だったようね。その様子を見て大丈夫だと思った母は、私をおいて打ち合わせのためにオフィスを離れた。時間的には僅かな間だったけど、母の姿を見失った私は、ものの十分も経たないうちに大泣きして医務室に運び込まれたの。過呼吸だったわ……」
* * *
打ち合わせから抜け出したママが医務室に駆け込んで、私を強く抱きしめる。ママの腕の中で、私を飲み込もうとしていた不安が溶けていく。その様子を見ていた会社の勤務医は、こんな状態が続くようならと前置きした後で、私を精神科のカウンセラーに診せることを勧めた。
保育園に行くような年齢になっても症状は改善しなかった。私は手間のかかる子供のままで、ママがトイレに行くために席を外しただけでも私は恐怖の発作に襲われそうになる。唇を噛み、両手を固く握りしめる。ママが戻るのを待つ間、私の体中の筋肉はこわばり、いやな汗が浮く。トイレのドアの前で膝を抱え、泣き出さないようにしていた私を癒してくれるのは、トイレを出たママだけで、ママの抱擁とゆっくりと背中をさする手の感触だけが、不安に凝り固まった私を解きほぐしてくれる。それが当たり前だった。試しに連れて行かれた保育園では、ママの姿が見えなくなると大声で泣きだし、それが他の子供たちに伝染して大騒ぎになった。呼び戻されることを予期していたママは、保育士からの連絡があると、慌てて私を宥(なだ)めに戻るのだった。
私は変わらなかった。家にいて、ママの姿が見えているうちは上機嫌ないい子供。ママの姿が見えなくなると、感情のタガが外れ、溢れた不安に飲み込まれてしまう。ママが私を精神科に連れて行ったのは五歳になってすぐで、ママはそのときまでにあったことを全てカウンセラーに話した。
診断の後で私に処方されたのは抗うつ薬だった。フルボキサミンという薬で、分離不安症にも効果があるとされていた。けれど、私がその薬を口にしたのは最初の一回だけで、ママは二度と飲ませようとしなかった。薬を飲んだ後の私は、胃の内容物を全て吐き出してしまった。その時の私が感じていたのは、世界がベールに隠され、焦点が合わないような感覚だ。
画面に向かってキーボードを叩き、マウスを使うママの横で、幼い私は毎日を過ごした。カウンセラーに勧められママが買い与えてくれた大きなウサギのぬいぐるみは、私にいろいろ話しかけてきたけれど、私はいつも上の空で、働くママの様子をただうっとりと見ていた。そんな私が小学校に行く年齢になったところで、まともに通学できるはずはなく、ママはリモート学習できる私立学校を選んだ。
優秀なママの血を引く私は成績も良く、画面上の授業は馬鹿馬鹿しいくらい簡単だった。結果は飛び級に次ぐ飛び級で、私は十二歳でハイスクールの受験資格を取得した。
しゃべるウサギを勧めたカウンセラーの元には、ママと一緒に定期的に通っていた。電池が切れたままのウサギはもう話すこともなく、ママの物だった天体模型と一緒に書棚の上から私を見下ろすだけだった。ママと一緒にいたいという想いに病的なものがあるという発想はなく、変わりたいとはこれっぽっちも思っていなかった。家ではママの仕事の邪魔をしたことはないし、買いものには必ず一緒に行き、ママを手伝っているような気分でいた。
「試験があるんです」
カウンセラーにママが言う。想像しただけでも心臓を握りつぶされるような恐怖を感じる。特別な事情がある受験生には特別な配慮が可能。ただし、第三者の立ち会いや、外部との通信機能のある機器の持ち込みは、他の受験生との公平性を確保する観点から認められない。つまり、ママは私の試験に立ち会うことはできないし、ママの様子を画像で見ていることもできない。せいぜい、ママの写真をプリントして机に置いておくくらいのことしか許されない。
「残念ですが今の状態では難しいでしょうね。お嬢さんには無理です。負担が大きすぎるでしょう。抗うつ剤が使えればいいんですが」
フルボキサミンは合わなかったし、それ以外の分離不安に有効とされる選択的セレトニン阻害薬をいくつも試した結果は好ましいものではなく、疲労感や意欲の減退と言った副作用を招いた。私に言わせれば半分死人になったような気分になるだけのもので、ママからの分離不安そのものは一向に解消されなかった。
「やっぱり、手術しかないんでしょうか?」
ママの言葉に私は恐怖を覚える。脳の中に埋め込む小さなチップは不安を生み出すサイクルに介入し、不安そのものをなかったことにする。分離不安への適用例はまだ少ないが、他の不安神経症への適用では既に実績が積み上げられつつあった。
「私、手術なんかしなくて大丈夫だから」
思わず声を上げていた。自分の頭の中に異物を入れることに耐えられる気がしなかった。
「すぐには無理です。事前に十分な準備をしないと必要な刺激のパターンを決められません。そのためには測定用のキャップを着けて過ごしてもらう必要がありますが、時間が足りません。それに、お嬢さんに納得してもらわないと……」
そう言って、カウンセラーは私を見た。私にはわかっていた。最初にチップの話をしたのはカウンセラーの方だったし、今までも折に触れては手術の有効性をほのめかしていた。目の前の男は、私のことなんかこれっぽっちも考えていない。きっと、手術をしたくてたまらないのだろうし、私の手術について論文を書き、それで有名になるつもりなのだ。睨みつける視線をカウンセラーはあっさりと無視する。
「ええ、そうですよね……」
ほっとしたようなママの返事に、私は少しだけ安心したけれど、このままではまずい。
クリニックからの帰り、ママの運転する車の助手席で、私は改めて自分のママへの愛着と、ママから引き剥がされることへの恐怖を考えていた。薬物やチップに頼らないで、どうしたら不安をコントロールできるのか。
車の中で私は、受験の延期を決めていた。まだ十二歳だった私には、分離不安障害に向き合う時間がある。一年で受験できるようになると宣言した私をママは心配そうに見ていた。
それまで私は、自分の不安を障害だと思っていなかった。ママがいなければ不安を感じるのは当たり前で、おかしいことなどない。そんな私の感情を、ことさら病気に仕立てようとするカウンセラーに対しては不信感しかなかったし、そんなカウンセラーの元になぜ私を連れていくのかと、ママにも不満を抱いていた。
ただ、このままではいけない。学校に通えないことに不満はなかったが、ママへの強すぎる愛着が自分の可能性を狭めていることをはっきりと認識していた。それに、ママの夢でもあった宇宙工学を学ぶには進学が不可欠だった。
もう一つの問題はママの負担だった。ママの側を離れることのできない私は、間違いなくママの重荷になっている。私にはママの姿が見えてさえいれば良かったので、仕事の邪魔をしてはいけないことは学んでいたが、それでもママは私に対して苛立ちを見せることがあった。その一方で、苛立ちを見せたことに対して落ち込むママがいる。そんな夜、ママが仕事をしているリビングのソファーで寝たふりをしている私に向かって、ママは小さく「ごめんね」と言い、時には聞き取れないほどの嗚咽を漏らす。
私の家に父親はいない。どうしてか教えられてもいないけれど、ママは、そのことが私の分離不安の原因になっていると考えているようだった。乳児期に愛着の対象となったのがママ一人で、その状態が変わることなく続いているというのだ。直接にママの考えを聞いたわけではないが、カウンセラーとの話や、寝たふりをしている私に向けて話すことから、ママがそう考えているのはわかっていた。でも、それが本当のことなのか私にはわからない。
私はママに買ってもらったタブレットで、分離不安症のことを調べた。カウンセラーから聞いた以上に新しい話はなかったが、犬や猫にも分離不安症があるというのは驚きだった。私は犬猫並なのかとも思って悲しくなった。治療法も、これと言った情報はなく、薬物療法か行動療法かのいずれしかない。行動療法は執着の対象から徐々に引き離すというもので、その程度ならママが何度も試していた。
話すウサギは安心毛布のようなものだろう。多分、父親のいない私が、ママ一人に愛着を示しているのに対し、愛着の対象を増やすことによってママからの分離不安を和らげようとしたのだ。結果は失敗だったが、他人事だと思えば悪くないアプローチのような気もする。でも、私が好きなのはママだけだった。
きっかけはママの苛々の発作だった。会社が宇宙開発プログラムへの関与を縮小させることになり、ママのチームから優秀なスタッフが外されたのが原因だったと聞いたのは、随分後になってからだ。忙しそうなママに変わってお昼を準備しようとした私は、シリアルの入ったボールをキッチンの床に落としてしまった。
「なにやってるの!」
覚えているのは最初の一言だけだ。ママはわめき散らし、私は大きな声を上げて泣いた。近所の人に通報されなかったのは、それがいつものことだったから。
気が付くとママは背中から私を抱きしめていた。ママの腕と胸の感触。私の鼓動と重なり合うようなママの鼓動に気づいたとき、私は泣いてたけれど、同時にこれ以上ない安心感を覚えていた。
そのとき、私には何が必要かがわかった。ママの心臓の鼓動を拾う加速度センサーと、鼓動を再現するアクチュエイター、その二つを繋ぐための通信アプリ。システムとしてはシンプルで、難しいものはなにもない。最初にそのアイデアを話したときは怪訝そうにしていたママが、ネット経由で部品を注文し、アプリはママが自分で作った。
「うまく行くと良いわね」
スマートフォンとカップリングした大きめのコインのようなセンサーを、ママは心臓の位置に張り付けた。
「ちゃんと伝わるかしら」
そんな言葉とは裏腹に、心配してる様子はない。ママの手には、もう一つのものがあった。ママのコイン状のものより一回り大きい、白くてオパールのような光沢のある扁平な楕円体。そっちの方は私のスマートフォンとカップリングしてあった。
「早くちょうだい!」
私は両手を差し出し、カップの形にした手のひらで、ママからの贈り物を受け取る。私の手のひらの中で、オーバル型のそれは、穏やかに脈動していた。
「どうかしら?」
ママが私を背中から抱きしめる。背中から伝わるママの鼓動とオーバルの脈動、完全にシンクロしたリズムに、私自身の鼓動が重なる。
「ちょっとトイレに行くわね」
そう言ってママが部屋を出てから三十分、小さなそれを握りしめていた私は、不安に駆られることも、取り乱すこともなかった。ママは私の手のひらの中にいた。
ハイスクールの入試も上手く行った。成績は常に上位で、奨学金も手に入れた。それでもママから離れることに不安があった私は、家から車で二時間ほどの所にアパートを借り、大学へと進学した。
ママは在宅勤務を減らし、管理職に昇進した。学会に参加するために町を離れることもあったが、私は大丈夫だった。ママの鼓動は常に私を包み込み、私は普通の大学生らしい生活を送っていた。
「……お母さんが事故に遭いました。今、集中治療室に入っています」
電話越しの声に私は混乱する。ママの鼓動を伝えているオーバルを握りしめながら、私は慌てて車を捕まえ、病院に急いだ。
* * *
そこまで一気に話した母は天を仰いだ。祖母の事故の記憶は、辛い物だったのだろう。
「大丈夫?」
母にそう尋ねた僕は、ちょっとした疑問に気づいた。もし、母が話したオーバルが僕の手の中にある物なら、祖母が亡くなった今も、脈動を続けているはずがない。
「ええ、大丈夫よ。あの時は確かに辛かった。でも、今あなたの手の中にあるそれがあったから乗り越えられたの。それを握りしめれば、母は私の中で生きてるって思えたから」
僕は手の中の脈動を意識する。
「事故はどうだったの?」
「交通事故よ。大量出血による失血死だったと聞いたわ。でもね、それは動き続けていた」
母の言うとおりなら、祖母の心臓の鼓動を伝えるはずのものが、祖母の心臓が止まっても動き続けていたことになる。
「でも、どうして?」
僕の問いに、母が笑みを浮かべる。
「通信状態が悪いときがあるでしょ。通信が途絶しても私がパニックにならないよう、ちゃんと考えてあったみたい。鼓動のパターンが記録されていて、通信が途切れたときにはそのパターンがランダムに再生されるようになっていたのね」
それはまだ動き続けている。この鼓動は永遠に続くのだろうか。
「でも、何でこれを僕に?」
「単なるお守りよ。それで良いんじゃない?」
落ち着いたペースの鼓動を感じていると、確かに気持ちが安らぐような気がする。
「大事にするよ」
そう言ったときに、母がほっとした様子を見せたことを、僕は見逃さなかった。お守りの意味もあるが、それ以上に、これを火星に持って行って欲しいのだろう。
「良かった。母も喜ぶと思うわ」
僕には父親がいない。母が精子バンクを使って産んだ子供だった。その母にも父親がいない。もちろん祖母が精子バンクを使った可能性はある。でも、僕はもう一つの可能性を考えていた。それくらい、母は祖母に似ている。
「母さんは、火星に行きたかった?」
今まで聞けなかったことを聞いてみる。もし、僕の想像通りなら、母は祖母のクローンだ。母が生まれる少し前から、女性が自分のクローンを生むケースが報告されており、批判が多いにも関わらず、今でも実施されていると言われている。
「どうかしらね」
母を生む前、軍にいた頃の祖母は宇宙飛行士の候補として訓練課程に進んでいた。ただ、当時の宇宙飛行士は極端に狭き門で、優秀であることだけでは選ばれなかった。
「おばあさんの夢だったんだよね?」
祖母は自分の代わりに宇宙に行かせるため、自分と同じ遺伝情報を持った母を生んだのだろうか。
「そうね。私の母は宇宙に行って欲しかったようだけど、母から離れられない私には無理だった。母にもよくわかっていたと思うわ。それに、母が亡くなって、自分が何をしたいとか、そんなことがみんなわからなくなってしまったから」
そう言った母は、少し悲しげに見えた。
「それで僕を?」
祖母の希望を叶えるために、母は僕を生んだ。そんな可能性を、僕は意識していた。
「私は子供が欲しかっただけ。誰かと一緒に暮らすとしたら、自分の子供と暮らすことしか考えられなかったからよ。あなたが、私の母が遺したものに関心を持つなんて、考えてもいなかったわ」
きっぱりと断言した母の言葉に、僕は安心していた。僕は、祖母のために生まれてきたんじゃないし、祖母のために火星に行くわけでもない。
「そうだね。僕は自分の意志で火星に行く」
最初の百人に選ばれるための努力は、誰かのためにできるようなものではない。それは確かだ。
「そうね。その方が母も喜ぶと思うわ」
僕は手の中にある物を意識する。内蔵しているのがベータボルタ電池なら、火星に着いた僕の次の世代になっても動き続けているだろう。
「もちろん、これは持って行くよ」
多分、単なる偶然なんだろうと思う。僕がそう言ったとき、僕の手の中の鼓動が早くなった。
