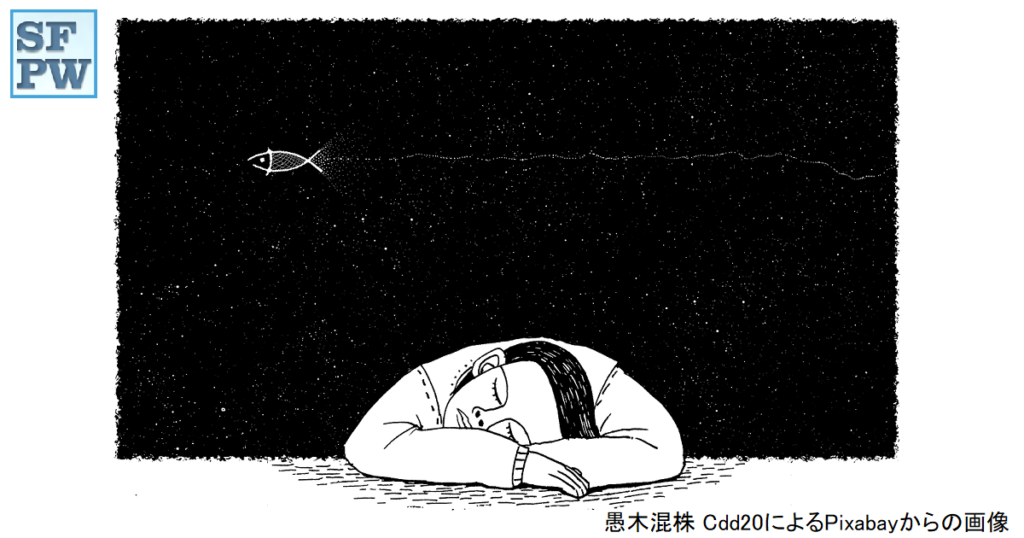
眠れない日々が続く。あまり眠っていないと意識が醒めたままで夢の中に入ってしまうことがある。寝ているわけでじゃない。ふと気づくとそこは夢なのだが、同時に現実も二重になって見えているのだ。夢は夢の中の過去を引き連れてやってくる。夢で見慣れた、というより懐かしい町並を歩いていて、ふと角を曲がると砂漠がある。虎が一匹横たわっており、私は虎を起こさないようにそっとその傍らを通り過ぎる。風が吹いて空が揺れる。虎など一度も見たことがないのにそれが虎だと知っているのは、むろん映像などで見たことがあるからなのだが、そのためなのかぺらぺらの虎はゆっくりと起き上がると思うや、あっという間に私を捕らえて大きな顎(ルビ・あぎと)で頭をくわえ、ひょいと持ち上げてぽーんと飛び上がって砂漠を抜け、森へ。暗く鬱蒼と茂る森を虎はまったくスピードを緩めず駆け続け、私は頭をがっちり顎で掴まれて布切れのように身体をひらひらさせながらついていく。いつのまにか森も消え、扇状になった山の、草木一本も生えぬ斜面を駆け下る。もちろんこれは夢で、私は寝台の中で何度も寝返りをうち、なま温かい寝具の中で目を瞑ったまま虎の口臭や胃の腑のにおいを嗅ぎ岩肌の埃っぽいにおいを嗅いでいるのだ。もう何時になるだろう。私は虎の口の中にも飽きて、強く瞑っていた瞼を開ける。寝台で半身をあげて周囲を見回すが、視界がぐらぐらし、まだぜんぜん夜で、物音一つしないので時間が過ぎていく実感がない。薄く引き延ばした月明かりが部屋を浸しているのがだんだんくっきり見えてきて、ひっそり佇む家具の姿がその中にぼんやり浮かび上がってくる。空気が淀んでいる。歪んだシーツを汗ばんだ皮膚に感じる。纏いつく。寝台から降りて浴室に入りシャワーを浴びるが、まったく目が覚めた気がしない。
暑さのために一睡もできなかった。ここいらは熱帯のはずだったが、もう何日も雨が降っていない。海を見渡せる小高い丘に立つマンションを借りたのは、当分のあいだ落ち着いて原稿を書き溜めようと思っていたからだった。最初の一週間は目論見どおりだった。というよりも予定以上だった。書き下ろしで出そうと思っている本の三分の一をあっさり書いてしまい、内容も申し分なしのクオリティーで、そこでちょっと気分を変えて町を散策してみようかと思ったのが間違いだったのだ。
火山を中心にした島の、扇状にひろがった傾斜に刻み込まれるように路地が縦横に走り、白い壁と赤や青や黄色、緑……と色とりどりの屋根が並ぶ美しい町で、私はその迷路のような坂と裏路地の連なりにすっかり魅せられてしまった。毎日毎日飽きもせず歩き回っては、海の見える自分の部屋があるマンションを海側から仰ぎ見ることができるカフェのテラスで渇きを癒す酒を飲む、ほっつき歩き、酒を飲む繰り返しに嵌り込んでいった。あたかも辞書を最初の一ページの一行目から読んでいくように、私は複雑に入り組んだ路地をいっぽんいっぽん順番に数えながら歩いていった。観光客もほとんど来ない忘れられた僻地で、とうぜんカフェに集まる面子はいつも同じだった。それもまるで判を押したように店を訪れる時間、飲んでいる時間、退出する時間までいつも同じなんだとカフェで唯一英語が話せるウェイターは言う。確かめてみたことはないが、たしかに私もいつも町中を歩き回って疲れきった夕暮れにこの店に入り、どっぷり日も暮れて月が炯々と光り出す閉店まで飲んだくれているので、そのあいだいつも同じ客の同じタイミングの出入りを見ていた。どうかすると会話の雰囲気や、酒や魚を注文するタイミングまで同じであるようにさえ思えた。永遠に続くかと思えるかんかん照りの青空がその変化のなさに拍車をかけていた。そして暑さ、とにかく暑かった。暑かったから、毎日浴びるように酒を飲まずにはいられないのだった。
浴びるように酒を飲めば今夜こそは眠れるに違いない。そして一度ぐっすり、思う存分眠りさえすれば、またふたたび机に向かい、今度こそ一心不乱に最後まで原稿を書き上げられるに違いないのだ。しかしタイプライターはすっかり埃を被ってしまった。昨日もまったくそれに触れることはなく、昼間眠れずに悶々と部屋の中で過ごし、太陽が燦々と照りつける中をどこに行くあてもなくただ幾何学的な自分自身の中にある道順に沿って彷徨うように歩いて歩いて歩いて疲れきってカフェに辿り着き、モヒートを頼み、その後はもう何が何だかわからず、いつも同じような話をウェイターにしていたのかどうかもわからないが(何せカフェにいる他の人間にはマスターでさえも英語が通じないのだから)、べろんべろんに酔っぱらってふらつきながらしかしまっすぐ部屋に戻り、シャワーも浴びずに寝台に倒れ込む。しかし、やはり今夜も一睡もできなかった。呻き声が聴こえ、それが自分の声だと気づくまで少し時間がかかる。私は寝台から出て、開け放っている窓外に向かって立つ。水平線の向こうが少しづつ色づきはじめていて、思ったよりも朝に近い時間だと気づく。もしかすると少し眠れたのだろうか。そういえば目を閉じてじっとしていれば、本人はまったく眠った意識がなくても少しは眠れているものだ、という言説をどこかで見たことがある。あるいは意識は置きていても身体だけでも休ませていれば睡眠と変わらないくらいの効果があるというのだったろうか。しかしこの混乱ぶりこそは不眠の為せる技ではないだろうか。考えていてもどうしようもない、私は汗だくになっていて、ともかくシャワーを浴びる。
冷蔵庫からペットボトルの水を出して、コップに注ぎごくごく飲んだ。キッチンを探ってクラッカーが出てきたので、やはり冷蔵庫からチーズとアンチョビの残りを出し、テーブルに雑に並べて朝食にした。酒は飲まなかった。着替えて部屋から出る。エレベーターの鏡で身なりをチェックしながら、今日はちょっといつもと違った行動をとってやろうと思いつく。にやついた自分の顔を見ると少し安心する。エントランスを抜け、白々と明けた空を眺めながら坂道を降りる。そして「彼」に会うことを考える。ウェイターによると、「彼」は私に瓜二つの男で、いつも朝一番にカフェに現れるらしい。どうやら夜通し起きているらしく、開店と同時に入ってきて、コーヒーとウイスキーを注文し、ウイスキーはものすごく早いペースでおかわりしてへべれけになるまで酔っぱらい、しかし長っ尻はせず昼前には店を出るのだそうだ。
トンネルのような、石造りの路面と同じ色をした白壁に包まれて坂を降りていく。いつもだったらそのまま左に折れるところをそのまままっすぐ歩く。小一時間も歩けば例のカフェだ。開店したばかりで閑散としているカフェのガラス戸を開けると、からんとした店内の、海側の大きな窓にほど近い四人がけの席に一人で彼が座っていた。他には客は誰もいない。彼のことは見てすぐにわかった。私と似たり寄ったりの薄汚れたジャケットに、薄い色のカーゴパンツと足下はジャングルブーツ。ちょっとした探検家のノリである。私と違うのは彼は帽子を被っていないことくらいだろうか。私は店の中をゆっくり歩いて、カウンターのマスターにいつものやつとジェスチャーで告げ、そして彼の席に近づいていった。私の気配にも、椅子を引く音にも、彼はまったく反応しなかった。テーブルの上には、ほとんど残っていないコーヒーと、ウイスキーのボトル、そしてなみなみ注がれたグラスがあった。不意に彼はシングルもダブルもない量の琥珀色の液体をとって一気に飲み干した。そしてまたウイスキーを同じくらいなみなみと注ぐ。私のことは一切顧慮していないなめらかな動きで、視線は海に向けられていた。向かい合わせの席に着き、いつもの英語を話すウェイターではなくマスターみずからモヒートをテーブルの上に置いたとき、ついに彼は私が目の前に座っているのを発見した。
「ああ、お前か」つまらなそうに言った。
どこかで会ったことが、と思いかけて、おそらく例のウェイターが私に彼のことを語ったように彼にも私のことを語ったに違いないと気づく。
「一度お目にかかってみたくてね」
「お前、作家だろ?」
私は誰もが知っているような有名な作家ではない。思わず声をなくして見つめていると、彼は一度目を伏せ、何かに思いをめぐらせるように視線をさまよわせる。
「もうそういう頃合いか」
そして、ふたたび深いため息をつき、私をじっと見つめて一方的に話しはじめた。それによると、彼はもともと某国の軍人で、この町には特命を受けて訪れたとのことだった。任務はつまらないことで、ある重要人物の監視だった。何か画期的な薬剤を発明した科学者だったという。彼はとつぜん勤め先に辞表を出し、研究のすべてを放棄して出奔し、仕事だけでなく、妻とまだ幼い二人の子も捨ててこの町に転居し、海の見える丘の上に新築されたマンションに一人で暮らしていた。彼はそのマンションの一階下の同じ位置にある部屋に自分の拠点を作った。そして科学者が人目を避けて極秘のラボでも作っているのかと潜入して調べてみたが、部屋にはとくに変わったところはなく、一台のタイプライターと、それで打ち出した原稿の束があるだけ。その原稿も特に科学者の研究と関係するものではなく、どちらかといえば文芸的なものであるらしかった。また、科学者はよく外出した。ほぼ毎日、町をうろうろ歩き回っていた。彼は何度か科学者を尾行し、その行為の意味合いを探ってみたが、単に科学者は意味も目的もなく、ただちょっとした幾何学的な順列組み合わせの順番に沿って、縦横に刻まれた路地を一本づつ開拓しているらしいと知れた。毎日夕暮れまで歩き回っては、いま彼と私がいるこのカフェに入って、テーブルでウイスキーを飲みながら鉛筆で手帖に何やら書き込むと、あとはゆっくりこの店でただ一人英語が話せるあのウェイターにたまに声を駆けたり、流しの音楽に耳を傾けたりし、そのうちすっかりきこしめして帰っていく。判で押したような毎日だった。彼もはじめのうちは淡々と仕事をこなすつもりで科学者の後を追っていたのだが、迷路のような町の白い路地を歩いているうちに、自分が何のためにこうしているのかわからなくなってくるのだった。本部からの連絡は指示待ちのまま途絶えていた。彼はもうひそかに行動するのもやめてしまった。科学者にはまったく何か隠していることも、これから何かすべき意志も感じられなかったし、それは実はいまやこちらもそうなのだ。追われる者と追う者が反転してしまうことならばこれまでも何度かあったが、いまや彼と科学者は伴歩者とでもいうべき奇妙な関係に陥ってしまっていた。もちろん彼が一方的に科学者を見つめているだけなのだが、科学者は、すがたを隠さなくなった彼にウェイターや一緒にカフェで酒を飲んでいる地元の人間とまったく同じような穏やかな寡黙さで接した。それはずっと以前から彼のことをよく知っていて、親しみという以上の感情を抱いているようですらあった。その態度に驚きと戸惑いを覚えながらも、彼の方もとくに話しかけるでもなく少し離れた席に陣取って酒を飲むようになった。そのうちに科学者の存在を忘れ、海の見える窓辺のテーブルで、黙々と酒を飲んだ。あいかわらず本部から連絡は来なかったが、行動資金は十分もらっていたので不自由はなかったし、そもそももうそんなことはどうでもよくなっていた。気がついてみると、いつのまにか科学者は部屋を引き払って町を後にしていた。科学者がそれからどこへ行ったのか、または現場に復帰したのか、家族と再会したのか、それとも違う土地へと流れていったのか、彼は知らなかったし、知ろうともしなかった。そしてやはり本部から連絡はなかった。
「俺も自分から連絡はしなかったよ。もうどうでもよかったからな。でもまあ俺も軍人だから、いつまでも放っておいてくれるとは思っていなかったよ。ところがだ」
ここまでまったく抑揚のない語り口だった彼が、不意に笑った。クロコダイルが笑ったとしたらこんなふうだろうと思えるような顔だった。クロコダイルを直接見たことはなかったけれど。
引退通知が届いたのだという。退職金はかなりな額だった。何が起こったのかさっぱりわけがわからなかったが、問い合わせる気もなかったし、国に帰る気もなかった。なぜだか科学者が滞在していた部屋の鍵が彼の手に残されていた。奴の生活をなぞって遊ぶのもいいだろうと思った。しばらくは酒を飲んで、後はゆっくり眠りたいと思っていた。仕事柄つねに時間が不規則で、不眠は長い連れ合いになっていたからだ。部屋を変えればぐっすり眠れるかもしれないじゃないか。そして実際思惑通り、新しい部屋に移り住んでからは自分でも驚くほどによく寝られた。夜はもちろん、昼でも部屋の中で少しじっとしていればたちまち眠りに落ち、気がつくと丸一日寝たままでいることなども珍しくなかった。起きている間は酒を飲む。ぐでんぐでんになるまで飲んで、それでも毎日部屋には戻ってきて、そして何時間もこんこんと眠る。眠っていると夢を見る。自分が何か文章を書いている夢だった。それはあの科学者が書いていた原稿の続きで、覗き見たときと違ってその内容がまるで水のように自分の中に入ってきて、気がつくと自分が机に座りタイプライターを叩いているのだったが、それは本当に自分なのか、それとも自分とそっくりの誰かなのかわからなかった。その誰かはきっと作家だ。作家をすぐ後ろから眺めているような構図の夢で、だからそれは自分ではなかったかもしれないし、しかし自分自身を背後から眺めるというのは実は彼にとって現実でもよくある感覚だったので、それが夢の中であったとしても、というかそれならばむしろまったく不思議はないと言ってよいのではないかという気もした。何度も同じ夢を見て、そうやって見るうちに、作家には自分自身と同じような親しみを感じはじめていた。もっとも、自分自身についてそれほどの親しみを覚えているのかとあらためて考えてみれば、そもそも自分は自分にどれほど慣れ親しんでいるだろうか。自分が自分にとって理解の外にあるというか、いっそよそよそしい存在であることさえあったかもしれないし、いまも現にそうかもしれない。そうやって自分の境界があやふやになってくるうちに、不思議に夢に馴致されて生活が規則的になっていった。昼から夜までずっと眠り、眠り、眠り、真夜中に起きると、夢のなかで見ていた原稿の内容を思い出し、というよりもむしろ思い出そうとしているうちに朝になる。それでシャワーを浴びてカフェまできてコーヒーとウイスキーを頼む、飲んだくれて疲れきって家に帰って眠る。毎日がその繰り返しだった。原稿はいっこうに書き出せそうになかった。タイプライターさえ用意しなかったのだから当たり前だが、そのうちに、自分は何かを待っているのだと気づく。何かではない、誰か。いや、誰でもない。
「お前だよ」
そう言って彼は私の顔を撫ぜた。
顔が白くなった。
何かが爆発するような音がして、いっせいに激烈な雨が降り出した。子供の指くらいの太い雨が完全に視界を遮断して、窓はアクリルの板のように見えた。
マスターが何やら叫びながら店の外に飛び出していった。どうも幌をかけていないジープを外に停めてあるらしい。水浸しだ水浸しだというような意味の言葉を繰り返し、そのうちその声も雨音にまぎれた。カフェには私と彼の二人だけで、雨よりほかに物音はない。おもむろに彼は私の帽子を取って自分で被り、席を立った。ゆったりした動きなのにまるで捉え難い速さで、気がつくと彼は店を出て行ってしまっていた。
テーブルの上に鍵が置いてあった。彼が置いていったものだとすぐにわかった。
私はウイスキーを呷り、戻ってきたマスターにおかわりを要求する。マスターは、勝手にやっててくれよ、とでもいうように、カウンターから壜をつかみ出してテーブルに置き、びしょぬれのまま店の奥に入っていった。床に水たまりができている。この雨で少し暑さが緩まってくれればいいが。私は鍵をとってポケットに入れた。そこにあるはずの今朝出てきた部屋の鍵はなかった。窓の外で、雨水が濁流のようになっていた。この店はほんの少しだけ周囲から高台にできていて雨が入ってくる気遣いはなかった。あるいはいつもこういうふうに雨が降るのでこういった造りになっているのかもしれない。暗い店の中で私はウイスキーをグラスになみなみと注ぎ、口に運びながら雨がやんだら部屋に戻ろうと思った。部屋に戻ってぐっすり眠ろう。今夜からはきっと死んだように眠れるに違いない。まずは夢も見ずに眠る、眠る、眠る。そしてそのうち見るだろう夢の中で、今度は誰を待つことになるのだろうか。
【初出:電子フリーペーパー『北極大陸』第28号(2017.3.)】
https://www.1001sec.com/murbo/hokkyoku028/
(あとがき)
この小説はwebで無料配布されている雑誌『北極大陸』に書いたものです。ずいぶん前に「小説を書かないか」と誘ってくれて二年ほどいろいろ載せてもらっていたのですが、忙しくなってきて最近はずっとお休み中です。電子書籍として所有できるのも魅力的なのですが、もっと気楽にアクセスできるようにと、オンラインで読めるかたちにしたいと最近思い立って、縁あって「SF Prologue Wave」に掲載していただけることになりました。初出を加筆修正し少しだけ内容が変わっています。どうぞよろしくお願いいたします。
