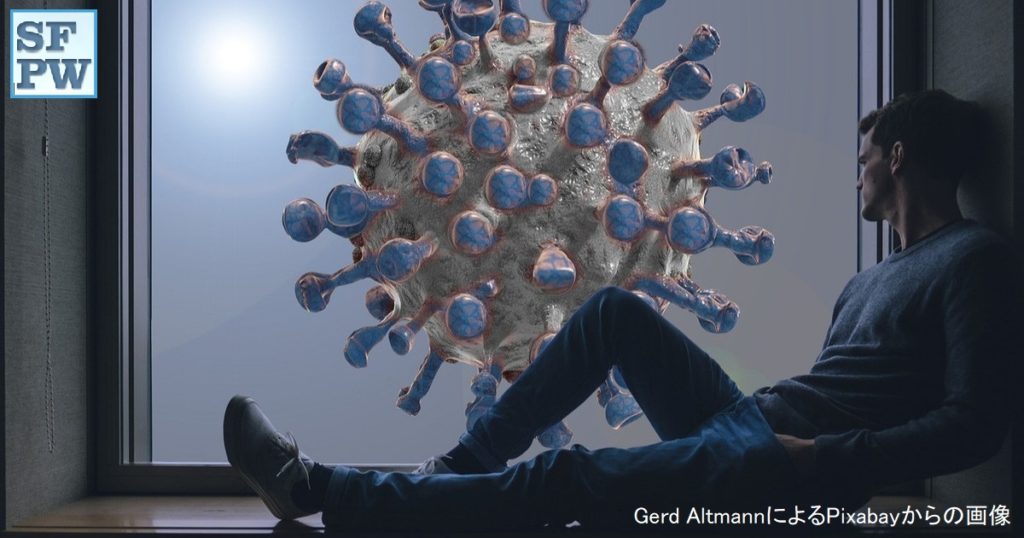
インプラントを埋め込んだ手術跡が消える間もなく、僕は同じように外に出ることを選んだ七人の仲間と一緒にサンクチュアリを出た。もちろん、その中にタンはいない。
僕たちが向かったサンクチュアリ出身者のための寮で、そこで外での生活が始まった。
大学では外の学生たちと一緒の授業を受けたが、なかなか馴染めなかった。多分、刷り込まれた感染への恐怖が邪魔をしているのだろう。
キクニに呼び出されたのは、外での生活が始まってから半年が経過した頃だった。
そこは単に「島」と呼ばれていた。東京湾海上新都心は、机上の計画だけで止まっている。埋め立てが終わったところで計画はストップし、それ以上、先に進むことはなかった。
僕の目の前で、キクニがたき火に乾いた小枝をくべていた。ナイジェリア人との混血だというキクニは、オレンジの派手なダウンに身を包んでいる。まだ九月だというのに、風が妙に冷たかった。
「本当に来たんだな」
僕たちの周囲はどこまでも広がる埋め立て地で、雑草が一面を覆っていた。地面の下はほとんどが瓦礫と焼却灰だから、木は生えても大きく育つことはない。
「大学の方が落ち着いたら、連絡しようと思ってたんです。寮で会えると思ってたんですが」
僕より一つ年上のキクニは、僕と同じサンクチュアリ育ちだった。いつもサンクチュアリから出ることを話していて、最初の機会に飛びついた。
「半年は経ってるだろ」
サンクチュアリを出て半年、寮での生活にも慣れ、大学でも新しい友人ができた。
「何で寮を出たんですか?」
キクニとは寮で会えると思っていた。けれど、キクニが寮にいたのは最初の三ヶ月足らずで、僕が聞いた範囲では、誰も行き先を知らなかったのだ。
「あそこはサンクチュアリと同じようなものだ」
都内にある寮は、サンクチュアリから来た学生のためのものだった。僕は全員の顔を見たことがあるし、全員に知られているだろう。確かに、サンクチュアリの中の学校を、そのまま延長したような気分がしたものだ。
「そうですね。出て行ったと聞いて、てっきりナイジェリアにでも行ったかと思いました」
キクニは、サンクチュアリにいた当時から、いつかはナイジェリアに行きたいと言っており、そのために英語の勉強にも熱心だった。キクニが誰に聞いたのかは知らないが、父親がナイジェリア人なのだという。
「俺たちにはパスポートは出ない。帰国できなかった時の安全が保証できないってさ」
僕たちのインプラントだ。免疫機能をブーストしていないと、僕たちは感染症にやられてしまう。
「そうなんですか。残念ですね」
僕にはさほど強い思いはない。それでも、日本の外を見てみたい気持ちは分かるし、それが叶わないとなれば悔しい想いになるだろう。
「諦めちゃいないよ。さすがに空路は無理だが、船なら日本を出られそうだ。待遇さえ気にしなければな」
簡単に諦めるのはキクニらしくない。パスポートが無くとも、きっと何とかするだろう。
「うまく行くと良いですね。ところで、今日は何をするんですか?」
キクニから人を介して島のこの場所に来るようにとの連絡があったのだ。僕がサンクチュアリを出た事も伝わっていたらしい。
「本当に来るとは思わなかった」
たき火の炎だけでは、キクニの表情は判らない。サンクチュアリにいたときの印象とは違い、妙に落ち着いている。どちらかと言えば、ゾンビプラネットでバディを組んでいたときのキャラクターに近い。
「何でですか?」
不愉快そうに答えた僕も、実際のところ、自分がこの島に来ようと思った理由を判っていなかった。ただ、毎日に変化のないサンクチュアリが退屈だったように、大学もまた日々のルーティンになりつつあった。
「忘れられた場所だからだよ、ここは」
立ち入りが制限されているといっても、東京湾に浮かぶ巨大な島は、周囲と何本もの橋で結ばれ、地下トンネルも通じている。桟橋もあり、ちょっとしたボートがあれば海を渡ってくるのもたやすい。島の管理にあたっている周辺自治体の協議体は、島の管理に予算を掛けていないようだった。
「追悼モニュメントがあるのに?」
三十年以上前に大流行した感染症の死者を悼むための施設だった。その年の国内の死者は百万人に迫り、そのうちの二十万人の遺骨が納められている慰霊塔は、島にある唯一の恒久的施設だった。
「忘れたいんだよ。大震災もそうだし、その前の感染症の大流行だって同じだ。語り継ぐなんて言いながら、結局忘れる。災害慣れした国だからな」
キクニが乾いた枝を折り、また火にくべる。周囲に明かりはなく、たき火は目立つ。
「そんなものなのかな」
すぐには納得できないけれど、僕には反論するだけの根拠がなかった。
「随分前の大流行の時だ。ロックダウンのせいで世界中が不景気になって、その対策で、この島を作ったんだそうだ。医療体制の強化をうやむやにして土木工事に予算をつぎ込み、それで次の感染症の流行で、また甚大な被害だ。あきれるよりないだろ?」
僕たちが生まれる前のことだ。再度の大流行があり、多数の感染者を治療するための仮設病院を、当時埋め立てが終わったばかりのこの島に作ったという。脆弱な医療体制が原因で死者が急増し、火葬場の能力が追いつかなくなった。
「今から思えばね」
そう言った僕を、キクニは鼻で笑った。
国は、この島に仮設の火葬場を作った。家族全員が感染症で死んだりして、引き取り手のない遺骨が積み上がると、さらに仮設の納骨堂が建設された。そんな場当たり的な対応に使われた島のイメージが良い理由がない。長引く経済の停滞もあって、進出を予定していた事業者が次々に撤退を決め、東京湾海上新都心の建設計画は無期限に凍結された。キクニは、そんなことを説明してくれた。
「でも、なぜこの島に僕を?」
改めてキクニに尋ねた。
「何なんだろうな、サンクチュアリって?」
僕の質問に、キクニは逆に質問で返してきた。
「えっ?」
「だから、何なんだろうって思うんだ」
僕は、自分が聞かされてきたことを話す。免疫系に問題があり、感染症からの厳格な隔離が必要とされる子供たち。サンクチュアリはそんな子供たちのための施設だ。
「どうして、そんなに手間をかけるんだ?」
「手間をかけるって?」
「結局、国に育てて貰ってるってことだろ?」
確かにそうかも知れない。ただそれは、僕が希望したことでも何でもなく、単にそう決められていたからに過ぎない。
「何が言いたいの? 死ねば良かったってこと?」
「そんなことはないさ。誰にだって生きる権利はある。誰にだってな」
そう言って立ち上がったキクニは、たき火に土をかけ、火を消した。
「おまえに見せたいものがある」
キクニが向かったのは感染症の犠牲者を悼むモニュメントだった。巨大な白いモノリスを思わせるモニュメントの後ろに回り込むと、鉄の扉があり、中に入れるようになっている。
「以前は警報装置や、監視カメラもあったようだけど、今は鍵が壊れてもそのままだ」
つまり、修理の手が回っていない。誰も好き好んでモニュメントの中にまで入ろうとしないだろうから、わざわざ修理する必要がないのかもしれない。
「不用心なんだね」
そんな僕の軽口を聞き流し、キクニは、懐中電灯を点け、モニュメントの内部へと入って行く。キクニが向かったのは、いくつもある納骨室の一つ。
「こっちは普通の納骨室だ」
扉を開くと、壁一面が棚になっていて、無数の白い骨壺が並んでいた。僕は自分の懐中電灯を点け、棚の骨壺をみる。名前は書いてあったり無かったりだったが、死んだ日なのか、全てに日付が書いてあった。
「同じ日付ばかり集まってる」
「当たり前だろ。この期間は、大流行の途中だからだな。ほかの部屋も大体同じなんだがな。ほら、そこにも日付があるだろ」
キクニの懐中電灯が、ドアの横にあるプレートを照らした。プレートに書いてある期間は、僅か一週間。一方で、その部屋にある骨壺は、ざっと計算して五千は下らないだろう。
「こんな部屋がいくつあるんだ?」
「このフロアだけで二十ある。でも、問題はそこじゃない」
部屋を出たキクニの後を追って、僕は薄暗いモニュメントの中を進む。
「ここだ」
今までと同じような部屋だったが、開いたドアの先の棚には空きが目立つ。
「どう思う?」
懐中電灯が壁面を照らす。
「どう思う、って?」
「ちゃんと見ろよな。まず、骨壺じゃなくて、小さな箱だ。開けてみろとは言わないが、全部が赤ん坊の骨だ。それに日付を見て見ろ」
確かに、それぞれの箱の大きさは、骨壺の五分の一くらいしかない。それに、日付はバラバラだ。
「最後の最後が二十年前だね」
つまり、サンクチュアリができる直前だった。しかも、その年に大流行は起きていない。
「なぜだと思う?」
「僕たちのような子供が、生まれてすぐに死んで、ここに納骨されてるとか?」
そう言いながら、自分でもおかしいと気づいていた。感染症で死んだなら、わざわざここに集める必要がないだろうし、それに、生まれた赤ん坊には名前も付いていたはずだ。
「それは多分違うな。おまえなら説明できるはずだ。サンクチュアリで一番の秀才で、しかも所長のお気に入りだからな」
結局、僕は謎の答えを見つけられなかった。
それから半年後、久しぶりのキクニからのメッセージは、ナイジェリアからだった。どうやって出国したのか判らないが、医療ボランティアとして働いているという。
さらにその半年後、ナイジェリアで新しい変異株の流行が始まり、しばらくして政府が崩壊したというニュースが伝わってきた。
その頃、政府が僕たちに関する政策を変更した。外にいたサンクチュアリ出身者は、半ば強制的に、サンクチュアリに戻されることになった。
僕はサンクチュアリに戻ったが、キクニは戻らなかった。
* * *
かろうじて放送を続けていたラジオは、同じ曲の繰り返しで、やがて電力が尽きたのか、ひっそりと放送を終えた。無線機の方は、いろいろな通信を拾ってはいたが、こちらから話しかける気になれないような陰鬱なものばかりだ。どれもが、感染症の拡大に伴う窮状を訴えるものばかりで、それも、日を追うごとに沈黙していく。結局、こちらから呼び掛けなかったのは、僕たちの間に外への恐怖が刷り込まれていたからかも知れない。
「これからどうするんだ?」
タンが言った。週に一度の自治連絡会は、今回も具体的な結論を得ずに終わった。外部との連絡が取れないとは言え、水と食糧に不足はなく、電力にも余裕がある。感染症に汚染された外部に対する恐怖はサンクチュアリに根付いており、インプラントを持っているメンバーで構成された調査隊を出す案は、僕が反対するまでもなく、様子見を主張する声にかき消され、具体化することはなかった。
外部との連絡が途絶えて、半年が過ぎていた。
「どうって?」
「いつまでも、ここに籠もっていていいのか、って……」
サンクチュアリを一歩も出たことのないタンですらそんなことを考えるんだから、外の様子を調べようと言う声は、次第に大きくなっていくだろう。外の世界の沈黙が続くなら、いつかは踏み出さなければいけない時がくる。それは、多分、必然なんだろうと思う。
「そのうち、手狭になってくるだろうしな」
赤ん坊が連れて来られることはなくなっていた。でも、そのかわり、サンクチュアリで生まれた赤ん坊がいる。
「それにはまだ時間があるよ」
タンの表情が、急ににこやかになったのは、タンのところにも赤ん坊がいるからだ。タンは、生まれてきた息子にヤスキと名前を付けていた。
「そうだと良いがな」
僕たちがサンクチュアリを出るとき、世界は取り返しが付かない形で変化する。今は、僕だけがそのことを知っている。
「おまえも、誰かいないのか?」
タンの言葉に、僕は曖昧な笑みを返した。
五年前、僕がサンクチュアリに帰ってきた時のことだ。吉永所長は、僕にキクニのことをしつこく尋ねた。インプラントにはGPS機能があり、僕たちが島で会ったことを知っていたのだ。ただ、その機能も万全ではなく、キクニの足取りは横浜港で途絶えているという。
キクニが父親の出身地であるナイジェリアに関心を持っていたことは、秘密でも何でもない。僕はキクニが何とかしてナイジェリアに行ったらしいことを、吉永所長に告げた。
サンクチュアリの内と外を隔てるガラス越しにも吉永所長の顔から血の気が引いたのが判った。
「やっぱり、そうだったのか……」
吉永所長の表情に現れたのは、落胆か、あるいは罪の意識だったのかもしれない。
「……やはり、ここから出したのが間違いだったようだな」
「どう言うことなんですか?」
そう尋ねずにいることは出来なかった。
「おまえたちのゲノムには内在化したウイルスが書き込まれている。インプラントは、免疫系を強化するものじゃなくて、内在化ウイルスの発現を防ぐものなんだ」
「それは、どういう意味なんですか?」
僕には吉永所長の言葉の意味が判らなかった。
「判らないのか? インプラントが機能を止めたら、おまえたちのゲノムに組み込まれている内在化ウイルスが発現し、増殖を始める。ウイルスが、感染力を持つようになるんだ。インプラントは、おまえたちを守るためではなく、私たちを守るためなんだよ。内在化ウイルスを持つということは、アーチンウイルスの自然宿主になるということだ。自然宿主であるおまえたちは、ウイルスに対して先天的な免疫があり、万一発症しても、ウイルスをばらまくだけで、重篤化しない。逆に、内在化ウイルスを持たない私たちは、ウイルスに対して無防備だ……」
渡航から時間が経過し、インプラントが効かなくなったキクニが、ナイジェリアで発生した変異株による感染爆発の原因だったのだろうか。
吉永所長が言葉を続ける。
「……つまり、サンクチュアリは、私たちの安全を守るために、おまえたちのような子供を隔離するための施設なんだよ」
僕は、キクニと見た島のモニュメントのことを思い出した。赤ん坊の骨を納めた無数の小さな箱。ゲノムの中に内在化ウイルスを持たないものを守るため、処分された内在化ウイルスを持つ無数の赤ん坊たち。僕の中で、突然、凶暴な怒りのようなものが頭をもたげる。
「だから赤ん坊を殺したんですか。実験動物みたいに!」
思わず口を継いで出た強い言葉に、吉永所長は、一瞬だけ驚いたような表情を見せた。
「やはり島で見たんだな。だがな、おまえたちのような赤ん坊が原因だと判る前に、あの数の何倍もの大人たちが死んでる。一方的に非難するのは、それも考えた後にしてくれ。私たちだって、あんな事はしたくなかった。だからサンクチュアリを作ったし、インプラントの開発も、将来的な共存関係を目指したものだ。おまえなら、それくらいは理解できるはずだ」
アーチンウイルス感染症の確実な予防法や、治療法が確立さえできれば、共存できる。だがそれまでは、厳格な管理が必要だった。所長が言ったのは、そういうことだろう。僕たちは普通の親から生まれるし、その数は、ゆっくりと、でも確実に増えていく。
吉永所長は、あの時の話を口外するなとは言わなかったけれど、僕は一切、口外していなかった。今思えば、僕と吉永所長の間には、暗黙の了解があったのだと思う。
それに、ナイジェリアの感染爆発の原因が、本当にキクニだったかどうかも判らない。世界中で、僕たちのような内在性ウイルスを持つ子供が産まれているはずだし、国が国として機能していないようなところで、ちゃんと管理しきれるとは思わない。
でも、育ててくれる親が死んでしまえば、赤ん坊も生きていられないし、生きていなければウイルスをばらまくこともない。
あれから五年、吉永所長は、サンクチュアリが外部に依存せずに存続できるように、いろいろなことをしてくれた。僕はそのことを思い起こす。財政難で予算が削減される中、貯水池や井戸を整備し、風力発電も増強した。それに大量の書籍を電子化して保管してある図書館もある。
所長は、こうなる可能性を考え、準備していたのだと思う。
僕たちは準備ができているか。僕は自分に問いかける。サンクチュアリを出れば、外の世界は変わり果てているだろう。ゾンビはいなくても、無数の死体を見ることになるし、生きている人がいたとしても、僕たちとは共存できない。サンクチュアリの外に出た僕たちは、確実に外の世界を終わらせることになるのだ。
僕たちは、重荷を背負えるか。
内在化ウイルスを持たない人類が築いた文明を、僕たちは受け継いでいけるのか。
いつかは前に踏み出し、サンクチュアリを出なければいけないし、いつまでも先送り出来ない。それだけは確かだった。
完
