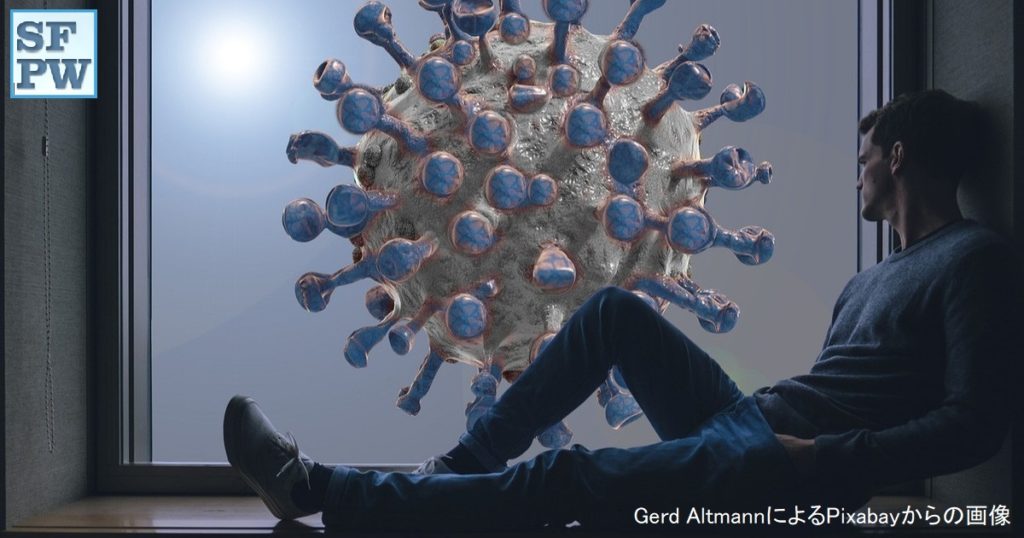
秋が深まるにつれて、外での感染者数の報告が増えていった。状況は、五年前の大流行並みか、それ以上に悪いようだった。
電子顕微鏡で捉えられた無数の棘を持つウニのようなウイルス、アーチンウイルスは、国境を越えたパンデミックを引き起こし、世界中で多くの人命を奪っていた。
「……医者の手が足りていないそうだ。まあ、毎年のことだから、仕方がないが、私たちはしばらく留守にする。食料や、医薬品の備蓄は十分だし、水と電力も心配ないから、孤立状態が長引いたところでここの運営には問題ないが、用心に越したことはない。しばらくして外の状況が落ち着いたら、すぐにこっちに戻る」
内と外を隔てるガラス越しにそんな言葉を残して、吉永所長がサンクチュアリを離れたのが三ヶ月前の十月だった。今年のクリスマスとお正月は完全なロックダウンで、ニュースは感染爆発一色だったが、サンクチュアリの中は平穏で、毎年と変わらない時間が過ぎていく。クリスマスには中央広場の大きなモミの木に飾り付けをしたし、お正月には恒例の餅つきイベントをやった。足りないのは、外から持ち込まれるクリスマスプレゼントだったけれど、プレゼントを運んでくる外の職員がいないのはみんな知っていたし、子供たちも、これといって欲しいものもないのか、僕たちが用意した手作りのおもちゃで満足しており、誰も落胆した様子を見せなかった。
「今年は特に酷いようだね」
天候のことを話すようにタンが言う。サンクチュアリの運営は、ほぼ僕たちに任されており、タンは自治連絡会の副会長だ。僕と同じく、ほぼ最年長だが、サンクチュアリを出たことはない。その分、世間知らずだ。
「五年前も大丈夫だったじゃないか。今回だって乗り切れるさ」
僕がサンクチュアリに戻るきっかけになった五年前の変異株の大流行は、ナイジェリアで始まったとされている。ナイジェリアでは、大量の感染者の発生と経済的混乱による国民の不満が爆発し、政権が崩壊。その後は内戦に突き進むというおきまりのパターンをなぞったらしい。
もちろん、被害は世界中に広がり、回復は進んでいない。今では世界中の国家のうち、半数近くがまともに機能していないと言われていた。世界の至る所で医療体制が崩壊し、そんな地域が新たな変異株の培養器になっていた。感染爆発が起きた地域から難民が流出し、新たな流行を世界中に広げる。それが、毎年のように繰り返している。
アーチンウイルス感染症の蔓延と強制隔離、市民の暴徒化と武力鎮圧、難民の流出と新たな感染爆発、世界中のいろんなところで負の連鎖が続いており、島国の日本も無縁ではなかった。
「随分、楽観的なんだね」
呆れたように、タンが言った。
「いちいち心配しても仕方がない」
今年の変異株も、二週間近い無症状期間と急激な重篤化というやっかいな性質があり、封じ込めは上手くいっていない。元々弱っていた経済はガタガタで、いつ何が起きても不思議のない状況だった。
「それはそうだけど……」
サンクチュアリではSNSは使えない。外についての情報源である地上波は続いていたものの、チャンネル数は減っていたし、閲覧が許されているネットニュースの配信も減り、アクセスできなくなったウエブサイトも増えていた。
「そんなに悲観的になる必要はないさ」
自分でも気休めに過ぎないと判っている。サンクチュアリの責任者であるはずの吉永所長の不在が続いていること自体、相当に状況が厳しいことを示している。蔓延する変幻自在のウイルスを前に、ワクチン開発は後手に回り、有効な抗ウイルス薬も見つかっていない。繰り返す感染爆発に、人間社会そのものの抵抗力が弱まっている。サンクチュアリの中にいては実感できないけれど、それが現実なのだ。
管理棟の僕たちの側、つまり、サンクチュアリの内側に区分されている会議室で、僕たちは、唯一の外部との接触となっている毎週のビデオ会議の開始を待っていた。大した話をする場ではなく、言ってみれば、僕たちが忘れられていないという事を確認するための機会だ。
「……回線の問題かな」
予定時間を五分ほど経過したところで、つぶやくようにタンが言った。画面には、待機状態を示す表示が貼り付いている。
「まあ、もう少し待ってみよう」
楽観的であることは、最悪の事態を想定しないということを意味しない。
「電話してみますか?」
じれたようにタンが言った。外部と連絡出来る電話は、管理棟にあるものに限られていた。ここから電波が届く範囲に携帯電話の基地局はないし、携帯電話の持ち込み自体が禁じられている。外部との接触を厳しく制限されたサンクチュアリは、自由に外部との連絡が出来るような場所ではなく、外部に連絡する必要もなかった。
「そうだな。優先電話を使ってみるか」
年に二回の訓練時にしか使わない優先電話は、サンクチュアリとビデオ会議の相手である保健衛生省の管理本部を繋いでいる。建前としては、二十四時間の連絡体制が出来ているはずだった。
「……呼び出し音はしてるけど、出ませんね。トイレでも行っているのかな」
軽口を装うタンの声が、心なしか緊張しているようにも聞こえる。
「一時間後に、もう一度連絡してみよう。それでも反応がなかったら、とりあえずは自治連絡会の召集だろうな」
僕が議長をしている自治連絡会は、公式な位置づけはないにせよ、サンクチュアリの議会のようなものだ。しばらくの間は自給自足できるとは言え、外部との連絡が取れないのは、明らかな異常事態だ。
「どう説明する?」
タンは心配そうに言う。
「事実を説明するだけだな。子供たちが不安になるといけないから、変に騒がないよう注意しておいた方が良いと思うけど」
サンクチュアリは大丈夫だ。今まで通りの運営を続ければ、一ヶ月どころか半年、いや一年でも問題ないだろう。
「確かに、ここで慌てても何にもならないね」
自分に言い聞かせるようにタンが言った。
「そういえば、ラジオがあったよな」
外にいたときに買ったものだった。最初は熱心に聞いていたものの、サンクチュアリの中との大きなギャップに、すぐに聞かなくなってしまっていた。
「無線機の組立キットもあったはず……」
思いついたようにタンが言う。僕がサンクチュアリに戻った五年前は、消毒さえすれば、持ち込む物の管理は厳しくなかった。自分で組み立てるつもりだったが、結局、手を着けることなくタンに譲ったのが三年前。そのタンも、まだ組み立てていない。
「そっちの方が良いかもしれない」
無線機の組立キットを探しに会議室を出るタンを見送り、僕は吉永所長が言っていたことを思い出す。
もし、外の世界に何かあったら……。
* * *
十七歳の春から適応教育の最終段階が始まる。どうしたら僕たちが病原菌まみれの外部世界で生きていけるのか、居住空間の消毒法や、安全な食事の摂り方、外出時の防護といったサバイバル方法だ。
「やっぱり、出て行きたくなんかないよな」
授業の合間に、僕はタンと一緒に屋上に出ていた。ベトナム系のタンは、ベトナム語を話せない。出生前診断で隔離対象と判定された僕たちは両親を知らないし、生物学的な意味は分かっていても、そもそも親や家族といったものを本当に理解しているかどうかも怪しかった。つまり、僕たちには家族が家で話す言葉を聞く機会がなく、サンクチュアリの中で聞き、学んだ言葉しか話せない。
「まぁ、外は危ないからね」
そう答えた僕は嘘をついている。確かにサンクチュアリの中での生活は悪くない。犯罪はないし、安全で、毎日の食事も保証されている。それでも、閉じこめられていることは事実だった。
「そうだよな。伝染病や寄生虫とか、銃で撃たれたり、内蔵を盗まれたり、飢えて死んだりとか、ひぃ~っ!」
学習の時間で見せられた物を全部鵜呑みにしているのか、タンが大げさに言う。それを聞いた僕は、つい、苦々しく思ってしまうが、表情に出さないくらいの分別はある。
「まあ、ここだって、退屈で死にそうだけどな」
娯楽はある。図書館もあるし、サンクチュアリの外で作られた映画や、ゲーム、みんなでやるスポーツの時間もある。僕たちはサンクチュアリの中心部にある学校にいて、屋上から見渡せる範囲には山や湖もある。今日は天気が良く、遠くに冠雪した富士山も見えていたが、さすがにサンクチュアリの範囲はそこまで広くない。目立たないように彩色された高さ四メートルの壁と、総延長七〇キロを超える有棘鉄線のフェンスに囲まれた場所が、僕たちの世界だった。
「そうか。もう、ゾンビプラネットをクリアしちゃったとか?」
タンが言うのは、最近、僕たちの間ではやっているゲームだ。ゲームデザインとしては古典的すぎるくらいだけれど、背景やキャラクターが作り込まれているにしてはVRのレスポンスがよく、ストレス無くプレイできる。
「どこが面白いんだかわかんないよ。すぐ死ぬし」
ポイントの低い雑魚ゾンビを倒し、コミュニティを作って仲間を増やす。農場を作って経験値を積み上げ、武器と特殊アイテムを集めて、襲ってくるゾンビの親玉を倒す。ステージごとにシチュエーションが変わっても、結局はそんなことの繰り返しばかりだ。それはある意味でサンクチュアリでの生活にも似ていると思う。パターン化され、パターンから逸脱することはない。
「まあ、好きか嫌いかは、人に依るからな」
そう言ったタンは、少し残念そうだった。ゾンビプラネットには、バディモードがあり、多分、僕にバディになってほしいと思っているのだろう。補完的な武器を選べば、対応できるシチュエーションも増えるし、サクサクとステージを進めるようになる。
「いや、やっぱグロいの苦手だし」
有棘鉄線をぐるぐる巻きにしたバットには威力がある。一撃でゾンビの頭蓋骨がつぶれ、ウイルスに侵されたどろどろの脳漿が周囲に飛び散る。そんな武器を愛用していた僕が、グロいのが苦手だなんて大嘘もいいところだ。
「ここは良いよな、さっき見たようなことが無くてさ」
ふと真顔になったタンが、遠くの富士山を見ながら、そんなことを言った。
「なんだよ、それ」
「ほら、授業で見せられただろ」
スクリーンの中で外の教師が話し、それに併せて大型ディスプレイの画面が切り替わる。そんな授業でも、みんながまじめに聞いているのは、ほかにやることがないからだ。サンクチュアリでは、反抗してみても、得られる物は何もない。
「ああ、あれね」
麻薬シンジケートの報復で、蓑虫のように木に吊り下げられた死体には、言い訳のようにモザイクがかかっていた。それでもはっきりと判るのは、吊されていたのが家族だと言うこと。見せしめに殺されたのは、両親とまだ幼かっただろう二人の子供たちだ。大きく枝を張った巨木につり下げられた一家の死体の画像は、アーカイブに保存されている大昔のウェスタン映画のアートワークを思わせる。
「子供に手を出すなんて、酷いよね」
「確かに酷い話だ」
タンは優しい。サンクチュアリの中で、年長になると幼い子供たちの世話を任される。タンはその仕事をうまくやっているし、子供たちに好かれている。何より、タン自身が、幼い子供の相手をするのが好きなようだった。
「たぶん、子供たちは十歳にもなっていなかったと思う。それくらいの大きさだったよな」
僕は、子供たちの世話が苦手だった。大声で走り回り、何に触ったかも判らない手でべたべたと触ってくる。鼻水を垂らしながら泣きわめく子供たちを、よく、タンは世話できるものだと思う。
「まあ、世界中があんなではないと思うよ」
犯行現場はメキシコシティの郊外だった。世界は広いし、麻薬シンジケートが勢力を保っているところの方が珍しい。それに、麻薬シンジケートに報復されるようなことをしなければいいのだ。
「でも、ここ以上のところはないと思うけど」
タンは改めてサンクチュアリの安全性を強調した。でも、それが僕にとっては疎ましい。
「安全なのは本当だな」
安全で退屈。それが、サンクチュアリだ。
「ほんとに、もう、飽きちゃったのか? バディプレイは結構ハマるけど」
確かに順調に進んでいる間のバディプレイは面白かった。けれど、バディを失ったときに、自分の能力の限界を嫌というほど思い知らされる。
「そうか?」
タンとゾンビプラネットをプレイしたのは、バディだったキクニがサンクチュアリを出てすぐだった。獲物を日本刀に持ち替えた僕は、ゾンビの頭蓋骨から抜けなくなった刀と格闘しているうちに、別の雑魚ゾンビに齧られた。
「今度はちゃんと援護するからさ」
タンは悪くないけれど、キクニとは違う。僕は二度と、バディプレイをやるつもりはなかったし、その理由をタンに教えるつもりはなかった。
「まあ、気が向いたらな」
曖昧にはぐらかした僕には、もう、時間があまりない。サンクチュアリでは、外部と連携したオンラインの大学課程もあるが、僕はサンクチュアリを出たかったし、出ることに決めていた。もう、外の大学入試検定を終えていたし、奨学金への申し込みを含めて必要な手続きを進めており、引き返すつもりはなかった。
「寂しくなるな」
突然のタンの言葉に驚かされる。
「知ってたのか?」
入試検定のことはともかく、サンクチュアリを出るための手続きについては、誰にも相談していなかった。僕は、思わずタンの肘をつかみ、日に焼けた顔をのぞき込む。
「まさか。ちょっとカマを掛けただけさ。そんなんじゃ外では生きていけないぜ」
そう言ったタンの、口の端がゆがんでいた。
僕たちは、遺伝的な原因で免疫系に問題があるのだそうだ。外部では、医師による定期的な観察下でも、一歳まで生き延びられる確率は五十パーセントもないらしい。家に籠もっていたとしても、家族が感染源になり、結果として死ぬか長期入院する羽目になる。家の中で健康に育てることがほぼ不可能ならば、生まれてすぐの段階で親から引き離してしまった方が良い、というのがサンクチュアリが作られた理由なのだそうだ。
今では母親が僕たちのような新生児を抱くことはない。感覚としては、流産とか、死産とかに近いのだと思う。僕たちのような赤ん坊が生まれるのは新生児千人に対して一人以下という割合で、死産の割合よりも遙かに低い。
僕たちのような遺伝形質を持った子供は、確率的にはもっと多いはずだという話を聞いたことがある。胎盤への着床自体が難しいのか、それとも流産してしまうことが普通なのか、いずれにしても僕たちのようなやっかいな子供が生まれる割合は低いというのが、吉永所長の説明だった。
吉永所長は、サンクチュアリで僕たちの世話をしてくれている大人たちの責任者だった。大人たちはいつだって完全防護で、ゴーグル越しの目配せと、マスク越しのくぐもった声、ぴったりしたゴム手袋越しの接触だけが、大人との触れ合いだった。
「本当に、いいんだね」
僕は、管理棟に併設された医務室にいた。僕の目の前にいるのは、防護服姿の医務官で、これから僕の手術を担当する。
「ええ、外の世界に出て、しっかり勉強し、ちゃんと社会に貢献したいんです」
僕たちは、サンクチュアリで育った四年目の世代だった。年上のサンクチュアリ育ちは、最高で二十歳で、多くは毎年のように送り込まれてくる子供たちの面倒を見ている。実際、サンクチュアリの運営のかなりの部分は、サンクチュアリで育った者に委ねられつつあり、それでもさほど困ることはないのだった。
「それは良い心がけだ」
ゴーグルとマスクに隠され、医務官の表情は判らない。
「ここでは学べないことが、外ではたくさん学べると思います」
完全にフラットになる手術用の椅子に座った僕の口から、吉永所長との面接で繰り返したせりふがすらすらと出てくる。サンクチュアリでは息が詰まるとか、そんなことは、一切、口に出すわけにはいかない。
「そうだな。じゃあ、まずは麻酔からだ」
左腕の内側に埋め込むインプラントは、血中の薬剤濃度を一定に保つ機能がある。免疫系を最適な状態に保ち、僕を感染症から守ってくれる。
「判りました。でも、以外と小さいんですね」
インプラントは十センチほどの長さで、太めのペンのようにも見えた。
「これでも容量は十二ミリリットルある。これだけで、一年以上の間、君を感染症から守ってくれるんだから、よくできた機械だよ」
タブレットで何かを確認しながら防護服の医務官が言った言葉に、僕は、何日か前に受けたレクチャーを思い出す。少なくとも、年に一回はインプラントに薬液を補充しなければならない。さもないと、僕の免疫機能は急激に低下し、多様な感染症に対して無防備になる。そんな説明に、臆病なタンでなくとも感染症に苦しんでいる人々の映像を思い出すだろう。僕たちは、そうやって脅されてきたのだ。
「一年は大丈夫なんですね」
そう確認した僕には、これといった計画がある訳ではない。とりあえずは進学し、もし、チャンスがあれば、海外にも行ってみたい。そんなことを漠然と考えていた。
「普通の生活をしていて、免疫系に過剰なストレスがかからなければね」
これもレクチャーで聞いている。それを、医務官の言葉で再確認している。
「じゃあ、安心ですね」
にこやかな笑みを作る僕は、ちょっとした不安を感じていた。免疫系にストレスがかかるような環境に身を置けば、インプラントの免疫ブースターは一年保たない。今聞いた医務官の言葉を逆に解釈すれば、そういうことになるが、毎年のように感染症の流行がある外は、免疫系にストレスがかかる環境のようにも思えた。
「予定も詰まっているから、早く進めよう」
サンクチュアリの収容人数には限界があり、投入可能な予算も限られている。外部の労働力に依存しないで居住棟の拡充を図るのには時間がかかり、子供たちの収容人数に釣り合うように、一定人数はサンクチュアリの外に出した方が良いというのが吉永所長の考えだった。高校卒業に当たる十七歳は、外に出る最初の機会で、僕はその機会に飛びついたのだ。
「ええ、大丈夫です」
インプラントの埋設に、本当は、全身麻酔は必要ない。ただ、自分の腕が切り開かれる様子を見て、気分が悪くならないはずもなく、全身麻酔で意識がないうちに手術を終わらせてしまうのが標準的なやり方だ。
「じゃあ、まず、吸入マスクをつけて」
医務官の指示に従い、鼻と口を覆うマスクをつけ、頭の後ろでバンドを締める。
「しっかり締めて。椅子をフラットにするから、そうしたら大きく息を吸って」
椅子全体がせり上がり、背中が後ろに倒れるのと同時に足を乗せる部分もまっすぐに延びて、ほとんどベッドのような感じになる。医務官が左の手首に何かを巻き付けたのは、多分、血圧や脈拍を計測するためのモニターで、コードでつながったディスプレイにはグラフと数字が表示されていた。
意を決して大きく息を吸うと、その瞬間に僕の意識は消え去っていた。
「サンクチュアリ(後編)」に続く。
