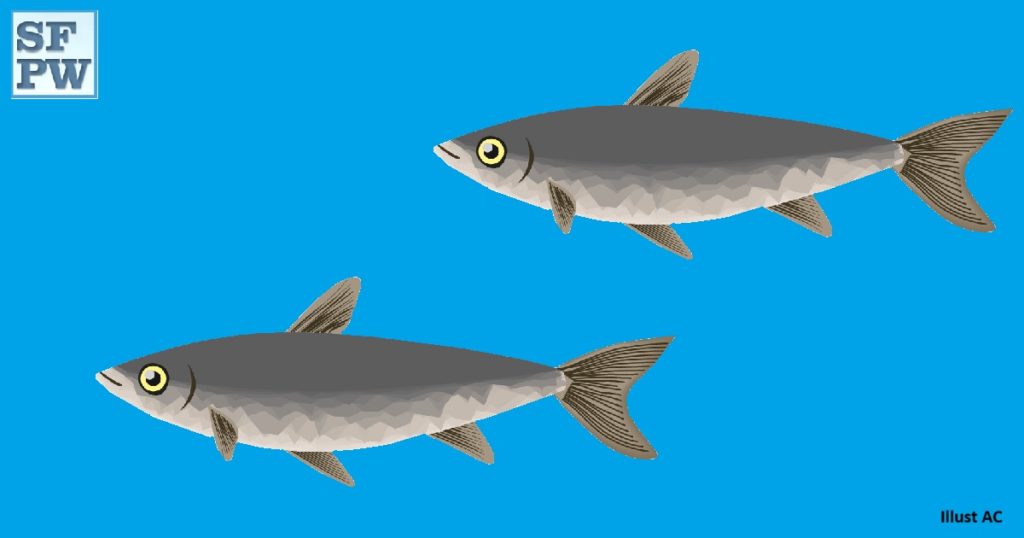
[ハヤ煮]
夢は今もめぐりて
忘れがたき……
うつらうつらしていると歌声が聞こえる。窓を開けると、アパートの前の路地を、数人の子どもたちが歌いながら歩いていた。一人が私を見た。怖がらせたか、私は照れ笑いを浮かべた。それで緊張がほぐれたのか、子どもたちも微笑みを浮かべ、一人が言った。
「今度の土曜、小学校の音楽祭で歌うんです」
子どもたちを見送って、窓を閉めた。兎は追ったことがないが、小鮒ならぬ小魚なら。
それに呼応するかのように玄関の扉が開いた気がした。鍵は掛けてある。空耳か勘違いだろう。そうは思ったけれど、いったんそう思うと、気になって仕方がない。やおら小便でも行くかとわざわざ口に出して言い、誰に言い訳するでもない一人暮らしのくせに、腰を上げて、トイレに向かった。
まっすぐトイレに行き、茶の間へ戻るとき、別に気にしているわけではないとまたしても自分に言い訳しながら、玄関戸に目を向けた。明かりの消えた薄暗い三和土(たたき)に何か置いてある。どうやら、バケツで、どうしてと思って立っていると、ぴしゃんと水を打つ音がした。バケツに水が張ってあり、その水面が茶の間から届く暗い蛍光灯に照らされて、波打っているのがわかる。
中を覗くと魚が泳いでいた。ハヤだとすぐにわかった。地域によってウグイ、オイカワ、カワムツなどと呼ぶところもあるらしいが、私の郷里では、もっぱらハヤで通っていた。そのハヤを昔、家から近かった荒川に行って、釣ったことがある。
最初はクラスの男友達に誘われたのだが、私がおもしろかったのに対して、その子はすぐに飽きたらしく、休日に誘いに行っても、頭が痛いだの宿題が残っているだのと言い訳するようになり、そんなことが何度かつづくうちに、私は一人で荒川に出向いたのだった。
「釣りってそんなにおもしろいの?」
「おもしろいっていうか」
横に並んで歩くUは、つぶらな瞳で私を見つめ、答えを待っている。どう答えていいのかわからず、口から出任せではないけれど、
「ハヤが好きなのかな。きれいっていうか、かっこいいっていうか」
「ハヤが好きなの。それじゃ、あたしも」
あたしも? つづきを待ったけれど、学校に着いたこともあって、話はそこで終わった。
実際、釣り自体が好きだったわけではないし、それ以後、興味を持ったこともない。ただあの頃、ハヤを釣るのが、なぜだか楽しかった。家から近くで釣れたから、大した準備をしなくても釣れたから、それに……。そんなことをたどたどしく説明した記憶も朧気にある。そういえば、こんな話もした。
「釣ったら、食べるの?」
「いや、小骨が多いし、美味しくないから」
それは父の受け売りだった。一度食べてみたいと思ったけれど、母も気乗りせず、まずいならいいか、と、それっきりになった。
「それじゃあ、どうするの?」
「帰るとき、川に戻すよ」
最初のうちは家の池に放したこともあるけれど、可哀想な気がして、帰るときに川に戻すようになった。
「せっかく釣ったのに?」
「釣り上げたとき、きらきら輝いてて。きれいなまま川に返してあげたくて」
顔を上げると、目があった。私を見ながら微笑むUの顔は、今でも鮮明に浮かんでくる。生涯、一番の笑顔だったのではないか。やがて彼女は私の妻となる。しかし……。
◇ ◇
まただと思った。酒のせいか怠惰な生活の賜(たまもの)か、自分がどこにいるのかわからなくなる。この頃は飲んでばかり居る。それは前からのことだが、家飲みばかりとなった。理由は金銭的な問題も大きいが、ただ怠惰に飲んで、人と話す気も起こらず、ライブに足を運ぶ気にもなれない。好きなときに飲んで、酔えばごろんと横になり、起きたら飲める、勝手な生活。飲んだくれて転寝(うたたね)すると夢を見る。
私は台湾に居て、歩きながら手にした土瓶か徳利を口に運び、飲んでいる。観光をする気にもならずただ歩きながら飲んで、それでいて楽しんでいる。見知らぬ町を歩きながらも、気持ちは酩酊の中に佇んでいる。そのギャップというか、不思議な酩酊が楽しい。起きても、夢の中の世界が脳裏に残っていて、実際に焼酎を口にすると、ふたたび夢の中へ引き戻されるかのようで、これだけ楽しめるのなら、わざわざ高い金を出して旅行することも、外で飲む必要もなかった。
◇ ◇
扉をノックする音がする。
「開けて、井之君」
Uの声にまちがいがない。ただ成人する前の、まだ幼く、私と出会ったばかりの頃の声だ。小学校二年のはじめに、Uは父親の仕事の関係で、甲府へ引っ越し、転校してきた。社宅は私の住む町内にあって、クラスこそちがったけれど、集団登校で同じ班になり、二年生は私とUだけだったので、自然と並んで登校し、話すようになった。
◇ ◇
「荒川に行ってきたの。そしたらハヤが、やっと釣れて。はじめて釣れて。覚えてる、約束したの? はじめて釣ったハヤは井之君にあげるって。やっと釣れたの。ずっとずっと釣ってたの。それがやっと。だから、はやく」
開けよう、玄関扉の向こうにUが来ている。しかし私に決心はつかなかった。
浮かぶのはジェイコブスの『猿の手』か。何かに、何か願い事をしただろうか。している。その墓石にしがみつき、願った。骨壺から取りだした遺骨を食べても、願った。飲んだくれその度に、彼女の写真にすがりついて願ってきた。その願いがやっと叶ったんじゃないか。それなら、はやく。しかし『猿の手』が。『古事記』のイザナミが。
そうか、ここは黄泉の国か。だから彼女と会えた。しかしイザナミは「見るな」と言ったはずだ。見たから関係は終わってしまった。見なければ、ずっとつづいていたかもしれないのに。開けられないんだ、それはお前だって知ってるだろう。こころで思った。
「それじゃあ、なぜ呼んだの?」
そう言われると返す言葉がなかった。
そうだ荒川に行こう。あの頃ハヤを釣りに行った河原へ。昔のように釣り糸をたれて、餌にする虫を探そうとひっくり返した石を、河原に積んで、石塔を造って。そして。
玄関戸に向かって、なあ、と言いかけたけれど、すぐに「ねえ」と言い直した。扉の外にいるUは、まだ子どもらしい。
「なに?」
「荒川に行かないか?」
「これから?」
「おれ……じゃなくて、ぼくも久しぶりにハヤを釣りたくなったんだ」
「せっかく、あたしが釣ってきたのに」
「いっしょに、もっと釣ろうよ」
「いっしょに……うん、わかった。行きましょう、いっしょに」
「先に行っててくれないか?」
「どうして? 今、いっしょに行くって言ったのに」
コップに残っていた焼酎をくいと空けた。いっしょに行けばいい、と思った。すぐに、しかし、とも思う。
「ほら、母さんの××をしなければ」
しまった大人の口調だ、と思ったが、Uは疑いもせずに、答えた。
「わかった、わたしがするから、先に行ってて。済ませたら、すぐに行くから。だめよ、今回はすっぽかしたりしたら」
今回はって……。思ったとき、私もUも大人の口調だったことに気づいた。そして、あの会話の後に起こったことも――。
「だめだ。行くな」
起ち上がって、玄関戸を開けたけれど、そこにUの姿はなかった。
◇ ◇
どろどろとまとわりつくような心地よい風が川面から吹いてくる。河原に腰を下ろし、流れる川面に釣り糸を垂れている。浮子が沈んで、ちょっと浮いたもののすぐにまた沈んで、釣り竿を揺らす。引き上げると、糸の先でナイフのようにきらりと輝く。ハヤだ。
竿を上げて、引き寄せ、揺れるハヤを左手で掴むと、脇に置かれたバケツに入れた。バケツの中では半分近く入っていた水が、すでに水ではなく、ぐつぐつと煮えている。河原の石で小さいが巧みに炉を作り、下では火が、上に置かれたバケツを炙(あぶ)っている。すでに何匹か放り込んであったハヤは、煮えて、動いてはいるけれど、自力ではなく、沸騰する湯の流れで、動いている。そこに釣ったばかりのハヤを入れると、二度三度、飛び跳ねるのを見ただけで、視線を逸らした。
近くの石を持ち上げると下にうじゃうじゃと虫がいた。昔は気色悪くて、近くで釣りをしていたお兄さんが、石をどけて、取りなと言っても、手を伸ばせず、そんな私を見て「気持ち悪いか?」と笑った、笑われた。しかし、今は少しも気持ち悪くない。手の平を広げて、掴めるだけ掴み、釣り針に一匹二匹、残った虫は頬張ってしまい、焼酎の壜を取り寄せて、ぐいと流し込むと、なかなかに乙とさえ感じてしまう。
いつになく釣れた。釣り針を川に入れるとすぐに浮子が沈み、釣り竿を上げると、銀色の流線型が光りを浴びて、赤黒く輝く。赤黒く? 空を見ると、それまで気づかなかったのが嘘のように、太陽がどす黒い。対岸の銀の原も赤く染まっている。
「すみません。その魚、いただけませんか? いえ、ちゃんとお代は払いますから」
背後から声がした。Uが来たのか。しかしその声は嗄(かす)れていて、別人のものだ。どういう加減か一人の古い友が浮かぶ。そう思うと、次の声も次の声も。
「だめですか?」
「お代は払いますから」
振り向くどころか返事すらできず、釣り糸の先を川面に落とし、じっと浮子を見つめた。
「ああ、これ以上煮たら煮詰まってしまう。あんたみたいに……」
「どうぞ、ご自由に」
私は言った。それ以上何か言われたら、心身がささくれ立つ気がしてやりきれない。
「ああ、おありがとうございます」
「おありがとうございます」
幾つかの声が重なり、引きずるような足音、視界の隅、脇に置かれたバケツに身をかがめた輩が手を入れ、素手で、煮えたハヤを掴みだしているらしい。一人、二人、三人、四人……。その度、ちゃらんと足下に落ちる物、これまた視界の隅で、紐で結んだ頭陀袋から穴明き銭が顔を覗かせている。
ハヤは次々と釣れた。釣れたハヤの口から釣り針を外し、煮え立つバケツの湯に入れると、すぐに石の下から掴まえた虫を釣り針に付け、釣りをつづける。いつの間にか背後の気配が強まっている。引きずる足音、うめくような声、それらとは別に、
「ありがとうございます」
Uの声だった。いつ来たのか。いつの間にか銭を受け取っている。
「まだまだ釣れますから」
どうしてそんなことがわかるんだ。疑問に思う暇もなく、実際にハヤは入れ食い状態で、次々に釣れつづけた。口から釣り針を外すと、見もせずに、脇のバケツに放る。殺生。能の『鵜飼』が脳裏を過(よ)ぎる。あちらは甲府の東にある石和での出来事だったが、やがてこの川も、石和の川と合流する。私のハヤ釣りも、同じ殺生か。釣っただけではなく、煮て、喰らわせたとなると、それ以上の――。
煮えたぎっている湯で、ハヤはすぐに茹でられ、箸でつまむのか、笊(ざる)で掬うのかもわからず、茹だったハヤを居並ぶ者たちに渡すのはUの役目である。
「ありがとうございます」
「おありがとうございます」
「ありがとうございます」
「ああ、おありがとうございます」
式は挙げていない。私たちのはじめての共同作業が、これか。それならつづけるのが幸せか。酒が飲みたいと思ったけれど、次々に釣れるハヤのせいで、それもままならず、しかし隣りに感じるUの気配、声にとろりとろりと甘露と感じる私が居る。
[お魚言葉]
「河原に行かない?」
「これから?」
「おれ……いや、ぼくも久しぶりにハヤを釣りたくなったんだ」
「せっかく、あたしが釣ってきたのに」
「いっしょにもっと釣ろうよ」
「いっしょに。うん、わかった」
「先に行っててくれないか?」
「どうして? 今いっしょにって」
私は責められた気がして苦し紛れに言った。
「母さんの世話をしなくちゃ」
「……わかった。でもどこに行けばいいの?」
「飯田通りを進んで、長松寺橋から河原に降りて、川下に向かって少し進んだところに石を積んだ塔がある。そこで」
Uは不安そうに顔を曇らせたが、すぐに笑顔を私に向けて、頷いた。あれがUを見た最期だった。否、それはこの世での出来事。この世? それはどこだ?
Uと再会したのは二十年近く経ってからだった。怪獣映画のノベライズだったが、本を出版し、Uが出版社宛に葉書をくれたのだ。
〈あの場所で、待ってます。ずっと。〉
◇ ◇
取るものも取りあえず、私は中央線の電車に飛び乗り、郷里へ向かった。風呂にも入っておらず、髭も剃っていないことに気づいたのは、郷里に着いてからだった。取りあえず実家へ寄った。父はゲートボールに行って居らず、母が糠漬けの樽を掻き回していた。ゲートボールのコートは荒川の河川敷にある。Uが待っているすぐ近くだ。不思議な縁を感じ、やっぱりと私は思った。
「どうした、いきなり戻ってきて」
「ちょっと風呂を浴びるよ」
「まだ沸かしてないが」
「いいよシャワーで。剃刀はある?」
「ああ、父さんのが」
母が差し出した安全剃刀を持って、シャワーを浴びた。髭を剃った。
「腹は減ってないのか?」
「減っているけどすぐ戻る。急用があって」
「あり合わせで食うもんを作っておく」
玄関で靴を履き、玄関の引き戸をあけたところで、振り返って言った。
「人を連れて来るから。二人分頼むよ」
「友だちか?」
言葉に詰まったが、吐き出すように言った。
「結婚しようと思う。その人と」
「おいおい、藪から棒だな」
「反対かい?」
「そうじゃない。それどころか、まさかと思って、驚いただけだ」
「じゃあ、いいんだね」
「いいも悪いも。どんな人だ?」
幼なじみだった……対岸に広がる銀の原が浮かぶまま……すすき、須々木浮子ちゃん。覚えていないかな、小学校のときいっしょだった。否、覚えているかわからないし、まだ言わない方がいい。彼女は三年の終わり、転校してしまった。甲府市内に家を建てたという噂、それなら転校しなくてもいいじゃないか。
「すぐ連れて来るから」
私が言うと、母は顔を崩して、持っていた手拭いで目頭を拭った。
「わかった。買い出しに行ってくる。肉か魚か。それより寿司でも取るか」
任せるから、と私は言い残し、実家を後にした。そして。
◇ ◇
浮子は、あの場所に居た。河原の石の上に腰を下ろし、手には釣り竿を持ち、その先についた糸は川面に沈んでいた。浮子が沈み、彼女が竿をあげると、糸の先にきらりと光る魚が暴れていた。
「ハヤか」
彼女は振り返った。ふとあの頃、彼女が言った言葉が脳裏に甦る。
「お魚言葉つくらない?」
「なにそれ?」
「花言葉ってあるでしょ。あんな風に。たとえば『輝く幸せを運ぶ』ってどう?」
いいねと私は答えた。あの時は浮子が考えたんだから悪くはない程度にしか思わなかった。
◇ ◇
コップに残っていた焼酎をくいと空けた。いっしょに行けばいい、と思った。すぐに、しかし、とも思う。
「母さんのシモの世話をしなくちゃ」
浮子は疑いもせずに、
「そうね。じゃあ先に行ってて。わたしがする。済ませたら、すぐ行くから。だめよ、今回はすっぽかしたりしたら」
今回はって……。思ったとき、私も浮子も大人の口調だったことに気づいた。そして、あの会話の後に起こったことも――。
志を果たして
いつの日にか帰らん
何が耐えられなかったのだろう。今となってはわからない。浮子と離れた途端、私は突風に襲われた。敬愛する画家・牧野邦男の言葉が頭を覆った。
「我を生かすものは絵画也 酒にあらず金にあらず女にあらざる也」
私の場合、絵画ではなく作つまり創作也。実家にあった有り金を握りしめ、新宿へ向かう電車に飛び乗った。その頃、浮子は急いだせいか、点滅を始めた信号を渡ろうとして、無免許、飲酒運転の軽自動車に轢かれ、まだ犯人は捕まっていない。
「だめだ。行くな」
起ち上がって、玄関戸を開けたけれど、そこに浮子の姿はなかった。
如何にいます父母
恙(つつが)なしや友垣
河原に行くと浮子が居た。白無垢の花嫁姿だった。正装した私の両親も居る。もう二人の正装した男女は、会ったことはないけれど、浮子のご両親だとわかった。私だけこんな格好で、と、いつしか紋付き袴で、手には扇子を持っている。
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。私の場合、百年とは限らないけれど。こみ上げる涙をこらえ、浮子のご両親に頭を下げた。そして浮子と見つめ合う。
――うちの軽トラ使って。
地区の運動会、荷物を積んだ軽トラックを会場の穴切小学校まで、私に運転しろと言う。
――でも免許持ってませんし。
――軽トラなんて、玩具みたいなもんだ。うちのはオートマだし。
ちょこちょこっと運転を教えてもらい、ほんとうにかんたんで、私でも走らせられた。否、妄想だ。頭から払いのけ、私は言った。
「輝く幸せを運ぶ」
「覚えていてくれたんだ」
輝く幸せを運ぶ。言葉を脳裏で反芻(はんすう)する。待てよ、これって本当に浮子が考えたのか。私が考えたのではなかったか。輝くハヤを見ていて、私もこれくらい輝けたらと、すがるようにハヤを釣った幼い日々。しかし私はいつしか煮て、煮られて、輝きなど微塵もなくなっていた。それに浮子っていったい……。
「どうかしたの?」
隣から声がしたが、どこかくすんでいる。すべてが赤黒く淀んでいく。
「いや、会いたかったんだ」
目を凝らし、彼女を見た。彼女の瞳がきらり輝く。やっぱりこの笑顔が一番だ。輝く幸せを私の人生に運びつづけてくれた、この笑顔が。
雨に風につけても
思ひいづる……
河原に佇む異形たちが、ハヤ煮を喰らいながら懐かしい童謡を歌っている。(了)
注:本作には童謡「ふるさと」からの引用があります。
