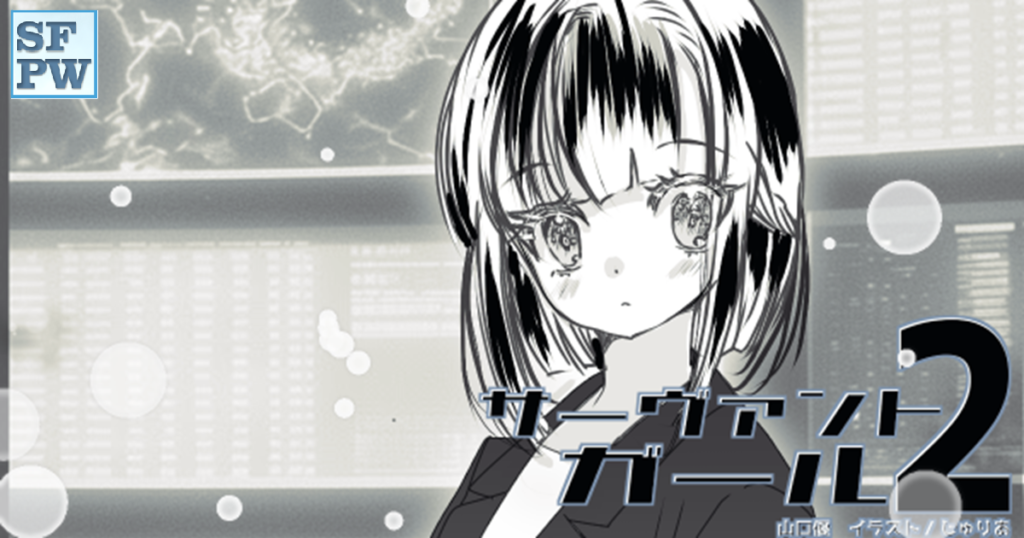
サーヴァント・ガール2第四章二話(通算一五話)「虚無」
<登場人物紹介>
- 織笠静弦(おりかさ・しづる):物理学を学ぶ大学院生。二年飛び級をして入学しているため二〇歳。ひょんなことから、平行世界からやってきた「機械奴隷」であるアリアの主人となり、平行世界と「機械奴隷」を巡る暗闘に巻き込まれていく。戦いを通じてアリアと主人と奴隷を超えた絆を結ぶ。
- アリア・セルヴァ・カウサリウス:ローマ帝国が滅びず発展し続けた平行世界からやってきた「機械奴隷」。アリウス氏族カウサリウス家の領地(宇宙コロニー)で製造されたためこの名となっている。余剰次元ブラックホール知性が本体だが、人間とのインターフェースとして通常時空に有機的な肉体を持つ。「弱い相互作用」を主体とした力を行使する。行使可能なエネルギー(=質量)のレベルは微惑星クラス。「道化」の役割を与えられて製造されており、主人をからかうことも多い。
- 御津見絢(みつみ・けん):織笠静弦の友人。言語学専攻。静弦に想いを寄せているようだが、研究に没頭していたい静弦にその気はない。おとなしい性格だが、客観的に静弦のことをよく見ている。いつしか静弦の戦いに巻き込まれていく。
- 結柵章吾(ゆうき・しょうご):織笠静弦の大学の准教授。少壮で有能な物理学者。平行世界とそこからやってくる「機械奴隷」に対応する物理学者・政治家・軍による秘密の組織「マルチヴァース・ディフェンス・コミッティ(MDC)」の一員。静弦にアリアを差し出すよう要求し、拒否すれば靜弦を排除することもいとわない非情な一面も見せる。かつて静弦と深い仲であったことがある。
- リヴィウス・セルヴス・ブロンテ:結柵に仕える「機械奴隷」。電磁相互作用を主体とした力を行使する。エネルギーは小惑星クラス。
- ヴァレリア・セルヴァ・フォルティス:結柵に仕えていたが、後に絢に仕える「機械奴隷」。強い相互作用を主体とした力を行使する。エネルギーは小惑星クラス。
- アレクサンドル(アレックス)・コロリョフ:結柵の研究仲間の教授。静弦が留学を目指す米国のMAPL(数理物理研究所)という研究機関に属している。
- ユリア・セルヴァ・アグリッパ:主人不明の「機械奴隷」。重力相互作用を主体とした力を行使する。エネルギーは惑星クラス。
- 雛森早苗(ひなもり・さなえ):結柵章吾のラボの職員。情報系の仕事をしている。
- 亜鞠戸量波(あまりと・かずは):静弦の同級生。二二歳。「サーヴァント・ガール2」から登場。
- ルクレツィア・パウルス:バンクーバーのAI学会で静弦らと出会った女性。台湾にあるスタートアップに勤務。「サーヴァント・ガール2」から登場。
- 勅使ヶ原悠奈(てしがはら・ゆな):織笠静弦の大学の准教授。亜鞠戸量波の指導教員。インペリウム世界の謎に気づき始めている。「サーヴァント・ガール2」から登場。
<「サーヴァント・ガール」のあらすじ>
岐阜県の「上丘(かみおか)鉱山」に所在するダークマター観測装置の当直をしていた大学院生の織笠静弦は、観測装置から人為的なものに見える奇妙な反応を受信した。それがダークマターを媒体としてメッセージを送信できる高度な文明の所産だとすれば、観測装置の変化を通じてこちらの反応を検知できるはずだと判断した彼女は「返信」を実行する。次の瞬間、目の前にアリアと名乗る少女が出現する。アリアは静弦が自分の主人になったと主張し、また、主人となった人間には原理的に反抗できないことも説明され、静弦は渋々アリアと主従の関係を結ぶ。
しかし、現代文明を遙かに超える力を持つ機械奴隷を静弦が保有したことは、新たな争いの火種となった。実は、アリアと同種の機械奴隷はアリアよりも前からこの宇宙に流れ着いており、それを管理する秘密組織「MDC」が存在していた。観測装置の実務責任者である結柵章吾もそのメンバーであり、彼は静弦がアリアを得たことを察知、自らの「機械奴隷」であるヴァレリア、リヴィウスを使って攻撃を仕掛け、アリアを手放すよう要求する。静弦は、自分を必死に守るアリアの姿を見て、アリアを手放さないと決意、辛くも結柵との戦いに勝利する。
勝利後の会談で結柵にもアリアの保有を認められ、しばし穏やかな時が流れるが、静弦は自分が研究中の理論を、遙かに進んだ科学を知るアリアに否定されけんか別れする。その隙を突き、主人不明の「機械奴隷」ユリアに攻撃されるアリアと静弦。危機を察知した結柵がヴァレリアを、静弦の友人・御津見絢に仕えさせ、二人に救援に向かわせたこともあって、ユリアの撃退に成功する。戦いを通じ、静弦とアリアは主従を超えた絆を結ぶ。戦いの後、これ以上の攻撃を撃退する目的から、静弦とアリアは、絢・ヴァレリアとともに留学生寮に住むことになる。
<「サーヴァント・ガール2」これまでのあらすじ>
静弦は留学生寮で新しく友人となった女子学生、亜鞠戸量波の部屋で彼女と一夜をともにする。アリアは静弦の行動にショックを受け、姿を消してしまう。アリアを追い、静弦は絢、ヴァレリアとともにアリアの目撃報告があったカナダ・バンクーバーに向い、そこで偶然出会った量波とも合流して、現地で開催されたAI学会に参加、アリアを見つけ出す。しかしアリアは、自らの存在をこの宇宙とは異なる余剰次元空間に逃避させる。静弦はヴァレリアとともにアリアを追うが、アリアは「自分は静弦様にはふさわしくない」と言い、姿を消す。静弦は絢の助言により心を決め、アリアの手がかりを求め、AI学会で出会い、アリアを見知っていると思われる女性、ルクレツィアの足取りを追って台湾に向かう。
三人は、台湾で量波、そしてアリアとも出会う。しかしアリアは再び逃げてしまう。絢によって「セルヴァ・マキナの力を阻害し、アリアの失踪を手引きしていた犯人」と名指しされた量波とルクレツィアは、静弦・絢・ヴァレリアを巻き込んで瞬間移動を引き起こす。量波は自らを「MDC行動派」と名乗り、他宇宙からの侵攻に備え積極的にインペリウム世界の技術を開発すべきだと説くが、静弦・絢は顕在化していない脅威に対し無用な混乱を招くとしてこれを拒否した。ドミナである量波のセルヴァ・マキナであるルクレツィアは、「他のセルヴァ・マキナを操る力」を行使しヴァレリアを操作、静弦・絢を葬り去ろうとする。そこに現れたアリアは、ヴァレリアに対抗し、静弦を助けるかに見えたが、自ら作り出した余剰次元空間に静弦を閉じ込め、彼女の身動きを取れなくしてしまう。それもルクレツィアによる操作のせいであった。しかし、アリアはルクレツィアによる操作をはねのけ、逆に量波・ルクレツィアを攻撃、撃退する。二人は姿を消した。
その後、日本に戻ってきた静弦は、量波の指導教員、勅使ヶ原に量波の行方について尋ねられるが、「知らない」と答える。勅使ヶ原はAI「クリュセオン」を駆使し静弦や結柵を疑い始めていた。
一方、量波は、MDC行動派のメンバーの「代理」として、ユリア・セルヴァ・アグリッパから、行動派の計画を明かされていた。その内容は、核戦争による現代の国際秩序の破壊と、MDC行動派による独裁体制の構築という、想像もできないようなものだった。
第四章二話(通算一五話)「虚無」
街の雑踏が、街を賑やかな雰囲気にしている。
二月。表参道。バレンタインデー。
東京国際学生館に一二月に入居して、量波と仲良くなり、――そして、バンクーバー、台湾の戦闘を経て、既に二ヶ月が経っていた。
「まあ、楽しい雰囲気ですわね」
アリアがうれしそうに言う。
「クリスマスにお買い物をしたことを思い出しますわ。あのときと同じように、雪が降っていますのね」
八王子、そして台湾の山中の戦闘が嘘のように平和だ。
あれから日本に帰国し、大学に戻り、結柵准教授、雀居教授、勅使ヶ原教授と会い、徐々に「日常」を取り戻してきた気がする。
東京国際学生館での生活も大分慣れてきた。入館初期に仲良くなった量波の不在は、鈍い心の痛みになって静弦の心を苛むものの、彼女を通じて知り合った内外の学生たちとの交流は楽しいものではあった。アリアの過度な嫉妬は相変わらずだが、最近はアリアも交えて仲良くすることも増えている。
(まあ、結柵先生はいい顔はしないだろうけどね)
アリアの正体は極秘中の極秘だ。
「……楽しい雰囲気ね」
静弦はほっとした様子で街を見渡した。
つい先ほどまで、彼女はオンラインでMAPLの指導教員――となる予定の教授――と会話をしていた。面接の時にも同じ教授だったので初対面ではないのだが、やはり肩は凝る。雀居教授と打ち合わせをしていたし、先方は雀居教授とも仲の良い教授だったので、その点は気安くはあったのだが。
ただ、「プロフェッサー・ササイの考えはそうだとして、ミズ・オリカサはどう思っているんだい? あなたの考えで研究を進めてほしい」と言われたときはどきりとした。
(そうだ。私が研究をするんだ。私の計画なんだ)
そう思い直し、雀居教授との打ち合わせでは出なかった話までしたら、先方は大いに感心していた。
それだけに、若干のむなしさもある。
(あの話は、そう……アリアが『筋が良くない』と言ったことを避けていた……。無意識に)
量波の言葉が頭をよぎる。
(本当に……いいのだろうか……このままで)
そう思っていたら、アリアがもの言いたげにこちらを見てくる。
「どうしたの?」
「いえ、一緒に来ていただいてありがとうと言おうとしたのです。以前は……静弦様がどなたとでかけてもしょうがないと思っていましたけれど、もうそれは嫌ですわ……不出来なセルヴァ・マキナをお許しくださいまし」
「いいって。それで。私も量波のようには振る舞えないよ。仲良くできるのは一人だけだって思ってる」
「ふふ……嬉しいですわ。静弦様を独占できるというのは、わたくしにとっては素晴らしいことですわ」
(――そうだね)
静弦はアリアの肩を抱き寄せてやった。
――そのとき。
「やあ。ミズ・オリカサ。こんなところで出会うとはね」
急に声をかけられ、静弦は振り向いた。
「アレックス先生……」
MAPLの教授、アレックス・コロリョフだった。外套にマフラー、それにウシャーンカ(ロシア帽)という出で立ち。その両手には買い物袋を提げている。
「MAPLの試験、おめでとうと言わせてほしい。同僚に聞いたが、研究計画も順調なようだ」
「それは……ありがとうございます」
静弦の心臓の鼓動は高鳴る。
「先生は、お買い物ですか?」
「ああ。まあね。今日は恋人のための日だが――私にとっては別の目的の買い物だな」
アレックスは微笑んだ。
「別の目的?」
静弦は何の気なしに聞いた。アレックスは笑顔を消し、覗き込むように静弦を見つめた。
「……帰国の準備だよ。日本からは出て行くことになるだろう。MAPLも辞める」
「まあ……いったいどうして……?」
静弦は衝撃のニュースにどう反応していいか戸惑う。
「原因は外交かな……。それも特殊な領域のね。君が原因の一つでもある……」
アレックスは謎めいた視線のまま、淡々と語る。
その時だった。
「アレックス! こっちにも欲しいものがあるんだけど!」
それは静弦が知らない外国語、おそらくはロシア語だったが、アリアが翻訳してくれたのだろう、静弦には意味の通じる言葉として響いた。
そして、その声音には聞き覚えがあった。とても、印象の悪い聞き覚えが。
足音が駆け寄ってくる。静弦は振り向いた。アリアがぎゅっと静弦の腕を抱きしめる。
「……ユリア・セルヴァ・アグリッパ……!」
流れるような艶やかな赤毛。緑の瞳は爛々と光り、アリアと静弦を見下すように見つめている。今は鮮やかな朱の外套に、アレックスとおそろいのウシャーンカ。
「おやおや。こんなところで出会うとはね。織笠静弦。それに、アリア・セルヴァ・カウサリウス」
「静弦様。下がってください」
アリアは静弦の前に進み出て、その手にメイスを出現させ、構える。
「くっく。ポンコツが」
ユリアも右手を構える。空間が揺らぐ。今にもピルムが出現するかと思われた。
「やめろ」
アレックスが鋭くひとこと、ユリアに命じる。
「チッ」
ユリアは出現させかけていたピルムを消した。
「……あなたが、こいつの、ドミヌスだった、わけですか、先生」
静弦の声は震えていた。自分とアリアを攻撃しただけではない。アリアの心も傷つけた。それを静弦は許していなかった。
「君にはヒントを与えたつもりだったが、存外察しが悪かったな」
アレックスは表情も変えず、淡々と返す。
「逆にユウキは優秀だった。君への襲撃を察知するやトーキョーとワシントンを味方につけ、冷徹に私を追い込んだ。結果として私は、自由に出入国することもできなくなり、東京にとどめ置かれた。今やこの身はペルソナ・ノン・グラータだよ。それで進退窮まってね……ついに、明日にでも祖国に帰ることになった」
「あなたもMDC……そして行動派だったわけですか」
「――カズハから話は聞いているか。そのとおりだ。尤も、統制派の連中は、派閥を形成すること自体に消極的だが、我が行動派を牽制するために仕方なく対抗派閥を組んでいるという形ではあるがね」
アレックスはそこで言葉を切った。
「往来で長話も無粋だな。喫茶店に入ろう。幸い、ここには良い店が揃っている。迷惑料ついでにご馳走しよう」
「――このユリアのドミヌスであるあなたの誘いに、この私が乗るとでも?」
静弦はアレックスを睨み据える。
「こういうときは、君の理性に相談することだ、感情ではなく」
アレックスの瞳は相変わらず何の感情も映し出していない。静弦は渋々助言に従った。
理性は、欺瞞情報が混じっている可能性が大であるにせよ、ここで彼から情報を得ておく意味はあると主張していた。
「アリア、どう思う」
アリアにも問う。
「憎らしいですが、それは別として、ご判断は間違っていないかと」
静弦の判断はアリアにも予想できたらしい。
静弦は無言で頷いた。
だが、次にこう言うのを忘れなかった。
「あなたを許したわけではありませんよ、先生」
アレックスは無言で僅かに微笑んだ。
「君はユウキらの思想がおかしいとは思わないかね」
ロシア風の喫茶店だった。静弦とアレックスの前には、ロシアンティーが、たっぷりのジャムとともに供されている。四人席。静弦とアレックスが向かい合って座り、静弦の隣にアリア。アリアの向かいにはユリア。アリアはユリアを睨むだけで、口を利こうともしない。ユリアはアリアの怒りに満ちた眼差しにも頓着せず、ただジャムと紅茶を交互に口に運んでいた。
「――あなた方の思想については、既に量波やルクレツィアから充分に聞きました。その上で否定しているのです。今更ご説明は不要です」
静弦もまたアレックスを睨んでいる。その言葉にも抑えきれない険がある。
「――ああ、それはカズハらから聞いているよ。他世界についての安全保障上の懸念については既に説明済みだとな」
アレックスは落ち着いた雰囲気で言う。喫茶店の中の数人がアレックスに振り向いたが、一様に戸惑った様子で、会話の真の意味を把握しているようには見えない。早口の英語だし、内容も一般の人間には意味不明だろう。
「そう。安全保障上の懸念は現実のものだ。統制派は現実を見たくないだけなのだ。我々はもはやMDCの合意には縛られない。来るべき他世界との戦争に勝つべく、準備を始めている。このユリアも小惑星クラスから惑星クラスに強化したのだ。ルクレツィアがセルヴァを統制する能力も、インペリウム世界の時よりも強化してあったのだ」
「な……そんなことが……」
そもそも可能なのか。静弦は深い疑念を抱く。欺瞞情報である可能性が高い、そう心に書き留めておく。だがアレックスは冷静な表情を変えない。虚偽を吐く人間特有の動揺も焦りもない。彼は言葉を続ける。
「ユウキら統制派は最近それを察知してね。我々への締め付けを強め始めた。我々行動派のメンバーを社会的に葬り去ろうとしたり、離反を誘ったり、あの手この手を使ってだ。こちらも反撃が必要だった。離反しそうな統制派側のメンバーをこちら側のものにする。不可能ならセルヴァだけでも手に入れる……それも不可能ならセルヴァを破壊する」
「それで私とアリアを攻撃したわけですか。あなたと……量波が」
「ああ。君のセルヴァは一番弱そうだったからな。最も勝率が高い戦いを選ぶ。つまり最も弱い相手から戦いを挑む。戦争の基本だよ」
淡々とアレックスは言う。
「だが失敗した。物理的にも――そして精神的にも。だが私は、そうした戦いのデータを見て、君とアリアには興味が湧いてね。改めて我が派に誘おうと今試みているわけさ。量波は失敗したようだが」
「勝てないから仲間に誘う――順番が逆でしょう。量波のときにもそう思いましたが」
静弦は相手をきつく睨み据える。
「逆なものかね。順当だ。敬意は強い相手にしか払う必要はない。それに、セルヴァは多いほどよいが、ドミナは少数でよい。ドミナが多ければ多いほど、様々な議論が起き、派の方針がぶれる。微惑星クラスのセルヴァのドミナを、丁重に我が派に迎える必要を感じなかった。セルヴァを奪えればそれでよし、無理なら破壊、そう思っていた」
「私があなたと量波を撃退したから、考えを変えたと」
「そのとおりだ」
悪びれずアレックスは言う。それから、ぱくり、とジャムを食べた。
「今の君にはこれ以上のことは話せんな。だが、我々MDC行動派の方が人類の為になる、これだけは明言しておこう」
「人類の、為に……」
静弦はあきれた。いつまでそんなことを言い続けるつもりなのか。
静弦の様子を見て、アレックスは言葉を続ける。
「――安全保障面での我々の正当性は量波が説明したはずだ。よって私は別の面から説得を試みよう。君はおそらく、ユウキから、アリアを使って研究するなと言われてるはずだ。それで君の情熱は耐えられるのかね? MAPLに行っても同じだ。インペリウム世界の人間たちが七〇〇年以上も前に通った道を、試行錯誤しながら足?いて進むことに何の意味がある? そこにあるのは自己満足という虚無だけだ。七〇〇年先の未来の技術の、更にその先を追究しなければ、セルヴァが到来したこの世界においてもはや真の研究とは言えぬ。君は研究者を目指しているのか、それともただの自己満足の自慰をしたいだけなのか」
徐々にアレックスの言葉は熱を帯びていく。先程の淡々とした調子が嘘のように。
「――女性に『自慰』とは、紳士的ではありませんね」
静弦は僅かにそう皮肉を言うのが精一杯だった。
「だが内容には同意してもらえるはずだと確信している」
アレックスは紅茶をもう一口。
「ユリア。臨時超空間リンクをアリアに与えろ」
ユリアはアリアを見つめた。
「ちっ。しゃーねーな。手、出せよ」
命じるようにアリアに言う。アリアはむっとしてユリアをにらみ返す。続いて静弦を見遣る。
「……私との連絡に必要だ」
アレックスは意味を解説した。
「……受けなさい」
静弦は小さな声で命じる。
「……静弦様……!」
アリアは何か言おうとしたが、俯く。
「はい。仰せのままに」
アリアは手を差し出した。
ユリアはそっと、アリアの手の甲にキスする。
「ふん……ありがたく思えよ、ポンコツ」
が、そう憎まれ口を叩くのを忘れない。
「汚らわしい。静弦様のご命令がなければ受けませんでしたわ」
アリアはキスされた手の甲を撫でつつ、あからさまな嫌悪の視線をユリアに向けた。
「こっちだって」
ユリアもにらみ返す。
「これでよい」
アレックスは二人の対立には頓着せず、静弦を見て言った。
「いつでも連絡をくれたまえ。君とアリアには我が派は敬意を払うだろう」
言いながら、彼は立ちあがる。
「お勘定、お願いします」
下手な日本語で、そう店員に呼びかけた。
買い物をする気分ではなくなり、静弦は駅に向かっていた。アリアは静弦の腕にしがみつくことをせず、ただ手を握っている。先程の二人が仲の良い恋人同士に見えたとすれば、今はただの友人か姉妹のようだ。
雪が降り始めていた。
「ホワイトバレンタインデー……ですね」
アリアが言う。雪は静かに通りの上に降る。楽しげに笑い合う親子の上に。恋人たちの上に。一人で道行く人々の上に。雪が大気を降り行く中でも、街路に面したショウウィンドウは宝石箱のように煌めき、優しく街路を照らしている。
「ねえ、アリア」
静弦は隣のアリアを見返しもせず、じっと前方、やや上を見つめ、早足に歩きながら言う。
「はい。静弦様?」
「みんな虚無なんだろうか? この人達は、この街は、この私たちの文明は……」
アリアは数秒、黙っていたが、やがて言った。
「『明日の生活はあまりに遠い先にある。今日を生きよ』。我がローマの詩人の言葉です。この世界は虚無などではありませんわ。断じて。あなた様は、もしタイムマシンがあったとして、古代の人々の生活を見て、彼等は『虚無』と思われるのですか?」
「いいえ。でも、私たちは隠している。あなたたちの存在を。あなたたちセルヴァを、インペリウム世界を知ってしまった以上、私たちは……」
前へと進むべきなのではないか。静弦の心はその方向へ傾いていた。アリアは静弦の手を握る力をやや強くする。迷う静弦を元気づけるように。
「静弦様。わたくしは想像します。もし我が誇り高きインペリウム世界の人間が、彼等よりも遥かに進んだ科学文明に、突拍子もないやり方で接触したとき、どうするのか、と。彼等はまず、科学技術は何の為にあるかを考えるでしょう。それは勿論、市民の生活のためにあるのです。市民の生活の質の向上の為にあるのです。まず、そのために役に立つのか、生活に混乱をもたらさないかを考えるでしょう」
「……もし、インペリウム世界が……あるいはインペリウム世界の技術を得た他の世界が攻めてきたら?」
アリアは頷いた。
「インペリウム世界については……あの世界に数百億の機械奴隷がいることは間違いありません。しかし、彼等は我がインペラートルのものでも、元老院のものでもありません。ただ誇り高きローマ市民ひとりひとりのもの。そして、市民たちは、それぞれの領地たるスペースコロニーで、一人一人が王侯貴族のように、数多の機械奴隷を従え豊かな暮らしをしております。わざわざ他世界に攻め込む動機は、鴻毛よりも尚、軽く微かなものでしょう。無論、我がローマ軍団は、その栄誉ある役割を終え、とうの昔に永久に解散しております。我がインペラ―トルの手には指揮する軍隊はなく、その地位は象徴的なもの……。カピトリウムの丘のヤヌスの神殿の門は、永久に閉ざされたままでございます」
市民一人一人が王侯貴族のように――。
それは真に理想的な社会のように思えた。
「でも他世界はどうかしら?」
アリアは大きく息を吐いた。
「そうですわね。疑心暗鬼は、人の常です。他の世界が、どう出てくるかはわからない――と」
心底残念そうに。
「それについては、私には説明すべき言葉はありません。なぜなら、私にも全く分からないのですから。ただ、人類のあり方を変えてでも、まだ見えぬ危機に備えるべきなのか――そのような問いのように感じられます」
そのとき。不意に背後から声が響く。
「それは正しいあり方よ。健全な疑いの心を失った人間や組織は、早晩足元を掬われ、滅びるでしょう」
その声に、静弦の心臓は跳ね上がる。反射的に振り向いた。黒髪のショートカット、切れ長の瞳が印象的な女性が、そこに立っていた。
「……雛森早苗、二尉」
結柵章吾の研究室の職員。――しかしそれは表の顔で、裏の任務は、彼と政府をつなぐ職員であり、MDC関係者。有り体に言って、スパイだ。
「今は一尉ね」
雛森はさりげなく訂正する。
「それは、おめでとうございます」
雛森は軽く頷いただけだった。探るように彼女を見つめる静弦の視線を受け止め、彼女を見返す。その瞳は優しげだが、それも演技かも知れない。
「先程のアレックス・コロリョフとの接触について、話を聞かせてもらおうかしら」
柔和な口調。だがその裏には明らかな強制の意志がある。
「……もし、拒否したら?」
「もう一度アリアは戦うことになるでしょうね」
間接的に雛森は告げる。
――そう。相手には結柵先生がついている。リヴィウスが。
静弦は肩にかけたバッグの紐を両手で握った。
「……いいわ。行きます」
黒塗りのバンが静かに道ばたに止まる。
「どうぞ。お姫様」
雛森はドアを開け、バンの中に静弦を誘う。その冗談めかした言葉――それでいて口調は全く平板で冗談のかけらもない――が、静弦の内臓を冷え上がらせる。静弦は無言でバンに乗る。続くアリア。雛森は助手席に座った。運転席には、体格のよい背広姿の男。
「出して」
雛森が短く指示すると、バンは静かに発進した。
「量波との接触は受け流したのに、アレックス先生との接触は気にする――この違いはなんです?」
「……亜鞠戸量波の時までは、ただの末端メンバーの単独行動の可能性があった。だから泳がせていたのだけれど、アレックス・コロリョフは行動派内でも重鎮だと我々は見做している。正直なところ、その彼があれほどあからさまにあなたに接触するとは思っていなかった。先の八王子での攻撃も彼によるものと分かったことだし」
そこで、アリアが口を挟む。
「……量波が末端メンバー? その分析は誤っていますね。私の見るところ、量波のセルヴァ・マキナ――ルクレツィアは行動派の中でもナンバーツーの実力ですよ。ルクレツィアは自分の能力を隠せる。ヴァレリアがリヴィウスに報告したと思いますが」
「そのようね。しかし確信が持てず、その可能性は可能性のままとどめている」
「――判断が遅いのは致命的ですね、MDC統制派は」
雛森は苦虫をかみつぶしたような顔をする。
「……アレックス先生があのユリアのドミヌスだと、いつから分かっていたんです?」
今度は静弦が聞いた。
「候補は複数いたわ。一人ずつ監視し、追い詰め、その結果彼が最も怪しいと判明したのはつい最近よ。監視がきつくなった次の日、彼は種明かしをするようにユリアを伴い始めた。これは警告でもあった。効果的な警告だったわ。もはや彼に手出しはできなかった。ただおとなしく国外に出て行ってくれるのを待つのみ」
「私に教えてくれても良かったじゃないですか」
「秘密を知る者はそれだけ危険に近づく」
雛森はぴしゃりと言う。
「それに、あなたを泳がせて、どう動くかを確認する必要もあった。例えば、我々が教えないのに、あなたが能動的にコロリョフに会いに行けば、それはあなたとコロリョフの何らかのコネクションを意味する……」
(――バカバカしい。MAPLで何か聞きたいことがある場合も、会いにいったに違いないのに)
「亜鞠戸量波と友人同士になったあなたが、いつの間にか行動派に寝返っていても不思議はないわ」
「疑うことしかできないんですね」
「それで今まで生きて来れたのよ。私も、この国もね。この世界にいるのはポリアンナだけじゃないの」
「『怪しいところ探し』ですか。素敵な遊びです。さぞやポジティヴな人生が送れることでしょう」
静弦はカバンからヴェープを取り出した。
「よろしいですか?」
相手から拒否されても吸うつもりだった。もともと、この状況で静弦の方が充分嫌がらせを受けている。ヴェープの煙ぐらいでは、仕返しにしても全く足りない。お釣りが山のように積み上がるだろう。
「どうぞ。我々としてもまずはあなたに落ち着いて欲しいからね」
「そうですか」
寧ろ相手に望まれている行為だと知らされて、急に静弦は吸う気がなくなった。それでも意地でリキッドをセットし、ヴェープの蒸気を吸い込む。
シトラスの香りが車内に漂う。
「あら、良い香り。ヴェープが敬遠される習慣が理解できないわね」
雛森は微笑みかける。
――ご機嫌取りのつもりだろうか。それとも何かの皮肉?
静弦はヴェープを咥えながら、横目で助手席の雛森を見遣る。
数秒、間があった。
「何を言ったのかしら、彼は」
静寂を破るが如く――といった風に、雛森が尋ねてくる。単刀直入、という言葉がまさに相応しい問いかけ。
「私と彼の秘密ですが。簡単に他人にバラすようでは、誰も私に秘密の相談を持ちかけてくれなくなります」
「一般的にはね。でも彼もあなたが当局に彼との話の内容を打ち明けることは織り込み済みだと思うけど」
バンは高速に乗ったようだ。徐々にスピードを上げていく。
「おそらく、彼は『これは秘密だ、誰にも言うな』とは一言も言ってないはずよ」
「それは――確かに」
静弦はヴェープを咥えたまま腕を組んだ。胸を支えるように。二、三時間ショッピングで歩き回り、ブラジャーの紐を通じて肩にかかる荷重がそろそろ辛くなっていたので、胸を支えたかった事情もある。
腕を組みつつ彼女はしばし考え、アレックス・コロリョフの秘密を守る義理が自分に全く無いことに気づいた。雛森や、そしてその背後にいるであろう結柵や日本政府のやり方は気に入らないが、あのユリアを静弦とアリアにけしかけたアレックスの方がもっと気に入らない。
組んでいた腕を解き、ヴェープを口から離す。ふう、と蒸気を吐きつつ、バンの天井を眺めてから、雛森に視線を移す。
「内容は量波と同じですよ。MDC行動派に誘われました」
「そう」
予想通りだったようで、そっけなく雛森は言った。残念そうな響きを帯びていたのが、静弦には若干痛快に思えた。
「もうひとつ。おそらくあなた方には重要かと思いますが、彼の主張に依ればあのセルヴァは小惑星クラスから惑星クラスに改造したそうです。ルクレツィアの能力も従来から強化していると」
雛森は眉根を寄せた。
「まさか。そんなことが」
静弦は首を振る。
「ブラフだろうと思いますが、私にも確証はありません」
そう付け足す。
「それで全部?」
雛森は更に期待しているようだ。静弦はヴェープをひとつ吸う。
――臨時超空間リンクのことは言うべきか。
だが同時にアレックスの言葉が静弦の頭を支配した。
君は研究者を目指しているのか、それとも――。
彼女は唇を噛む。
「いえ、全部です」
雛森はしばらくじっと静弦の表情を伺っていたが、やがて微笑んだ。
「そう。ありがとう。悪かったわね、付き合わせて。送るわ、家まで」
東京国際学生館まで雛森の車で送ってもらった後、静弦はベッドに寝転がっていた。頭の後ろで手を組んで、天井を見つめている。睨むように。或いは訝るように。
(――アレックス先生の話には理がある)
彼女はそう感じてしまう自身を否定できない。
(――研究のこと。本当に耐えられるのか。このままずっと、インペリウム世界の人々の辿った道を追いかけ続けることに。人類社会に真の意味では貢献できていないという虚無に……)
静弦は首を振った。
(――いや……)
「静弦様、眠るなら電気は消すべきですわ……」
キッチンで洗い物を終えたアリアが近づいてきて、ベッドの静弦に話しかける。
「いや……寝てるわけじゃないよ。考え事」
静弦はぼそりと呟く。アリアはじっと静弦を見つめた。
「静弦様、お隣、失礼してもよろしいでしょうか?」
「ん? いいけど?」
静弦はベッドの隣のスペースをやや空ける。これまで、アリアは頑なに「わたくしは機械奴隷でございますから」と言い、ソファで寝ることを続けていた。だが、バンクーバー、台湾での戦いからは、となりに寝ることを常としていた。
「静弦様……」
アリアは静弦に寄り添う。
「わたくしが、インペリウム世界で一〇年間考えていたことは、ただ一つでした」
「うん」
続きを促す。
「特別な何かになりたい……ずっとそう思っていました。でもわたくしはそうはなれませんでしたわ。我が主人の寝所には、わたくしの他に、用途がわたくしと同じセルヴァが五体ほどいました。主人はその日の気分によって、誰を使うかを決めておりました」
すんすんと鼻をすする音がする。
――泣いている。
静弦の腕は自然にアリアの肩を抱き寄せていた。アリアは静弦に身を寄せ、胸にすがりつき、その豊かな膨らみに頬ずりする。
「わたくしたちの『個性』といったものは、わたくしたちの本体のブラックホールを擁する娘宇宙のパラメータの設計段階でおおよそ決まっております。しかし、宇宙誕生の瞬間の量子ゆらぎまでは制御できません。この宇宙で言えば『宇宙背景輻射』のようなものは、全くの偶然に形成され、わたくしたち一体一体に固有なキャラクターの基盤を形成します。故に、主人の為の話し相手や伽の相手の為のセルヴァ、として設計されたわたくしも、同僚とは異なる話し方や、ウィットのポイント――などを持っていると自負しておりました」
「うん」
静弦はその時のアリアの心を思った。想像もつかなかった。ただ、結柵に「楽しいこと」を提案されたときの屈辱を何倍にも濃縮して、一〇年に亘って飲み込み続けた時を想像した。アリアの肩を抱く手が強くなった。静弦の腕はアリアの肩から細い腰に回り込み、ぐっとアリアを引き寄せた。
「静弦様」
アリアは静弦の首筋に両手を回す。そのまま、耳元で言葉を続ける。
「けれど主人には既に言葉をしゃべるなと言われておりましたから、伽のお相手をするときにどういう姿勢をするのか、どういう体勢をするのか、できるだけ主人に気持ちよくなってもらおうと、そこで個性を出して認めてもらおうとしましたわ。でも、それもくだらないからやめろと言われ……。ただの人形としてわたくしは一〇年を過ごしました。誇らしく思っていたはずのわたくしの胸や腰の曲線が、憎らしくなってしまうほどに、ただただそれだけの為に使われておりました」
「……もう、話さなくて良いよ、そんなこと」
かすかな、乾いた笑い声。
「ひどいです。『そんなこと』なんて。わたくしの一〇年の人生のほとんどが、『こんなこと』ですのに」
静弦にはもう何も言えなかった。
「静弦様。どうか、お好きな方を選択してくださいまし。わたくしは、あなた様のアリアは、統制派でも行動派でも、どちらでもついていきます。統制派の支配する世界は、確かに研究者としてはお辛いでしょう。真の意味で特別な存在にはなれないのかもしれません……。ユリア・セルヴァも、そしてルクレツィア・セルヴァも、確かにわたくしにとって憎むべき存在ですが、わたくしはそんなことより、あなた様の心が遙かに心配です。あなた様に、わたくしが経験したような虚無を味わわせるのだけは、わたくしは嫌でございます。どうか、あなた様の望むように……」
「そうね」
静弦は呟いた。アリアの絹のような柔らかな金髪を撫でる。ユリアへの感情を抑えてまで、静弦に行動派を薦めてくれるアリアの優しさは嬉しかった。だが、心の中ではどちらが彼女を特別な存在として遇するのかも分からないとも思っていた。
行動派の支配する世界なら、研究者として特別な存在になれる――そうかもしれないが、アレックスは「ドミナは少ない方が良い」とはっきり言った。静弦自身ではなく静弦が支配するアリアの力だけが目的なのだろう。静弦からアリアを奪えると相手が思ったら、その隙を見せたら終わり――そんな結末が待っているような気もした。
そう考えると、どちらを選択しても結局、静弦には虚無しか待っていないようにも思えた。
――エゴとエゴがぶつかり合う世界、か……。
静弦は胸の内に渦巻く虚無感に息がつまりそうになった。
ただ、アリアの有機媒体の体温だけが救いだった。

