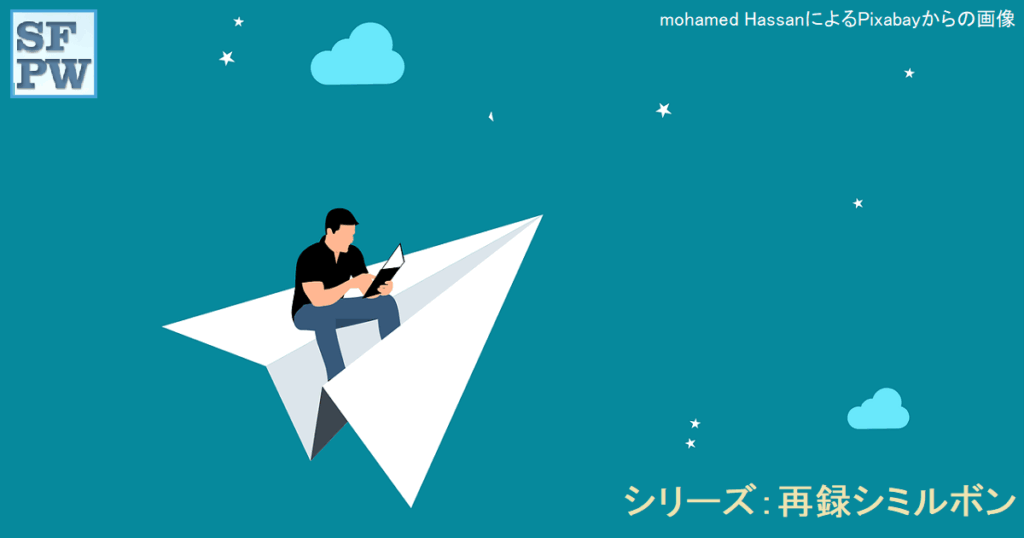
『ドン・キホーテ』再入門 その5 樺山三英
書物としての『ドン・キホーテ』
20世紀に入ると『ドン・キホーテ』に対するアプローチも多様になってきます。とくに顕著なのは、言語や書物という、作品そのものを構成する要素への関心が高まってくることです。この点に絡めてまっさきに挙げておきたいのは、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短篇「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」です。20世紀を生きる作家メナールが、17世紀を生きたセルバンテスに「なって」、再び『ドン・キホーテ』を書こうとするという奇妙なお話しです。短い作品なので、ぜひ一読いただければと思います。『伝奇集』という作品集に収録されています。試行錯誤の結果、メナールはセルバンテスの原文と一字一句違わない同じ文章を書くことになるのですが、ボルヘスはその両者の文章を並べ、そこから別々の意味を読み取っていきます。この短編が示唆しているのは、同じ言葉を用いてはいても、それが書かれた歴史的文脈によって(そして読みの手の受け止め方によって)、意味は無限に多様になるということでしょう。おそらくはこれと同じ原理を使って『ドン・キホーテ』は書かれていた。つまり騎士道物語という古びた言葉を、同時代に置き直すことで、まったく別の意味を生じさせるという手法で。ボルヘスはじつに手の込んだ仕方で、その事実を示してみせるのです。
続いてミシェル・フーコーの『言葉と物』(ちなみにこの本の序文は、ボルヘスの短編の引用から始まります)にも、『ドン・キホーテ』をめぐる一節があります。これは安易な要約を許さない難解な書物なのですが、ざっくり言うと、中世と近代の間の認識の断絶を扱った研究と言えます。中世人は世界を類似性の元で認識していた。風車を見れば巨人を思い、羊の群れを見れば軍勢を思う、といったように。しかし近代にさしかかると「言葉」という枠組が出来上がってしまい、こうした連想を阻害するようになる。この変化の境界線をさ迷っているのが、つまり騎士ドン・キホーテなのだというわけです。フーコーのもう一つの重要な指摘は、前篇と後篇の関係についての言及です。前篇が騎士道物語という先行テクストに即して書かれていたとすれば、後篇は前篇の内容それ自体に則って書かれている。要するに「「書物についての書物」それ自体についての書物」に変化している。ドン・キホーテは、こうして自らを書物の内に閉じ込め、ついには自身が書物そのものになってしまう。このように、あらゆる書物/言葉は、他の書物/言葉についての書物/言葉と化し、物の世界から浮遊していく。それが中世の終焉以降、人びとの認識にもたらされた変化と断絶だというわけです。
もう一人、マルト・ロベールという人にも触れます。フランスのドイツ文学研究者で、カフカのフランス語訳者としても知られています。彼女が『古きものと新しきもの』のなかで論じているのは、叙事詩の伝統についてです。ヨーロッパ文芸には、ホメロス以来の長い叙事詩の伝統があり、セルバンテスもカフカもその流れのなかに位置づけることができる。じっさいホメロスとセルバンテスは「すでによく知られた伝承の再話者/編纂者」という立場を共有している。そしてカフカ(彼もまた『ドン・キホーテ』の愛読者でした)は、この伝統を自覚的に継承した書き手なのだといいます。だからこそ、彼の描く人物はしばしば遍歴や放浪を運命づけられている。けれど近代以降の叙事詩の主人公は、もはや現実のなかを渡り歩くことができない。ドン・キホーテが書物と現実の合い間を遍歴していたのに対して、カフカ描くの主人公たちは、書物が織りなす象徴的な秩序のなかをあてどなくさ迷い歩くことしかできません。『城』や『審判』、「万里の長城」といった作品群が描く不条理は、こうした秩序からの脱出不可能性を描いているのではないか――。おおよそこれが彼女の指摘していることです。さきほどのフーコーの指摘と併せて読むと、たいへん興味深い議論になると思います。
近代社会と『ドン・キホーテ』
言語論/書物論としての『ドン・キホーテ』は、かくのごとく多様で複雑です。しかしそれとはまた別に、小説というメディアが社会においてどのような機能を果たしてきたか、という問題もあるのではないでしょうか。そうした視点からまず取り上げたいのが、現代作家ミラン・クンデラの文学論です。彼の『小説の技法』という本は、小説の歴史を通じて、近代社会そのものを見つめ直すたいへん野心的な評論集です。その第1章にあたるのが「不評を買ったセルバンテスの遺産」という『ドン・キホーテ』論でした。クンデラはまず近代哲学の歴史を概観し、それが「生の世界」を捕らえ損ねてきたと指摘します。そしてただ「小説」だけが、曖昧さと多義性に満ちた我々の生をとらえることができるのだと言います。そうした「小説の知恵」の源にあるのが、『ドン・キホーテ』だというのです。神の秩序により、善悪が定められていたのが中世。しかし近代の訪れとともに、そうした尺度は通用しなくなった。唯一の真理が、おびただしい数の相対的真理に解体されてしまう。そのような不確実性に満ちた世界をいかに生き抜いていけばいいのか。そのヒントを与えてくれるのが、この遍歴の騎士だというわけです。風車は巨人であるのかもしれず、羊の群れは敵の軍勢なのかもしれない。そうした惑いと躊躇いのなかを、臆することなく進んでいくこと。その意味で『ドン・キホーテ』は喜劇でも悲劇でもない。むしろ喜劇か悲劇を決定できない、本質的な多義性を有するがゆえに、この作品は偉大なのだとクンデラは言います。このように要約してしまうとやや味気ないのですが、すばらしい名文で綴られているので、ぜひじっさいに読んでもらいたい本です。
クンデラとも親交が深く、また近いスタンスを持つのがカルロス・フエンテスです。彼もまた『ドン・キホーテ』の熱烈な愛好者として知られています。彼の代表作『テラ・ノストラ』は、原著から40年以上を経て今年ようやく邦訳が出版されました。訳書で1000ページ超の怪物的作品。虚構と史実を交えて展開する一種のメタ歴史小説なのですが、このなかにはセルバンテスも登場しています。年代記作家ミゲルと名づけられた彼は、フェリペ2世の臨終に立ち合い、その最期を記録する役目を負います。その過程で、中世的秩序が終焉を迎え、近代社会が始まろうとする変化を、ひとりの騎士の物語として描こうと思いつくのです。つまりそれこそが『ドン・キホーテ』だったと、そういうお話です。もちろんこのエピソードは史実ではなくフィクションですが、その背後にはフエンテス独自の『ドン・キホーテ』読解が控えています。『テラ・ノストラ』と同年、フエンテスは『セルバンテスまたは読みの批判』という小著を刊行しています。これはいわば前者の副残物として産まれた評論なのですが、非常にユニークかつすぐれた『ドン・キホーテ』論として高く評価されています。
フエンテスがもっとも注目するのは『ドン・キホーテ』前篇と後篇の関係です。騎士道物語を読み耽り、ついに狂気に陥った男の物語――つまり「読む者」の冒険を描いたのが前篇でした。しかし後篇のドン・キホーテはむしろ「読まれる」存在に変わってしまっている。先述のとおり、後篇は「前篇の内容が作中世界でも出版されており、皆がドン・キホーテについての情報を共有している世界」が舞台になっています。そのなかを旅する騎士は、すでに書物のなかの人物であり、人々に読まれることによって実在性を保証されている。この変化の意味は何かと、フエンテスは問いかけるのです。そして『ドン・キホーテ』刊行当時のメディア環境に注意を促します。17世紀初頭、勃興しつつある市民階級を下支えしていたのは、印刷技術の急速な普及でした。大量の書物が刷られ流通することで、市民たちはそれまでにない情報を得ることができた。限られた層に占有されていた知識が、広く社会に開かれていく。このことが近代市民社会を生んだわけです。前篇から後篇の変化は、この推移を反映しているのではないか、というのがフエンテスの見解です。ドン・キホーテに体現される中世的世界像、それが多くの人々の「読み」に曝されることで、あたらしい世界像へと鋳なおされていく。古い一面的世界が、大勢の批判検討協議によって、多義的世界に刷新されていく。そうした過程に、近代民主主義の萌芽を見るわけです。いくらか牽強付会の感もありますが、これはやはり驚くべき読解ではないでしょうか。とくに前篇と後篇のあの謎めいた関係性について、これ以上に鮮明な「読み」を与えた例は他になかったように思います。
(初出:シミルボン「樺山三英」ページ2016年10月14日号)
