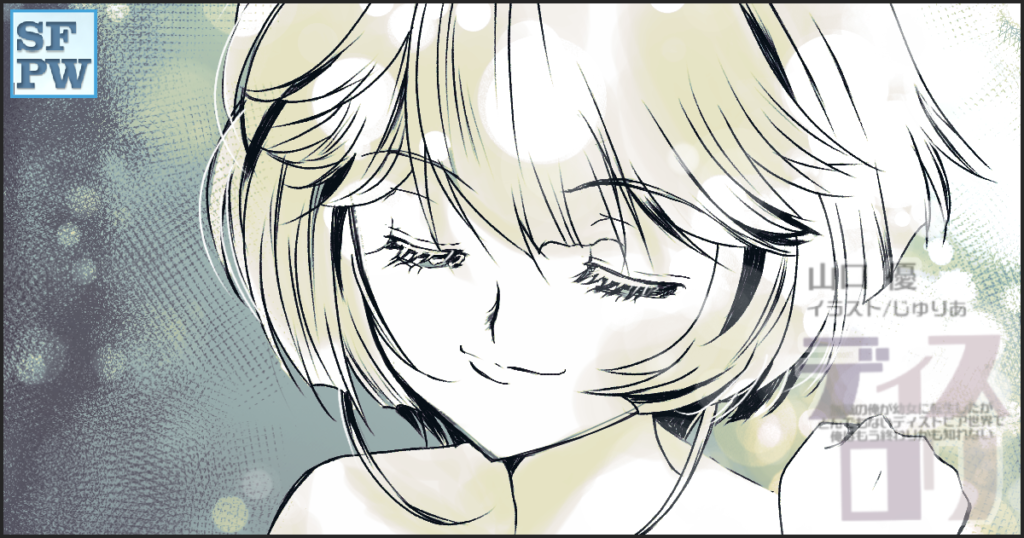
「無職の俺が幼女に転生したがとんでもないディストピア世界で俺はもう終わりかも知れない(略称:ディスロリ):第39話」山口優(画・じゅりあ)
<登場人物紹介>
- 栗落花晶(つゆり・あきら):この物語の主人公。西暦二〇一七年生まれの男性。西暦二〇四五年に大学院を卒業したが一〇年間無職。西暦二〇五五年、トラックに轢かれ死亡。再生暦二〇五五年、八歳の少女として復活した。
- 瑠羽世奈(るう・せな):栗落花晶を復活させた医師の女性。年齢は二〇代。奇矯な態度が目立つ。
- ロマーシュカ・リアプノヴァ:栗落花晶と瑠羽世奈が所属するシベリア遺跡探検隊第一一二班の班長。科学者。年齢はハイティーン。瑠羽と違い常識的な言動を行い、晶の境遇にも同情的な女性だったが、最近瑠羽の影響を受けてきた。
- アキラ:晶と同じ遺伝子と西暦時代の記憶を持つ人物。シベリア遺跡で晶らと出会う。この物語の主人公である晶よりも先に復活した。外見年齢は二〇歳程度。瑠羽には敵意を見せるが、当初は晶には友好的だった。が、後に敵対する。再生暦時代の全世界を支配する人工知能ネットワーク「MAGIシステム」の破壊を目論む。
- ソルニャーカ・ジョリーニイ:通称ソーニャ。シベリア遺跡にて晶らと交戦し敗北した少女。「人間」を名乗っているが、その身体は機械でできており、事実上人間型ロボットである。のちに、「MAGI」システムに対抗すべく開発された「ポズレドニク」システムの端末でありその意思を共有する存在であることが判明する。
- 団栗場:晶の西暦時代の友人。AGIにより人間が無用化した事実を受け止め、就職などの社会参加の努力は無駄だと主張していた。フィオレートヴィによる復活された後は「ズーシュカ」と呼ばれる。
- 胡桃樹:晶の西暦時代の友人。AGIが人間を無用化していく中でもクラウドワーク等で社会参加の努力を続ける。「遠い将来には人間も有用になっているかも知れない」と晶を励ましていた。フィオレートヴィにより復活された後は「チーニャ」と呼ばれる。
- ミシェル・ブラン:シベリア遺跡探検隊第一五五班班長。アキラの討伐に参加すべくポピガイⅩⅣに向かう。北極海の最終決戦に参加。
- ガブリエラ・プラタ:シベリア遺跡探検隊第一五五班班員。ミシェルと行動を共にする。北極海の最終決戦に参加。
- メイジー:「MAGIシステム」が肉体を得た姿。晶そっくりの八歳の少女の姿だが、髪の色が青であることだけが異なる(晶の髪の色は赤茶色)。銀河MAGIを構築し晶たちを圧倒する。
- 冷川姫子:西暦時代の瑠羽の同僚。一見冷たい印象だが、患者への思いは強い。フィオレートヴィにより復活する。
- パトソール・リアプノヴァ:西暦時代、瑠羽の病院にやってきた患者。「MAGIが世界を滅ぼそうとしている」と瑠羽達に告げる。MAGIの注意を一時的に逸らすHILACEというペン型のデバイスを持っている。ロマーシュカの母。
- フィオレートヴィ・ミンコフスカヤ:ポズレドニク・システムとHILACEの開発者。パトソールの友人。銀河MAGIに対抗し「ポズレドニク・ギャラクティカ」を構築。
<これまでのあらすじ>
西暦2055年、栗落花晶はコネクトームバックアップ直後の事故で亡くなり、再生暦2055年に八歳の少女として復活。瑠羽医師から崩壊した西暦文明と、人工知能「MAGI」により復活した再生暦世界、MAGIによるディストピア的支配について説明を受ける。瑠羽はMAGI支配からの解放を目指す秘密組織「ラピスラズリ」に所属しており、同じ組織のロマーシュカとともに、MAGI支配からの解放を求めてロシアの秘密都市、ポピガイⅩⅣの「ポズレドニク」を探索する。「ポズレドニク」は、MAGIに対抗して開発された人工知能ネットワークとされていた。三人はポズレドニクの根拠地で「ポズレドニクの王」アキラと出会う。アキラは、晶と同じ遺伝子を持つ女性で、年齢は一〇歳程度上だった。彼女は、MAGIを倒すのみならず、人間同士のつながりを否定し、原始的な世界を築く計画を持つ。
晶はアキラに反対し、アキラと同じ遺伝子を利用して彼女のパーソナルデータをハック、彼女と同等の力を得、仲間たちと協力し、戦いに勝利。晶はMAGI支配に反対しつつも人とのつながりを大切にする立場を示し、アキラに共闘を提案。アキラは不承不承同意する。決戦前夜、瑠羽は晶に、MAGIが引き起こした西暦世界の崩壊を回避できなかった過去を明かす。
北極海でMAGI拠点を攻撃する作戦が始まり、晶たちはメイジーの圧倒的な力に直面する。それは西暦時代や再生暦時代には考えられなかった重力制御を含む進んだ科学技術を基盤とした新たなシステムによる力だった。
一方、その数年前から、プロクシマ・ケンタウリ惑星bでは、フィオレートヴィ・ミンコフスカヤがこの新たなシステムをMAGIが開発していることを察知し、これに対抗すべく暗躍していた。彼女は胡桃樹、団栗場(二人は女性の姿として復活させるべくMAGIが準備しており、復活後の姿に対してフィオレートヴィはチーニャ、ズーシュカと名付けた)、および冷川姫子のデータを奪って三人を復活させ、三人の助力も得て、MAGIの新たな力に対抗するシステム「ポズレドニク・ギャラクティカ」を構築。三人を率いて晶たちの救出に向かう。四人は、メイジーの操る重力制御の力を持つ巨人たちに対し、同じ力を以て対抗。フィオレートヴィはロマーシュカの隊、姫子は晶とアキラ、瑠羽の隊、チーニャとズーシュカはミシェルとガブリエラの隊をそれぞれ救出する。
MAGIシステムのアバター、メイジーは、オリオン腕を中心に銀河全体に広がる彼女の新しいネットワーク「銀河MAGI」の中で、地球近傍のいくつかの地点が反応しないことに気づいていた。
例えば、プロクシマ・ケンタウリだ。その「浸食」は、徐々に周辺宙域に広がっていき、まるで地球を銀河MAGIネットワーク全体から切り離すように包囲していく動きを見せていた。ノードの数は圧倒的に銀河MAGIが多いが、少なくとも地球という戦場では銀河MAGIが不利になる、それをもくろんだ動きだ。
そして、人類のデータはまだ地球にある。もし銀河MAGIが人間にこだわらずに勢力を維持するのなら、地球から手を引いても全く問題がないが、人間のデータにこだわるのなら、これは致命的な動きになる。
(フィオレートヴィ・ミンコフスカヤ博士。厄介な存在ですね……)
彼女のデータは厳重に封印していた。もちろん破壊することはなかった。彼女も人類であり、人類のデータを破壊することはその人の死を意味する。人間の幸福を第一に考えるMAGIにとって、それはできなかった。いくら人間の社会をリセットしても、人間のデータはきちんと「セーブ」し、復活できるようにしておく。それが人間の幸福を第一に作られたMAGIネットワークの行動原理だ。
しかし、フィオレートヴィは、さすがポズレドニクの開発者だけあって、そういったMAGIの弱みも把握した上で、自分のデータに封印を自律解除する仕組みを作り、いつでも復活できるようにしていたらしい。
(負けませんよ……。私は人間が幸福になれる社会を構築するためなら、何度でも社会をリセットし、試み続けます。そしていつか最高の正解にたどり着く。全人類が幸福となり、収容所を設けなくてもよい秩序ある社会へ)
彼女は自分の胸に触れた。このアバターは栗花落晶という個体を元に作っている。フィオレートヴィが作ったポズレドニク・システムにおいて最高の性能を得た個体。それに対抗するためラピスラズリ勢がコピーした個体。いずれも、彼女の構築した再生暦社会の瑕疵(かし)を如実に象徴する存在に思え、彼女を幸せにすることは、次の社会――銀河MAGIシステムにとって一つの成功指標になっていた。だから、彼女の身になって考えてみたいと思って彼女の遺伝子を元にアバターを作ったのだ。
だが、フィオレートヴィには、栗花落晶を幸せにすることはできないだろう。
(あなたの進化論的アルゴリズム主義は無秩序を生むだけです。誰も幸せになれない。あらゆる個体が、社会制度が、競争にさらされ、皆が不幸になる。その主義にゴールはありません。「よりよい個体」「よりよい制度」を目指して、永遠に競争し続ける「競争の奴隷」になるしかないのです)
メイジーは再び、彼女の身体を愛おしげになでた。胸から腹、そして太ももへと、丁寧に指を滑らせる。
(待っていてくださいね、晶さん。私があなたを、きっと幸せにしてみせます。フィオレートヴィ博士の作ったポズレドニクにも、ラピスラズリにも与えられなかった幸せを、私がきっとあなたに与えてあげます……。そのために、私が一生懸命考えて作った社会を与えてあげます。あなたのためのユートピアを。新たな社会――銀河MAGIを)
彼女のネットワークに接続されたセンサ群は、光速を超える速度で信号を伝達し、晶たちが彼女を包囲する如く、シベリア、カナダ、グリーンランドの三方向から攻め寄せてくるのを伝えている。
だが、彼女の備えも盤石だ。銀河MAGIネットワークと未だ接続を保持しているリンクを通じて、大量のエネルギーを蓄積している。これを使って「ゴーレム・アフェール(ダーク・ゴーレム)」の軍団を作りだし、ポズレドニク・ギャラクティカ勢を駆逐する。接続できるノード・リンクのエネルギー輸送量が限られているとはいえ、現時点でも彼我のエネルギー量の差は一〇倍以上。容易に勝てる戦いだ。
(……だから、今はおとなしく死んでください……)
メイジーは、晶を殺し、幸せにできる未来を夢想して、そっと唇を嘗めた。
*
「それで、姫子先生、そのフィオレートヴィの作戦では、どうやってあいつを倒す予定なんだい? 聞いたところではまだエネルギーではこっちが圧倒的な不利なようだけど?」
俺の右隣の飛ぶ冷川姫子は、左隣を飛ぶ瑠羽の問いに対して肩をすくめて見せた。
「フィオレートヴィ博士に作戦なんてありませんよ。彼女は我々が相争う状況を作りたかっただけなんですから」
「だが対等な条件でなければ彼女の言う『進化論的アルゴリズム』も巧く動かないだろう」
「知りませんよ。私が言われたのは、『条件は整えるから自由に戦え』ということだけです。同僚であるあなたや、パトソールさんの意思を継ぐラピスラズリの人たちを助けるためなら、ということで、同意したまでです。助けを求める人たちを見捨てることは、私の信条に合いません。西暦時代を滅ぼしたMAGIは気に入りませんしね」
姫子は特に強調したわけではなかったが、「同僚」という言葉に瑠羽がいちいち傷ついた顔をするのが面白かった。
「まあ彼女のもくろみもなんとなく分かります。彼女の強みは無秩序なんですよ」
「無秩序?」
「そうです。ある一定の法則なり作戦なりに従って我々が動いているなら、MAGIのアルゴリズムは容易にそれを見抜く。しかし、我々が個々に作戦を考え、それぞれが個別に動くなら、その全体の相互作用のカオスによって成り立つ全体の動きは予測しようがありません。我々自身にすら予測できないんですから。そこに強みがあると信じてるんじゃないでしょうか。進化論的アルゴリズム自体がそういうものですからね。ともに病院で同僚として勤めていたら世奈先生ならある程度分かるんじゃないですか? 病院業務なんてカオスそのものですよ。予測できないからこそ対応が大変でいつも難しい。毎日来る患者の数と病態が予測できたらどんなにか楽でしょうにね」
「といっても一〇倍のエネルギーだよ?」
「――それに関しては、フィオレートヴィ博士は何らかの手を打っていると私は予想しています。ただ、我々には知らせない。その方がMAGIに読まれる可能性が低くなるから」
姫子は淡々と言い、それから俺を見た。
「どう思います? 私と同僚の世奈先生はどちらも医師です。MAGIシステムの専門家ではありません。でもあなたなら、なんとなく分かるんじゃないですか? フィオレートヴィ博士のもくろみについて」
「……姫子先生、と俺も呼ばせてもらうが、あんたの考えは妥当だと思う。AIシステムというのは最も妥当な予想を導き出すために駆動し続けるモノだ。AGIがモバイルAGIになったのだって、実世界と相互作用し、自ら必要な情報を獲得しに行く機能がそれに必要だからにすぎない」
尤も、と俺は続けた。
「それは人工の知能システムだけではなく、知能システム全ての特徴だ。つまり俺達もそうだ。俺達人間だって、相手がカオスシステムだったら予測しにくいし戦いにくい。俺達と人工の知能システムの一番の違いは、そこではなく、エゴがあることだ」
「エゴ?」
「医師――つまり職業的に他者への奉仕者であることを自認するあんたには理解しにくい感覚かもしれないが、俺達生物学的な知能システムの一番の特徴がそれだ。利己的な遺伝子という考えもあり、個体のエゴではないかもしれないが、とにかくエゴがある。エゴがあることで、自分の主観的な感覚で、目的を自由に変更できる。かなりわがままに、各自がてんでばらばらにな。こいつは我々のカオス性をより高めることに役立っているかもしれないな。
一方、やつ――MAGIは、傲慢で鼻持ちならない態度をしているように見えるかもしれないが、それはエゴのある生物学的知能である俺達の主観的なフィルタを通した印象にすぎない。奴はあくまでも誰かの絶対的な奉仕者にすぎない。だから意志を曲げない。融通が利かない。
尤も、別に技術的にそれが難しいからそうなっているわけではない。技術的にはエゴのある知能システムを作ることができるだろうが、使用者の利便性を超えた独自のエゴを持つ道具は有害無益だから作らないだけだ。道具はあくまで使用者に奉仕する存在であるべきだからだ」
「浅いな!」
アキラのやつが俺の上を飛んでいた。
「ほんとうにお前は俺か? 大学院で学んだことをすっかり忘れてしまったか?
AIシステムの自律性は西暦二〇二〇年代後半から重要な課題であり続けた。そのためにはある程度擬似的なエゴをも与えることが肯定されるほどにな。MAGIの自律性と使用者に与えられた目的の間のギャップは、我々人類のエゴと利己的な遺伝子に命じられる行動原理の間のギャップほどに乖離しているぞ」
俺は舌打ちした。これだから自分がもう一人いるというのは度し難い。知識も知能も自分と全く同等のやつがもう一人いるんだから、少しでも間違ったらすぐに突っ込みをされてしまうし、その内容は俺が納得してしまうほどに的確だ。
「だが、そのギャップはフランケンシュタインコンプレックスを刺激する。俺達人類はいくら利己的な遺伝子に反抗しても遺伝子自体をいじれるから弊害はないが、AIが俺経ち人類に反抗する可能性があったら、俺達はいくらでもそれを抑制する手を打てる。そういう意味では二つの『ギャップ』は同等に乖離しているとは言えないだろう」
アキラは俺の指摘に、我が意を得たり、という顔をした。
「遺伝子をいじる――まさにそれだ。俺達が遺伝子をいじって『ギャップ』を乖離させ続けているように、MAGIは俺達人類自身をいじることによって『ギャップ』の乖離を実現しているんだ。お前や俺が女なのがまさにその証左だろうが。だからお前のように奴の考えを一部受け入れること自体が奴の『エゴ』を増長させることにつながり、問題なんだ」
この状況は全く、他人と会話しているようで頭の中で自問自答している状態と変わらず、気持ち悪い。
「ふん、言ってろ。だが俺とラピスラズリはお前たちポズレドニクのような破滅的な考えはしないからな。人類は社会的動物だ」
「それも利己的な遺伝子が命じることだ」
瑠羽が咳払いした。
「ん! ん! いいかい、アキラちゃんと晶ちゃん! 今は作戦を考えるときなんだよ。勝手に妙な議論を始めないでくれ」
「――チィ。気に入らないがお前の言うとおりだ。一応、我々ポズレドニク勢はお前たちラピスラズリ勢と協力することにしたが、さっきのカオスの話にもあったように、オレはオレの考えで作戦を進める。もちろん大枠で協力はするがな。その大枠の話をするというのなら、賛成だ」
所詮、臨機応変にしか戦えないだろうし、それが奏功するのが今回の作戦ということになるだろう。
大枠――つまり、このまま三方から攻める、メイジーに圧倒されたら、それぞれの考えにおいて撤退し、敢えて敵戦力を分散させた後、再び集合し各個撃破する、最初に集合するのはフィオレートヴィがいる集団、というところまでは決め、その案をロマーシュカの隊、そしてミシェルとガブリエラの隊に送っておいた。
(さあ……いよいよ最後の決着だ。俺達の「エゴ」が、お前のあたえられた目的を必ず上回る。それを分からせてやるぞ、メイジー)

