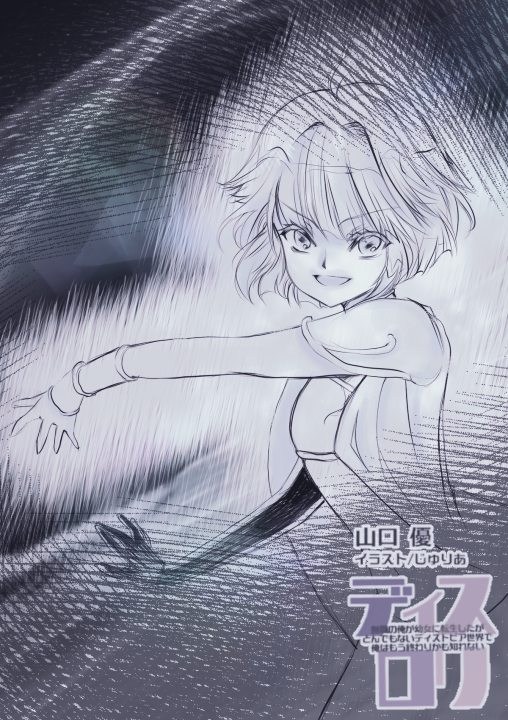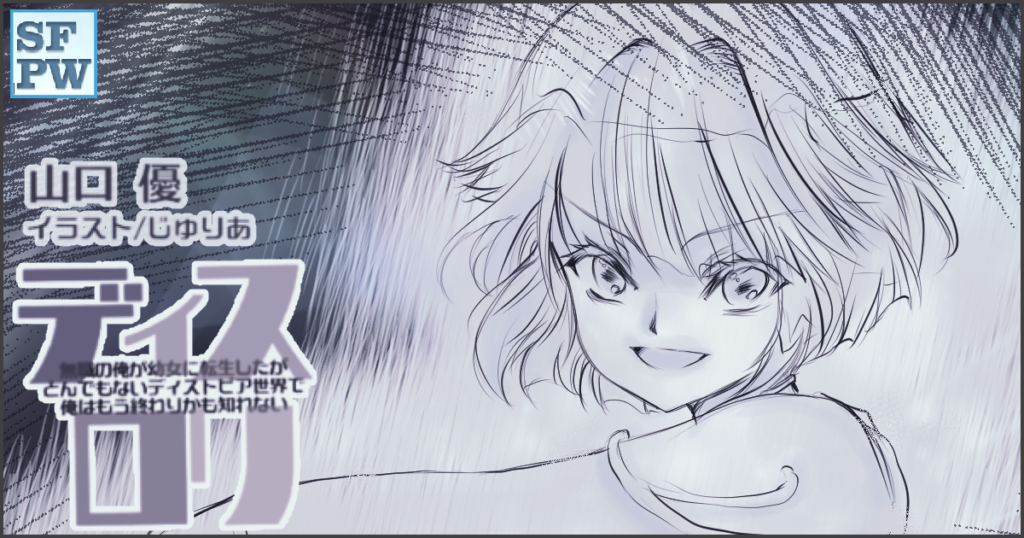
「無職の俺が幼女に転生したがとんでもないディストピア世界で俺はもう終わりかも知れない(略称:ディスロリ):第35話」山口優(画・じゅりあ)
<登場人物紹介>
- 栗落花晶(つゆり・あきら):この物語の主人公。西暦二〇一七年生まれの男性。西暦二〇四五年に大学院を卒業したが一〇年間無職。西暦二〇五五年、トラックに轢かれ死亡。再生暦二〇五五年、八歳の少女として復活した。
- 瑠羽世奈(るう・せな):栗落花晶を復活させた医師の女性。年齢は二〇代。奇矯な態度が目立つ。
- ロマーシュカ・リアプノヴァ:栗落花晶と瑠羽世奈が所属するシベリア遺跡探検隊第一一二班の班長。科学者。年齢はハイティーン。瑠羽と違い常識的な言動を行い、晶の境遇にも同情的な女性だったが、最近瑠羽の影響を受けてきた。
- アキラ:晶と同じ遺伝子と西暦時代の記憶を持つ人物。シベリア遺跡で晶らと出会う。この物語の主人公である晶よりも先に復活した。外見年齢は二〇歳程度。瑠羽には敵意を見せるが、当初は晶には友好的だった。が、後に敵対する。再生暦時代の全世界を支配する人工知能ネットワーク「MAGIシステム」の破壊を目論む。
- ソルニャーカ・ジョリーニイ:通称ソーニャ。シベリア遺跡にて晶らと交戦し敗北した少女。「人間」を名乗っているが、その身体は機械でできており、事実上人間型ロボットである。のちに、「MAGI」システムに対抗すべく開発された「ポズレドニク」システムの端末でありその意思を共有する存在であることが判明する。
- 団栗場:晶の西暦時代の友人。AGIにより人間が無用化した事実を受け止め、就職などの社会参加の努力は無駄だと主張していた。
- 胡桃樹:晶の西暦時代の友人。AGIが人間を無用化していく中でもクラウドワーク等で社会参加の努力を続ける。「遠い将来には人間も有用になっているかも知れない」と晶を励ましていた。
- ミシェル・ブラン:シベリア遺跡探検隊第一五五班班長。アキラの討伐に参加すべくポピガイⅩⅣに向かう。
- ガブリエラ・プラタ:シベリア遺跡探検隊第一五五班班員。ミシェルと行動を共にする。
- メイジー:「MAGIシステム」が肉体を得た姿。晶そっくりの八歳の少女の姿だが、髪の色が青であることだけが異なる(晶の髪の色は赤茶色)。
- 冷川姫子 :西暦時代の瑠羽の同僚。一見冷たい印象だが、患者への思いは強い。
- パトソール・リアプノヴァ:西暦時代、瑠羽の病院にやってきた患者。「MAGIが世界を滅ぼそうとしている」と瑠羽達に告げる。MAGIの注意を一時的に逸らすHILACEというペン型のデバイスを持っている。ロマーシュカの母。
- フィオレートヴィ・ミンコフスカヤ:ポズレドニク・システムとHILACEの開発者。パトソールの友人。
<これまでのあらすじ>
西暦2055年、栗落花晶はコネクトームバックアップ直後の事故で亡くなり、再生暦2055年に八歳の少女として復活。瑠羽医師から崩壊した西暦文明と、人工知能「MAGI」により復活した再生歴世界、MAGIによるディストピア的支配について説明を受ける。瑠羽はMAGI支配からの解放を目指す秘密組織「ラピスラズリ」に所属しており、同じ組織のロマーシュカとともに、MAGI支配からの解放を求めてロシアの秘密都市、ポピガイⅩⅣの「ポズレドニク」を探索する。「ポズレドニク」は、MAGIに対抗して開発された人工知能ネットワークとされていた。三人はポズレドニクの根拠地で「ポズレドニクの王」アキラと出会う。アキラは、晶と同じ遺伝子を持つ女性で、年齢は一〇歳程度上だった。彼女は、MAGIを倒すのみならず、人間同士のつながりを否定し、原始的な世界を築く計画を持つ。
晶はアキラに反対し、アキラと同じ遺伝子を利用して彼女のパーソナルデータをハック、彼女と同等の力を得、仲間たちと協力し、戦いに勝利。晶はMAGI支配に反対しつつも人とのつながりを大切にする立場を示し、アキラに共闘を提案。アキラは不承不承同意する。決戦前夜、瑠羽は晶に、MAGIが引き起こした西暦世界の崩壊を回避できなかった過去を明かす。
北極海でMAGI拠点を攻撃する作戦が始まり、晶たちはメイジーの圧倒的な力に直面する。それは西暦時代や再生暦時代には考えられなかった重力制御を含む進んだ科学技術を基盤とした新たなシステムによる力だった。
一方、その数年前から、プロクシマ・ケンタウリ惑星bでは、フィオレートヴィ・ミンコフスカヤがこの新たなシステムをMAGIが開発していることを察知し、これに対抗すべく暗躍していた。彼女は胡桃樹、団栗場(二人は女性の姿として復活させるべくMAGIが準備していた)、および冷川姫子のデータを奪って三人を復活させ、三人の助力も得て、MAGIの新たな力に対抗するシステム「ポズレドニク・ギャラクティカ」を構築しつつあった。
「詭弁だな」
俺はメイジーに向かって言い放つ。同時に、俺は思考を司る開闢MAGIC「グネーハ」を密かに口の中で唱えていた。その瞬間、レベル99の俺の権限に従って、ポズレドニクが掌握する演算資源の大半が、「この状況をいかに切り抜けるか」という命題を解くことに費やされることになった。
「詭弁?」
メイジーが問い返す。
「新たな世界に転生(ログイン)だと? それで人間が全て幸せにできると思っているのか? お前はすでに二度、失敗しているんだぞ」
「失敗するなら、また作り替えるまで。私は失敗を経て新たな学びを得ることのできる超知能ネットワークシステムです。西暦時代の失敗を経て、私は、あなたがた人間にできる程度に簡単でありながらそれなりに意味があり、楽しめる仕事を創り出し、配布する体制を整えました。無論、人と人のつながりも担保できる形で。しかしそれでも人と人がつながっているかぎり、諍いは絶えず、それによって絶望する人もいる……。残念なことです。できるだけの救済手段は用意していたつもりなのですけれどね……」
アキラを意味ありげに見て、メイジーは言う。
「きさま……」
アキラの横顔が蒼白になり、ぎりりと歯をきしませている。俺はああいう顔を知っている。俺が西暦時代、就職活動をしていて「お祈りメッセージ」を送られるたびにしていた顔と同じだ。お前は失敗作だというレッテルを貼られた時の、最大限の怒りを含んだ顔だ。
「人と人がともにあれば諍いが起き、絶望する人もいる。にもかかわらず、人は人と交じり合いたい。人は社会的存在だから。これを同時に達成するにはどうすればいいでしょう? 私は考えました。そして答えを得たのです。そのためには、まだまだエネルギーが足りないのだと。全ての人間の自由な欲望をそのまま達成し、かつ親しく他者とつながりあうには、圧倒的に資源が足りないのだと……」
「それで、システムを銀河全体に拡張するというわけかい?」
瑠羽があきれたように問う。
「それが最も正当な解決策でしょう? 私は、皆様人間一人一人の真の幸せを願っているのです……。人間の皆様には、自由にできる惑星を一つ一つさしあげます。あなたたちの王国です。自由に支配すればいい……。同時に、親しい人々と交わるための超光速通信も用意しようではありませんか。意のままになる存在が必要なら、いくらでもロボットを用意しましょう。さあ、もう時間です。新たな世界へ」
メイジーは両手を広げた。
「皆が幸せになれる世界、『MAGI・ギャラクティカ』――銀河暦の始まりです……!」
メイジーが引き連れる光の翼を持つ巨人たちが、一斉にその槍を掲げ、俺達に向ける。暗黒の光が俺達に向かってきた。
その攻撃に重なるように、「グネーハ」が回答をもたらした。
「推奨対策:ゴーレムを捨てて急速退避。地球上の重力波探知装置を総動員して地球近傍の最大重力波発生源を探知」
「――避けろ! 防御はできない!」
俺は鋭く叫ぶ。
アキラは反射的にゴーレムを捨てて全速で後方に退避する。俺も瑠羽を抱えて北極海からまっすぐに逃げながら、グネーハの回答をアキラ、瑠羽、そして、北極海に攻め込んできている全ての仲間にも転送した。
平行して、西暦二〇五五年までに建造され、MAGIによって再建された世界中のあらゆる重力波検知装置の検知ログのデータを分析する。ポズレドニクとMAGIのシステムの奪い合いにおいて、ポズレドニクは特にこうした研究施設へのハックを重視していた。その理由は知るよしもないが、このシステムを開発したというフィオレートヴィはある程度抜け目のない人物だったような印象を受けているので、MAGIが「システムアップデート」を必ず行うと予測し、曲がりなりにもそれが検知できるように観測システムを押さえた可能性は充分にあるだろう。
ログを解析する。
ポズレドニクには組織はなく、アキラのように力のある者が適宜他の者を従えるだけの組織なので、専門で解析している人物などは存在しなかった。だが、かなり以前に解析した痕跡があり、それを活用することで、俺の思考MAGIC「グネーハ」は、すぐに解にたどり着いた。
「……分かったぞ」
俺はつぶやく。
「何が分かった!」
アキラが聞いてくる。
彼女と俺、そして瑠羽は、現在、飛行MAGICでシベリア上空を南下中だ。光の翼を持つ巨人が、俺達の後方、一〇〇キロを、全く距離を変えずに追随してくるのが分かる。
(余裕ぶりやがって。力では勝てないと俺達に分からせるつもりか)
果たして、メイジーは俺達の記録を残したまま復活させるつもりか、あるいは俺達の記録のないバージョンのデータを使うつもりか。
(前者……だろうな、しつこく追ってくるところをみると)
俺は考える。
(――メイジーは失敗を考慮してシステムをアップデートしていくといった。それはシステムとしては至極まっとうな方向性だ。そのためにも、敢えてシステムに反抗した俺達の記憶をそのままに復活させ、奴の新たな世界――銀河暦で『満足』したかどうかを確認するつもりなのだろう)
だとするならば、それは極めて誠実な対応とも思えた。「人間の幸せを追求する」というメイジーの、MAGIのシステム設計目的は死んでいない。寧ろその実現手段を手にしつつある今、その「信念」ともいうべきもの、――システム的には報酬関数のパラメータに過ぎないが――を強化していることだろう。
「――分かったことは、奴の通信ノードの場所だ」
俺はアキラの問いに答えてやる。
「通信ノード?」
「MAGI・ギャラクティカは超光速通信で銀河全体をつなぐネットワークだ。俺達の科学技術からの正統進化でそれにたどり着くには、ブラックホール関係の技術を利用していると思うのが妥当だ。とすれば、重力波観測設備ならそれが分かるかもしれない」
「なんともあやふやだな」
「当たり前だ。数百年後の技術を予想するようなものだからな。中世の人間がコンピュータチップを表現しようとするなら、『石の中を小さな雷が走っている』とでも言うだろう。その程度の予想だと思え。それでも、石の中の雷光を探そうとすることには意味がある」
俺は世界中の重力波観測施設のデータ解析結果を仲間に共有した。解析結果によれば、通信ノードのブラックホールと思われる重力集中点は、太陽・地球系のラグランジュポイント2に位置している可能性が高い。
太陽から見て常に地球の裏側にある位置で、地球からの距離は一五〇万キロ。光の速度でも五秒かかる距離である。過去には、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などが置かれていた宙域だ。
グネーハの推奨は明確。
「破壊せよ」であった。
「ここを撃て!」
俺は言う。
「了解した」
アキラは応じる。
俺とアキラ、瑠羽の3人は、そのときロシア国境から中央アジアに入っていた。カザフスタンやトルキスタン、タジキスタンなどの国境が複雑に絡み合う領域だ。いずれもMAGIの支配する世界では、「国家級管理区」とされている。
「だが、奴らの追跡をかわさねば撃てないぞ!」
彼女の指摘は尤もだ。最大級のエネルギーを発揮できる開闢MAGICは、レベル99の俺かアキラしか撃てないし、それ以下の攻撃で、ノードが破壊できる可能性は低いだろう。
(開闢MAGICでも可能かどうかは分からんがな……)
既にチベット高原に入っている。その向こうは――ヒマラヤ山脈だ。
「晶!」
アキラが呼びかけてくる。
「ヒマラヤでオレが食い止める。その間にお前が撃て!」
「いいのか?」
アキラは不敵に微笑んだ。
「勘違いするな。お前のためじゃない。オレのためだ。やつめ……オレを失敗だときめつけやがった。オレは奴に救われたいんじゃない……オレはオレの意思でこの世界を生き抜くんだ……! 奴の支配する世界など何度でも否定してやる!」
「わかった」
俺は目の前の巨大な山塊を見つめる。
(瑠羽の飛行MAGICでは心許ないな)
「瑠羽、俺の手をしっかり握ってろ!」
瑠羽の顔にも流石に余裕がない。瑠羽の手を握り、口の中で、開闢飛行MAGIC「ペトハー」を唱える。
同時に、俺の背中の飛行モジュールは大幅に変形し、翼が巨大化、エンジンはラムジェットエンジンとなった。スキンタイト冒険服に包まれていない頭部にも、ヘルムが被さる。宇宙で戦ったときと同じだ。
瑠羽もヘルムを被ったのを確認し、そのまま加速した。
ヒマラヤに向けてまっすぐ突っ込む進路だった俺達は急上昇し、高度一万メートルに至る。それを追ってくる光の翼の巨人たち。その周囲の空間は微妙にゆがんでみえ、俺達とは全く異なる科学技術体系で飛行していることを暗示させる。
だが、こいつらに対処している余裕はない。
(頼んだぞ……アキラ!)
俺はMAGICソードを構えた。
「光よ……! 天の檻を穿て! 『バハラーク』!」
その瞬間、はるか天空にちかっと光がまたたいた。今、ポズレドニク支配下にある全地球軌道上のレーザー衛星が、太陽・地球系のラグランジュ2宙域にあるブラックホール通信ノードに向けて、一斉にレーザーを放ったのだ。
光は走る。
あと五秒。
下方からは光の翼の巨人たちが迫ってくる。その槍の先端には、暗い光がまたたいている。原理も全く分からない力で、俺と瑠羽を撃とうとしている。
そのとき、下方でアキラがMAGICソードを構えた。何かを唱える。それに応じ、上空からレーザーが降ってくる。
光の翼の巨人どもは難なくそれらを避け、更に俺と瑠羽に迫る。
そのとき、はるか天空に虹色の光が瞬いた気がした。
「――ブラックホール通信ノードにレーザー攻撃到達。但し――破壊は確認できません」
各地の重力波観測施設からのデータを高速で解析し、その結果を伝えてきたのだ。
「……ここまでか……っ」
光の翼の巨人どもが迫る。その槍は暗黒のビームを今にも放とうとしていた。
そのとき、瑠羽が俺の頭を胸に抱きしめる。
「生まれ変わっても……きっと一緒に戦おう……どんなに離れていても……君と私はずっと一緒だ。諦めないで」
「……ああ」
俺は、頷いた。
諦観はなかった。瑠羽の心臓の鼓動。ぬくもり。そして、俺の小さな身体にみなぎる血潮を感じた。
奴の思い通りにはならないという不屈の意思を、少なくとも俺達二人は、最期の瞬間まで共有していた。
いや、下方にいるアキラも。北極海をともに攻めた仲間たちも、それは同じはずだ。
(負けるものか……メイジー……次こそ、必ず……!)
暗黒のビームが、もうすぐそこまで迫っていた。