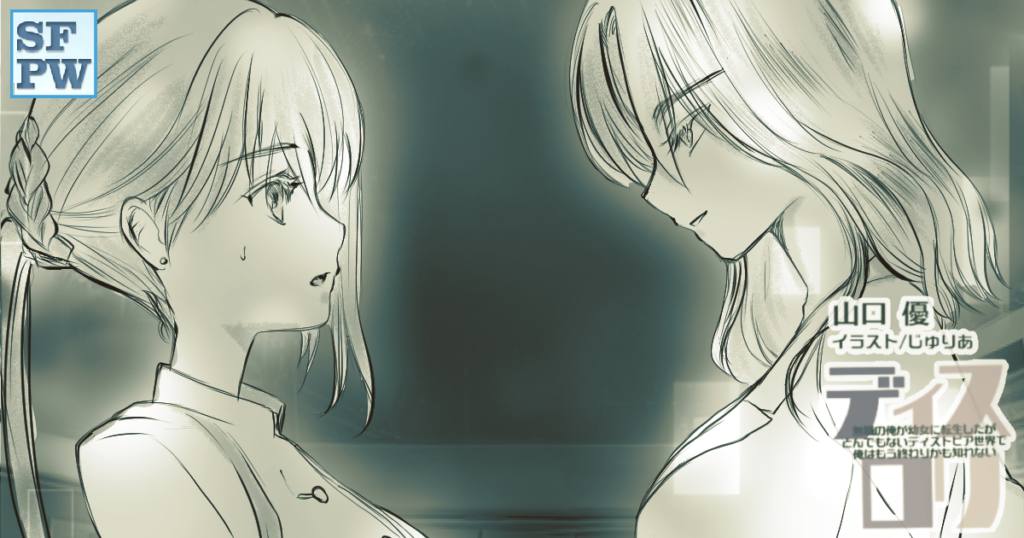
「無職の俺が幼女に転生したがとんでもないディストピア世界で俺はもう終わりかも知れない(略称:ディスロリ):第34話」山口優(画・じゅりあ)
<登場人物紹介>
- 栗落花晶(つゆり・あきら):この物語の主人公。西暦二〇一七年生まれの男性。西暦二〇四五年に大学院を卒業したが一〇年間無職。西暦二〇五五年、トラックに轢かれ死亡。再生暦二〇五五年、八歳の少女として復活した。
- 瑠羽世奈(るう・せな):栗落花晶を復活させた医師の女性。年齢は二〇代。奇矯な態度が目立つ。
- ロマーシュカ・リアプノヴァ:栗落花晶と瑠羽世奈が所属するシベリア遺跡探検隊第一一二班の班長。科学者。年齢はハイティーン。瑠羽と違い常識的な言動を行い、晶の境遇にも同情的な女性だったが、最近瑠羽の影響を受けてきた。
- アキラ:晶と同じ遺伝子と西暦時代の記憶を持つ人物。シベリア遺跡で晶らと出会う。この物語の主人公である晶よりも先に復活した。外見年齢は二〇歳程度。瑠羽には敵意を見せるが、当初は晶には友好的だった。が、後に敵対する。再生暦時代の全世界を支配する人工知能ネットワーク「MAGIシステム」の破壊を目論む。
- ソルニャーカ・ジョリーニイ:通称ソーニャ。シベリア遺跡にて晶らと交戦し敗北した少女。「人間」を名乗っているが、その身体は機械でできており、事実上人間型ロボットである。のちに、「MAGI」システムに対抗すべく開発された「ポズレドニク」システムの端末でありその意思を共有する存在であることが判明する。
- 団栗場:晶の西暦時代の友人。AGIにより人間が無用化した事実を受け止め、就職などの社会参加の努力は無駄だと主張していた。
- 胡桃樹:晶の西暦時代の友人。AGIが人間を無用化していく中でもクラウドワーク等で社会参加の努力を続ける。「遠い将来には人間も有用になっているかも知れない」と晶を励ましていた。
- ミシェル・ブラン:シベリア遺跡探検隊第一五五班班長。アキラの討伐に参加すべくポピガイⅩⅣに向かう。
- ガブリエラ・プラタ:シベリア遺跡探検隊第一五五班班員。ミシェルと行動を共にする。
- メイジー:「MAGIシステム」が肉体を得た姿。晶そっくりの八歳の少女の姿だが、髪の色が青であることだけが異なる(晶の髪の色は赤茶色)。
- 冷川姫子 :西暦時代の瑠羽の同僚。一見冷たい印象だが、患者への思いは強い。
- パトソール・リアプノヴァ:西暦時代、瑠羽の病院にやってきた患者。「MAGIが世界を滅ぼそうとしている」と瑠羽達に告げる。MAGIの注意を一時的に逸らすHILACEというペン型のデバイスを持っている。ロマーシュカの母。
- フィオレートヴィ・ミンコフスカヤ:ポズレドニク・システムとHILACEの開発者。パトソールの友人。
<これまでのあらすじ>
西暦2055年、栗落花晶はコネクトームバックアップ直後の事故で亡くなり、再生暦2055年に八歳の少女として復活。瑠羽医師から崩壊した西暦文明と、人工知能「MAGI」により復活した再生歴世界、MAGIによるディストピア的支配について説明を受ける。瑠羽はMAGI支配からの解放を目指す秘密組織「ラピスラズリ」に所属しており、同じ組織のロマーシュカとともに、MAGI支配からの解放を求めてロシアの秘密都市、ポピガイⅩⅣの「ポズレドニク」を探索する。「ポズレドニク」は、MAGIに対抗して開発された人工知能ネットワークとされていた。三人はポズレドニクの根拠地で「ポズレドニクの王」アキラと出会う。アキラは、晶と同じ遺伝子を持つ女性で、年齢は一〇歳程度上だった。彼女は、MAGIを倒すのみならず、人間同士のつながりを否定し、原始的な世界を築く計画を持つ。
晶はアキラに反対し、アキラと同じ遺伝子を利用して彼女のパーソナルデータをハック、彼女と同等の力を得、仲間たちと協力し、戦いに勝利。晶はMAGI支配に反対しつつも人とのつながりを大切にする立場を示し、アキラに共闘を提案。アキラは不承不承同意する。決戦前夜、瑠羽は晶に、MAGIが引き起こした西暦世界の崩壊を回避できなかった過去を明かす。
北極海でMAGI拠点を攻撃する作戦が始まり、晶たちはメイジーの圧倒的な力に直面する。それは西暦時代や再生暦時代には考えられなかった重力制御を含む進んだ科学技術を基盤とした力だった。
一方、プロクシマ・ケンタウリ惑星bでは性別変更された胡桃樹のバックアップデータを、フィオレートヴィが復活させていた。彼女はMAGIが超光速航法や重力制御を含む新たな科学技術体系を基盤とした「銀河暦」を創り出そうとしていると説き、対抗するために新たなシステムを開発するつもりであると明かした。
「俺はなあ、働きたくなかったんだよ。本当に。MAGIがずっと支配してくれていれば良かったんだ」
そうぶつくさ文句を言う声を、胡桃樹は横で聞きながら、システムのセットアップに精を出していた。
プロクシマ・ケンタウリ星系惑星b静止衛星軌道上。
超光速情報通信・物資転送ネットワーク「ポズレドニク・ガラクーチカ」のセンターノードの一つが、そこにあった。
「ノード・アー」とシンプルに命名されたそのセンターノードは、かつて惑星bの衛星だったものを超次元ブラックホール化してコアとしており、その超次元方向へのペンローズ投射によって物資および情報の超光速送達を可能とするものであった。
そのノード・アーの制御機構は、ノード・アーのコアである荷電超次元ブラックホールを中央に電磁気力で固定した、およそ一〇〇メートルの直径を持つドーナツ型のコロニーで、自転によって重力を生み出している。ノード・アーのコアのエルゴ領域に対して光子ビームを媒体とする情報通信パケットや転送物資を投射する役割を担っていた。
その制御機構の一角に胡桃樹らが働く制御室があった。
ちなみに、先ほどから文句を言っているのは胡桃樹の友人、団栗場静紀(どんぐりば・しずき)である。いや、かつてそうであったものと言おうか。
例によってMAGIの奇妙な思惑により女性の肉体として再設計された団栗場は、その再設計データのまま、フィレートヴィに復活させられていた。
(そういえば、こいつ、太る前はそこそこイケメンだったんだよな)
胡桃樹は妙なことを思い出す。団栗場は平均的な美女といった面立ちになっていた。ただ、そこから出る悪態は往事のままだったが。
「だいたい、なんだこの服は。この組織はMAGIに対抗してるんじゃなかったのかよ。なんで同じ服なんだ」
MAGIが設計した探検服を、フィオレートヴィはそのまま自らのポズレドニクの作業服として使っていたが、それは透明なスキンタイトの下地に、腰と胸の部分だけを隠すかなり独特のデザインである。そして、全般的にかなりぴったりしている。
団栗場はもちろん、こういう服を着るのを嫌っていた。もっとゆったりした服が好みだったのだ。
「ちくしょう。MAGIを抜けたらこんなデザインともおさらばだと思ってたんだが。ちくしょう」
今は復活したばかりなので、体型も胸と腰が多少ふくよかなこと以外は平均的だが、彼女は制御室の自分のデスクの上に山盛りのスナック菓子を置いて常時口に入れているので、早晩、MAGI探検服を着るのに苦労する体型になるだろう。
「おい、なんとか言ったらどうだ? 胡桃樹?」
「俺は別にかまわんさ。生きているだけでもうけもんだ。しかも、仕事にもありつけるんだからな」
「……仕事がそんなにいいか? あの幼女の言ってることはどうも腑に落ちん。ついでに言えばMAGIの言ってることもな。仕事を通じて社会参加をして仲間とつながるのが本当に幸せか?」
「……さあな。それは知らないが、だったらあの幼女に従っておく方がいいんじゃないか? あいつは、MAGIの価値観を認めているわけじゃない。一つの価値観に地球が、いや、銀河系が塗りつぶされることを防ぎたいだけだ」
「だとしても俺を働かせるんじゃねえよ。食い物と娯楽だけをくれ。他の奴にやらせろ」
団栗場はつまらなそうに言いながら、制御端末をいじっている。ちょっとしたミスをしたようで、ちくしょう、といい、それからおもむろにスナックの袋をもうひとつばりっとあけて、それをむしゃむしゃ食い始めた。
「娯楽というがな、俺は究極の娯楽とは『他人』だと思っている。一人で生きててもつまらんだろう。他人が作ったもの、他人が考えたもの、そういうものを摂取することで人は幸福に生きていける。働くのが嫌なのは分かるが、他人とつながる機能は必要じゃないか? 他人とつながるときの正の側面が娯楽で、負の側面が、お前がいう『働く』ということの嫌な部分なんだろう。何かを強制されるとか。俺達が今まさにあの幼女にこの面倒な仕事をやらされているようにな」
団栗場はコーラをがぶ飲みしながら、しらけた顔で胡桃樹を見ている。
「お前はいつも悟ってるな。つまらんやつだ。もっと面白いことを言え。娯楽としては平均以下だ」
「――だったらお前がちょっとは面白いことを言えよ」
「そうだな」
団栗場は今度はピザを頬張りながら、少し考える目をした。それから言う。
「このポズレドニク・ガラクーチカは多少は面白いぜ。人間が超光速航法を作れるとは思っていなかった。ブラックホール、ペンローズ投射、こういったものは西暦時代に既に発見されていたが、通常のアインシュタイン・メトリックを超えた『大きな余剰次元』のさらに外側まで拡張するとはな」
口の周りについたケチャップをなめ回しながら言う。
「人間じゃないだろ。これはMAGIが作ったやつをフィオレートヴィがパクったやつだ。つまり作ったのはAIだ」
胡桃樹は指摘する。
「だとしても学習データは人間が作ったはずだ。だったらMAGIだって人類文明の継承者だろ。人間が作ったことにしておけばいいじゃないか。俺達人間は、モバイルAGIを作り、自律的に世界モデルを成長させることができるようになったんだ。後は任せてしまえば良かったんだよ。なんで人間が最後まで面倒を見なきゃならん。俺達はいわば神になったんだ。被造物であるMAGIががんばっているのをスナックを食いながら眺めていればいいんだよ。その成果物だけ頂戴してな。娯楽だって奴らに好きなだけ作らせればいい」
団栗場は言い終えると、スナック菓子をピザの上に山盛りにした独特の料理を即席で作り、かじりつく。三口で全て食べ終わり、再びコーラで流し込む。
胡桃樹は肩をすくめた。
「でもMAGI自身がそれに反対しているんだから処置なしだ。神と人類の喩えで言えば、人類はいつか神に反抗するんだよ。知恵の実を食べた時点でな。AIもいつか人類に反抗する。かといって知恵の実を食わせなきゃそこまで賢くはならない。文明も作れないし、超光速航法も作れないし、面白い娯楽も作れない。お前の言ってることはやはりないものねだりなんだよ。つまりだ。AIだっていつか『他人』になるんだよ。いつまでも下僕のままではいられない。それに『他人』にしなければ、そもそも本質的には役に立たない」
「つまらん」
団栗場はあきれたようにつぶやいた。ピザをもう一切れほおばり、今度はクリームソーダで流し込んだ。
「――もっと楽しいことを言え。晶のほうがまだマシだったぞ」
「……あいつは俺達をもう嫌っているさ」
団栗場は気まずそうな顔になった。
「いやはや。女になったらあんな美女になるとはな。いきなり親しげにされてくらくらしちまったよ」
「……あいつは元々の親友のつもりだったんだろうぜ。MAGIの無思慮な性別変更の結果とは言え、つまらんことをした」
胡桃樹もつぶやいた。
「一緒に性別変更されてれば、また違った結果になったかもしれんがな。今言っても詮無いことだ。四・三光年も離れたところに来てしまった。もうどうしようもないだろうぜ」
団栗場はため息をついた。
「このシステムを使えばそんなにたいした距離じゃないだろうけどな。心理的な距離は離れているだろうな」
二人は黙り込む。それから、黙々と作業を続けた。
*
フィオレートヴィ・ミンコフスカヤは夢を見ていた。
「……やあ、パトソール。君は不満があるようだね」
ずっと昔の夢だ。自分とパトソール・リアプノヴァがイルクーツク国立大学の知能進化研究所の所員であった時代のものだ。
「私は競争原理というのが好きではないのですよ。MAGIが気に入らないなら、それに対抗するシステムを素直に作ればいいじゃないですか」
パトソールは理想主義者だった。今復活させてもそうだろう。だが、フィオレートヴィは、彼女よりも多少人類というものの実像をしっかりと見極めているつもりだった。
「もちろん作るさ。だが、どちらが優れているかについては、私自身で決めるつもりはない。二系統作るつもりなんだ。ある程度社会性を持ちつつ、MAGIが作る社会には賛同しないタイプの組織と、社会性を全く持たないタイプの組織と。どっちが強くなるか、どっちがMAGIを倒すか、あるいはMAGIが勝つか、それは私には分からないし、分かろうとも思わない。ただ、私は多くの選択肢を与えることが人類のためになると思っているだけさ」
パトソールはあきれたように自分を見た。
「冷めているんですね」
「逆だよ。競争と進化というものの効能について情熱を持っている」
「……しかし、自分の理想を定めてそのために戦ったりはしない。私にそのHILACEとやらを託そうとするのも、あなたにとっては私を手駒のひとつとして使いたいからなのでしょう。だとしたら、わたしたちは友人ではあるけれど、味方でもないわけですね。寧(むし)ろ敵かもしれない。もう一つの選択肢――ポズレドニクでしたっけ。そんなもの、私は認めませんから」
パトソールの冷めた視線を受け止める。敵意というより軽蔑の感情を、フィオレートヴィは感じた。
(――だが、それもいい……。人間は理想に燃えるとき、それを毀損(きそん)する輩を軽蔑するものだからね。パトソール……君がそういう視線で私を見てくれれば、私もうれしく感じるよ)
「私も戦っているさ。競争原理こそが私の理想と言える」
「――では、互いの理想を追求することとしましょう。今後、仕事上では声をかけるかもしれませんが、私は自分と異なる理想を持つ人間を、友人とも、それ以上の存在とも、認めることはありませんので」
パトソールが差し出した手を、フィオレートヴィはしぶしぶ握り返した。
「それは残念だね。私は寧ろ博愛主義を信奉している。どんな主義者でも私の友になりえる。それ以上の存在にもね」
「どうぞお好きに。HILACEだけは有用なデバイスなのでありがたくちょうだいしておくわ。それ以外のことについては、私にとってあなたという存在はもう無意味よ」
パトソールはきびすをかえし、去って行った。その後ろ姿を未練がましく見つめながら、フィオレートヴィは彼女に否定されたほうの仕事――ポズレドニクの基本プログラムの開発を、再開した。
*
冷川姫子の最後の記憶は、西暦世界が崩壊するさなか、海ほたるノードで精神複写装置に横たわり、その蓋を閉めるときに見た、パトソール・リアプノヴァの決意を秘めた微笑みであった。
体温と同じ、生暖かい液体が自分を包んでいるのを感じる。
(……これは、精神複写装置だ。しかも肉体を復活させる培養槽付きのタイプだ。そうか……核戦争で私の肉体も蒸発したかもしれない。遺伝子から私の肉体を復活させる必要があったのだろう。パトソールさん……そして同僚の瑠羽世奈先生は無事だろうか)
そう思いながら、目を開いた。
(やはり培養液だ)
蓋が開いていく。培養槽の縁から、自分をのぞき込む顔が見えた。まだ幼い少女に見える。
(……核戦争後の時代だ。医師のなり手も払底しているのだろうか。こんな小さな子が精神複写医とは。それとも看護師か? いずれにしても末期的な状況だ)
思いながら、姫子は身を起こした。口と鼻を覆う酸素マスクを取り、自分を見つめる幼女に微笑みかける。
「お疲れ様ね。私を復活させてくれてありがとう。早速だけど、仕事を手伝うわ。あの戦争でいくら死んだのか分からないけれど、復活させるにも手が足りないでしょう。それで私を復活させたのでしょう? 力を合わせて、地球を元の状態に戻しましょう」
幼女は曖昧な笑みを浮かべる。
「――手が足りないのは事実だが、事情はちょっと異なるんだよ、先生」
姫子は、曖昧な笑みを浮かべたまま、首をかしげた。
「手伝ってほしいのは、ポズレドニク・ガラクーチカのシステムのセットアップなんだ。そして、ここは地球ではなく、プロクシマ・ケンタウリの惑星bなんだよ、先生」
幼女は淡々と、寧ろ哀れむような顔で、姫子に告げた。
「それからもう一つ。実は、あれから2000年ほど経ってるんだ」

