![]()
(PDFバージョン:ookaminohokori_takahasikiriya)
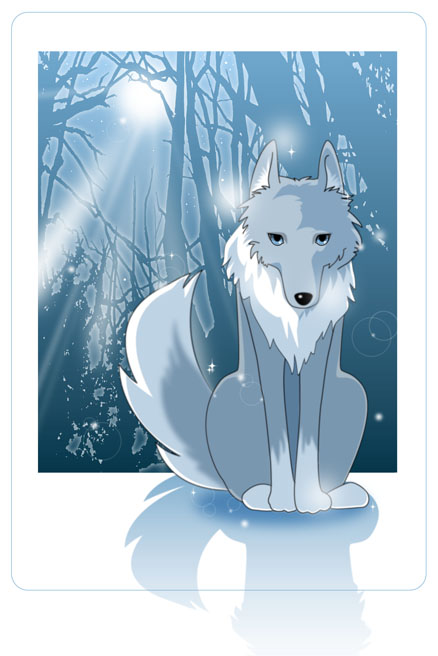
オオカミは、カラスから気になるウワサを聞きました。
古里の谷間の森に住む、オオカミの父親が、ひどくやせていたというのです。
なにかあったのでしょうか。そういえば、父親も母親ももうずいぶん会っていません。両方ともかなりの年のはずです。
そう思ったらいてもたってもいられなくなりました。
「様子を見に行ってみるか」
ひとり立ちしてから、古里に帰るのは初めてかもしれません。
途中で一匹のウサギをしとめました。ウサギを口にくわえて、森の細いけもの道を進んでいきます。
子供のころのぼってあそんだ倒木や、兄たちと追いかけっこして遊んだ空き地の先に、目指す目的地……古くて大きなカシの木が見えてきました。
あのカシの木の根元のくぼみに、両親が住んでいるのです。
オオカミは、ウサギを口にくわえたままハッとして立ち止まりました。
カシの木の根元の巣穴から、誰かがよろよろと出てくるのが見えました。
やせおとろえ、毛もまだらなオオカミが二頭。
それは年老いた父親と母親でした。
オオカミは、目を見開きました。
姿を見るのは何年ぶりでしょうか。思っていた以上に、父も母も年老いて、弱っていました。
声をかけるのもためらわれるほどでした。
両親は、ウサギをくわえたオオカミに気づきもせず、森の奥へ歩いていってしまいました。オオカミは胸を締め付けられるような気がしました。狩りをする者なら、足音や、ごくごくわずかな気配に、気づかないはずがありません。
二人とも、耳は遠く、目も悪くなっているのです。
これではとても、狩りなどできるはずがありません。
ウサギどころか、のろまなモグラさえつかまえられないでしょう。
狩りができなければ、飢えて死んでしまいます。
お土産のウサギを口からはなそうとしたその瞬間、オオカミは、昔のことを思い出しました。
それは、オオカミが、まだ若く、ひとり立ちしたばかりのころのことでした。
最初はヘタだった狩りも、だんだんうまくなってきていました。三人兄弟で一番小さかったので、両親には心配されましたが、若いオオカミは、気ままな一人暮らしを楽しんでいました。
そんなある日、若いオオカミは、猟師がしかけた罠に足をひっかけてしまったのです。
あわてて引きぬきましたが、足の指の骨が折れていました。たかが指の骨ですが、足の先がぱんぱんにはれてしまいました。
それからまる二日、痛くて動くこともできませんでした。やっと三日目に片足で川まで水を飲みに行きました。
そのころにはいくらかはれはおさまっていましたが、足をつくと痛みがはしります。片足のまま、えさになる動物を探しました。
けれど、若くて未熟でおまけに足の悪いオオカミにつかまる間抜けな動物などいません。
しかたなく、その日も次の日も、川の水だけを飲んで過ごしました。三日たっても、一匹もえものをつかまえることはできませんでした。
足はだいぶ治ってきていましたが、狩のカンがにぶっていたのかもしれません。惜しいところでウサギを逃し、ネズミに逃げられ、リスには手も足もでませんでした。
その夕方、ぺこぺこのお腹をさすりながら、巣穴にもどろうとしたときのことです。えものの匂いに、体じゅうに力がみなぎりました。
一匹の小さなウサギが、巣穴の近くで、うずくまっているのでした。
ウサギは、オオカミに気づいていません。
若いオオカミが近寄っても、うずくまったままでいます。
そろり、そろりと近づきます。
このチャンスを逃がしたら、もう飢え死にしてしまうでしょう。
オオカミは、痛くないほうの足をふみしめ、ウサギにおそいかかりました。
ウサギの首もとにぐさりと歯がくいこみます。
つかまえた!
温かいウサギに夢中でむしゃぶりつきました。
けれど何かが気になりました。オオカミは、一口かじっただけで、ウサギを口からはなしました。
次の瞬間、思わず、あっと声をあげました。
かみついたのはウサギの首です。
ところが、ウサギの後ろ足はおかしな方向に折れ曲がって、二本とも折れていたのでした。その足には、歯型がしっかりとついていました。知っている匂いがしました。
若いオオカミは、頭にカッと血がのぼりました。
怒り狂って、ウサギを口にくわえると、足の痛みも忘れて走り出しました。
川を越え、両親のいるカシの巣穴にやってきました。
若いオオカミは、怒りに任せて、巣穴の前に、死んだウサギを投げつけました。
巣穴から、父親と母親が出てきました。
びっくりしたような、とまどったような顔でした。
若いオオカミは、さけびました。
「おれを馬鹿にしているのか!」
「どうしたの。何があったの」
母親オオカミはおろおろとするばかりです。若いオオカミは、父親の顔をにらみつけました。父親オオカミは、そのころはまだ、若いオオカミより一回り大きくがっしりとしたりっぱな体つきでした。
その父親が、何のことかわからないという顔をしています。足元に投げつけられたウサギを、不思議そうに見おろしています。
若いオオカミは、悔しくて情けなくて、涙を流していました。
「おれはオオカミだ! ひとり立ちしたオオカミだ。たとえ片足でも、おれにはオオカミの誇りがある。狩りができなければ、飢えて死ぬかくごはできている。誰からもほどこしは受けない! それなのに、それなのに……足をかみくだいたウサギなど」
若いオオカミの言葉を聞いた父親は、顔をゆがめました。
「おまえもひもじかろうと」
若いオオカミは、痛くないほうの足を踏み鳴らしました。
「それが許せないんだ! おれの足が折れたから、お情けで、めぐんでやろうというのだろう。たえられない! 不愉快だ!」
何よりもお情けのウサギを一口食べてしまった自分が許せなかったのです。
父親と母親は、顔を見合わせました。悲しげな目をしていました。
若いオオカミは
「二度とこんなことをするな!」
と言い捨てて、その場を去りました。
それから川向こうの森に戻って、また水を飲みました。
えものをとらえることができたのは、その翌日でした。足を折ってから一週間が過ぎていました。もう本当に飢え死にするぎりぎりのせとぎわでした。
でも、自分の力でえものを取ることができて、若いオオカミは満足しました。
それから、誰にもたよらず、一人で暮らしてきました。何年もたち、狩りもうまくなりました。うっかり猟師の罠にかかることもありません。
そんなことがあったと、自分でも忘れていました。
そして今、オオカミは久しぶりに生まれた巣穴に帰ってきました。
口には途中でつかまえたウサギをくわえています。
オオカミは、年老いた両親が歩いていった先を、ながめました。
年老いた父親は、やせ細ってよろけながらも、胸を張って歩いていました。
オオカミの誇りを忘れていないのだと、一目見て分かりました。
いったい、ウサギを土産に持ってきて、喜んでくれるでしょうか。
切なく苦い思いが胸の中に広がっていきます。
昔、感じた思いがあざやかによみがえります。
オオカミの誇り……。
若かった自分は、誇りを傷つけられて、本気で怒りました。
そのとき、両親は悲しそうな目をしていました。
どんな思いで、足をくだいたウサギを置いていったのか、両親の気持ちも、今なら分かります。
オオカミは、両親が行ったほうにもう一度目を向けました。
そして、まだあたたかいウサギを、巣穴の入り口にそっと置きました。
年老いた両親は、ウサギをありがたいと思って食べるでしょうか。
それとも、息子のしわざだと気づいて、「馬鹿にするな!」とどなりこんでくるでしょうか?
もしそれほどに父親が元気なら……。オオカミは、ふっと笑いました。
それはそれで嬉しい気がします。
オオカミは、そんなことを考えながら、川向こうの自分のなわばりへ帰っていきました。
(了)
高橋桐矢既刊
『ドール
ルクシオン年代記』
