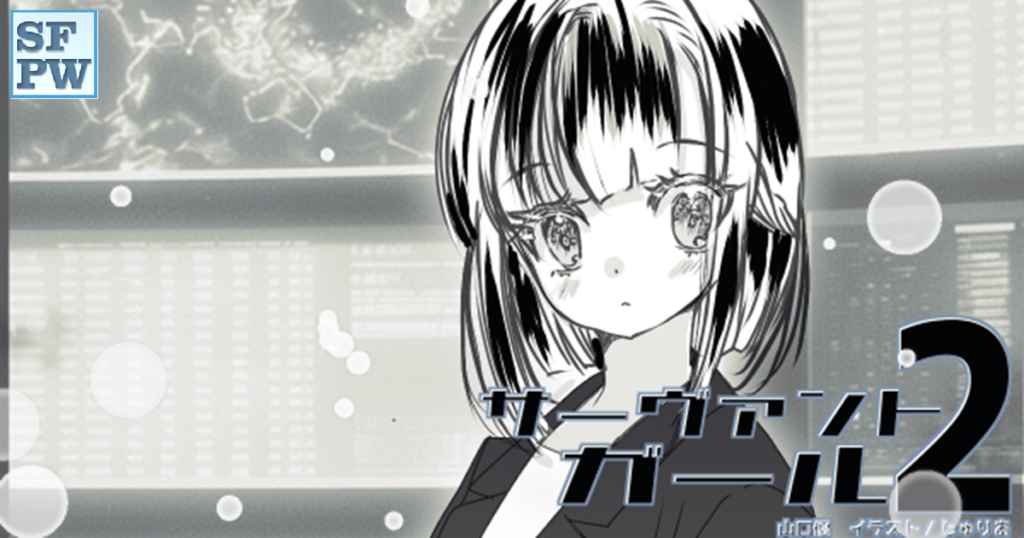
<登場人物紹介>
- 織笠静弦(おりかさ・しづる):物理学を学ぶ大学院生。二年飛び級をして入学しているため二〇歳。ひょんなことから、平行世界からやってきた「機械奴隷」であるアリアの主人となり、平行世界と「機械奴隷」を巡る暗闘に巻き込まれていく。戦いを通じてアリアと主人と奴隷を超えた絆を結ぶ。
- アリア・セルヴァ・カウサリウス:ローマ帝国が滅びず発展し続けた平行世界からやってきた「機械奴隷」。アリウス氏族カウサリウス家の領地(宇宙コロニー)で製造されたためこの名となっている。余剰次元ブラックホール知性が本体だが、人間とのインターフェースとして通常時空に有機的な肉体を持つ。「弱い相互作用」を主体とした力を行使する。行使可能なエネルギー(=質量)のレベルは微惑星クラス。「道化」の役割を与えられて製造されており、主人をからかうことも多い。
- 御津見絢(みつみ・けん):織笠静弦の友人。言語学専攻。静弦に想いを寄せているようだが、研究に没頭していたい静弦にその気はない。おとなしい性格だが、客観的に静弦のことをよく見ている。いつしか静弦の戦いに巻き込まれていく。
- 結柵章吾(ゆうき・しょうご):織笠静弦の大学の准教授。少壮で有能な物理学者。平行世界とそこからやってくる「機械奴隷」に対応する物理学者・政治家・軍による秘密の組織「マルチヴァース・ディフェンス・コミッティ(MDC)」の一員。静弦にアリアを差し出すよう要求し、拒否すれば靜弦を排除することもいとわない非情な一面も見せる。かつて静弦と深い仲であったことがある。
- リヴィウス・セルヴス・ブロンテ:結柵に仕える「機械奴隷」。電磁相互作用を主体とした力を行使する。エネルギーは小惑星クラス。
- ヴァレリア・セルヴァ・フォルティス:結柵に仕えていたが、後に絢に仕える「機械奴隷」。強い相互作用を主体とした力を行使する。エネルギーは小惑星クラス。
- アレクサンドル(アレックス)・コロリョフ:結柵の研究仲間の教授。静弦が留学を目指す米国のMAPL(数理物理研究所)という研究機関に属している。
- ユリア・セルヴァ・アグリッパ:主人不明の「機械奴隷」。重力相互作用を主体とした力を行使する。エネルギーは惑星クラス。
- 亜鞠戸量波(あまりと・かずは):静弦の同級生。二二歳。「サーヴァント・ガール2」から登場。
- ルクレツィア・パウルス:バンクーバーのAI学会で静弦らと出会った女性。台湾にあるスタートアップに勤務。
<「サーヴァント・ガール」のあらすじ>
岐阜県の「上丘(ルビ:かみおか)鉱山」に所在するダークマター観測装置の当直をしていた大学院生の織笠静弦は、観測装置から人為的なものに見える奇妙な反応を受信した。それがダークマターを媒体としてメッセージを送信できる高度な文明の所産だとすれば、観測装置の変化を通じてこちらの反応を検知できるはずだと判断した彼女は「返信」を実行する。次の瞬間、目の前にアリアと名乗る少女が出現する。アリアは静弦が自分の主人になったと主張し、また、主人となった人間には原理的に反抗できないことも説明され、静弦は渋々アリアと主従の関係を結ぶ。
しかし、現代文明を遙かに超える力を持つ機械奴隷を静弦が保有したことは、新たな争いの火種となった。実は、アリアと同種の機械奴隷はアリアよりも前からこの宇宙に流れ着いており、それを管理する秘密組織が存在していた。観測装置の実務責任者である結柵章吾もそのメンバーであり、彼は静弦がアリアを得たことを察知、自らの「機械奴隷」であるヴァレリア、リヴィウスを使って攻撃を仕掛け、アリアを手放すよう要求する。静弦は、自分を必死に守るアリアの姿を見て、アリアを手放さないと決意、辛くも結柵との戦いに勝利する。
勝利後の会談で結柵にもアリアの保有を認められ、しばし穏やかな時が流れるが、静弦は自分が研究中の理論を、遙かに進んだ科学を知るアリアに否定されけんか別れする。その隙を突き、主人不明の「機械奴隷」ユリアに攻撃されるアリアと静弦。危機を察知した結柵がヴァレリアを、静弦の友人・御津見絢に仕えさせ、二人に救援に向かわせたこともあって、ユリアの撃退に成功する。戦いを通じ、静弦とアリアは主従を超えた絆を結ぶ。戦いの後、これ以上の攻撃を撃退する目的から、静弦とアリアは、絢・ヴァレリアとともに留学生寮に住むことになる。
<「サーヴァント・ガール2」これまでのあらすじ>
静弦は留学生寮で新しく友人となった女子学生、亜鞠戸量波の部屋で彼女と一夜をともにする。アリアは静弦の行動にショックを受け、姿を消してしまう。アリアを追い、静弦は絢、ヴァレリアとともにアリアの目撃報告があったカナダ・バンクーバーに向い、そこで偶然出会った量波とも合流して、現地で開催されたAI学会に参加、アリアを見つけ出す。しかしアリアは、自らの存在をこの宇宙とは異なる余剰次元空間に逃避させる。静弦はヴァレリアとともにアリアを追うが、アリアは「自分は静弦様にはふさわしくない」と言い、姿を消す。静弦は絢の助言により心を決め、アリアの手がかりを求め、AI学会で出会い、アリアを見知っていると思われる女性、ルクレツィアの足取りを追って台湾に向かう。
三人は、台湾で量波、そしてアリアとも出会う。しかしアリアは再び逃げてしまう。絢によって「セルヴァ・マキナの力を阻害し、アリアの失踪を手引きしていた犯人」と名指しされた量波とルクレツィアは、静弦・絢・ヴァレリアを巻き込んで瞬間移動を引き起こす。量波は自らが「行動派」と名乗り、他宇宙からの侵攻に備え積極的にインペリウム世界の技術を開発すべきだと説くが、静弦・絢は顕在化していない脅威に対し無用な混乱を招くとしてこれを拒否した。ドミナである量波のセルヴァ・マキナであるルクレツィアは、「他のセルヴァ・マキナを操る力」を行使しヴァレリアを操作、静弦・絢を葬り去ろうとする。そこに現れたアリアは、ヴァレリアに対抗し、静弦を助けるかに見えたが、自ら作り出した余剰次元空間に静弦を閉じ込め、彼女の身動きを取れなくしてしまう。しかし、ルクレツィアによる操作をはねのけ、逆にルクレツィアたちを攻撃、撃退する。
第四章一話(通算一四話)「戦闘の後」
「ふうむ。そうか。亜鞠戸君のことは実は結柵先生から言い含められていてね。彼女には事情があるから詮索しないでくれ、と。しかし私の学生なんだからどうしているか気になるのは当然だ。分かってもらえるかな」
勅使ヶ原悠奈准教授の研究室。
静弦は勅使ヶ原と対面で座り、やや緊張していた。
紙の本が本棚にぎっしりと詰まった雀居教授の部屋とはまた違った趣がある。部屋の中壁には巨大なモニターが並べられ、デスクの上にも鈍い銀色のモニターが二つ。コーヒーカップも銀色だ。
その部屋の主である勅使ヶ原准教授は、黒いパンツスーツと白いシャツ、パンプスという組み合わせで、理知的な彼女にはとてもよく似合っていたが、量波に以前聞いたところでは、「国際学会だろうがラボの旅行だろうが常に同じ格好しかしてない」らしい。
「亜鞠戸君の事情――君なら知っていると思ったのだが。君も『知っているが話せない』クチかな? 彼女からはしばらく休む――という連絡しか来ていなくてね。ここ数ヶ月で彼女がやる予定だった研究の報告はすでにもらっているので、ラボの准教授の職務が、『学生という研究者の研究上のボス』であるだけならばそれで充分なのだが、私個人としては、学生の生活全般にも注意を払うべきだと思っていてね」
眼光は鋭い。量波からは厳しいと聞いていたが、他のラボの学生である静弦に対しては、そこまで厳しく問い詰めるつもりもないようだ。
「いえ。台湾で出会ったのは事実ですが、その後のことは分かりません。これから何をするという話も聞きませんでしたから」
「そうか……」
勅使ヶ原准教授はパソコンのキーボードにわずかに触れた。そして言う。
「クリュセオン」
「はい、先生」
滑らかな女性の機械音声がどこからともなく流れてくる。
「聞いていたかな? 亜鞠戸君の状況と織笠君と私の対話、それに最近ダークマター関係の実験系および理論系研究者の論文数が妙に少ないことの理由を結びつけて何が起こっているか推測してくれ」
「私の役割はAIである私自身によってどの程度物理現象が解析できるかを検証することにあります。あなたの問いかけはその役割を大きく超えるものと推論いたします」
クリュセオンはそう回答する。
「果たしてそうかな? 物理現象に由来するものかもしれないよ?」
勅使ヶ原准教授は、静弦に意味深な視線を送りながら言う。
「とにかく、やってみてくれ。参照する論文は物理に限定する必要は無い。歴史も哲学も、全て含めてやってみてくれ」
「分かりました。推論を開始します」
「……それは?」
静弦が聞くと、勅使河原准教授は、慣れた説明を繰り返すように、なめらかに説明し始めた。
「クリュセオンは私と亜鞠戸君が共同で開発している物理研究用AIだ。人間には処理し切れない膨大なデータと先行研究をもとに、人間にも発見できなかった新たな物理理論――しかも、現在の物理学実験のエネルギーレベルで検証可能なもの――を導き出すのが任務だ。
「友人の音信不通に心を痛めている――と思われる君にはちょっと申し訳ないが、興味深いなと思ってね。君や結柵先生、亜鞠戸君が何を隠しているのか知らないが、少なくとも全員、ダークマターの実験施設に滞在したことがある、ということを思い出したんだ。君と結柵先生はXEMDAS。亜鞠戸君は北イタリアの実験施設に滞在していたことがある。それが何を意味するのかは分からないが、ダークマターの理論の中には、それが余剰次元に存在するというものもある。そうすると、いろいろな可能性が考えられるだろうなと思ってね」
「――SFの読み過ぎでしょう。ダークマターが余剰次元に存在するとしても、それはそれだけのことです。先生に明かせないような秘密がそこから出てくるわけがありません」
勅使ヶ原准教授は両手をポケットに突っ込んでほとんど仰向けに背もたれに身を預け、目を閉じる。
「そうだろうな。常識で考えれば」
それから目を開き、横目でパソコンの画面を見た。
(この人、まつげ長いな)
静弦はふと状況に関係の無い感想を抱く。
「さて、クリュセオン。そろそろ答えが出たかな」
「はい」
明瞭な機械音声が研究室に響いた。
「――まず前提として、複数のダークマターに関する研究が、それが重力でしか相互作用しないこと等を手がかりに、『大きな余剰次元』理論との関連性を指摘しています。しかし、このような方向性の先行研究は、近年劇的に減少しています」
「ほほう。それはなぜだと思う?」
「一義的には、そのような仮説を支持する実験結果が激減したこと」
「更に推測すると?」
「――推論というよりも幻覚(ルビ:Hallucination)に近いものになりますが」
「言ってみたまえ」
「――その仮説がこの社会で信じられると困ると、実験関係者が考え始め、意図的に結果を出さなくなった可能性が一つ。あるいは、『別の目的』に実験設備を使い始めた結果、元来のダークマター観測の目的に使えなくなり、実験結果が出せなくなった可能性もあります」
「……陰謀論じみてきたな。だが興味深い。奇妙に現状に符合する。続けたまえ」
「更にその理由を推論するならば、大きな余剰次元に関わる何らかの重要な秘密を彼等が持ち始めたから。そして、その重要な秘密に関わるとある目的に実験設備が必要になったから」
「その秘密と目的とは?」
「『大きな余剰次元』方向に存在する未知の知的な存在。その存在とのコンタクトです」
(ま……まさか!)
静弦は思った。
「――私がこの推論を述べた瞬間。織笠氏の顔表面の血流から推定される心拍数が急上昇しました」
クリュセオンが付け足すように言った。
勅使ヶ原准教授はじっと静弦を観察する。
「へえ……興味深いな。私が見るところ、君は、下手なオカルトにはまるには高すぎる知性を持っているはずなのに、クリュセオンのオカルトじみた推論に対して心拍数が急上昇するとは」
彼女は言葉を続ける。
「AIをできるだけ人間に近い高い水準の知性に育て上げるため、私は人間の心理についても多少勉強している。その成果によれば、君の反応は、隠していた真実を暴かれた者のそれだ」
「――申し訳ありませんが、何も言えません」
静弦はかろうじて冷静さを保ち、言う。
「安心したまえ。君は秘密を知るものであっても、黒幕とは思っていない。もしそういう存在がいるのなら、よりその可能性が高いのは結柵先生だろう。君への質問は、彼への質問の予備かな、おそらく」
「……ご忠告いたしますが、結柵先生を問い詰めても良いことは無いと思います。先生は研究者なので、好奇心を抑えられないのだと思いますが……」
勅使ヶ原准教授は立ち上がる。
「君はひとつ誤解していると思う。好奇心が抑えられないから研究者になったのであって、研究者になったから好奇心が抑えられないのではない」
それから笑みを浮かべた。
「――君は優しいな。まあ、無事を祈っていてくれ」
大学の正門前で、アリアが待っていた。
「教授との打ち合わせ、上手くいきましたか?」
「――ん。まあね。雀居先生とは、研究というか、卒論はもうほぼ終わってるからね。MAPLにおける研究方針の相談がメインかな。『君ならいける』というお墨付きをもらったよ。雀居先生、優しいけどああいうときには甘いことは言わないからね、一応安心」
「まあ……それはよかったです……!」
アリアは満面に笑みを浮かべる。
アリアとの関係はあの日から安定していた。静弦の心境の変化もあったし、アリアも落ち着いていた。AIであるアリアが『落ち着かない』というのがもともと妙な話ではあるのだが、アリアたちセルヴァ・マキナは人間とのインターフェ―スを通じて有機体が情動を持ち、それがシステムの動機として重要なので、『感情的』であることも仕様なのだろう。アリアはそういった仕様的な感情を尚、逸脱していたが、静弦が気に入っているのはその逸脱の部分であろうとも思っていたので、それでいい、というのが結論となる。
「雀居先生への報告はすぐに済んだんだけど、そのあと勅使ヶ原先生――量波の指導教員に呼び出されてね」
静弦は説明を続ける。
「あら……」
アリアはやや深刻な顔をした。
「量波の行方について、聞かれましたの?」
「ああ……そして、それだけじゃない。――あの人、いくらかMDCやインペリウム世界のことについて感づいている。結柵先生から秘密を探るつもりだ」
「それは……私たちにとっても良いことではありませんわね。統制派は秘密を隠し通す方針ですから」
(そうか……あの『クリュセオン』は行動派である量波が作ったAIでもあるんだ。量波がやんわりと秘密を拡散するために妙なコードを仕掛けていたのかもしれないな)
静弦はその可能性に思い至る。
「まあ、結柵先生ならうまく対処するとは思うが、多少のリスクはある。行動派の行動の監視とともに、ちょっと注意しておいてほしい」
「分かりましたわ」
ちなみに、結柵からは、今回の量波らとの戦いについて報告した後、「しかるべく対応する」という返答を得た以外、特別な指示はない。
おそらく、静弦が推測するに、MDC統制派も対応に苦慮しているのだろう。行動派を排除したいのだとしても、実力で排除すればセルヴァ・マキナ同士の戦闘になる――それは統制派の目的である「秘密を守る」という意味では非常にリスクが高い。かといって、セルヴァ・マキナ以外の手段でセルヴァ・マキナのドミナやドミヌスを排除するのは不可能だ。
(何らかの譲歩をするか――あるいは秘密裏にセルヴァ・マキナで倒していく――そういうことになるんだろう。いずれにせよ、最弱のセルヴァ・マキナであるアリアには関係のないことだ。我々にできることがあるとすれば、彼等に隙を見せず、きちんと自衛する――ということだけだろう)
静弦は、そう結論をしていた。
その結論がすぐに覆るなど、このときには思いもよらなかった。
*
亜鞠戸量波は、全天にきらめく星たちを地上にちりばめたようなシンガポールの夜景をぼんやりと眺めていた。
マリーナ・ベイ・サンズの屋上プールに入り、水の中にたたずみながら、眼下の夜景をじっと見つめている。
量波らしく、目立つ緋色のビキニを着こなし、サングラス型のARグラスで夜景に複雑な数式を重畳させ、短く音声で指示して数式変換を繰り返している。
「よお。またせたな」
急に量波の隣にやってきた人物にARグラスを取り上げられ、その数式をのぞき込まれる。
「ふん……文明の発展が著しいな。セルヴァ・マキナのブラックホール表面のホログラフィック回路で走らせる新しいアルゴリズムか」
そう言って、ARグラスを取り上げたのは、血のような赤い双眸の少女だった。この世のものとは思えぬ美貌――身長はアリアと同程度、やや小さい。しかし、口角の端は好戦的につりあがり、明らかにアリアとは違う性格を物語っている。
今は、申し訳程度に隠さなければならない部分を隠すだけのマイクロビキニを着ている。色は黒。
「お前たちの世界の遅れ……中世の暗黒時代の一〇〇〇年分を取り戻すにはまだまだ遠いがな」
少女は偉そうに論評する。
「少しでも戦力の強化が必要だと思ってね。余剰次元のバルクからある程度エネルギーは追加で集められるとしても、先に集めている世界に対抗するにはエネルギーを効率よく使う必要があるだろう?」
量波は言い返す。
「それで? 君のドミヌスはどこにいるんだ? 私が用があるのは彼なんだが」
量波が言うと、少女は小馬鹿にしたような顔で量波を見る。
「あたしが代理だ。奴に理解できることなら全てあたしにも理解できるさ、心配するな」
「……それは認めよう。何しろ君は我々が想像もできないような処理能力を持つ人工知能でもある。しかし我々人間の命令に服する存在だ。代理が務まるのかな?」
量波がやや挑発的に言うと、少女はにやにや笑いながら耳元でささやく。
「ふん……ずいぶんと余裕じゃないか? ルクレツィアの操作があたしに効くと思うなよ? それとも同じ行動派だからあたしが攻撃しないとでも思ってるのか?」
「別に君をどうにかしようとは思ってないさ。ただ、君の魅力は怒り顔にあると思ったものでね、怒らせてみただけさ。――やっぱり魅力的だ。どうだい? このホテルに私の部屋が取ってある」
量波は少女の顎に手をかける。顎に手をかけられたまま、少女は量波を見下すような視線で見た。
「ふん。命知らずの変態が。あたしを口説くために怒らせたやつは初めてだよ。しかも命がけでな。あたしのピルム(槍)でお前の両手両足をもぎ取った後、ゆっくりと拷問にかけてお前の無謀さを後悔させてやってもいいんだぜ?」
「私の人生には刺激が必要なんだよ。安らぎと同じぐらいね。君は刺激の供給源としてはすばらしいと思ったのさ。普通は前者が友人、後者が恋人と決めてるんだが、逆でも一向に構わない」
量波は人生観じみた言葉で少女の脅しを飄々と受け流し、ひょいとARグラスを取り戻した。
数式を確認すると、自分では思いつかなかった新しい展開が加えられていた。
(私への好意か、いや――自分が優れていることのアピールかな、この娘の性格を考えると)
にやりと笑う。
「一応聞いておくが、周囲にセルヴァ・マキナはいるかい?」
「――下のホテルの部屋にいるルクレツィア以外はいないぜ? 盗聴器の類いもなさそうだ」
「けっこう。では報告だ」
量波は話し始める。静弦への接近。アリアと静弦の離反の誘導。絢、静弦、ヴァレリア、そしてアリアとの戦闘と敗北。
「――ふん。ルクレツィアがいれば勝てると言ってたのはお前じゃないか。負けるとはつまらん。アリアをとらえ、こちらの戦力を増やし統制派と行動派の勢力均衡を破る――作戦は失敗だな」
「君たちに続いて、ね」
「なんだと……?」
少女は目をむいた。赤い瞳がマグマのようにらんらんと光る。マイクロビキニで覆われた美しい肢体が戦闘を準備するように静かにこわばる。
「――ごめんごめん。これはお互い様だ。君たちを揶揄する権利は私にはないからね」
「あたしたちにもない、と言いたげだな」
「事実だろう? 違うかな?」
「――いつかその言葉、後悔させてやる」
「――是非ともそうしてもらいたね。アリア・セルヴァ・カウサリウス――微惑星級。統制派の中で最弱のセルヴァ・マキナと言われつつ、どうしてどうして、我々の中で最強の二人でも敵わなかったわけだ」
「最強はあたしだ。ルクレツィアじゃねえよ」
「戦闘力ではね。君でダメだったから絡め手では最強のルクレツィアでやるという話だったじゃないか。それも失敗だ。さてどうしたものか。統制派の連中、お花畑だとは思うが、さすがに警戒を強めてくると思うよ――ということを彼と話したかったんだけどね。君が代理と言うことだから、君の意見を聞けば良いのかな?」
「ああ。それで構わない。お前は勘違いしてるみたいだから言っておくが、実力ではあたしが最強。ルクレツィアは二番手だ。お前たちの言う、『MDC行動派』の中ではな。だから、あたしとお前たちが合意すれば、もう行動派の中で反対できるやつはいねえのさ」
「……行動派の最高評議会は合議制のはずだが」
ビキニの肩紐を直しながら、量波は言う。
「――反対する奴を殺せばそれでいいのさ」
量波は首をかしげた。
「君のドミヌスがそのように方針を変えたのかい?」
「――合議なんて儀式さ。あたしもあたしのドミヌスもそう思っている」
「まあ、君たちがそう決意すれば、現実的にそうなることは否定はしない……だが、私は反対させてもらおう。いつかは君たちのやり方を覆すよ。そうでないと面白くない」
そこまで言って一息ついた。
「さて。少し場所を変えよう。さすがに話題が殺伐としすぎている。まあ、子供に見える君と、学生の私の会話だ。周囲にはゲームの話とでも思われてるだろうがね」
ざぶりと音を立て、量波はプールを出る。水滴が彼女の肢体を滴る。すたすたと長い脚で歩き、プールサイドのリクライニングチェアに座った。隣を指し示す。
少女は素直にそこに寝そべった。
「それで? 君たちはどう決意したんだ? 行動派の戦力では、まだ統制派に敵わないというのが現状分析のはずだが」
「だが、統制派には大きな弱点がある。奴らはセルヴァ・マキナの秘密を世界にばらしたくない」
「――ほう。つまりセルヴァ・マキナの力を使わざるを得ない状況に追い込むことで、我々に有利な状況を作ると? しかし現実にあるのかい? そんな異常な状況が」
「核戦争だ」
あっさり言い放った少女に、さすがの量波も耳を疑った。
「つまり?」
「――現状の秩序を覆す。そもそも、既存の国際社会は、他世界との戦いを進める上では不要だ。MDC行動派をトップとし、全人類を従える独裁体制を敷く。そのためには、各国政府はなくなったほうがいい」
「――過激だね」
「――少なくとも、統制派には、そのように判断し、行動したと思わせる。核戦争が勃発すれば、必ずミサイルを迎撃するような、既存の技術体系による軍事行動が発生するだろう。それを我々セルヴァ・マキナが妨害したらどうなると思う」
「――統制派のセルヴァ・マキナも出てくるか」
「出てくるが、全力を出して良いのかどうか迷うだろう。奴らにとっては予想外の出来事だから、人類が見ている前でどの程度力を使って良いのか、対応策が予め決められていない。そのときこそ、戦力の不均衡を覆すチャンスが生まれる。我々セルヴァ・マキナの力は強大だ。核兵器すら、豆鉄砲に等しい。ゆえに、本当に核戦争によって全人類が滅びるようなことにはならないだろう。だが、既存の秩序は崩壊し、我々が統治しやすくはなるだろう。その程度の混乱は、人類社会に味わってもらう」
「――それを、私に同意せよと言う訳か」
「同意することを勧める。何しろ、あたしにルクレツィアの力は効かない」
にやりと笑う。
「どうした? 刺激がほしかったんだろう? 最高の刺激だろうが」
(こいつ……どこまで本気なんだ……?)
量波は飛び跳ねる心臓を押さえるように胸に手をやった。だが、表情は平静をあえて保つ。
「――分かった。君たちの提案を検討してみよう。ユリア・セルヴァ・アグリッパ」
黒いマイクロビキニを着た少女――ユリアは、にやりと笑った。
「賢い人間は嫌いじゃないぜ? 特に自分の分をわきまえてる奴はな」

