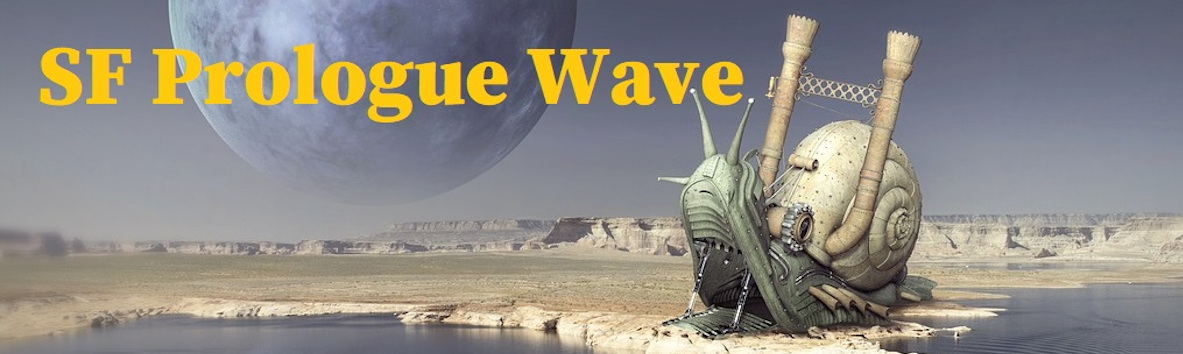服部伸六『カルタゴ――消えた商人の帝国――』復刻企画「Ⅰ カルタゴ」
●復刻にあたって(岡和田晃)
「SF Prologue Wave」で進めている詩人・評論家の服部伸六を再評価する企画につき、いよいよ本丸たる大物『カルタゴ――消えた商人の帝国――』の復刻を開始します。
底本は1987年に社会思想社現代教養文庫のために書き下ろされましたが、2002年に同社が倒産してからは、アクセスが難しくなっていました。
フェニキア人による建国、名将ハンニバルのアルプス越え、ポエニ戦争の敗北により滅亡といったキーワードのみで語られがちなカルタゴについて、早い時期に日本語で概観した入門書にして研究書として有用です。
しかしそれ以上に、それまで中心的だったローマ中心史観を裏返した一冊、という点が重要でしょう。
詩人としての学際的な知見を随所に盛り込みながら、コートジボワール共和国、レバノン、中央アフリカ共和国等の大使館で勤務をしてきた現場での実感が本書を今日でも参照に足るものとしています。
復刻の企画は岡和田晃、翻刻は著作権継承者である大和田始氏にご担当いただきました。
カルタゴ――消えた商人の帝国――
服部伸六著
社会思想社 現代教養文庫 初版1987年3月30日
目次
Ⅰ カルタゴヘの道
「デレンダ・エスト・カルターゴ」
おれが行きたいのはザマだ
人種偏見の源泉
オクシダンはアクシダン
「ひとつの文明の死」の意味するもの
Ⅰ カルタゴヘの道
――というのも、かつて強大であった国の多くが、
今や弱小となり、私の時代に強大であった国も、
かつて弱小であったからである。
(ヘロドトス『歴史』松平千秋訳、岩波文庫)
「デレンダ・エスト・カルターゴ」――Delenda est Carthago
ポール・ヴァレリイは、その『ヴァリエテ(Ⅰ)』の冒頭に入れられている「精神の危機」を、次のように書き出している。
「もろもろの文明を作ったわれわれ、今や、このわれわれは知っている。われわれもまた死すべきものであることを。
亡んでしまった世界があったこと、その人民のすべて、その所持していた器具のすべてと共に海底ふかく沈んでしまった幾多の帝国があったということを聞いたことがある……地表の土すべては灰から出来ており、その灰は何ものかを意味していることもわれわれはよく知っている。われわれは歴史の厚みを通して財物と精神とを満載していた巨大な船の亡霊を見たことがある。」
こう書いてからヴァレリイは、エラム (現在のイラン西部をさす古名)、ニネヴェ (アッシリア帝国の都市)、バビロンなどの古代帝国の名をあげて「ひとつの文明は、ひとつの生命と同じように、同じような脆弱性をもっていることが感じられる」と結んでいる。
ヴァレリイは「カルタゴ」の名は挙げていない。彼の頭の中に、この薄幸の海の帝国の名があったのかどうか、私たちにはわからない。だが、いま在るカルタゴの土のなかに、亡びてしまったカルタゴの人びとの肉体や、その日常使用していた家具や器物などの灰が埋もれているに違いなく、このヴァレリイの言葉は、そっくリカルタゴにも当てはめることが出来るはずである。
しかるに、各国の学校教科書では、カルタゴは「ポエニ戦役」の名で、ローマの敵国として登場するに止まっている。ローマ帝国が栄光への道を歩みはじめる道程のなかのひとコマとして取扱われているにすぎない。カルタゴという名の海洋帝国が繁栄を誇っていた実態には、ほとんど触れられていないのである。「カルタゴは、じじつローマが大きくなろうとしていた時に巨大であったという過誤[あやまり]を犯していたのだ」と、カルタゴの意味を問いかけるのはごく少数のカルタゴ史の専門家たちである。
ローマが地中海世界、ということは当時の文明世界の全体といっても差支えなかったころの地中海で勝利者として登場してくるに当って、さしずめその庭先で邪魔になったのが、カルタゴだった。「デレンダ・エスト・カルターゴ」(カルタゴは滅ぼされねばならぬ) と、その演説を必ず結んだローマの老カトオのスローガンは貫徹されねばならなかった。違った音色を持つ楽器は排斥され圧殺されねばならなかった。
テュニジアの、いまはその場所さえも判然とはしないザマの野で、独眼竜のハンニバルが奮戦しながら、ついにローマの若い将軍スキピオ・アフリカヌスに敗れねばならなかったのは、その序曲であった。
おれが行きたいのはザマだ
異なった音色。カルタゴ人がパレスチナ (カナーン) の地から持って来た文化の音色は異なった響を奏でる楽器だったのであろうか。
カルタゴが亡びて2000年以上も経った現代になってからも根づよく西欧人の意識の底辺に鳴りひびいている音色、それが現実に存在していることを証するエピソードがある。第二次世界大戦の英雄といわれるイギリスの宰相ウィンストン・チャーチルの逸話である。
第二次世界大戦の終局の見通しがょうやくつき始めていた1943年の冬、連合国の首脳がモロッコのカサブランカに集まって会議が開かれた。参加のために飛来したチャーチルは、会議が終ると北アフリカ戦線を指導するため、5月13日、ドイツのロンメル軍の降服まで居残って連合軍の作戦の調整につとめた。
チャーチルは北アフリカを去るに当って戦線の視察を行なった。そのときのことをチャーチルは『第二次世界大戦』のなかで書いているが、「私には、アルジェとテュニスで過した八日間ほど、戦争中の楽しい思い出はない」(佐藤亮一訳、河出書房新社) と、書き記すにとどめている。
ところが、この八日間の視察行のあいだにチャーチルは、じつはテュニスでザマの古戦場に行っているのである。そのときのエピソードを探険家のジャン・マゼルというフランス人が、側近から聞いた話ではあるが、と断りながらも記録している (ジャン・マゼル『フェニキア人とともに』(Jean Mazel , Robert Laffont, 1968)。
「参謀部は彼 (チャーチル) のため戦線視察のプログラムを用意していた。到着したチャーチルは、用意されたプログラムに眼を通してから了承を与えたものの、ただ一つだけ重要な戦場が忘れられていることを指摘した。参謀部のスタッフが、それはどこのことだろうととまどっていると、サー・ウィンストンは地図の上を指差して『おれが行きたいのはここだ』と、テュニス湾を見下ろす丘を示した。
この丘の頂上がフェニキア人の聖なる山だったブー・コルニィヌにほかならなかった。この頂上にはかつて太陽神に捧げられた祭壇のあったところだったのだ。
この丘と湾との中間に、紀元前201年に戦いが行なわれたザマの古戦場があったのである。カルタゴがローマの将軍スキピオに敗れた戦場である。この武勲のおかげでスキピオはスキピオ・アフリカヌスの異名をもらうことになった。
この戦場視察のあとでサー・ウィンストンは側近に次のように言った。『この戦闘は、何といっても西欧の命運がきまった歴史上もっとも重要な戦いの一つだ。カルタゴは西欧の面前に突き出た東方[オリエント]の顔だったのだが、そのときハンニバルはほとんど勝利をおさめていたんだ。もしスキピオが敗けていたらカルタゴの支配下に入ることを意味していた……つまリヨーロッパはオリエント化されることになっただろう。』
ひとりのアングロサキソン人にとって、それは身の毛のよだつ恐怖だし、おそらく西欧人にとって常識でもあった認識だったのである。
じじつ、ザマの戦いは第二次ポエニ戦役を終結させ、カルタゴを無条件降服に追いこみ、ローマはカルタゴの『最後の息の根』だけを残して、農産物や鉱物の供給源を断ったのである。
この息の根は、その後50年もの間もつづくが、前147年のデレンダ・エスト・カルターゴによって断たれることになった。」
ザマの戦闘が歴史の転回点を占める重要なものであったことを、西欧文明のチャンピオンをもって任ずるイギリスの指導者が認識していたことは、このエピソードがよく物語っている。
しかし、チャーチルが素朴にも考えたょうに、カルタゴはオリエントの顔であり、ローマはこの顔を潰して、その後西方[オクシデント]の優位の歴史を開いたチャンピオンだったのだろうか。
チャーチルはおそらく西欧人の常識を代表していたのであろう。じじつ、ローマ以後の歴史は西欧文明の世界支配だからこういう認識は今までのところは通用してきたが、果して未来永劫にわたっての不変の史観なのであろうか。私はこのような疑いをもってカルタゴの歴史をたどることにしたのである。
人種偏見の源泉
チャーチルが考えたようなオリエントに対する西欧文明の防御というような意識が、果してポエニ戦役 (ローマとカルタゴの対決戦) のころにあったものだろうか。老カトオの頭のなかに人種偏見にもとづく憎悪があったものだろうか。セム種といわれる種族に対するインド=ヨーロッパ人種の差別的偏見がそのころから存在していたものであろうか。そういう差別観に比較的無縁に生きて来た私たち日本人の理解を超えるものが、そこにはあるように思われる。
そもそも西欧人が、その文明の祖先と考えているギリシア・ローマ文明はエーゲ海のほとりに忽然として生れたものではなかろう。人類が石器時代を経て都市文明へと発展する過程を辿るならば、ギリシア文明もメソポタミアに生れた古代オリエントや、ナイルのほとりに生れたエジプト文明の深い影響下に生れたことは自明のことである。そして、そのような文明の取次人として文化伝播の役割を担っていた人びとがいたこと、それが私たちがこれからその歴史を調べようとしているフェニキア人であり、カルタゴ人であったことは動かせない事実なのだ。
たとえば、西欧人が使用しているアルファベットはフェニキア人の寄与なしには成立し得なかったのである。じじつ、エジプト人の発明になるヒエログリフとシュメル・バビロンを故郷とする楔形文字とを総合して使い易い文字に考案したのはフェニキア人であった。それを土台にして、ギリシア人は今日のアルファベットの原形をつくり出したのである。この文字が、今や地球上のどこに行っても使用されているのは周知の通りである。
それでは、セム人種に対するインド=ヨーロッパ人種の偏見は、いつどこから生じたのであろうか。
偏見は、イエス・キリストを磔刑にしたユダヤ人に対して向けられたのが、そもそもの始まりだとすると、ユダヤの民と源を同じくして、類似点をたくさん持っていたフェニキア人やカルタゴ人に対する偏見もそれと同様に生れて来たものであろうか。
フランス人でアラブ研究家のピエール・ロッシが1975年に『イシスの市[まち]』(Pierre Rossi Nouvelles Editions Latines 1975) という本を出した。イシスというのはエジプトのオシリスと対にされている夫婦[めおと]神の女神の名である。ロッシは、そのなかでセム人種に対する不信の神話は、ある一人の学者のイマジネーションの産物であると、断定を下している。その学者とは『聖書と東方文学総覧』という書物を1781年に書いたドイツの学者A・L・シュレーゼルその人だという (A. L. Schlözel 1781)。ロッシは言う。
「諸国民をオリエント人とオクシデント人とに分割することが疑うべくもない真理として受け入れられているが、これがわれわれの歴史の鍵であって、この地理的分割が人種と言語との二重の国境に対応している。つまり、インド=ヨーロッパとか、時にはアリアンと呼ばれている人種と、セムと呼ばれる人種のあいだの国境である。今日まですべての良識のある人びとが、このドイツ人学者のイマジネーションから生れた発明のまえに脆いて来ているのだ。」
ここに書かれているドイツ人学者の説が、どのくらい広範な影響を西欧人のあいだに与えたのか、それを検証することは容易な業[わざ]ではないものの、その後19世紀になってダーウィンの進化論が書かれ、「自然淘汰」という概念が知性に革命をもたらした時点で、影響がはっきり見えてくる。ダーウィンは自然界に限ってこの説を主張したのであるが、彼の後につづくネオ・ダーウィン主義者たちの間では「社会淘汰」という概念が導き出される。その結果、さきのシュレーゼルの説と相乗効果を生んで、19世紀末の植民地争奪の傾向を生み出したものと考えられるからである。弱肉強食のジャングルの法則の理論的支柱がこうして生れることになったのだ。
オクシダンはアクシダン――L’occident est accident
西欧人のあいだに、第二次大戦の深い反省のあと、特に石油ショックのあと、ユーロ・ペシミズムといわれる一種の弱気がひろがっている。
その一つとして気がつくのは、西ヨーロッパの文明だけが唯一最良のものではないとの反省ではないだろうか。フランス共産党の理論家であったが、1970年に異端の故をもって除名処分になったロジェ・ガローディという哲学者がいる。彼は党を去ってからあと、インドや中国の古代文明の研究書を著して、『諸文明の対話に向けて』(Roger Garaudy <Pour un dialogue des civilisations 1977. Danoël) などの著書を発表している。そしてその中で、「オクシダン (西欧) は、アクシダン (事故) だった」という駄洒落に近い発言をしている。私はこの意味をどう受け取っていいのか当惑した。アクシダン accident という語は偶然の所産で必然のものではない、という意味であろうとは見当はつくが、それでもハッキリしたイメージが浮かばなかったのである。
ところがある時、ハタと思い当る出来ごとに出逢った。フランスの国内旅行に出ていたときのことである。ブルターニュの南岸の小さな岬を一巡するドライブ旅行を思い立って、朝の出掛けに、宿のお内儀[かみ]に道の具合はどうかと尋ねたのだった。するとお内儀の返事はこういうものだった。「C’est très très accidentel」、アクシデントが多いということなら運転に気をつけねばならんぞ、と私はその日の行先の状況を想い浮かべたものである。崖の下を通るとき落石があるかも知れない。急カーブで滑って海に落ちるかも知れない。えらいことになったぞ、とそのとき私は思ったのだ。
しかし、いざ行ってみると、道路はよく、危険なところは一切ないのである。風景は素晴らしく、大西洋の海風にたわめられた松林は独得の姿をして私を迎えてくれた。そこで私はようやく気がついた。宿のお内儀が言わんとしたのは、変化に富んだ風景であるということだったのだと。そして期せずしてガローディの言葉の意味もハッキリと私の心の中におさまった。西欧の近代400年の文明も、移り変る景色のひとコマのようなものであるということだったことに気がついた。西欧文明の優位は決して恒久のものではない、とガローディは言いたかったのだ。
かつてフェニキア人という航海に巧みで商才に富んだ民がいたこと、そしてその支族のなかにカルタゴ人という海の帝国を作った民があったことも、長い歴史のなかの一つの風景だったということになるのだろうか。
フェニキア人は、ギリシア人やローマ人のように、すぐれた美術品や文学、それから年代記のような歴史書も残していないので、これまでその存在したことさえ疑われるという始末だった。ローマ軍に焼き払われて塩をまかれたカルタゴの遺蹟も、その発掘はようやく今世紀になって始められたばかりである。また地中海のあちこちには、この海洋民族の残した植民地のあとが散らばっているが、それらの遺蹟も、ユネスコなど国際機関の手でなされている遅々たる調査を除けば、物好きの手で散発的に掘り出されているに過ぎない。「ポエニ戦役」で名高いザマの会戦の古戦場にしても、さきに見たとおりその場所は今なお確定されてもいないのである。
「ひとつの文明の死」の意味するもの
ヴァレリイは言う。「われわれもまた死すべきものである」と。ここで言外に匂わされているのは、個人の死のほかに集団の死、すなわちひとつの集団が維持発展させて来た、ひとつの文明の死でもある。
これと、ほとんど同じ言辞がカルタゴの終りの日にローマ人の口から出た。焼けただれて灰となろうとしていたカルタゴの市[まち]を前にして言ったローマの将軍スキピオのつぶやきである。
「いつか聖なるイリオンが亡びる日が来るだろう。そして、イリオンと共に、プリアモスも、また槍の巧みな使い手だった人民も亡びるであろう。」
これはホメロスの『イーリアス』の詩句である。イリオンとは、ギリシア軍に亡ぼされたトロイアのことであり、プリアモスはその最後の王であった。そのとき、スキピオの傍らにいたギリシア人の歴史家であり、スキピオの師であったポリュビオスが、そのつぶやきの意味するところを聞き返した。するとスキピオは答えたという。「ローマも何時の日か同じ運命を辿るだろうということだ」、と。
この故事に照らしても明らかなように、ヴァレリイが「われわれ」といっているのは、西ヨーロッパの知識人ということであろう。
ヴァレリイが亡くなってからすでに半世紀に達しようとしている今日、西ヨーロッパにはペシミズムの影が色濃くただよっている。
「ヨーロッパは気が狂って死にかかっている。葬式を準備せねばならぬときが迫っているのだ。しかし死なせるには及ばない。ヨーロッパは、その競争相手が実現した科学と経済の進歩から来るショックで、放っておいても死んでしまうことであろう。」(クロード・ジュリアン「息たえだえのヨーロッパここに眠る」1984年6月、『ル=モンド・ディプロマチック』(Claude Julien Le Monde diplomatique, Juin 1984)。
ここで競争相手と呼ばれているのは、もちろん、アメリカと日本である。しかしクロード・ジュリアンは右の一文をペシミズムだけで書いているのでないことは明らかで、彼はその次に長ながとECの統合問題に言及し、ヨーロッパの再生論に処方箋を出して、その上で次のように結論している。
「病んだヨーロッパは共同”市場”という考えを編み出した。つまり米国と同じような人口規模にまで消費者という顧客を拡大しようというのである。(しかし)もし明日のヨーロッパが存在し得るとするならば、それは共同”[太字→]生産者[←太字]”としてでなければならない。単にヨーロッパの市場だけではなく世界の市場を相手として[太字→]生産[←太字]しなければならない。そうするためには、ヨーロッパは少なくとも、新しいテクノロジーに根ざした共同科学研究と工業政策を持つ必要がある」(太字筆者)。
ミッテラン仏大統領が提唱したヨーロッパ全体が参加する「ユーレカ計画」のまさに原案がここにあると思われる。
今からおよそ2500年まえ、地中海のほとりに「海に投げ出された碇[いかり]」と形容された小さな港町があった。後方には未開の原住民が住む陸地があったが、原住民たちの生活程度ではこの港町に住む商才と技術をもつ移住者たちの致富の欲求を満足させることはできなかったから、彼らにとっては前面の海こそが世界だった。だが、彼らは志なかばにして灰に帰せられねばならなかった。海を隔てた対岸の国の若い軍事力に必死の抵抗を試みながら、ついにはほとんど皆殺しの目に逢い、財宝もほとんどが持ち去られるという悲運に見舞われる結末になった。これが海洋民族フェニキア人の子孫であった通商国家「海の帝国カルタゴ」の運命だったのである。いま、カルタゴがあったという土地に行ってみると、そこには「世界の七不思議」に数えられるエジプトのピラミッドもなければ、ファラオの壮麗な宮殿跡もない。ギリシア人が残したアクロポリスもなければ、ローマ人が残したコロシアムもない。カルタゴのあとを継いで地中海の通商の中心となったヴェネツィアのサン・マルコ寺院も残されていない。これはいったい、どうしたことなのだろう。そこで、衰亡や再生を繰返す世界史のなかで、カルタゴの歴史の意味を探ろうというのが、この本の主題である。
(つづく)