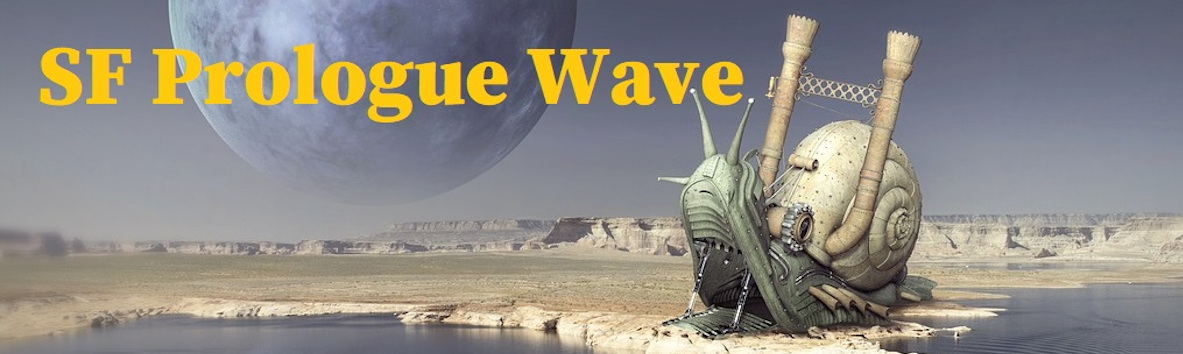1 元夫の場合
「今晩、空いてないか」
電話をしてきたのは、別れてから死んだ夫だった。
死んでから話すのは、これが初めてだ。驚いたけどOKする。彼のことが懐かしかったからというよりは、噂に聞く蘇生プログラムがどれほどのものなのか、実際に見てみたいという好奇心のほうが強かった。
都心のビル地下のバーで会うことにした。つきあい出した頃、お互いに残業が早く終わった時に落ち合っていた場所だ。あの頃のように、カウンターのすみっこに座る。正面には高級酒の瓶が並び、頭上で二列に吊されているグラスはどれもよく磨かれて光を弾いている。彼に連れられて、おそるおそる入った時には、わたしもこんなところに入れるような都会の大人になったんだな、という感激があった。あの頃はほんとうに若かったなどと思っているうち、約束の時間が過ぎた。
必ず遅刻するところはあいかわらずだ。
「やあ、待たせて悪かったな」
現れた人物は、まさしく死んだ夫そのものだった。ゴルフ焼けした顔に浮かんだ、許されることを確信している笑みも昔のままだ。
「いいよ。これで時間通りだったら、別人になったかと疑っちゃうから」
「おおお、怖い怖い。あいかわらず辛辣だなあ。それに、あんまり驚かないんだな。もっと驚くかと思った」
「話には聞いてたからね。電話をもらった時のほうが驚いた」
「そうか、そうかもな。まあ、見てくれよ。この義身、よくできてるだろ」
背格好や顔立ちはもちろん、カウンターに掛けた手の形にも見覚えがある。少し派手なネクタイの趣味も同じで、女とみれば、それが老婆であれ別れた女房であれ、愛想がよくなるところも一緒だ。
「触らせてもらってもいい?」
許可をもらって、彼の手の甲に触れてみる。長い指の形がピアニストのようで美しい。つきあい出したきっかけは、彼の口説き文句でも、整った顔立ちでもなく、その手の美しさだったから忘れはしない。ただし、その皮膚の感触は成人男性のものとしては柔らかめだった。
「この肌の質感の再現に、けっこう金がかかるらしいんだよ」
義身としては二番目に上等な機種だと自慢した。通常の行動には何ら問題ない。消化はできないが食べるふりをすることはできる。とある機能を除けば生身の体と遜色ない。海で泳ぐことだってできるそうだ。
「後悔はしてないの」
「後悔? 何の後悔だよ」
「たとえば、なんか違和感があるとか。データを取り始める前、たとえば子供の頃の記憶は完全には復元できないんでしょう?」
「エピソードとして知っていれば充分だ。おふくろや妹と会話してたって、『そんな古い話、忘れちまった』で終わりだよ。生身の時だって、子供の頃のことなんて、たいして思い返さなかったしな」
「それは、そうかもしれないけど」
「なあ、俺は死んだんだぞ。これを選んでなきゃ、こうして古い馴染みに会うことだってできなかった。後悔なんてあるはずないだろ」
水割りのなかの氷をみつめて、彼はゆっくりグラスを揺らした。こういう場合、なんと答えたらいいのだろう。
わたしを困らせたのを悟ったかのように、彼はニヤリと笑った。
「おまえだって、そろそろ準備を始めたほうがいいぞ。生前データは多いほうがいいんだからな」
「まあね。興味はあるから、今日だって誘いに乗ったわけよ」
「うわあ、あいかわらず愛想ないなあ。もうちょっとこう、あなたにまた会えて嬉しいとか、言えないわけ?」
「うん。まあ、古い馴染みとしては、会えて嬉しかった」
その後は、お互いの近況などを語り合った。けっこう楽しかったと言うべきだろう。
別れ際、彼は冗談めかして言った。
「もっと金が手に入って、無事、プレミアムタイプに乗り換えられたら、そんときに、また会おうな」
別方向に歩き出してから、彼の発言の意図に気づいて、思わず「バカ」と呟(つぶや)いてしまった。そういう図々しい台詞を平気で吐けるところも、生前の彼と同じだった。
2 父の場合
田舎で一人暮らしをしていた父が死んだのは、その直後だった。
契約を結んでいた見守り業者からの連絡を受けて郷里に戻り、業者の担当者と葬儀をおこなった。白いユリに囲まれた顔をみつめて別れを告げ、小さい扉を閉ざす。鉄の台に載った白木の棺が火葬炉に呑み込まれていくのを見送って、焼き上がりを待った。
「蘇生プログラムはお考えにならなかったんですか」
さりげなく、担当者が訊いてくる。
「父が望んでいませんでしたから。母のところへ行きたい一心だったの、ご存じでしょう」
毎朝、母の遺影に水をそなえて話しかけていたというから、それは担当者にも説得力のある理由だったようだ。一人でうなずいていた。
「立ち入ったことをお尋ねしてすみません。考え方は人それぞれですよね。わたしにも老母がいて、どうしようか悩んでいるので、それでつい、うかがってしまいました」
二三年前、蘇生プログラムが一般人の手が届く金額になり始めた頃、まだまだ元気だった父にプログラムを受けたいかどうか、質問をしたことがあった。そのときの父の答えは明確だった。「ごめんだね。あんなのは、どうせインチキだ。そんな金もないしな」
お金なら、あるにはあった。
独身時代からの貯蓄と彼からの慰謝料を合わせれば、一人分のプログラム代くらい出せないことはなかった。けれど、父にその気がない以上、お金は今後の介護や施設入居のためにとっておくべきだろうと判断した。結局、そのお金を使うまでもなく、父は逝ってしまった。
死後の手続きがすべて済んだところで、父が遺したデジタルデータをメモリアル業者に加工してもらった。自宅の端末画面に父の顔をしたアイコンが一つ増えて、その気になれば父の画像を立ち上げて、声を聞くことができるようになった。
「玲子、元気にしてるか?」
元気だった頃の父から、そんなふうに話しかけてもらえるのは嬉しかった。AIが父の遺したデータから判断して作成している言葉だと理解はしていても、亡くなる前、あまり喋らなくなっていた父よりもずっと、本来の父に近いと思えた。母が亡くなって落ち込みはしたものの、そのうちに一念発起、母の得意料理だったポトフをつくれるようになって自慢げにふるまってくれた頃の父だった。
母の時には、このデータメモリアルサービスが一般的ではなかったのが残念だ。遺影の母に話しかけても返事は戻ってこない。
3 わたしの場合
わたしには兄弟がない。別れた夫との間に子供もなかった。職場の人たちとはうまくやっていて、たまにプライベートでも遊びに行けるくらいの関係だけど、所詮は仕事上のつながりだ。学生時代の友人たちは子供の受験や介護に忙しそうだ。父が生きている間は父関係の用事で休日が潰れることがたびたびあったが、そんなこともなくなって、一人で本を読んだり動画を観たりして過ごすようになった。画像の父とは毎日、話していたが、そうそう長く話し込むような話題もないし、かえってつらくなることもあった。
ふと思いついて、地下のバーでもらった元夫の連絡先に電話をしてみた。
もちろん、寂しいとかつらいとか、そんな愚痴を口にはしない。
ただ、彼は話し上手だった。そして、父を亡くした女に優しかった。電話をするたび、わたしのプライドを傷つけないように、わたしの欲しい慰めを言ってくれ、わたしの望む励ましの言葉を与えてくれた。
そんなつきあいが続いて、彼の軽口に笑うこともできるようになったところで、彼は言った。
「なあ、例の件、そろそろ、本気で考えてみないか」
「例の件って?」
「蘇生プログラムだよ。興味はあるって言ってたじゃないか」
「ああ、あれね」
「まだ若いって思ってても、人間なんて、いつ死ぬか分からないぞ。気づかないうちに病気が進行してることだってあるし、事故なら一瞬だ。そのときになって後悔しても遅いんだからな」
「縁起でもないこと言わないで。あなたは一度、死んだことがあるから抵抗ないんだろうけど、生きてるわたしとしては、死ぬ死ぬってあんまり言われるの、気分悪いんですけど」
「ははは、そりゃそうか」
「それにね、蘇生プログラムで生き返って、それからいつまで生きるのか、生きてて何になるのかって思ったら、積極的にプログラムを受けるような気にもなれないのよ」
うっかり本音を漏らしてしまったと気づいた時には、怒鳴られていた。
「生きてたら、何だって、できるだろう」
受話器を離したくなるほどの大声だった。
付き合おうと切り出された時、別れ話の時でさえ、ふざけてばかりだった彼なのに。
「やり直したいんだよ。俺のこと、許せないと思っているのは知ってる。すぐに、とは言わない。けど、永遠に近い時間があったら、気持ちが変わるかもしれないじゃないか」
わたしはもう、バーへ入るのさえおどおどしていた田舎の女の子じゃない。
彼の言葉を百パーセント信じる純朴さはない。
それでも、暇つぶしのためだけにでも行ってみようか、と気持ちが動いた。
蘇生センターでは人間の脳の仕組みが丁寧に説明された。また、すでに法律が整備されており、蘇生者は生存時の法律的権利、義務をすべて引き継ぐものと規定されていることも知った。
「以前から義手義足はありました。脳波は完全にその人のものですから、それ以外の部分が義身になったからといって、別人の扱いを受けるのは不合理ですからね」
担当は微笑みながら、タブレットを渡してくれた。
「その法律で、蘇生希望者は、この条項を読むことが義務づけられています。いちおう、目を通してもらえますか」
「一、意識の同一性を外側から判定することはできない。
一、可能であるのは、脳波の同一性もしくは思考、感情、感覚の表現方法の類似性の認定のみである。
一、すなわち、蘇生者とは自己に限りなく近い他者であることがありえる」
「なんだか、抽象的な文章ですね。わたしにはよく理解できません」
「皆さん、そうおっしゃいますが、プログラムの参加前に読んでいただくことが法的に義務づけられているものですから。形式的なものです」
わたしのような反応には慣れているのだろう、担当の口調は滑らかだった。
説明はそこまでだったが、ついでだからと全身スキャンを提案されて受け入れてしまった。プログラムを受けないとしても、全身の復元設計図を保存しておけば義手義足が正確につくれる。何かあった時の保険になりますよ、今がいちばん若いんですから若いうちに保存しておいたほうが、と説得されたのだ。
さらに、せっかく全身スキャンをしたんですから、脳波の収集はしておきましょうとイヤホン状の機器を渡された。今後、寝る時もこれを耳につけておくことで脳波が収集され、死の直前の脳波が義身へ受け渡されるということだ。
「つまり、交通事故や飛行機事故の衝撃で、このイヤホンがふっとび、その後死亡された場合は事故前の脳波が用いられることになります。厳密には死の直前の脳波でなくなりますが、そこは了承いただいています。よろしいですね」
わたしは頷いた。病院のベッドで死ねるとは決まっていない以上、それを問題にしたら、この蘇生プログラムは成り立たないだろう。
よく考えてみますと言って、その場は帰ったものの、一週間後、わたしは契約書にサインした。
4 生身のわたし
そして、わたし、渡部玲子は死亡した。
朝の通勤途中、駅のホームで心筋梗塞を起こしたのだ。
その後、予定どおり、蘇生プログラムによって蘇生者とされたらしい。
しかし、わたしは医師による死亡判定から二十四時間たった後、火葬場で焼かれる直前に本来の意味での蘇生を遂げた。すなわち息を吹き返したのだ。棺の小扉を閉めようとした焼却の係官が、わたしの瞼(まぶた)が痙攣(けいれん)しているのに気がついたという。わたしは救急車で近くの病院に運ばれて処置を受け、十日後に意識を取り戻した。
そのとき、わたしの枕元には、わたしの蘇生者がいた。
「ほんとうに驚いたわね」
わたしとそっくり同じ顔、同じ口調で蘇生者は言った。
「これだけ医学が進歩していて、まだ、こういうことが起きるんだもの。びっくりよ」
ほかに、そばにいたのは医師と蘇生センターの担当者だった。医師は倒れてから今ここに至るまでの経過を丁寧に説明してくれたが、わたしは自分とそっくり同じ顔の蘇生者から目が離せなかった。
「ちょっと待って。わたしがこうして生きているのに、どうして、この人がここにいるの?蘇生プログラムの開始が早すぎたってこと? だったら、キャンセルしてもらわなくちゃ」
蘇生者は答えず、代わりに、センターの担当者が口を開いた。
「大変、申し上げにくいのですが、先ほどご説明があったとおり、医学的に、あなたはいったん亡くなられました。だからこそ、蘇生プログラムが発動し、こちらに新しい玲子さんがいらっしゃるのです。現時点で、あなた、渡部玲子さんが持っていらした法的権利はすべて、こちらの玲子さんに引き渡されています」
「それ、どういうこと」
「現時点では、こちらの玲子さんが、社会的法的に渡部玲子さんとして認められている、ということです」
わたしの意識がない間、わたしと同じ顔をした、この蘇生者がわたしづらをして動き回っていたかと思うと、おぞましくて吐き気がした。
「裁判でも何でもするわよ。この人なんて、機械の体にわたしの脳波を載せただけの、サイボーグじゃない」
「その発言は取り消していただけますか。差別にあたります。プログラムのご説明の際に申し上げましたとおり、蘇生者の権利は自然人と同様に守られます」
「それってつまり、今のわたしは死んだも同然、いっそ焼かれてしまうほうがよかったってこと?」
おもいきり声を張り上げたつもりだったが、喉が重く、口も開くことができず、金切り声にはならなかった。
「感情的にならないで。誰も、そこまでは言ってないでしょう。でもね、面倒を抱え込んだって思ってしまうくらいは許してもらいたいものだわ」
理知的でクール、自他ともに認めてきたわたしの長所だけれど、今この瞬間、わたしと同じ顔をした蘇生者に再現されると、猛烈にムカついた。ムカついたけれど、この蘇生者の立場に立ってみれば、その言葉にも一理あるのかも、とつい思ってしまった。 どうやら、今のわたしは、この蘇生者のお情けによって生き延びさせてもらっている、という立場らしい。
5 義身のわたし
わたしがそれを聞いたのは、義身に馴染むためのリハビリ中だった。たかだか、ガラスのコップを割らないように持ち上げる、それだけの動作が難しい。意識を集中させて、水の入ったコップを口元へ運ぼうとしているところで「玲子さん」と呼びかけられた。
センターの担当者だ。顔色が変わっている。
「火葬場から連絡がありました。あなたが生き返ったそうです」
「わたしが生き返った?」
「あなたの体が息を吹き返しました。いや、なんて言ったらいいんですかね。体だけとも言えない。生身のあなたが甦ったそうです」
担当者は何度も言い直しながら、心臓停止と脳死が確認された肉体に生体反応が復活して、火葬が取りやめになったと伝えてきた。
「焼かないって? でも、わたしの体だけ生かしておいたって仕方がないでしょう?」
わたしは、病院のベッドにたくさんの管をつけられて横たわっている体を想像した。まっさきに心配したのは費用のことだ。貯金は蘇生プログラムのために使い果たした。二度と使いもしない体のために、高額の療養費を請求されるのは困る。
「それが、意識が戻って会話ができるようになる可能性もあるそうなんです」
いかに異例の事態であるか、センターとしても対応を協議中であることなどなど、担当者はいろいろ話しかけてきたが、わたしはとにかく今すぐに、わたしの元の体が収容された病院へ行きたいと主張した。
ベッドの上で呼吸器をつけて眠り続ける、わたしの寝顔は真っ白で、生きているとは思えなかった。正直なところ、このまま、もう二度と目覚めないでほしい、と思ってしまった。いや、もっと正直な話、目覚めないまま死んじゃってほしい、とすら思った。もし、この人が起き出してきたら、このわたしの立場はどうなる?
リハビリの合間を縫って病院へ通うようになったが、その寝姿を見れば平静ではいられなかった。ぐったり疲れて、リハビリにも集中できなくなる。それでも病院へ行くのをやめることはできなかった。
幸か不幸か、恐れていた瞬間は意外に早くやってきた。瞼が開き、意識が世界を認識し、もう一人のわたし、生身のままのわたしが、義身に移ったわたしを認める瞬間。
「ほんとうに驚いたわね」
とっさに本音を隠してしまった。本当は「ほんとうに困ったわね」と言いたかったのだ。
怪訝(けげん)そうな顔でわたしを見ている女性、それがかつてのわたしであることはどこか信じがたかった。生き別れだった双子の姉妹、と説明されるほうが納得がいく。
姉でも妹でもない、ベッドの上のわたしは白衣を着たまま、叫び散らした。
「それってつまり、わたしは死んだも同然、いっそ焼かれてしまうほうがよかったってこと?」
もっと冷静にふるまってもらいたいけど、死んでいた自覚がないのだし、蘇生プログラムを受けたことも記憶にないのだから、混乱するのも無理はないのかもしれない。
落ち着かせてあげたいとは思ったけれど、当たり障りのないことしか口にできなかった。
「まあ、とりあえずは治療に専念するほうがいいわね。あとのことは治ってから、ゆっくり考えましょう」
6 生身のわたし
退院の日、わたしは蘇生者とともにタクシーに乗り込んだ。マンションのエレベーターでは他の階の住人と乗り合わせたが、衛生処置のために髪を短く刈り込まれたわたしと、以前のとおり長い髪の蘇生者とでは印象が違うためか、同じ顔を見比べられるようなことはなく、無事、九階の部屋まで上がることができた。
部屋に戻ったからといって、病院にいる時より状況がよくなったわけではない。
わたしのなけなしの財産は蘇生者が握っていて、わたしは下着の一枚も持っていない。頼れるような身内はもうどこにもいないし、職場の同僚たち友人たちには蘇生プログラムのことを話していなかった。蘇生者はすでに、わたしの名を名乗って職場へ出勤しており、何の苦もなく、わたしの職務をこなしているらしい。
だが、お気に入りのクッションを抱え、お気に入りのソファに座ったことで、少しは気分がよくなった。
「そうそう、リラックス。こういう時はそれがいちばん」
蘇生者は北欧産のラグに腰を下ろして足を伸ばした。
来客者の前で、そんな恰好をするのは行儀悪い。でも、わたしが相手なら、そんなふうにくつろいだ姿勢をとったってかまわないわけだ。わたしも少し肩の力を抜いた。
「お茶、入れようか」
そう提案したのは同時だった。
蘇生者もわたしも顔を見合わせて笑ってしまう。
これが同じってことなんだ。同じ人間、同一人物だ。
蘇生者がお湯を沸かしてくれている間に、わたしが棚から長らく使っていない萩焼の湯飲みを出した。二人でラグの上にぺたりと座り込んで、ふうふう言いながらお茶を啜る。
「コーヒーのほうがよかったかな」
「たまに煎茶もいいでしょ」
「あなたが治療を受けている間、考えてたんだけどね。二人で暮らせないことはないと思うのよ。他の人には双子の姉妹ですってことにして、二人で仕事と家事を分担すれば、わたしのほうは食費がほとんど要らないから生活費が増えるってこともないし、話が合うってことは折り紙つきなんだから、最高の同居人じゃない?」
残業してくたくたになった後、夕飯の用意ができていたら、どんなにいいか。突然、降り出した雨にも、外に干しておいた洗濯物の心配をしないでいいのは、どんなに楽なことか。難しいクレームに対応しなくちゃいけない日、どちらが出勤するかは揉めそうだけど。
わたしがその気になったのを察したのだろう、蘇生者は笑顔になった。
「それじゃ、お父さんに報告しましょう」
蘇生者は端末を起動させた。画面に父の顔がアップになる。
「おや、玲子、お帰り」
この父と話すのは倒れてから、これが初めてだ。
返事をしようとすると、画像の父はわたしを待たずに蘇生者に向かって言った。
「お友達の具合は、どうなった? 退院できたのか」
「今、ここにいるのよ。それで、あの、挨拶してもらうんだけど、驚かないでね、」
わたしは蘇生者を押しのけて、端末の電源を切った。
父は消え、画面は暗くなる。
「何をするの。強制終了させたら、お父さんのデータが壊れちゃうじゃない」
「どうして、わたしが、あなたの友達ってことになってるの」
「これから説明しようとしてたのに、いきなり切るなんて、ひどい」
「どっちがひどいのよ」
「だって、あなたのこと、説明しようと思ったら、わたしが蘇生者だってことから説明しなきゃならないでしょう。わたしは、まだ、お父さんに自分が死んだこと、話してないの」
わたしは、わたしとそっくり同じ顔を睨(にら)みつけた。
悪意はなかったのだろう、そうだろう。
でも、このわたしモドキはこれからも、誰に対しても自分が蘇生者であることを隠そうとするはずだ。自分がただ一人の渡部玲子としてふるまうだろう。わたしが同じく蘇生者であったとしたら、そうするから間違いない。
モドキがいる限り、わたしはわたしとして認めてもらえない。
わたしはモドキと同居できない。同じ空間を分け合うことなんてできない。
モドキとわたしとは最悪のライバルだ。
わたしは体中をめぐった激情を必死で押さえ込もうとした。
7 義身のわたし
生身のわたしが、わたしを本気で憎んだことを、わたしは悟った。
隠しきれるはずがない。その気持ちは体の隅々にまで現れていた。生身だからこその反応だろうか。
画像の父に蘇生プログラムのことを話さず、心臓発作を起こしたこと、生身のわたしが息を吹き返したことも説明せず、ことここに至るまで、この人のことを父に打ち明けておかなったのは悪いと思う。だけど、だからといって、いきなり、こんな態度をとるなんて。
できるなら、面倒な裁判などはせず、二人で静かに暮らしていけたら、と思ったけど、それは無理かもしれない。他の人に対しては冷静に理性的にふるまうけれど、それは言葉や行動を抑えているだけで、心の中はとても感情的、それがわたしだってことは、このわたしがいちばんよく知っている。
8 生身のわたし
蘇生者は静かな表情でわたしに向き合った。
「こんなふうに、すぐにお互いを憎み合うなら、とても一緒には暮らせないわね。これから、どうする? トラブルが大きくなれば、センターや他の機関も介入してくると思うわ。その前に、自分たちで決着させたくない? あなたとわたし、これから渡部玲子として生きるのはどちらがふさわしいと思う?」
ふさわしくないほうが消える、ということだ。
わたしは蘇生者を睨み返した。
「こんなことになったのは、本来の時期よりも早く蘇生プログラムが発動してしまったのが原因でしょ。義身から、わたしの脳波を取り外してもらうのが当たり前だわ」
「死んだ後に蘇るなんて、誰も想定してないの。イレギュラーな事態を起こしたあなたがいなくなったほうが、法律的にも社会的にもスムーズ、プログラムを推進したいセンターもそれを望んでいる、と言っても、あなたには納得できないでしょうね」
蘇生者の腕が、わたしの首元へ伸びてきた。
腕力勝負となったら、生身の体をもつわたしのほうが圧倒的に不利だ。
「人殺し」
後ずさりしながら罵る。
「違う。間違って存在してしまった自分の別バージョンを消すだけ」
蘇生者はあくまで冷静に見えた。それが義身の性能の限界なのか、それとも、わたしは人を殺そうとする時、こんな顔をするのだろうか。
殺される間際にまで、どうでもいいことを考え続けてしまう自分が呪わしい。
蘇生者の親指が喉に触れた。
苦しいのは嫌。お願いだから、やるんなら一気にやって。
目をぎゅっと瞑って、痛みと呼吸困難を予想した。だが、それ以上、喉に圧力は加わらなかった。目を開くと、相手のほうが目をそらしていた。
「どうしたの? やるんじゃないの」
わたしは大きく深呼吸をしながら、蘇生者の隙をうかがった。
次に蘇生者が顔を上げた時、その表情はこれまで、わたしが一度も鏡のなかに見たことのないものだった。
「わたしに、できるわけないでしょう。あなたはできるの? そうね、あなたならできるわよね。あなたのほうが本物のわたしだもの、偽物を消すことに心は痛まないわよね」
え? と思った。わたしが心の中で思っていることを、そっくりそのまま相手が認めるとは思わなかった。何も言い返せないまま、相手の呟きを聞く。
「こうなったのも仕方ないわね。だって、わたしたちって、本当に」
蘇生者の言葉をさえぎるように、ピンポン、とチャイムが鳴った。
体が勝手に跳ね上がる。こんな時に、誰がここへ訪ねてくるのだろう。
蘇生者も動こうとしたが、インターフォンにはわたしのほうが近かった。
「おい、俺だよ。早く入れてくれよ」
元夫のにやにや顔がモニターにアップになる。
わたしは画像を体で隠し、受話器の集音部分を掌で覆って、蘇生者を振り返った。
「あんた、まさか。この部屋にあいつを入れてたんじゃないでしょうね」
「いけない? あなただって、彼とよりを戻すの、悪くないって思ってたじゃない」
「彼はあなたが蘇生者だって知ってるの?」
「ほかに打ち明けられる人、いなかったから」
「なあ、入るぞ」
受話器から彼の声が漏れる。彼は合鍵を持っているらしい。ドアが開く音がした。
「彼に決めてもらいましょうか」
蘇生者が言った。
同じ蘇生者同士だから、彼が自分を選ぶことに自信があるのだろう。
でも、どうだろう。彼は生身のわたしのほうが好きなのではないだろうか。わたしのことが好きだからこそ、やり直そうと言ってくれたのだし。
わたしは蘇生者と並んで、彼を迎え入れた。
9 生身のわたし/義身のわたし
髪の長いほうと短いほう、それ以外は同じ二つの顔を見比べながら、彼は言った。
「選ぶ必要なんてないだろう。俺としては渡部玲子が二人いたって全然、かまわないぞ」
張り詰めた気持ちが一気に緩む。彼のほうはニヤニヤしている。
「いまは冗談言わないで」
わたしたちは、ほぼ同時に叫んだ。
「冗談じゃないさ。気分が変わって面白いと思うな。三人なら、かえって前よりも関係が長持ちするんじゃないか」
そうとも、冗談じゃない。
知っている。これは、そういう男なのだ。
「ああああ、尋ねる人間を間違えた」
わたしたちは協力して、彼を部屋から追い出した。
そうして、静かになった部屋のなかで、お互いの顔を見合わせた。
これがわたしだ。髪の長さ以外、どこをどうとっても、小さなシミ、瞳の輝きにいたるまで、うり二つな顔。きっと、その瞳のなかにも、わたしが映り込んでいるだろう。
「ねえ、わたしたちって、本当は」
ふたたび同時に発話して、そのせいで、何を言いかけたのか、また分からなくなってしまった。合わせ鏡のなかに、どこまでも続く自分の顔をみつめているような気分だった。