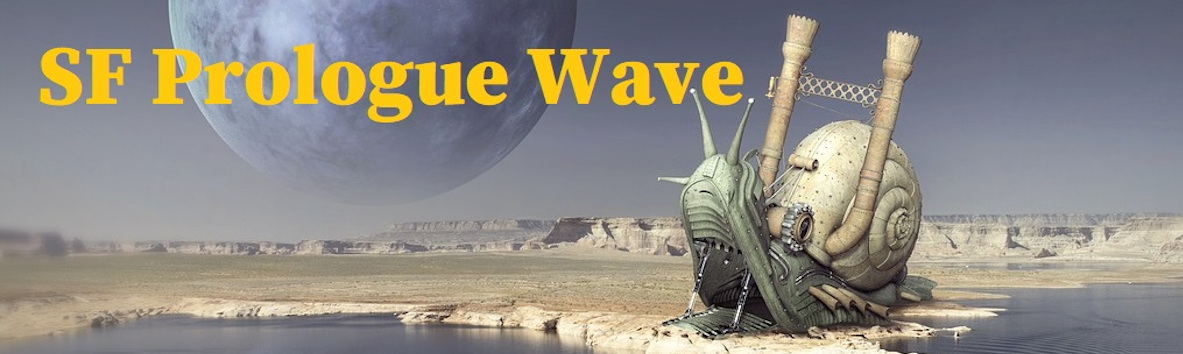![]()
(PDFバージョン:kietesimattamessage_kimotomasahiko)
特別支援学校の指導員という仕事をしていると、色々な子供に出会う。
タケシは喋らない子供だった。
小学三年生になっているが、喃語──いわゆる赤ちゃんが出すような言葉を数語使うだけで、発語は少なかった。せいぜい二語文が限界だった。
それでも、身振り手ぶりや、マカトンという簡単な手話を併用することで、彼は周囲に意思を主張していたし、周囲も彼のことを、部外者が想像する以上に理解していた。友達にしろ先生にしろ、付き合いが三年にもなると、以心伝心という部分が出てくるから、当然とも言えた。
僕が勤めている特別支援学校は、主に軽度から中度の知的障害の子供を受け入れている。軽度の知的障害というのは、だいたい知能指数が50から70程度の子供のことを指す。平均が100なので、普通を基準に考えればやはり低い。
いくつかある知能検査や発達検査の方法に共通して言えるのは、言語能力が大きな割合を占めるということだ。たとえば指差した絵に書かれている動物の名前を言えるかとか、青い鉛筆はどれ? という質問に回答できるか、など。後者の場合は、青と鉛筆というふたつの属性が合わさったときに理解できるかという設問になる。
僕は指導員なので、直接試験をすることはないが、試験の様子を見学することはある。その様子を見ていたり、結果の説明を聞いたりしていると、こういう試験で子供の成績というか知能指数の数値を測るというのは、難しいものだなと感じることがある。
飛行機というものを理解しているけれど、発語できない子供の場合、これはなに? と聞かれると両手を広げてブーンとやったりする。彼は飛行機を理解しているのだが、それを言葉では表現できない。しかし彼にとっては、両手ブーンが言語の替わりなのだ。
理解力だって意外にあるように思う。僕がタケシと関わっている範囲で感じるのは、多分この子は僕の言っていることをほとんど理解しているであろうということだ。だけど彼自身は言葉を出せないから、もどかしいだろうな、と。
そんなことを心理士の先生に話してみたところ、
「日常生活での理解ってのは、その前後の流れや習慣や視覚情報から総合的に判断したりする部分が混ざってきます。色々な情報源から得られたものから彼は反応しているので、一見すると言っていることを理解しているように思うかもしれませんが、言語単体の理解力は検査結果として出てくる通りなのです」
という答えが返ってきた。周囲が思っているほど、彼は「言語」を理解しているのではないというのだ。
そうなのだろうか。
そんな疑問を抱えながら、僕は今日もタケシと遊ぶ。
タケシはタブレットを使って勉強していた。この支援学校では、教材のひとつにタブレット型端末を導入している。学校のカリキュラムの範囲は、ひらがなとカタカナ、算数だったら足し算と引き算くらいまでだが、生徒の進度によっては掛け算を自習させたりもする。文字の学習にも、指で書き順をなぞれるタブレット端末は有効だった。
タケシが使っているアプリケーションは、一見するとゲームのようなものだった。
見たことのないアプリだった。
僕は彼の隣に座って、彼がそのアプリを使う様子を見ていた。
画面の下のほうに、四角い枠が三つ並んでいる。その上に同じように三つの枠があり、そこに変な図形が表示されていた。画面の上半分には、お化けのようなキャラクターが表示されていた。どうやら表情の豊かなキャラクターのように見えた。
上の三つの枠に図形が表示される。それを見たタケシは下の枠に違う図形を描く。すると、画面上半分のキャラクターが笑ったり怒ったりする。
図形当てゲーム? 何かのパズル? それにしては、図形のルールが分からないと思いながら、タケシがアプリを楽しそうに操作する様子を見ていた。
「なあ、タケシ」
「アイッ」
「それ、面白いの?」
「アイッ!」
彼のタブレットの操作と、お化けのようなキャラクターの反応を見ていると、まるで会話をしているみたいだなと思った。そのとき、ある可能性が僕の中でひらめいた。
「なあ、タケシ、それ僕もやっていい?」
タケシはうんとうなずいた。僕は彼のタブレットを借りてアプリの名前を調べて、同じアプリを自分のスマホにダウンロードした。アプリは無料で、広告も出ないものだった。
僕はタブレットをタケシに返し、自分のスマホでアプリを起動した。画面が小さいから若干扱いづらくはあったが、同じものがちゃんと動作した。
少し使ってみて首をかしげる。ルール説明が何も出てこないのだ。そもそも日本語がどこにも出てこない。じゃあ英語アプリかというと英語もどこにも出てこないし、中東のほうの文字が出てくるわけでもない。文字らしき文字がどこにも出てこない。
だけどタケシはアプリを使いこなしている。楽しそうに遊んでいるように見える。
もう少し調べようと思いながら、その日は帰宅した。
帰宅した僕は、アプリを起動し──そしてアプリをプレイし続けた。
集中してやり続けた。止められなかった。
3日間、仕事を休んだ。
3日して、さすがに仕事場から電話がかかってきた。僕はほとんど食事もしていない状態で、ふらふらになりながらも「すいません、行きます」とだけ返事した。
途中のコンビニでゼリー飲料とエナジードリンクを5本ずつ買って、一気に飲んだ。腹がタプタプになったけれど、手っ取り早い栄養補給だ。おそらく死にはしまい。
仕事場につき、僕はタケシのところにいった。画用紙を出して、3つの枠と、その中に図形を描いた。タケシは驚いた顔をしたけれど、次の瞬間にペンを持ち画用紙の別のページに3つの図形を描いた。そうだ、枠は必要ない。3つの図形が重要だ。
僕はそれに対する返事として3つの図形を描いた。その次にタケシの番。次は僕の番。
これは会話なのだ。言語なのだ。あのアプリは言葉を学ぶアプリなのだ。
三つの枠をAとBとCとしよう。Aには主語が入る。Bには述語が入る。Cはない場合もあるが、目的語が入ることが多い。英語のSVO文型と同じと言えば通じるだろうか。厳密には主語や目的語は述語によって役割が変わる。AとCの関係を記述するのがBであるというのがシンプルな文法の説明だ。AとBとCを表現するのは、様々な図形であり、図形の3つの連なりで、色々な表現が可能になる。
これはつまり、日本語とも英語とも違う、独自の言語であり、タケシはそれをアプリで学習して身につけていたのだった。
そして三日間の没入の成果として、僕もこの言語を身につけた。いまや僕は、タケシと会話ができる。タケシは言葉が遅れているのではない。彼の中には豊かな言葉が内在していて、それを発現させる方法だけ用意してあげればよかったのだ。
タケシはもう、喋れない子供じゃない。僕と会話ができる。
タケシはもう、言葉を持たない子供じゃない。豊かな言語能力を持っている。
「すごいなタケシ。すごいなこのアプリ」
スマホのアプリを起動しようとしたら、アプリは消えていた。おや? と思って、タケシのタブレット端末を見せてもらったら、こちらもアプリが消えていた。幸い名前は覚えていたので、検索してみたが、アプリは見つからなかった。どこかに記録が残っていないかと思って、ネット全体で検索してみたけれど、そんな名前のアプリは見つからなかった。
消えてしまった。
タケシに言葉を与えてくれたアプリは消えてしまった。
どういうことなのだろう。誰かが半分いたずらで、期間限定で公開していたアプリだったのだろうか。
誰かってのは、……たとえば神様みたいな誰か。どこかの宇宙人かもしれない。
いやしかし、と僕は考える。僕は既に言語をマスターしたし、タケシもマスターしている。だったら僕とタケシの会話に問題はないじゃないか。僕が彼と話すことができることに、間違いはない。
僕は欠勤の謝罪をすると同時に、顛末を校長に説明した。
「すばらしいことだと思いませんか?」
「それで?」
校長先生はなぜか冷静だった。興奮するに違いないと思っていたのに拍子抜けだ。
「喋れないと思っていた子供が、実はものすごい言語能力を持っていたんですよ!」
「しかしそのアプリは消えてしまった」
「はあ……まあ……でも大丈夫です。僕とタケシは会話ができます」
勢いづく僕を、校長は制止した。そしてゆっくりと、諭すように言った。
「言葉というのは、それを使う社会があって意味を持ちます。タケシくんがその言葉を使えたとしても、他の人が使えないのでは意味がありません。それともあなたは、タケシくんの社会すべてになれるのですか?」
社会……すべて?
僕とタケシしか使えない言語が作るのは、僕とタケシだけの社会ということか。
それは社会と呼べるのだろうか。……いや、呼べない。何より、僕はそこまで、彼の人生に責任を負えない。
もう少し落ち着いてから今後のことを話しあおうと校長先生に言われ、僕は校長室を後にした。
僕とタケシだけの言葉に意味は……ないのか?
それなら僕とタケシだけじゃなくて、他の人にも言葉を広めればいいんじゃないだろうか。教科書を作って辞書を作って……無理だ、そんなこと、僕には無理だ。僕は学者ではないし、専門の教師でもない。自分が覚えていることを書き出し終えるまでに、言葉を覚えていられるかすら、怪しいものだ。
タケシが僕の手を引っ張る。彼は何を求めているのだろう。
……ああ、言葉だ。僕はあらためて、彼に言葉を教えないといけない。誰にでも通じる普通の言葉を、だ。
それは複雑で、煩雑で、曖昧で、いびつで、不格好な文法——あるいは文法を外れた用法の集合だけれど、ひとびとが使っている言葉だ。
僕らで言えば、すなわち日本語だ。
僕はタケシにこのことを伝えないといけない。僕らの言葉では意味がなくて、これまでと同じようにみんなが使っている言葉を覚えないといけないのだと。
彼にそれを伝えるための、3つの記号を書こうとして、僕ははたと気づいた。僕らの言語には「言語」という語彙がない。必要十分な文法と語彙を持つはずのその言語は、自己完結しているが故に、それ自身を示す語彙を持たないのだ。
だから僕は、タケシに日本語で伝えなければならない。
「言葉を覚えよう」
「バ?」
膝をついて、彼と同じ目の高さになった。この姿勢は子供に合わせているようでいて、子供を大人扱いしていないことだからよろしくないと書いてあったのは、何の本だっただろう。でも僕は、タケシの目を正面から見たかった。
「そう、コトバ。みんなが使っているコトバ。みんなと話せるコトバ。どこの誰とも知れない神様か宇宙人がくれたような言葉じゃなくて、みんなが使っているコトバだよ。ゆっくりでいい。どうしてかって言うと……」
「ト?」
「僕たちは、人の中で生きていかなけなきゃならないからだ」
タケシは不思議そうな顔で、僕をみつめていた。
木本雅彦既刊
『人生リセットボタン』