![]()
(PDFバージョン:otokohaonnnanotekidehanai_miyanoyurika)
光瀬龍氏が「仕事」について語ったことについて書いておこうと思う。
小説家専業となるまで、彼はある女子高校の先生をしていた。
教師をやめた事情について、話を伺ったことがある。
いろいろな「物理的な事情」についてリアルに語ってから、彼は言った。
あらゆる「物理的な事情」は、本当はたいしたことではなかった、と。
「結局、育てることにおいて、男は女の敵ではないと思い知ったからなんだ」
この「敵ではない」とは、「敵(かな)わない」「絶対に勝てない」という意味である。普通に話しているときでも、こういう漢文直訳的な言い回しをする人だった(註1)。
「担任していた生徒の妊娠」を、彼はそれを象徴する事件として話題にした。
生徒の妊娠を知った時、彼には「妊娠=淫行の結果=退学」ということしか頭に浮かばなかった。同僚に年配の女性がいて、上手に周囲に根回ししてツジツマを合わせて卒業させてしまった。
「すべてが丸く納まるようにしたんだ。高い見識と実行力のある人だった。こちらの顔も立つように配慮までしてくれてさ、もう、心の底から『敵(かな)わない。負けた』と思ったよ」
その同僚のことを、彼は高く評価していて、他のエピソードも聞かせてくれた後、こういう意味のことを言った。
「とにかく、最初の発想の時点で自分はダメだ。そう思ったら、すべてがそれなんだね。そういう絶望が根本にあった。結局、男には『育てる』ことなんかできないんだ。根本的にできないんだよ。それがよくわかったんだ。それは、努力でどうなるものでもない。絶対に敵わないんだ。最高地点に自分は行けない。仕事をしていく上で、そう思ってしまったら、これはつらいよ。だから、別の道を模索せざるを得なかったということだ」
○
このような話を伺ったのは、平成2(1990)年の正月のことだ。場所は彼の仕事場である。5年ぶりの訪問だった。
昭和60(1985)年、就職と同時に、私はそれまで住んでいた下宿を引き払った。そして、光瀬氏に引っ越し先も電話番号も伝えなかった。
大反対なさる光瀬氏のご意見を無視して、私は就職した。その反対ぶりというのは、かなり徹底していた。こんな話をしてくれたこともあった。
「僕は東京教育大学の動物学科を卒業した時、○○中学校(註2)の理科の教師として採用されることが内定していたんだよ。そこで講師もやっていたから、試験は作文だけの形式的なもので、まず落とされる恐れはなかった。だけどね『来年からはお仲間ですね』なんて、したり顔で言われると、『そうなってたまるか』と思ってしまってね。紹介してくれた人の立場とかもあって、自ら辞退はできなかったから、作文の答に、横書きでカタカナで自作の詩を書き綴ったんだ。……で、思惑通り、見事に落ちたよ」
彼は笑ったが、私は笑わなかった。一生懸命、就職活動をしている真面目な学生がこのような話を聞かされたら当然するであろうような反応をし、もちろん、就職活動をやめなかった。
就職の1次試験に合格したことをお伝えしたら、原稿用紙10枚の手紙がきた。「2次の方、休んでしまえばいい」「あなたの才能を惜しむ」「(就職したら)雑用に埋没」「若い時は2度とはない」「あとで困るような試験など受けたりしないこと」「きっと後悔します」などなどと書かれていた。
ちょうど月末だった。「(来月は)1、3、8、9、15、21、26日以外はいつでもいます。おりを見てお出かけください」としめくくられていたが、私はそれきり行かなかった。就職を急ぐ事情について説明したくなかったし、もちろん、「休んでしまえばいい」という彼のアドバイスを受け入れる気もなかったからである。
かくて、5年が経った。
5年目に、ふと思い立って年賀状を出した。来訪を求める返事が来たので、出かけていった。その時にこの「男は女の敵ではない」ということを光瀬氏は口にしたのだ。
だから、この発言は就職して5年たった私を励ますつもりで言ってくれたという部分もあるのだろうと思う。しかし、彼の話を聞きながら、私の頭に浮かんだのは『征東都督府』のことだった。この作品をはじめて読んだ時、「光瀬龍は自分が男であるということに、ひどく傷ついているんじゃないかな」と、私は思った。深くて治らない傷口をグリグリとえぐるような作品。しかも、それがポルノ的に享受されてしまうことを、作者は十分に承知している。このような作品の由来は、もしかしたら、このあたりにあったのかもしれないと考えた。
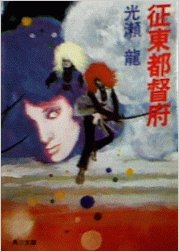
(『征東都督府』(角川文庫))
○
光瀬氏の結婚に先立って、結婚相手の妊娠があったことがわかった今(註3)、改めて、この彼の発言の意図と意味と背景を考えている。「妊娠=淫行の結果=退学」しか思いつかなかったとは、いったいいつの時点の彼だったのだろう? また、「最高地点に自分は行けない」から「別の道を模索せざるを得なかった」彼の旅は、いつから始まったのだろう?
彼が亡くなってから、彼の仕事について、妻の飯塚千歳氏が次のように語っている記事を見た。大橋博之氏によるインタビューである。
「私は一人っ子でしたので、両親は(結婚に)猛反対でした。彼は長男で男の子は一人でしたからね。ちゃんとした職がなければ結婚させないということで、学校の教師になったんです。ほんとうは動物園に勤めたかったんですって」
――宇宙塵に入会したのは、ご結婚される頃なんですね。
「ええ。『何で毎日、帰って来るのが遅いんだろう』と思っていたら星新一さん達と集まっていたみたいですね」
――遅くなるとは言わない?
「何も言って行かないんですよ。意外と無口でしたね。編集者さんなんかとはよく喋るのに」
(徳間書店〈SF JAPAN〉VOL.9 2004年 春季号 184ページ)
彼は「仕事をする以上、最高地点まで行きたい」と考えるような人だった。最高地点とは、もちろん出世のことではない。彼が心から「負けた」と思ったのは、校長でも教頭でもない、「年配の女性の同僚」だったのだから。
「動物園に勤めたかった」彼は、そこでなら最高地点にいけるような自信があったのだろうか。だが、状況はそれを許さなかった。かくて、彼の魂は居場所を求めてさまようことを始めたのだろう。
彼が勤務先にしていた高校は目黒区洗足にあった。当時、〈宇宙塵〉を主宰していた柴野拓美氏は、そこから1kmも離れていない大岡山に住んでいた。ここに運命の分かれ目があった。
この柴野氏との出会いについて、光瀬氏は次のように語っている。
柴野さんにある日手紙を出したら懇切な返事がきて、それでとうとうつかまってしまってSF作家になってしまったわけですがね。
それは、ちょうど、純真無垢な家出娘が「どこかに休むところはないだろうか」というところを、たまたま悪い奴が目をつけて甘言でたらしこむという、そういうのに似ていた。だから、他の方たちはどうかわかりませんが、私に関して言えば「悪い奴にひっかかったものだ」と(笑)。
(「TOKON7」での講演「宇宙塵のころ」より)
柴野氏と出会った頃の光瀬氏は、まさに精神的な意味での「家出娘」だったのだろう。
だから、彼の作品には「どこにも居場所がない魂の叫び」が詰まっている。それは、同じ思いをかかえる人間の心を救うものとして、正しく評価されなくてはなるまい。
(註1)この他にも漢文の素養をうかがわせる発言は多々あった。〈SFマガジン〉に連載された自分の評伝のタイトルを彼が知ったら、さぞ驚くだろう。「色即是空」の「是」は英語のbe動詞のような役割を持つ助字である。「A是B」で「AはBである」という意味になるというようなことは、彼にとって常識だったと思われるからだ。その意味では、彼および彼の作品の置かれた状況を象徴する素晴らしいタイトルであり、その発想はとても私に真似ができるところではない。
(註2)その中学校の名前をもちろん彼は口にしていたが、ここには記さない。大橋博之編『光瀬龍 SF作家の曳航』292ページ「光瀬龍略年譜」25歳の項目に、その中学校名が書かれている。
(註3)大橋博之編『光瀬龍 SF作家の曳航』292ページ「光瀬龍略年譜」31歳・32歳の項目参照。あるいは、拙稿『30年前の「ユリーカ!」』参照。
宮野由梨香 参加作品
『北の想像力
《北海道文学》と《北海道SF》をめぐる思索の旅』
