(紹介文PDFバージョン:meathubmurderersshoukai_okawadaakira)
『エクリプス・フェイズ』日本語版翻訳監修者の朱鷺田祐介による「ミートハブ・マーダーズ あるいは肉でいっぱいの宙(そら)」をお届けしよう。
あなたは、筒井康隆の「あるいは酒でいっぱいの海」をご存知だろうか。あるいはアヴラム・デイヴィッドスンの「あるいは牡蠣でいっぱいの海」は? いずれも劣らぬユーモアSFの名編で、ネタを割らないために詳述は避けるが、未読の方は、ご一読をお薦めしておきたい。
これらの作品にオマージュを捧げた「ミートハブ・マーダーズ あるいは肉でいっぱいの宙(そら)」は、『エクリプス・フェイズ』のゲーム・セッションの雰囲気を活かしながら、たっぷりもユーモアが盛り込まれている。
といっても、独自解釈で世界観を破壊しているわけではなく、舞台となるハビタット「ミートハブ」は、基本ルールブックに記載されているれっきとした公式設定で、土星圏に位置する。
高速培養されたベーコンが、そのまま居住区域になったものだ。このような奇抜な設定もまた、『エクリプス・フェイズ』の魅力である。
「ミートハブ」や土星圏については、「Role&Roll」Vol.117でも詳しく紹介されているので、あわせてお読みいただければ幸いだ。
ゲームデザイナーとしての朱鷺田祐介を語るうえで、ユーモアという切り口は外せない。もとは読者参加ゲームだった『パラダイス・フリートRPG』は、トランプの「大貧民」をベースにした独自の判定方法を駆使して宇宙を駆けまわるユーモア・スペースオペラRPGだが、現在は電子書籍で入手が可能になっている。
(岡和田晃)
![]()
(PDFバージョン:meathubmurderers_tokitayuusuke)
我は肉の内にあり、肉は我の内にあり。
我は肉を取り、肉は我を生かす。
我は肉を持って、我が存在を維持する。
肉は我が全て。
—スカムの宇宙詩人 ドミニス・マキシムズ
1:美味の案内人

ダンビルは肉色の壁を杖で叩いて軽く頭を傾けた。
その後、ナイフで壁を形成する肉を削り、口に含み、ゆっくりと咀嚼する。やがて、表情はとろけたようになり、ほほ笑みに変わる。
「いい熟成具合だ」
さらに、万能工具(フレックス・カッター)を四角い角型のノミに変えて打ち込んで、深さ20センチほどの深さまで穴をあける。穴の中を照らし出し、肉の壁の色を確認する。奥ほど色味が明るい。掘り出した肉片は表層に近いほど乾燥し、内側ほどしっとりとしている。
「どんぐりで育てたイベリコ豚のような出来ですね」
ダンビルの説明に、宇宙冒険家のランディ・シーゲルの脳裏で、〈大破壊〉以前にスペインで育成されていた高級豚の品種の説明が重なる。
ダンビルから受け取った肉片を口に入れると、肉片から脂が溶け出し、舌の味蕾を刺激する。脂の複雑な味わいは脳の快楽中枢を直撃する。糖分など含まれていないのに、甘いようにも思える。
「ワインが欲しいところだな」
「ブルゴーニュの特級畑とはいかないが、土星の荒波で熟成させたタイタン・ポルトなら、用意した」
ダンビルはかばんから古式ゆかしきガラスの瓶を取り出して見せる。
ランディは思わず、拍手した。
地球が〈大破壊〉で滅び去って10年。ワインもまた滅び行く文化だ。そもそも、ぶどう畑も醸造所も、地球とともに滅び去った。パリはナノスウォームに食い尽くされた。ブルゴーニュもシャンパーニュも同様だ。現在、残る地球産ワインはとんでもない貴重品の上、もともとデリケートな嗜好品だ。宇宙船で運ぶような代物ではない。
まあ、メタンの海が広がる土星の衛星タイタンで葡萄が育成しているとは思えないが、それは〈大破壊〉以来、どこでも一緒だ。
万能合成器(コルヌコピア)があれば、葡萄果汁に相当する液体成分は合成できるし、一人前のバイオエンジニアなら誰でも、酵母菌をDNAから立ち上げることはできる。そして、醸造したワインに酒精強化して、土星軌道上の荒々しい重力と電磁波の中で熟成させたのだ。
「まあ、一杯」と、ダンビルはさらにワイングラスを取り出す。古式ゆかしいコルク栓をこれまた奇妙な形状のナイフとコルク抜きで開栓しようとする。
#ラギニョール#
脳裏で、支援AI(ミューズ)が補足説明をする。
地球、ヨーロッパ中部山脈地帯のスイスで作られた高級なソムリエ・ナイフだ。かつて、ワイン好きが愛用したものである。当然、10年前の〈大破壊〉でメーカーごと消滅したが、どこかのスカベンジャーが拾い上げたものらしい。メッシュタグが由来を説明したがっていたが、持ち主が話題にするのを待つことにした。
ミートハブの重力は0.5G。気圧は0.9。
回転型小規模コロニーの生み出すものとしては十分な環境だ。
低重力ならでは、ややゆったりとした動きで、濃厚な飴色のポルトワインがグラスに注がれる。やや甘い、それでいて奥行きのある薫りが香る。
支援AIが臭覚センサーの分析結果を表示しようとするのを、精神コマンドひとつで排除する。野暮な話だ。
「あとはバケット」
ダンビルは薄くスライスしたパンを取り出し、壁から切り出した肉片をはさみ、別のチューブから黄金色のガーリック・バターを絞り出して添える。
ランディは口に運んだ。
美味い。脂身の甘さと赤みの強い味が入り混じる。
ワインを一口含むとパンの小麦が薫り、肉の旨味をさらに加速する。
酒と肉とパン、そして、ガーリックの効いたバター。ああ、もう天国だ。
ああ、これがファイアウォールの任務でなければ、どれほどよかっただろう。
そして、目の前のダンビルが殺人事件の容疑者でなければ。
2:ミートハブについて
まず、ランディがいる場所について説明すべきだろう。
土星の軌道上に浮かぶこの宇宙居住地(ハビタット)の正式名称は、”君も芸術のために宇宙ミートの巨大な塊になろう!”だ。
宇宙ミート!
なぜか、名前が判明していない生体義体設計者というある種の芸術家が作り出した稀代の芸術品だ。名称が示すように、ハビタット構造体の90%は高速培養によるベーコンである。そう、肉(ミート)だ。
ハビタット自体が一種の巨大な生体義体(バイオモーフ)で、自分で土星の輪から資源を採取し、自らベーコンである肉体を育成し、成長を続けている。外壁は10メートルの厚みを持つベーコンで、外から見ると、ヒレ肉のステーキのようにも見える。
簡単に言えば、ミートハブはベーコンで出来た「生きたハビタット」だ。
構造体の残り10%はハビタットとしての環境を維持するための躯体、エアロック、万能合成器などに費やされている。内部空間は生物発光パネルで照らされており、劣化した皮膚組織は小型の爬虫類のような共生生物が食べることで免疫構造を維持している。内部の重力は0.5Gで、気圧も高く、十分に生身で生活できる。
ミートハブはどこの国家にも属していないし、これを作った人物が誰かも分かっていない。発見された時、すでにミートハブは、ミートハブであり、製作者はいなかった。
ミートハブは宇宙居住区(ハビタット)と分類すべき宇宙構造物であると同時に、生体義体(バイオモーフ)であることはすでに述べた。
大破壊後(AF)10年、人類が魂(エゴ)をデジタル化して、バックアップできるようになってすでに数十年が経過している。身体形状(モーフ)は義体(モーフ)と呼ばれる、一時的な乗り物になった。バイオ技術の発達で病気を克服し、必要に応じて義体を乗り換えることで、事実上の不死を手に入れた。その技術を応用して制作された太陽系有数の大きさを持つ義体(モーフ)がこのミートハブである。
ハビタットを義体のように運用すること自体は既存の技術であり、ハビタット管理部門の技術者(ハビテック)の魂(エゴ)を、ハビタットの管理コンピュータに着装させることはすでに複数の場所で行われている。いわゆるオニール・シリンダーの発展形である自己増殖型の円筒コロニー、ハミルトン・シリンダーでは珍しい話ではない。
……とはいえ、それを宇宙ベーコンの塊で行うのは、たぶん、正気の沙汰ではない。
ミートハブに着装しているのは、ミートハブ・サポートと自称する女性型AIであり、製作者の情報は彼女のメモリーから削除されていた。
現在のところ、ミートハブには500名ほどが住み着いている。彼らは極度の肉好きか、前衛芸術の信奉者、生体設計者のいずれかである。
「いや、その全部だろう?」
ランディは思わずひとりごとを言った。
「あと、ほぼ全員が食文化の信奉者だということを加えてほしいな」とダンビルが言う。「この宇宙居住区(ハビタット)は、肉好き(ミートマニア)の楽園だが、ここで生きていくには、その肉への愛を試される」
「肉への愛?」
「そう、愛だ」
まあ、その結果が壁の一番美味い場所を探すミート・コンシェルジュを自称するダンビルらの存在であり、土星でもっとも美味いワインを飲むチャンスだとしたら、それはそれでアリだろうな、とランディは思った。
「では、次のポイントへ向かいましょう」
ダンビルはグラスを綺麗に拭いてしまいながら言った。
「次のポイント?」
「ええ、熟成度の違いをお見せしないと」
「さらに肉?」
「ええ、さらに肉です」
確かに、このハビタットでは、肉への愛が試されるようだ。
3:殺人は美味くない。
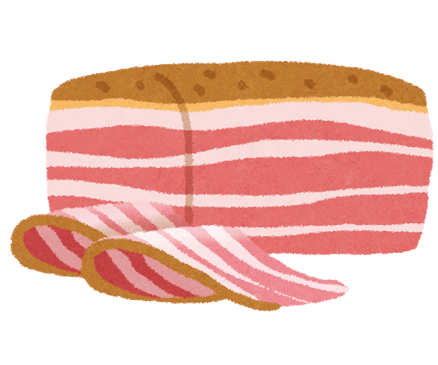
この時代、殺人事件という概念がどれほどの価値を持つかというとなかなか難しい。
魂(エゴ)をデジタル化した瞬間、コピーとバックアップが可能になった。ここ、ミートハブにいるランディ・シーゲルは、タイタン連邦からエゴキャスティング装置で送信された魂(エゴ)データを、耐久性の高いオリンピアン型生体義体に載せたものだ。オリジナルのランディはタイタン連邦で活動をしているので、正確に言えば、α分岐体(フォーク)と呼ばれるコピーである。たとえ、このランディが死んでも、オリジナルは生きているし、オリジナルが死んだとしても、バックアップから魂(エゴ)データをダウンロードして義体(モーフ)に着装させれば、復活したものとみなされる。
義体(モーフ)の多くは、魂(エゴ)データを記録する大脳皮質記録装置、通称スタックと呼ばれるコインサイズの中枢部品があり、たとえ、その義体が死んでも、人造ダイヤモンドで出来たスタックが破壊されない限り、死の瞬間から復活できる。
ランディ自身、宇宙探検家という危険な商売柄、そして、人類の滅亡の危機(Xリスク)と戦う秘密組織ファイアウォールのエージェントであるセンティネルの任務を果たす過程で、何度も「死んだ」。現在のランディがいったい、何人目なのか、もはや覚えてもいない。
その都度、バックアップ保険を使ったり、ファイアウォールが手配したりした結果、蘇ってきた。今、ミートハブにいるような分岐体を作ることもあり、幾人かの分身が太陽系内で活動している。
資金か評判かが許せば、同様のことが誰にでもできる。
バイオ保守主義の牙城である木星共和国以外では、老衰で死ぬ者などほとんどいないし、何かの理由で死んでもたいていどうにかなる。もはや死ぬことは、珍しい「風土病」か何かに過ぎず、いまやトランスヒューマンと呼ばれる人類の多くは不老不死を手に入れたも同然なのだ。
その時、殺人は罪になるのか?
加害および資産の破壊という意味で、殺人は重大な犯罪だが、取り返しのつかないものではない。人を完全に殺すのはほぼ不可能なのだ。
その上で、ファイアウォールは殺人事件の調査という名目で、ランディと仲間たちをこのミートハブに送り込んだ。犯人はダンビルと名乗る人物だという。
観光客を装い、ミートハブに入ったランディはダンビルにガイドを依頼した。ミート・コンシェルジュを名乗るダンビルは、快諾し、ランディとともに肉のパラダイスめぐりをしているという訳だ。
2つ目のポイントは、ミートハブの躯体に近い「生のベーコン」の部分である。躯体に組み込まれた万能合成器、通称「豊穣の角(コルヌコピア)」機械(マシン)がベーコンを生成している。その近くの「新鮮な肉」を味わうために、ダンビルと仲間たちは、ここまでベーコンの外壁層を掘削し、坑道というべきものを維持している。ここで切り出した肉は回廊部分に建設された厨房へ運ばれ、調理される。肉の鉱山である。
「この鉱脈を策定するのは苦労したよ」
ダンビルは生に近いベーコンを削り出し、味わうように進めながら言った。
「製作者のデザインはベーコンに含まれる脂身と赤身のバランスにも気を使っている」
指差す先で、脂肪の白い線が何本も壁を走っている。「掘削の方法で、我々は脂肪と肉質の黄金比を味わうこともできるし、脂肪と肉質を別々に入手することもできる」
「採掘という言葉が肉に使われる日が来るとはねえ」
「でも適切な表現だ」
ダンビルは満足気にそう答えた。肉という食文化に人生を捧げた男の顔がそこにあった。
ふと、ランディは聞いてみるしかないと思った。
「人間の肉を食べてみたいと思ったことは?」
すると、ダンビルは爆笑した。
「あれはそれほど美味くないよ」
「食べたのか?」
「ミート・コンシェルジュとして、当然だ」
「殺して喰ったのか?」
「やっぱり」とダンビルがさらに爆笑する。「そういう話になるが、ご安心を。
人間のクローン肉なんて、いくらでも培養槽で作れる。いいかい、無菌でクリーンな肉だ。ご希望次第で、若いコーカソイドの女性の腿の肉でも簡単に作れる」
生体義体(バイオモーフ)が工場生産できる時代だ。ちょっとした施設があれば、人間の肉をクローン培養することなど簡単だ。魂(エゴ)を着装する前ならば、人格も存在しないから、それは物体でしかない。食べたかったら、食べたっていい。
「古代の中国人は、双脚羊と言って密かに人肉食を行った。三国志演義にも、劉備玄徳に妻の肉を振る舞う狩人の行為を美徳として描く場面がある。乙女の生き血を美容の特効薬としたエリザベス・バートリのような話も色々ある。映画に登場するハンニバル・レクターのような人喰い犯罪者も多数存在する。
だがね、それは精神的なものに過ぎないよ。
私は食べて分かった。
一回目は背徳感で興奮するが、実際、食べてみると、それほど美味いものじゃない。やはり、同種族を食べても美味しくはないのだよ。牛や豚など、食用の家畜の方が味わいも優れているし、料理するにしても洗練されている」
そこで、ダンビルは少しだけ険のある顔つきになった。
「そういう刺激が欲しいなら、私のツアーはここで終わりにするよ。
ここはそういう場所じゃない」
「いや、食べてみたい訳じゃないよ」
ランディは率直に謝った。
ダンビルは肉の信奉者であって、人肉食にハマったカルトのメンバーなどではない。なぜ、彼がファイアウォールに目をつけられるような殺人を企てたのか?
そこが分からなかった。
「まずは食べて、食べて」
機嫌を直したダンビルの勧めるまま、ランディはベーコンとワインを味わった。
そして、医療用ナノウェア「メディシン」の存在を呪った。さっきからワインを飲んでいるのに、ちっとも酔えないのだ。体内のナノマシンが飲んだワインのアルコールを速攻で分解して酩酊状態を防止しているのである。
一方、目の前のダンビルはほんのりほほに赤みがさして、実に楽しそうだった。明らかに酔っている。
「ナノウェアの停め方をお教えしましょうか?」
得意げにダンビルがそう言った。
ナノウェアをハッキングしてアルコール分解を行わないようにできるのだ。
断る理由などなかった。
4:火と肉のはざまに
3番目のポイントは、文化的なレストランだった。
「二十世紀後半、とある日本人のエッセイストが『料理の四面体』という概念を提案しました。料理とは、食材と加工手段、すなわち、火との距離で定義できると」
ダンビルはカリカリに焼かれたベーコンを散らしたシーザー・サラダの皿を進めながら、解説した。同時に、拡張現実(AR)上に正四面体の図式が表示され、ピラミッド状の四面体の頂点に「火」と表示され、底面に「素材」と表示される。
ランディの支援AI(ミューズ)がメッシュ検索の上、玉村豊男という日本人グルメの著作を探し出す。肉料理の可能性を構造分析して見せた上、理論上、刺し身とサラダは同列の料理であると定義する。なかなか面白い考え方だ。
「火と食材の距離に加え、食材と火の間を満たす熱伝達物質が何かも重要です。
水を間におけば、煮る、茹でる、蒸すと言ったサブジャンルが生じますし、空気ならば、直火で焼く、遠火で焼く、燻製する、干すなどになる。油なら、揚げる、炒めるなどがある。スペインのアヒージョのように、油で煮る料理もある。
肉は焼くことでうまくなる」
ダンビルの合図で、さきほど切り出したベーコンの肉塊がステーキ状に焼かれて出てきた。玉ねぎのみじん切りを多用したシャンポリオン・ソースに、わずかに青草のような爽快さを含む薫り。ぴりっとした辛さが、レアに近い焼き加減の肉の旨味を引き立てる。
「この味は、辛子ではないな」とランディ。そして、支援AI(ミューズ)が分析結果を表示する。「日本産の山葵? それもすりおろされて10分以内?」
ダンビルは満足げにうなずいた。
「DNAデータがあれば、植物組織の培養自体は簡単なのですよ?
あとは日本の環境に近い外部環境の影響を再現してみるだけ」
理論上、可能なことだが、それをこの肉の王国で実践しているのか?
「肉をどれだけ美味く食べるか?
そのために、人類は発展してきたといえるでしょう」
そこで、急に、ダンビルは苦痛に満ちた顔になった。
「どうしたのですか?」
ランディの質問に対して、ダンビルはミートハブ・サポートから流れてきた情報を転送した。
「クレストンの焼き肉の会再び@ミートハブ・セントラル」
ダンビルはしばらく何も言わなかった。
「どうしたんですか?」
「私は決して、焼き肉を否定する訳ではない。
『料理の四面体』理論を追求するならば、肉を焼くという行為は美味を生み出す素晴らしい試みのひとつだ。アメリカ風のステーキは素材そのものを楽しむもので、添えるソース次第でいくらでも芸術性が高まる。ヨーロッパ風のバターを活かしたソテーもいい。
アジアでよく行われるタレをつけて焼く手法もいい。
味噌に香味野菜、主にニンニクと唐辛子、さらに酒、醤油やラー油の調味料を組み合わせたタレで焼いた肉はひとつの芸術品と言ってよかろう。だが……」
そこで、ダンビルは拳を震わせた。
「焼き肉は周囲への影響が大きい。壁に匂いがつくのだ!」
「あ」
ランディは気づいた。殺意の源に。
このミートハブはすべて肉でできている。壁も床もすべて肉だ。
ミートハブ・セントラルで焼き肉を行うということは、その空間すべてに焼き肉の匂いがつく。焼き肉の匂いがついた肉の壁は、ダンビルにとって許しがたい代物だったのだ。
「それで、あなたは前のクレストン氏を殺したのですね?」
ランディは静かに言った。
「ああ、そうだ」
「反物質を使って?」
反物質は高価だが、それだけの価値のある燃料として使用されている。
もちろん、反物質は危険だ。わずか0.1グラムにも満たない反物質が人間を完全に熱へと転換してしまう。クレストンが焼き肉の会で突然、反物質で対消滅し、発生した莫大な熱が参加者全員と周囲の肉の壁を焼き払ったのは二ヶ月前のことだ。
「奴のタレも消滅させたくてね」
しかし、バックアップから復活したクレストンは、性懲りもなく、またもや焼き肉を追求しようとしている。
「だから、今回は反物質の量を増やしたと?」
ファイアウォールが人類絶滅の危機(Xリスク)とみなすほどの反物質がミートハブに運び込まれた。全ての量を使用したら、数十万トンにおよぶミートハブのベーコンが純粋な熱量に変換されてしまう。当然、ミートハブはおろか、土星の輪の半分が吹き飛び、土星圏の人口は半減してしまうだろう。
「そうだ」とダンビルは叫ぶ。
「ヤツには、肉への愛が足りないんだ!」
ランディはため息をついてから、メッシュ通信で仲間にこれを告げた。
「じゃあ、アタシが対応する」
ミートハブ・セントラルにいるシュガー・ヴァイオレットがそう答えた。
「とりあえず、クレストンを焼いておくわ」
通信の中で、男の悲鳴が上がった。彼女がレーザー・ボルターを使用したのだ。熱線銃で自分の肉を焼かれるという体験をクレストンは楽しんでくれるだろうか?
「殺すな、生(レア)に止めろ、あと、傷口にタレをかけろ」
最後のセリフはダンビルに聞こえるように言った。
「これでいいかい?」
「ああ」とダンビルが答える。「奴のタレには唐辛子が入りすぎなんだよ」
(終わり)
参考文献
「料理の四面体 東西美味発見法」 玉村豊男 紀伊國屋書店

Ecllipse Phase は、Posthuman Studios LLC の登録商標です。
本作品はクリエイティブ・コモンズ
『表示 – 非営利 – 継承 3.0 Unported』
ライセンスのもとに作成されています。
ライセンスの詳細については、以下をご覧下さい。
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
朱鷺田祐介既刊
『シャドウラン4th Edition リプレイ
帝都の天使たち』
