(PDFバージョン:12kyuu12_ootatadasi)
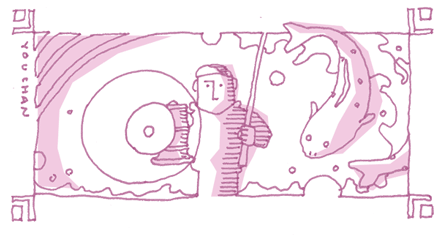
案内された漁場は、生臭い風が吹く真っ暗な海だった。
「ここで本当に釣れるんですか」
思わずそう訊いてしまった。
「釣れますよ」
案内人の笑みが、釣り舟に吊るしたアセチレン灯のオレンジ色の光に浮かぶ。
「ここは本当の穴場です。たくさん釣れます」
彼の英語は私のそれより拙かった。それでもなんとか意味は理解できる。
それならば、と仕掛けを用意した。竿も針も自前のものでないのが残念だが、出張先まで釣り道具を持っていくわけにもいかなかった。ただ仕事を済ませて帰国するまでに時間が空いたら、必ず釣りをしようと決めていた。学生の頃に開高健のエッセイを読んで以来、ずっと海外で釣りをすることに憧れていた。今やっと、その夢が果たせるのだ。
釣り糸を海に投げた。凪いだ海面に一瞬波紋が広がり、すぐに消える。
そのまま待つことしばし、程なく竿に反応があった。
一気に引く。釣り針の先にかかっていたのは、五十センチほどの長い魚だった。
船の上に引き上げると、ぬめりとした体がのたうった。銀色で、ところどころに赤い斑点が浮いている。正直、あまり見栄えのいい魚ではない。
「これは何ですか」
と訊くと、案内人は何か言った。現地語なので聞き取れない。
「美味しいですよ」
それだけは理解できた。食べられる魚らしい。
餌を付けなおして、再度竿を振る。今度も待つことなく反応があった。
釣れたのは、同じ魚だった。
「美味しいですよ」
案内人は、同じことを言った。そして付け加えた。
「今年は、この魚がたくさん取れます。なぜだかわかりますか」
「さあ」
私は首を捻ってみせた。案内人は得意気な表情で、
「春にたくさん雨が降って、洪水になったからです」
と言う。
「どうして洪水になると、この魚がたくさん取れるのですか」
「山から水が溢れ出て、村を襲いました。たくさんのひとが、溺れて死にました。死体は川から海に流れていきました。そして、ここに来ました。だから魚は、増えました」
話の繋がりが、よくわからなかった。
「どうして死体が流れてくると魚が……」
はっ、とした。
「……つまり、この魚は死体を食った?」
「山で洪水になると、海で漁師が喜びます。昔から、そうです」
私は舟底で蠢く魚を見た。ひどく気分が悪かった。
「この魚だけではありません。他の魚も、蟹も、海老も、この海に住む生き物はみんな、人間の味を知ってます。美味しいですよ」
美味しいですよ、という言葉が別の意味に聞こえた。
「あまり気持ちのいい話ではありませんね。私は帰りたくなりました。舟を戻してください」
そう言ったが、案内人は動こうとしなかった。
「私の言葉、聞こえていますか」
「はい、聞こえています。あなたは疑似餌を使って釣りをしたことがありますか」
突然、妙な質問をされた。
「疑似餌? いや、ルアーフィッシングはしたことが……それがどうかしましたか」
「とても楽しいですよ。釣りの中で一番楽しいです」
案内人は言った。
「釣られる者は、最後まで疑似餌を本物だと信じています。うまく騙せることが、楽しいです。あなたのように」
「私の? それはどういう――」
聞き返したときだった。案内人の体が、突然破裂した。
いや、それまで案内人の姿でいた者たちが、一斉に元の姿に戻ったのだ。それはぬめりとした体を輝かせながら、次々と海へ落ちていった。
気が付くと、私は腰を抜かしてへたり込んでいた。残されたのは、私ひとり。先程釣った二尾の魚の姿も、なかった。
凪いだ真っ暗な海に、取り残された。生臭い風は、体にまとわりつく。
「お……おい、どういうことだ? どうしたんだ? おい……」
呼びかけても、返事はない。
奇妙な音が聞こえた。低く響く、軋むような音だ。
それは四方八方から私を包み込んだ。
まるで、何かの中に放り込まれたような……。
まさか。
舟に掛けてあるアセチレン灯を頭上にかざした。そして、悲鳴をあげた。
そこにあるのは夜空ではなかった。血管の浮き出た、分厚い膜だったのだ。
つまり、私はもう……。
膜が震えた。あの音が聞こえた。そして私を舟ごと、消化しにかかった。
太田忠司既刊
『星町の物語
奇妙で不思議な40の風景』
