(PDFバージョン:12kyuu11_ootatadasi)
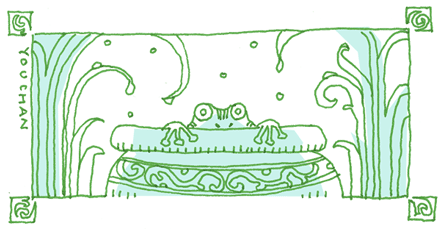
小学生の頃、夏休みになるといつも虎尾のおじいちゃんの家に泊まりに行った。
虎尾のおじいちゃんは母の父親だ。虎尾というのが住んでいる町の名前で、僕の家からは電車で二時間くらいのところにある。山があって田んぼがあって川がある。絵に描いたような田舎だった。
僕がおじいちゃんのところに行っている間、父親と母親が何をしているのか僕は知らない。なんとなく知らないほうがいいような気がしていた。だから正直おじいちゃんの家にいることが楽しいわけではないのに、文句も言わずに毎年泊まっていた。
おじいちゃんは僕を歓迎してくれていたと思う。おばあちゃんは僕が生まれる前に死んだので、ずっとおじいちゃんは独り暮らしをしていた。家の近くに田んぼと畑があって、そこで米とか野菜とかを育てて暮らしていた。僕が泊まっている間も朝早くから仕事をしていた。僕はおじいちゃんの家でひとり、ぼんやりと過ごしていた。
庭にはニワトリがいた。放し飼いでいつも何かをついばんでいた。濡れ縁でおじいちゃんが茹でておいてくれた枝豆を食べながら、僕はニワトリをずっと眺めていた。そうしていることが嫌いではなかった。友達と遊ぶとか誰かと話すとか、そういうことは苦手だった。
庭には大きな水瓶もあった。高さが小学校四年だったときの僕がやっと覗き込めるくらい。僕が両手で抱えきれないくらいの大きさだった。茶色くてつやつやしていた。それに水がいっぱい溜まっていた。
これは何、と訊いたとき、おじいちゃんは水瓶だと教えてくれた。それで水瓶という言葉を覚えた。何に使うの、と訊いたら、さて、何に使うのかな、と言った。何かに使うために持ってきたんだが、何をしたかったのか忘れたよ。
覗き込むと、溜まっている水は濁っていた。中に何かいるの、と訊いたら、何もおらんよ、と言われた。ただ雨水が溜まっているだけだ。
小学校五年の夏、前の夜に降った雨で庭は濡れていた。ニワトリは相変わらず地面をついばんでいた。僕はサンダルを履いて庭の隅のあたりをぼんやりと歩いていた。
何か動くのが見えた。草むらを見ていると、そいつが顔を見せた。
灰色の体に緑色の筋が入っている。眼が飛び出していて、のたのたと歩いていた。カエルだ。
気付かれないようにそっと近づいて、前のほうから手を伸ばした。カエルは前にしか飛べないと聞いたことがあったからだ。ジャンプしたタイミングで、さっと捕まえた。
冷たくて、ぬめっとした感触だった。僕の手から逃げようとじたばたしている。それを持ったまま水瓶に駆けていった。そして中に落とした。
カエルは頭と背中を出して浮かんでいた。手足は水の中で広げている。飛び出した眼が僕のほうを見ていた。
どうした、と声がかかった。振り向くとおじいちゃんが立っていた。
なんだ、カエルか。捕まえたのか。
僕が頷くと、おじいちゃんはカエルをじっと見つめた。これはトノサマガエルだな。
トノサマガエル。名前は知っていた。図鑑で見たことがある。それがそうなのか。
飼ってもいい、と訊いたら、飼ってもいいが、ここに入れておくと死ぬぞ、と言われた。オタマジャクシは水の中でも呼吸できるが、カエルはできん。掴まるところのないところに入れておくと溺れる。
どうしたらいいの、と訊いたら、逃がすのが一番だ、と言われた。昼飯、食うか。
僕はカエルをそのままにして家に入った。昼御飯はおじいちゃんが作ってくれた焼きそばだった。
カエルはそのままにしていた。おじいちゃんも何も言わなかった。
その日、夕方になってまた雨が降りだした。かなり強い雨だった。僕は家の中でテレビを観ながら、雨音を聞いていた。そして水瓶の中のトノサマガエルを思った。
次の日も雨だった。一日ずっと家から出られなかった。
その次の日、やっと雨があがった。僕は庭に出て、水瓶を覗き込んだ。
カエルはもう死んでいるかもしれないと思っていた。でも、カエルの姿は、なかった。
僕はずっと水瓶の水を見ていた。どうした、とおじいちゃんに訊かれた。カエルがいないとと言うと、おじいちゃんも水瓶を覗き込んだ。
逃げたな。雨で水瓶の水が満杯になったから、逃げ出したんだ。
そうか、逃げたのか。僕はなんだか、ほっとした。
その日からずっと、カエルの姿は見なかった。
中学に入ると、夏休みにおじいちゃんの家に行くこともなくなった。父親も母親も行けと言わなくなったからだ。僕も小学校の頃よりは人付き合いができるようになって、一緒に遊ぶ友達もできた。夏休みの間、退屈はしなかった。おじいちゃんのこともカエルのことも、思い出さなかった。
最後におじいちゃんに会ったのは、中学二年の秋だった。おじいちゃんに生まれたばかりの僕の妹を見せに行ったのだ。おじいちゃんは前に会ったときより元気がなさそうだった。でも妹を見て笑った。僕には何も言わなかった。僕は庭の水瓶のことを思い出した。今どうなっているのか少しだけ気になった。でもわざわざ庭に出て見ることはしなかった。
その三年後、おじいちゃんが死んだ。葬式はおじいちゃんの家で行われた。僕は高校の制服を着て出席した。
葬式は近所のひとたちが総出で手伝ってくれていた。僕は何もすることがなくて、庭に出てみた。
あの水瓶があった。覗いてみたら、水は入っていなかった。
まだあったのね。声がしたので振り向いたら母親がいた。とっくに捨てたと思ってたのに。
この水瓶のこと、と訊いたら、わたしが小さいとき、おじいちゃんが買ってきたの、これに花を植えるって、どうしてこんな大きな植木鉢を買ってきたのかしらね。
植木鉢なの、と驚いたら、そうよ、見てごらんなさい、そこに穴があいてるでしょ、と母は言った。覗き込んでみると、たしかに底の中心に穴があいていた。
でも、前には水が溜まっていたよ。おじいちゃんは水瓶だって言ったんだ。僕はここにトノサマガエルを入れて。
ほったらかしにしておいたから、ゴミで穴が詰まってたんでしょ。それで水が溜まってたのよ。トノサマガエルって何。
いいんだ、と僕は言った。そして思った。あのカエルはおじいちゃんが逃がしたのかもしれない。
水瓶は水瓶ではなかった。でもおじいちゃんは本来の使い道には使わなかった。だから僕には水瓶と言った。
嘘つかなくても、よかったのに。
お坊様の読経が始まるから、家に入って。母親に言われ、水瓶、いや、植木鉢から離れた。
家に入る前、振り返った。鉢から大きな黒い眼が飛び出して、こちらを見ていた。
太田忠司既刊
『星町の物語
奇妙で不思議な40の風景』
