(PDFバージョン:12kyuu09_ootatadasi)
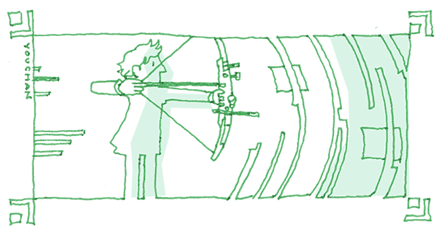
私はよく、機械のように感情のない人間だと言われる。
その言葉を、私はそれまで称賛の意味に捉えていた。感情などという低次元な衝動に左右されるような卑俗な人間ではないと讃えてくれているのだと思っていた。しかし実際は、そうではないようだ。
妻がその言葉を放ったとき、明らかに彼女の中に侮蔑の感情があることに気付いた。
一方、私の弟について語るとき、妻の瞳は輝き頬はそれとわかるほどに紅潮した。アドレナリンが噴出し気持ちが昂っていることを隠そうともしない。
私は鄭重な口調を心がけながら彼女の夫は自分であり弟ではないということを示唆したのだが、返ってきたのはお世辞にも節度があるとは言えない反応だった。
事ここに至って、私は判断した。妻は私より弟の存在に重きを置いているのだと。
そのこと自体は斟酌すべき事柄ではないのかもしれない。しかし私はその事実によって少なからず精神的安定を欠くことになった。常に静的な状態を心がけなければならない私のような研究者にとって、これは由々しき問題だ。このままでは手がけている課題の達成にも支障が出る危険性がある。
熟慮の結果、私はひとつの決断を下した。弟を排除しなければならない、と。
問題は、その方法である。野卑な人種が激情に駆られて実行するような刹那的な方法は絶対に採るべきではない。必要なのは確実性と、私という人間に相応しい科学的アプローチだった。考慮の末、私の最新の研究成果を応用することにした。
まだどこにも公表していないが、私が発明開発した機器は、控えめに言っても画期的な代物だ。どのような物質であっても、それをある地点Aから別の地点Bへと瞬時に移動させることができる。SFの世界ではテレポーテーションと名付けられている現象だ。しかも私は、その現象を生じさせる機器を極めてコンパクトに製作した。送信機は小型のアタッシェケースに納まるくらい。受信機に至ってはスマートフォンよりも小さいサイズに縮小することができた。
すでに実験も成功している。送信機に接続したチェンバーに移動させたい物体を入れ、発動させる。すると受信機のある場所に瞬時に移動させることができるのだ。送信距離は今のところ一キロメートルまで可能だ。送る物体の重量は四八〇グラムまでだが、今後はもっと重いものを転送することができるだろう。
だが今は、この重さで充分だった。私が送ろうとしているものの重量は、せいぜい三十グラム程度のものだからだ。
私の弟ではあるが、彼は性格も体型も趣味嗜好もまったく似ていない。書物で知識を蓄えるより体を鍛えていたほうがいいという考えの持ち主で、特にアーチェリーには子供の頃から没頭しており、ついにはオリンピック――これもくだらない催し物だ――の強化選手というものに選ばれたそうだ。自宅に練習場を作り、的に矢を当てるという退屈極まりない行為を繰り返している。しかも驚くべきことに、妻はどうやら矢を射ている弟の姿に魅了されているらしい。
ならば、その矢で彼を抹殺してやろうと私が考えるのも、理の当然といえるだろう。
念のために予行演習をしてみた。まず受信機を弟が持っているスマートフォンと同じものの中に収め、樫の幹に括り付けた。そして一キロメートル離れた位置に送信機を携え、チェンバーにアーチェリーの矢を収納した。
そして起動。矢は一瞬のうちに消滅した。
確認のため、受信機のあるところまで行ってみた私は、思わず歓喜の声をあげた。転送された矢は受信機を収納したスマートフォンを貫き、樫の幹に深々と突き刺さっていたのだ。
成功だ。これなら問題ない。
私はもうひとつ同じようにスマートフォンに模した受信機を手に弟の許に向かった。今日は彼の家で、彼と妻の三人で昼食を取ることになっていたのだ。
食事の最中、奇妙な目配せを交わす妻と弟を見ているのは、好もしいものではなかった。感情を完璧に制御できる私のような人間でなければ激昂していただろう。しかし私は冷静だった。機会を窺い、弟のスマートフォンを私が用意した受信機入りのものにすり替えることに成功したのだ。
その後もさり気ない態度を装い、ふたりに親愛の情さえ示して見せた。もしかしたら私は演劇の分野においても才能を発揮できたかもしれない。そんな満足感に浸りながら食事を終え、弟の家を辞すと、妻には所用があるから先に帰っていてくれと告げた。そして私は大通りに面したカフェに入った。ここなら私のアリバイを証明してくれる者が大勢いる。私はコーヒーを飲みながら悠々と殺人を決行できるのだ。
弟は自分が拠り所としているアーチェリーの矢に貫かれて死ぬ。なんとも愉快な死にざまではないか。
そろそろいいだろう。私はコーヒーカップを置き、送信機を組み込んだアタッシェケースを膝の上に置いた。
さらば、弟よ。
そう呟いて、スイッチを入れた。
※
俺が駆けつけたとき、その店は警察によって封鎖されていた。
近くに彼女の姿を見つけた。彼女も俺を見つけ、駆け寄ってきた。
「どうしましょう。どうしましょう……」
そう繰り返すばかりの彼女をなだめ、俺は近くにいた刑事に自分の身許を明かした。
刑事は現場に連れて行ってくれた。
俺もよく利用するカフェの中、兄は大の字になって倒れていた。
その胸には見慣れたものが深々と突き刺さっている。
「どうして……」
俺は呟いた。
「どうも話がわからないのですよ」
刑事は当惑顔で言った。
「被害者は、突然飛んできた矢に胸を貫かれて死んだ。即死です。だが不思議なことに、矢の方向から考えると店内のカウンターあたりから射られたとしか思えない。なのに当時、矢を放つような人物はいなかったと目撃者は口を揃えて言うんです」
「矢を射た者が、いない?」
「ええ、まるで矢だけが突然現れたかのようだったと」
俺はあらためて倒れている兄を見た。矢はシャツの胸ポケットのあたりに刺さっている。
「ポケットに何か入っているんですか」
「ええ、スマートフォンが」
「スマートフォン?」
「何か心当たりでも?」
「あ、いえ」
俺は適当にごまかした。
先程、兄と一緒に食事をしたとき、彼の様子は明らかにおかしかった。俺と彼女を交互に見て、恨めしげな顔をしていたのだ。俺たちの関係に気付いていたのだろう。俺はかまわず兄の目の前で彼女といちゃついてやりながら様子を窺った。
すると兄は俺が見ていないと思ったのか、テーブルに置いていた俺のスマートフォンを掠め取り、まったく同じ型のものを代わりに置いたのだ。
何か企んでいるな、と俺は直感した。だから今度は兄の隙を突いてスマートフォンをまたもすり替えてやった。
もしかして、その結果がこれなのか。
もしかしたら……。
「怖い……!」
不意に後ろから寄り掛かられた。彼女がしがみついてきたのだ。その仕種には馴れ合った媚びが感じられた。俺は突き放してやりたい衝動をなんとか堪えた。今は他人の眼がある。何をするにも慎重にならなければ。
考えなければならない。計画とはいささか違う形だが、兄は死んだ。女房を寝取られて悲観した挙句に自殺……という形で殺すつもりだったのだが、手間が省けた。兄の遺産は彼女と、そして俺のものだ。
残る厄介は、この女か。
体を擦り寄せてくる彼女の体温を感じながら、俺は次の計画に考えを巡らせた。
太田忠司既刊
『目白台サイドキック
女神の手は白い』
