(PDFバージョン:harunotabigokoro_hirayayosiki)
春になると、旅に出かけたくなる。
桜が咲く直前。枯れ色だった山々に、人々が気づくか気づかぬかの淡い萌え色が差す頃。
里の雪が溶けて、オオイヌノフグリの小さい水色の花が畦道に散りばめられ、フキノトウはもう天ぷらにしても苦いほどに伸びてしまった頃。
ぼくは無性に旅に出たくなる。
旅に出たくなる――。という言葉はちょっと違う。
胸が痛くなるような渇望。
飢えや乾きにも少し似ている。
そのようなものが勃然として日常生活の中に現れ、ぼくを困惑させるのだ。
昨年まで、それは教師時代の最初の赴任地へ引っ越しをした時の思いが“刷り込まれた”ものだと思っていた。
初任の地は岩手県の沿岸部、宮古市という街にある学校であった。自宅から一五〇キロほど離れた場所で、当然、自宅から通勤することはできない。公共交通機関を使おうと思えば、JRと長距離バスと、日に三本しかない路線バスを乗り継がなければならない場所である。
大学が大阪だったから、親元を離れて暮らすのは慣れていた。だが、社会人として独り立ちするという思いは、入学のために南河内へ引っ越した時の心境とはまるで違った。
大きな人生の節目であり、その強い思いが、〈春になると旅をしたくなる〉という衝動に繋がっているのだと思っていたのである。
一昨年までは、春になると、
『宮古へ行きたい』
という気持ちが勃然としてわき上がってきたのも、その推測の根拠であった。
だが、去年は『宮古へ行きたい』という思いは起こらなかった。
宮古は、東日本大震災の大津波の被災地であり、とても旅人気分で足を踏み入れられるような状況ではなかったのである。
しかし、春の旅心はぼくの中に存在した。
〈宮古〉という目的地は消えていたが、旅をしたいという強い思いははっきりとあった。
ぼくの、春の旅心は、初の赴任地へ赴いたときの思いの刷り込みではなかった。
いったい、どこへ旅をしたいというのか?
この旅心はどこから来るのか?
その疑問が氷解したのは、昨年の末である。
その頃、ぼくは遊牧民が多く登場する小説を執筆していた。
一〇世紀頃の中国と、日本の東北が主な舞台になる小説である。
当時、大陸には契丹(きったん)という国があった。
契丹は遊牧民の帝国である。
大陸の遊牧民は、季節によって異なる宿営地の間を移動しながら生活していた。それを〈捺鉢(なつはつ)〉という。
初代の皇帝は耶律阿保機(やりつあぼき)。阿保機は、皇帝になってからも、首都に住むことなく四季の幕営地を渡り歩き、生活していたという。
遊牧の民には、旅が体にも心にも染み込んでいたのである。
もちろん、ぼくは日本人で、大陸の遊牧民とはなんの繋がりもない。
大草原に馬を駆り旅をする彼らに憧れる気持ちはあるが、ぼくの〈春の旅心〉は憧れではなく衝動である。
契丹国が勃興する一〇世紀。北東北(きたとうほく)は、未だ日本という国には組み込まれていなかった。
平安時代の初期、北東北は〈日本〉から見れば異文化の土地。外つ国であったのだ。
異文化の土地とはいえ、縄文時代の中期頃からは、粟(あわ)や稗(ひえ)の栽培も始まり、米作りの技術も縄文時代の末には入っていた。しかし、発掘調査によれば、水田は二世紀あたりから数百年間、岩手の内陸部から姿を消す。寒冷な土地であるため、米作りが根付かなかったのであろうと推測される。
一〇世紀の北東北では、稲作は行われていたが、収穫量が気候によって大きく左右されるから、最重要の穀物ではなかったのではないかとぼくは考える。
未だ、縄文時代中期以降の〈狩猟、採集、食用になる植物の栽培〉の延長線上にあったのだ。
ここで言う〈縄文時代の延長線上〉とは、けっして〈遅れた文化〉と同義ではない。文化の選択であるのだが、それはまた別の話である。
縄文時代の人々は遊牧の民ではなく狩猟採集の民であるが、一つの場所に定住することなく、宿営地を転々とした。季節毎に獲物が異なり、それに合わせて移動するのである。
冬は狩猟に恰好の季節だ。
雪の上に獲物の足跡が残るから、追跡が容易なのである。
おそらく彼らは晩秋に森のそばに移動し、宿営地を作って冬の狩りに備えた。
土を掘って立てる竪穴式住居は、地面が壁の役割をするので外気の影響が少なく、意外に温かい。草葺きの屋根に土を被せて外気を遮断する方法もあった。
現在、ぼくたちが暮らしている世の中は農耕民族の文化の上に成り立っているから、冬と言えば家の中に閉じ籠もる閉鎖的な生活を連想するが、狩猟採集民であった縄文の人々は活動的であった。
それでも、曇天が続き、平原も山々も真っ白な雪に覆われる冬は移動もままならず、行動は制限される。
しかし、春――。
桜が咲く直前。枯れ色だった山々に、人々が気づくか気づかぬかの淡い萌え色が差す頃。
雪解けでぬかるんだ土地も乾き、歩きやすくなった頃。
縄文の人々は春の宿営地へ旅を始める。
おそらく、食用になる植物――今、ぼくたちが山菜と呼ぶ植物たちが生える野へと向かっただろう。そこは魚が多く生息する川もあり、冬の間暮らした深い森を遠く眺める土地である。
春になったら旅をする――。
ぼくは小説執筆の手を止めて、にんまりとした。
ぼくの中に縄文時代から連綿と続く衝動が棲んでいた。
そして、再び、笑った。今度は苦笑である。
あまりにもロマンチシズムが勝ちすぎた思いだったからだ。
それにぼくの旅心は春に限定されている。もし縄文人の衝動がぼくの内側に息づいているのならば、季節毎に旅をしたくなるはずだ。
おそらく春の旅心は、もっと根元的な、本能的な衝動なのだと思う。
だが、深く考察せずに、
「ぼくの中に縄文人が棲んでいる」
と、思った方が楽しい。
去年の春、今年の春は大きな旅はできなかったが、来年こそぼくの中の衝動にしたがって、旅をしてみよう。
書斎の窓から見える庭の桜の花吹雪を見ながら、ぼくはそう決心するのだった。
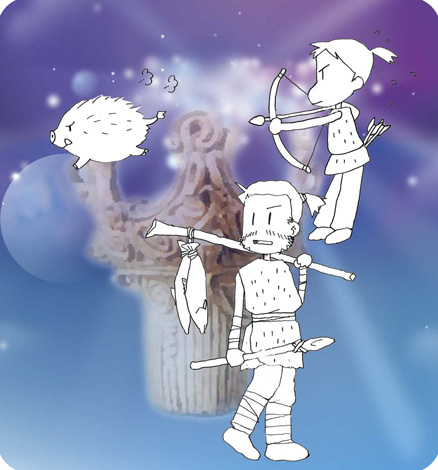
平谷美樹既刊
『風の王国(一)
落日の渤海』
